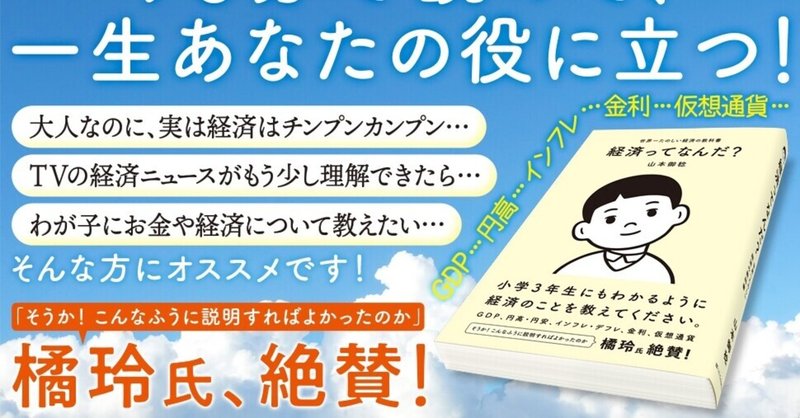
おじいちゃんが教える世界一たのしい経済の教科書9
第7章 インフレ・デフレってなんだ?
◉物価が上がること、下がること
ちちんぷいぷい、痛いの痛いの飛んでいけ~。
急にどうしたの? おじいちゃん。どこか痛いの?
そうなんだ……。最近腰が痛くてのぉ。血も神経もないはずなのだが、記憶の痛みっていうのかねぇ。それで、最近あっちの世界で友達になった医者に相談してみたら、言葉の痛み止めが効果あるというもんで。
言葉の痛み止め?
そう。昔は、病気や天災に対抗する科学的手段がなかったから、言葉の痛み止めである「おまじない」に頼るしかなかったそうなんだ。
科学的手段?
例えば、ケガをして痛い思いをしても、麻酔がないってことだよ。
え? そうなの? 手術する時も? 想像しただけであっちこっち痛くなりそう。
ほんとだね。だから、おまじないで痛みを取るしかなかったらしい。
へぇ~、そんな時代に生まれなくてよかったよ。でも、そのお友達はずいぶん昔のことに詳しいんだね。
そりゃそうさ。彼は江戸時代の医者だから。
江戸時代? 何百年も経つのに、まだ成仏できてないの?
言われてみれば……たしかに。ワシもそんなに長く成仏できなかったらどうしよう……。
おじいちゃんはいいの! 成仏できなくていいの! ずっとぼくと一緒にいて!
領太……。ワシもずっと領太と一緒にいたいよ。かわいい領太よ、どこか痛いところはないかい? おじいちゃんがおまじないをかけてあげよう。
急に言われてもなぁ……。風邪をひいた時とかは、おまじないよりおいしいものを食べる方が元気になるかも。
おいしいもの?
うん、焼肉とか寿司とかね。
ずいぶん高い薬になりそうだ。そうそう、焼肉といえば、デフレの影響で最近はずいぶんと肉が安くなったそうだね。
デフレ?
おや? そういえば、まだインフレ・デフレの話を領太にしてなかったね。
インフレ? デフレ? 初めて聞いたよ。
よし、じゃあ今日はインフレ・デフレの授業をするとしよう。では領太、一つおさらいだ。物価とはなんだっけ?
そんなの簡単だよ。モノの値段のことでしょ。
その通り。もう少し詳しく説明すると?
えーっと、形あるモノだけじゃなくて、手でさわることのできないサービスの値段も含まれるのが物価。
パーフェクト! そうだね。スマホとか車とか家とか、「さわれるもの」の値段と、アプリとかオンライン授業とか、手で「さわれないもの」などのサービスの値段を「物価」と言うんだったね。よしよし、それだけ理解していればインフレとデフレを理解するのは難しくないよ。インフレとは「物価が上がり続ける状態」のことで、逆に「物価が下がり続ける状態」のことをデフレというんだ。インフレの正式名称は「インフレーション」と言い、デフレの正式名称は「デフレーション」と言うんだよ。
ということは、焼肉屋さんの肉が安くなったのは、デフレの影響ってこと?
その可能性はあるね。デフレになると、さまざまな物価が下がってモノを安く買うことができるんだ。
それって最高じゃん!
いや、それがそうでもないんだよ。
どういうこと?
◉物価が下がるのはいいこと?
例えば、カルビの値段で考えてみよう。今月はカルビが一皿1000円だとするぞ。それが来月は900円、再来月は800円と値下げされるとしたら、うれしいかい?
うれしいに決まってるよ! ぼくが払うわけじゃないけど、安ければ焼肉屋にたくさん連れて行ってもらえるじゃん。
なるほど。領太はうれしいかもしれないけれど、焼肉屋さんの店長はどうかな?
店長さんも、安いから注文が増えて、うれしいんじゃないかな。
たしかに、安いと注文が増えるかもしれない。けど、もしも注文される量が変わらなかったらどうかな?
注文の数は変わらないのに、焼肉の価格が下がれば……お店の売上は減るってこと?
そうだね。お店の売上が減ると、店長の給料も、従業員の給料も、アルバイトのバイト代もいずれは減らさざるを得なくなる。
言われてみれば……そうだね。
それだけではないぞ。駅前の焼肉屋の店長は、いつも仕事が終わったあとに料理人仲間が集まる居酒屋でお酒を飲むのを楽しみにしていたのだけど、売上が下がったことによって、居酒屋には寄らずにまっすぐ家に帰ることにしたそうだ。
なんだかかわいそうだね……。仕事のあとに仲間と一杯やるのを楽しみにしていたのに……。
ほんとだね。そして、ここからが問題なんだ。毎日寄ってくれていた焼肉屋の店長が来なくなったことで、他の料理人仲間も寄りつかなくなってしまった居酒屋は、店の料理を値下げすることにしたんだよ。今までの値段では、お客がどんどん減ってしまうと思ったんだね。けれど、売上は下がるばかりで、居酒屋の店主もお金に余裕がなくなり、それまで仕事帰りに寄っていたスーパー銭湯に行くのをやめたんだ。すると今度は、スーパー銭湯の社長は……。
おじいちゃんさ。話が長いよ。そういうふうにみんながどんどん値段を下げたら、どうなっちゃうの?
物価が下がることを「デフレ」と言うと教えたよね? デフレになって安い金額で商品を買えるようになるのは、ありがたいことかもしれない。でも、モノが安いということは、売れないから安くしていることと同じで、会社の売上・利益は少なくなる。だから会社は社員の給料を下げたり、ボーナスをカットするなど人件費を減らすようになってしまうんだ。
マジで? それは超ヤバいじゃん。だってさ、例えばパパのお給料が減ったとしたら、ぼくのおこづかいも減っちゃうってことでしょう?
その通り。それだけじゃないよ。会社は人件費を削減するから、新しい人を雇わなくなる。だから、就職したいと思っている人がいても、就職することが難しくなってしまう。
え? デフレが続いたら、就職できない人が増えちゃうってこと?
そういうこと。このような連鎖的な(ずるずるつながるような)動きを「デフレスパイラル」と言うんだよ。そうならないために、日本銀行は物価を安定させているのさ。
じゃあ、デフレの逆のインフレは? 物価が上がり続ける方がいいの?
◉チョコレートが1個100万円!?
領太、景気の話をした時に、日本銀行は景気をコントロールする重要な役割を背負っていると話したよね。もしも、どこもかしこも商品が売れまくって儲かっていたら、「値段を高くしてもみんな買う」とさまざまな会社は判断して、物価が上がってしまう。今まで1本100円で買えていたジュースが、1本200円で売られることが当たり前になってしまう。そんなことが続いたら、いつの日かジュース1本1000円なんてことも普通になってしまうかもしれないって話。
あぁ、需要と供給のバランスがチグハグにならないためにも、景気をコントロールする必要があるって言ってたよね。
その通り。デフレスパイラルになることも恐ろしいけど、インフレが続くこともいいことだけではないんだ。ジュース1本1000円なんて、とんでもなくインフレ率が高くなることを「ハイパーインフレ」と言うんだよ。
ハイパーインフレ?
ハイパーインフレは、いろんな国で何度も起きている。2000年代の初め頃にはアフリカのジンバブエという国で起きたんだ。前日には100円で買えたチョコレートが、翌日は1万円になり、その翌日にはチョコレートが1個100万円になってしまったらしい。このように、とんでもないスピードで価格が上がることをハイパーインフレって言うんだよ。
100円のチョコが100万円になるなんて、むちゃくちゃだね。
あぁ、むちゃくちゃだね。その頃のジンバブエでは、みんなが大量の札束を持って買い物に行ったんだって。でもスーパーで買い物をカゴに入れている数分の間に価格が上がってしまう。そして支払いをする時には、またさらに価格が上がっているという悲惨な状況になったんだ。
そんなことが本当に起こったの? 信じられないや。お金がいくらあっても足りなそう。
ほんと、たまったもんじゃないね。インフレとは、モノの値段が上がり続ける状態のことだけど、言い換えると「お金の価値が下がり続ける」ことになるんだ。例えば、100円で買えていたジュースが200円になった場合、同じジュースを手に入れるために2倍のお金が必要になる。つまり、お金の価値は2分の1になってしまうというわけ。そしてハイパーインフレになったら、お金の価値が下がりまくり、もはや、お金は紙くずのようになってしまうことも……。
お金の価値が下がって紙くずみたいになるなんて、なんだか怖いね。その国のハイパーインフレは、今も続いてるの?
いいや。そんなことが続いたら大変だからね。新しく通貨を作り直したんだ。そして物価がさほど変わらないように国と中央銀行が監督するシステムを作り、国民に対して「安心していいよ」と約束したんだよ。
そうかぁ。日本も、日本銀行がしっかりしてないと、ハイパーインフレになっちゃうかもしれないんだね。
まぁ、ハイパーインフレはめったに起きないけどね。ただ、ハイパーがつかないただのインフレは簡単に起きる可能性がある。
え? 簡単に起きる可能性があるの? いつ? どんな時? 起きる時のサインとかあるの?
インフレが起きるサインというのは、実は誰にも見えないんだ。みんなが気づかないうちにインフレは起き、みんなが気づかないうちにデフレも起きる。両方ともハッと気がついた時には起きているものなんだよ。
こっわっ。目に見えないって、幽霊みたいじゃん。
幽……霊……?
あ、おじいちゃんのことじゃないよ。おじいちゃんは、しっかりとぼくの目に見えてるからね。それに突然出てきても、もう怖くないし。
そうかそうか。領太が怖くないって言うなら、ま、いっか。とにかく、物価があまりにも上がったり下がったりしないようコントロールする必要があるってわけ。
なるほどね~。そりゃコントロールが必要だ。
◉インフレ率は1%?2%がちょうどいい?
物価が上がりすぎないよう、インフレ率において、政府と日本銀行が一定の範囲の目標を決めることを「インフレターゲット」って言うんだよ。
インフレターゲット?
領太は、ターゲットって言葉を聞いたことあるかい?
ターゲット? あるけど、説明するのは難しいなぁ。
ターゲットとは、一言でいうと「目標」のこと。物価が上がることに対して、政府と日本銀行が一定の範囲の目標を決め、それに収まるように金融政策を行うことを「インフレターゲット」と言うんだ。
一定の範囲の目標?
政府や日本銀行は、インフレ率において1%~2%を目指しているんだよ。
1%~2%って、どういうこと?
例えば、100円のものに対して、101~102円ほどに物価が上がることを目指しているという意味さ。
どうして、1%~2%を目指してるの?
それは、物価を安定化させるということが目的なのと、もう一つは物価が1%~2%上がった方が、国民の給料も増え、仕事にやる気が出るからなんだ。つまり経済成長につながるということなんだよ。
物価が1%~2%上がると、経済が成長するの? どうして?
それは、人はそもそも「成長したい」と思う生き物だからさ。領太はテストで60点取ったら、「次はもっと高い点を取ろう」って思わない?
60点はちょっとヤバいね。70点はほしいな。
でも次のテストで70点を取れたら、次は80点を目指したくなる。80点の次は90点、90点も取れたなら100点目指したい!……というように、人間は常に成長を求めるんだ。
そういうことか。けど、その目標って誰が決めるの?
インフレ率の目標は、政府や日本銀行があくまでも目標値として出しているんだ。「目標値のようなインフレ率になるように、政府や日本銀行は金融政策を打ちます」って感じだね。
ふーん。経済ってやつは、つくづく活発に動く生き物みたいだね。
しっかりとノートに書きとめておくといいよ。
ノートにも書いておくけど、ぼくが大きくなった時にまた教えてよ。
領太が大きくなったら……か。
医者のお友達みたいに、何百年……とまではいかなくても、ぼくが生きている間は成仏しないで、大人になってもぼくのそばにいてよね。
……。
おじいちゃんどうしたの? 眠いの?
いや、最近ちょっと疲れ気味でのぉ。領太と話していると楽しくて、はしゃぎすぎたかな。
ちちんぷいぷい、おじいちゃんの疲れよ、飛んでいけ~!
領太……ありがとう。今日はこのままここで寝るとしよう。
うん。一緒に寝ようね。
この日、おじいちゃんはいつもより元気がない様子だった。
でも、突然消えることもなく、ぼくの横で静かに眠っていた。
朝になったら姿はなかったけど、それはよくあることで、ぼくは特に気にしていなかった。
けど、おじいちゃんと会える時間は永遠に続くわけじゃないということを、この時のぼくはまだ知らなかったんだ。
次回、第8章 「税金ってなんだ?」へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
