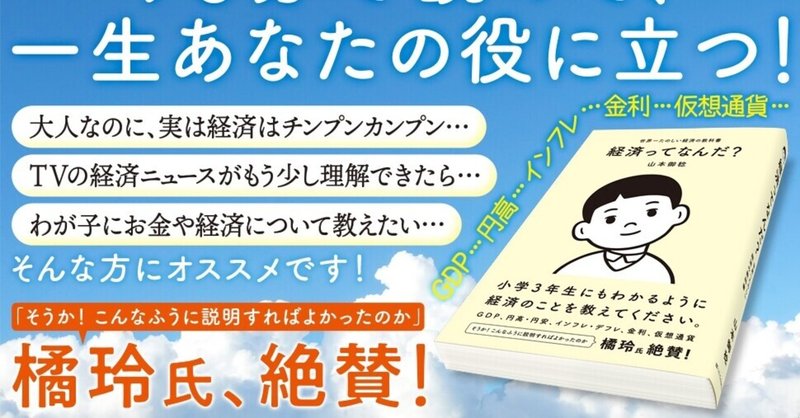
おじいちゃんが教える世界一たのしい経済の教科書10
第8章 税金ってなんだ?
◉憲法で定められた国民の義務
むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんとカエルとミミズが一緒に暮らしていました。おじいさんは、カエルを我が子のようにかわいがり、くる日もくる日も一緒の布団で……。
ストーップ! ねぇ、おじいちゃん。今日は昔話をしに来たの? それに、何その気持ち悪い話。せっかくの風呂上がりのアイスがまずく感じるよ。
な、なんだと? 気持ち悪いとはなんだ! このおじいさんはカエルの卵を大切に育てて、800匹の孫たちを川へ放ち、そしてミミズと……。
もういいから! わかったから! おじいちゃんが川の話をすると縁起悪いし。
ホワッツ? もしかして……三途の川のことを言っているのかい?
それしかないでしょ。
なんということだ。常々、自分が幽霊であることを忘れつつあるというのに、愛する孫はいつまで経ってもワシのことを幽霊扱いするとは……。そんなんじゃ、総理大臣になっても国民から愛され……。
え? ちょっと待って。ぼくが総理大臣ってどういうこと?
あ、いや、なんでもない。
もしかして、おじいちゃんって未来のことがわかるの? ぼく、総理大臣になるの?
いや、そうじゃなくて、例えばの話だよ、例えばの話。
うそだ! 本当のことを教えてよ!
本当に未来のことなんてわからないってば。領太が国民みんなの経済を豊かにするために、税金の改善に力を入れる総理大臣になるなんて……ハッ!
やっぱり未来のことがわかるんじゃないか! ってゆーか、ゼイキンって……貿易とか銀行の話をした時に出てきたあの税金? 国民の誰もが払わなきゃいけないっていうお金?
よしよし、話がそれたぞ。
なんか言った?
いや、なんでもない。そうだ、その通りだよ。税金とは、国や地方公共団体が必要な経費をまかなうために、国民が支払わなければならないお金だよ。最も重要な法律である憲法で決まっているんだよ。領太もそろそろ小学校で習うけど、「納税の義務」「勤労の義務」「教育の義務」という三大義務の一つが納税、つまり税金なんだよ。消費税とか所得税とか、いろいろな種類の税金があるって話したのを覚えているかい?
うん、なんとなく。
じゃあ、今日はいろいろな税金の話をしようじゃないか。
ちょっと待ってね、ノートを用意するから。
税金の起源は飛鳥時代?
さかのぼること、およそ1300年前の話。
また気持ち悪い昔話はやめてね。
まぁまぁ、ちゃんと聞くがよい。701年に大宝律令という決まりができたんだ。その決まりの中に税金制度が作られた。まだ電気もガスもない飛鳥時代のことだよ。
飛鳥時代? そんな昔の話、社会の教科書にも載ってないかも。そんな昔からお金のやりくりについて考えられてたの?
その頃はまだお金ではなく、米や布や絹を作って国に納めていたのさ。米は取れた分のうち3%くらい。日本で消費税がスタートした時の割合と同じくらいだよ。
消費税って最初は3%だったの? 知らなかった。
そうだろうね。その頃、領太はまだ生まれてないからね。消費税の話は、あとで詳しくするとして。当時の人々が納めた税金(すなわち米や布など)は、国のために仕事をしている人たちに渡していたんだ。国のために仕事をしている人たちは、お米を作っている時間がない。だから、そういう仕事をしてくれている人たちのために、お米などを渡すんだよ。
国のために仕事をしている人?
そう。今で言う「公務員」のことさ。それも銀行の話をした時に少し出てきたね。公務員とは、どういう人か覚えているかな?
もちろんだよ! お巡りさんとか公立の学校の先生とかのことだよね。モノやサービスを提供してお金を得る組織や会社のことを「民間」といって、国民から集めた税金で国民のためにやりくりする職員のことを「公務員」っていうんだよね。
素晴らしい! その通りだ。付け加えることが一つもないよ! さすが未来の総理大……。
え? なんか言った?
いや、いいんだ。続けよう。実は、米や布や絹を渡すのは、国の仕事をしている人たちだけじゃなくて、生活に困っている人にも渡していたんだよ。
生活に困っていた人?
何か事情があって米を作る体力がない人や、台風などの被害で田んぼが流されて米を作ることができなくなった人とかがいるよね。そういう人たちを助けなければならないから、国民みんなから少しずつ生活に必要なものを集めて渡していたんだ。
そっか……飛鳥時代の人たちは優しいんだね。
飛鳥時代の人たちに限らず、現代人も国や都道府県や市や区がお金をどのように使うかをしっかり決めて、管理しながら使っているんだよ。そういった管理のことを「財政」というんだ。
ザイセイ?
そう。みんなから集めた税金を、どうやってやりくりするかを考え、管理することを財政というんだ。税金にはさまざまな種類があるって話したよね。まずは身近な「消費税」について説明しよう。
◉消費税は「社会保障」に使われる
消費税とは、一言でいうと「何かを買った時に支払う税金」のことだよ、領太。
何かを買った時って、どんなものでも? ぼくみたいな小学生でも払わなきゃいけないの?
そうだよ。日本で買い物をすれば、買い物をしたすべての人が消費税を払わなきゃいけないんだ。ただ、外国から来た人たちは、支払わなくてもいい場合があるよ。
ぼくなんてお金を稼いでないし、おこづかいの中でやりくりしなきゃいけないのに、税金を払わなきゃいけないの? そもそも、消費税って何に使うための税金なの?
消費税は、さまざまな分野での「足りないもの」に使われるんだ。
足りないもの?
そう。足りないもの。例えば、医療、介護、年金あるいは子育てに必要なサービスだよ。そのためにお金が必要だから消費税が必要なんだよ。ちなみに、消費税が始まったのは1989年。その頃は、さっき言ったようにまだ3%だった。その後、1997年に5%となり、2014年に8%となり、さらに2019年に10%になったわけだが、払う割合が増えるごとに消費税の使い道は広げられるんだ。これまでは、主に医療や介護など高齢者中心だったけど、子育て世代にも拡大し、全世代の保障を充実させるために、「幼児教育・保育の無償化」や「高等教育(高校)の無償化」などにも使われるようになったんだよ。
けどさ、たった1%とか2%増えるだけで大人はギャーギャー騒いでたけど、なんで?
たしかに、100円の買い物だとしたら、108円が110円となり、その差はたった2円かもしれない。けど、車や家を買うことを想像してごらん? 100万円の車に8%の消費税が加算されたらいくら?
えっと……100円だったら108円になるから……100万円だと……8万円?
正解! じゃあ、10%になったら?
10万円!
そう、その差額は2万円。じゃあ5000万円の家だとしたら?
5000万円? えっと……8%だと40万?
ブッブー。ゼロが1個足りないよ、領太。
え? 400万円?
その通り。ということは、10%だと?
500万?
そういうことになるね。領太が「たった2%」と言っていたその差額は100万円。
ぜんぜん「たった」じゃない!
おっしゃる通り。厳密には、家の土地代には消費税はかからないのだけれど、いずれにせよ、馬鹿にできない額だよね。これがさらに、何千万、何億円もの大きな金額を扱う会社だったら?
脳みそパンクしちゃう金額になる。
そうした大きな金額じゃなくても、領太を含め一人一人が日々少しずつ納める消費税も、ちりも積もれば膨大な金額になるんだよ。それでも消費税だけではまだ十分ではないんだ。だから、その他の税金についても学んでおこう。例えば、住民税・自動車税・所得税については、こんな感じでノートにまとめるといいよ(『経済ってなんだ?』〈山本御稔・著〉本文150頁参照)。
さすが大学の先生だしょね。こうして書くとすごくわかりやすいや。
領太にそう言ってもらえるとうれしいよ。その他、会社が国に支払う法人税や、タバコを吸う人が払うタバコ税や、お酒を飲む人が払う酒税とか、亡くなった人の所有物やお金を受け継ぐ際に払う相続税など、日本にはさまざまな種類の税金があるんだよ。
そうなんだ。大人になるまでに全部覚えるのは大変そう。
大丈夫。大人になって、実際に払うようになると自然に覚えるよ。
そっか。大人になるといろいろな税金を払わないといけないんだね……。
◉日本の借金は1200兆円!?
ただ、税金だけじゃ国のやりくりは厳しいんだ。日本人は豊かになってきているけれど、政府は豊かではないんだよ。
どういうこと?
政府はお金儲けをしているわけではなく、税金としてお金を調達し、必要としている人や組織に渡してあげるのが役割だよね。銀行の話をした時に、政府について説明したのを覚えてるかい?
うん。もちろんだよ。政府は、国をまとめる権限を持つ人々の集団や場所のことだよね。
その通り。国がもらうお金、つまり収入のことを「歳入」、国が払うお金、つまり支出のことを「歳出」というんだけど、政府が集めた税金(歳入)の使い道(歳出)としては、道路や橋などを整備する公共事業費や国を守るための防衛費などいろいろあるんだ。でも、一番大きいのは、国民の健康や生活を守る社会保障費なんだ。そして、高齢化が急速に進む日本では、この社会保障費がどんどん膨らんでいるんだ。
日本には1年でどれくらいのお金が必要なの?
日本は毎年100兆円ぐらいの予算が必要なんだよ。
毎年100兆円も必要なの?
そうなんだよ。けれど、国民から税金を集めても60兆円ほどしかない。
え、ぜんぜん足りないじゃん! 残りの40兆円はどうするの?
それは、国がお金を借りるんだ。
国がお金を借りる? いったい誰から?
ほとんどは国民からだよ。そしてお金を借りたら、国は「国債」という券を発行するんだ。
コクサイ?
そう。例えば国債を1万円で買った(国に1万円を貸した)とすると、1年後には利子がついて1万1000円になったりするわけ。
え? 国債を買うとお金が増えるの?
そうだよ。国債を買うと、定期的に利子が支払われるんだ。利子はわかるね? 銀行に預けた時に増えるお金と同じ。そして返してもらう期日(満期)が来れば、買った時のお金がちゃんと戻ってくるんだ。
へぇ、そうなんだ。
国債には、個人向けのものや企業向けのものなどがあって、満期になるまでの期間によって種類もいろいろあるんだよ。
ふーん。国が借金してるなんてぜんぜん知らなかった。
これまでに発行した国債の総額は1000兆円ほど。これに地方債(地方公共団体が発行する債券)を合わせると、日本には1200兆円の借金があることになるんだ。
い、1200兆円? いち……じゅう……ひゃく……せん……まん……ぜんぜん想像つかないや! 日本、大丈夫なの?
恐ろしい数字だよね。その借金をどうにかするために、政府はいろいろ対策を練っているんだよ。
なんだか大人になるのが不安になってきたよ。
まぁまぁ、そんなこと言いなさんな。とはいえ、領太が大人になる頃には、消費税は今よりもっと上がっているかもしれないけどね。
えー! そんなの嫌だよぉ。
でも、海外には日本よりもっと税金が高い国もあるんだよ。
海外にも税金ってあるの?
◉幸福の国・フィンランドの付加価値税は24%
あるよ。北欧のフィンランドという国では、買い物をすると付加価値税という税金がかかるんだ。日本で言う消費税みたいなものなんだ。
へぇ~、何パーセント?
24%。
は? に、24%? 日本の倍以上じゃん! 税金がそんなに高かったら、フィンランドの人たちはみんな買い物しなくなりそう。嫌になって他の国に逃げ出す人もいるんじゃない?
それが、まったく逆なんだ。フィンランドに住みたい、場合によっては国籍すら変えたいと言う日本人もいるくらいなんだよ。
マジでぇ?
マジでマジで。
信じられない……。
国連の「世界幸福度ランキング」でも4年連続1位を取っているんだよ。
マジでぇ?
マジでマジで。
なんで?
それは、フィンランドの社会福祉が充実しているからなんだ。
社会福祉の充実?
子どもの教育費を国が出してくれたり、高齢者が安心して高齢者住宅に入れるようにしてくれたり、そうした社会福祉が充実しているんだよ。
税金は高いけど、その分ふだん生活するお金があまりかからないってこと?
そうだね。働ける間にいっぱい税金を払って、子育て中や老後は充分に支払った税金でゆったり豊かに暮らすんだ。だから人気が高いんだよ。
◉ふるさと納税って税金なの?
そういう国もあるんだね。あ、そういえば、「ふるさと納税」ってやつも税金なの?
ふるさと納税なんて、よく知ってるね。
この前、誕生日でもないのに夕ご飯にカニが出てきたんだ。「これどうしたの?」ってママに聞いたら、「ふるさと納税でもらったのよ」って。
そういうことだったのか。ふるさと納税とは、その名のごとく「ふるさとのためにお金を払うこと」なんだけど、一言でいうと、寄付をするということなんだよ。
寄付? それなら「ふるさと寄付」でいいじゃん。なんで「税」がつくの?
ちなみに、領太は「赤い羽根共同募金」をしたことがあるかい?
うん、あるよ。
赤い羽根共同募金をすると、何がもらえる?
赤い羽根。裏にシールがついてるやつ。みんな下敷きとか筆箱に貼ってるよ。
そうだね。募金をすると赤い羽根をもらえるね。その羽根のことを「返礼品」というんだ。
ヘンレイヒン?
そう。寄付をしたことで、もらえるお礼のこと。ふるさと納税も、寄付をした都道府県とか市町村等からお礼をもらえるシステムになっているんだよ。そして、寄付をしたことによって、納めた税金が戻ってきたり、翌年の住民税が少しだけ安くなったりするんだ。これを「控除」っていうんだよ。
返礼品というお礼をもらえるだけじゃなくて、支払うはずの税金が安くなるってこと?
その通り。
でもさ、ふるさとがない人はどうしたらいいの? ぼくみたいに、東京生まれの東京育ちだと、東京に寄付するってこと?
いや、それが実はそんなことないんだ。寄付をしたい自治体は、自分の生まれ育ったふるさとに限らず選べるんだよ。
え? 自分のふるさとじゃないのに寄付する人なんているの?
そうなんだ。自分がほしい返礼品をくれる自治体に寄付することができるんだよ。
お礼の品で寄付するところを決めるってこと?
そういう選び方もあるってことさ。
なんだか、見返りを期待してるみたいで悪いなぁ。
そんなことないよ。実際、寄付をしてもらった自治体は助かるしね。おじいちゃんのお父さん、つまり領太のひいおじいちゃんは滋賀県の小さな村で生まれたんだけど、その村は林業が中心でね。ただ、林業は年々人気がなくなっていて、困ってるんだ。村に住む人が少なくなると、それだけ村の税金も減ってしまう。医療とか介護をはじめ、村の公共サービスに必要なお金が充分ではなくなっているのが現状なんだ。
林業が人気なくて、みんなその村を出ていっちゃうと、残った人たちが使うための税金が足りないってこと?
そうだよ。税金が足りないからといって、その村に住んでいない人が税金を払うことは、今の日本の制度では難しいし、とはいえ、その村の人たちはお金がほしい。だから、寄付という形でお金を納めるような制度ができたんだ。寄付をすることは、個人の判断ですぐできるからね。そのお礼として、その村から返礼品がもらえるというわけ。
そういうことなんだね。じゃあ、ぼくもひいおじいちゃんのふるさとの滋賀県の村に寄付してあげたいよ。
領太は優しいね。滋賀県はいいところだよ。おいしいお米や、きれいな川でアユも取れる。そのお米やアユの佃煮とかを返礼品でもらえるかもよ。
へぇ~、ぼくも滋賀県に行ってみたいな。
いつか、パパとママと一緒に行くといいよ。
その時は、おじいちゃんも一緒に行こうよ。
家族旅行の邪魔をしちゃ悪いから、おじいちゃんは遠慮しとくよ。
何言ってんの? おじいちゃんも家族じゃん! 遠慮とかやめてよ!
ありがとう、領太。じゃあ、おじいちゃんも遠慮なく参加させてもらおうかな。その時、おじいちゃんがまだこっちに……。いや、なんでもない。とにかく、領太はまだ小学3年生だから、この先何十年も生きることができる。いろんなことをたくさん学んで、国内外いろんな場所へ足を運んで、自分の目と足でさまざまなことを経験するといいよ。
うん! おじいちゃんも一緒にね。
……。
おじいちゃん? 聞こえてる? おじいちゃんはすでに幽霊だから、この先ぼくとずっと一緒にいるよね? ねぇってば! まったくもぉ……突然消えないでって言ってるのに。
※いつもご愛読ありがとうございます。今回の「おじいちゃんが教える世界一たのしい経済の教科書10」にて、内容公開は終了です。これ以降「おじいちゃんが教える世界一たのしい経済の教科書11~13」は、本書『経済ってなんだ?』(山本御稔・著)のにてお楽しみください。
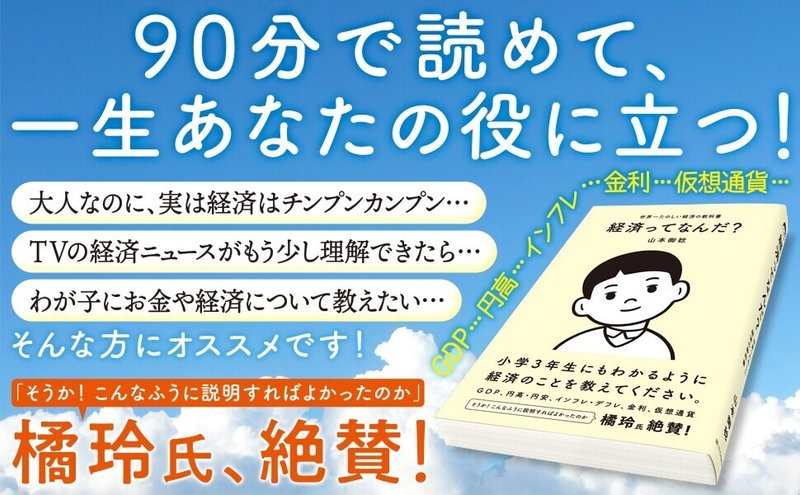
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
