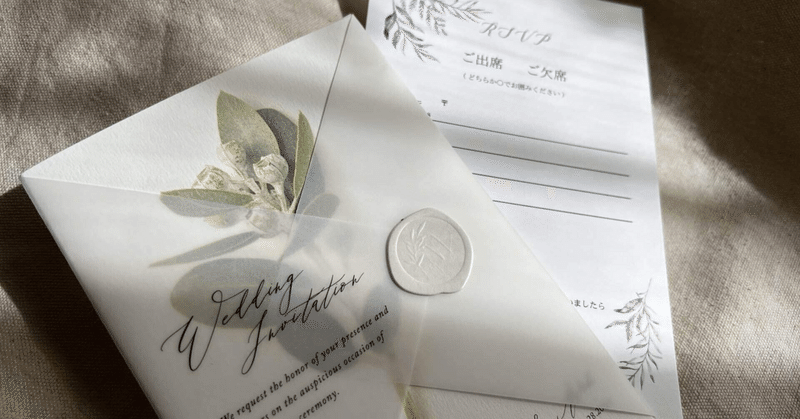
【創作】好きなようにして、いいんだ。〜第一話〜
"You have a golden heart!"
英会話教師のジェームズは
グレーの目を大きくし
両腕を広げて大袈裟に言った。
職業を告げたときの
周りの反応が私は好きじゃない。
「何て良い人なんだ!」
少し声を高くして
言われた後に
「私には出来ない」
と続く。
「他人の下の世話なんて」って。
どうしてだろう。
下の世話なら看護師だって
毎日行なっていることなのに、
あっちのイメージは「白衣の天使」で
私たちは、どんよりと
暗いベールを全身に被ったような
特殊な人、とみなされるんだ。
「お年寄りが好きだから。
好んでやっていることだから」
なんて返事しようものなら
更に「ココロのキレイな」
特異な人間扱いされてしまうから、
最近は曖昧に笑って
話を変えることにしている。
小さい頃から
両親より祖父母によくなついた。
祖父母の方が優しかった訳じゃない。
すぐに大きな声で
子どもには分からないことばを使いつつ
早口でけんかを始める祖父母のもとから、
それでも去らなかった。
私の存在に気づいて
どうにかやめないかな、って
思いは毎回打ち破られたけど、
ハラハラしながら
高齢の大人が顔を赤くして怒る様を
観察していた。
人間がよく出来ていたのは
両親の方だと思う。
優しくて、理不尽なことを
言わなかったから。
だけど私はいつも
同居の祖父母にべったりだった。
ただの好みの違い、
なんだと思う。
だから、
清い心で高齢者の介護を
ナリワイにしているんじゃない。
自分に合っているから。
頑固で偏屈なおじいさんとも
文句ばかり言うおばあさんとも
話をするのが楽しいから。
それだけなのに、
周りは私の立ち位置を
勝手に高みに追いやる。
高くも、「天使」のイメージとは
掛け離れた
マイナスのイメージの強い場所に。
___________________
「いやぁよ。
私、ソウくんが来ないと
起きないから!」
明るい朝の光がさす
キラキラした部屋の中で
そこの主は私の介助拒否をした。
「田島さん、またそんなこと言って。
私、ソウくんと結婚するんだから
譲ってあげませんよ」
茶化した声で言う私の顔を見て
田島さんは目をぱちぱちさせた。
「あれ、アンタ!
あんないい男、捕まえたの。
こんな小さい乳で、
いったいどうやって!」
そう言いながら両手を私に回して
介助しやすい姿勢になってくれる。
「へへ〜ん!」と
偉そうに笑った私の腰を
ペチンと皺だらけの手で叩いて
彼女は更に悪態を突く。
「それにこんな細っこい腰で
アンタ、子ども産めるの?
あんな良い男の子どもなら
たくさん産まないと」
「任せといて!私、頑張るから」
ガッツポーズをしてみせた私に
「心配だねぇ」と返した
96歳の田島さんとの
この同じやりとりを、
私たちはここ何日か繰り返している。
特養のイメージって
「普通の」人にはどうなんだろう。
暗いのかな。
臭いのかな。
近寄りたくないところかな。
私が働くこの特養は
窓が大きく設計されていて
天井も高いから
空気が明るく輝いている。
悪臭対策には気を使っているし
ご入居者に
暗い印象は無いと思うんだけど。
いつも中にいるから
そう思うのかな。
少なくとも私たちは
笑って楽しく
仕事をしている。
仕事だから嫌なことも
もちろんあるんだけどね。
私はこの
軽井沢にある教会のような設計の
たっぷり木材を使って出来たために
いまだに木の香りさえする
大きくてピカピカの窓を持つ
特養が好きだ。
ある日の
暖かさが戻って来て
幸せを感じるような
美しい春の日だった。
このくもりのない窓からさす光を
じゅうぶんに集めたホールで
ご入居者の水分補給をし終わった頃、
突然
「ドーン」と窓の方から
大きな音がした。
おばちゃんパートの
川口さんが大声をあげて
騒いでいる中、
ソウくんが冷静に窓の鍵を開けて
ベランダに出て行った。
「誰か、大きい段ボールを
持って来てもらえますか」
私は急いでリネン庫から
空いた大容量おむつの段ボールを
持って来た。
川口さんは
興奮して仕事もせず
きゃあきゃあ騒いでいる。
窓の方に向かうと
ソウくんが大きな鳥を
ごく自然に
何でもないことのように
優しく抱え上げていた。
枯れ草を集めたような
秋の色をした野鳥。
「ソウくん、それ、死んでるの?」
彼は優しい笑顔を私に向けて
首をゆっくり横に振った。
「死んでない。 気絶しているだけだよ。
窓に気づかないで
ぶつかったみたいだ」
そう言って段ボールを
私から受け取って
枯草色の鳥を
宝物を扱うようにそっと中に入れた。
「まだ少し寒いから
こうして中に入れて
フタを開けておこう。
ベランダにこの箱を出しておいたら
しばらくすれば勝手に気づいて
飛んでいくよ」
「ソウくんは、
鳥の介護まで出来るの」
そう言う私の顔を見て
眉を少し下げて、笑った。
「実家の近くに鳥がよくいたから」
ソウくんの癖のある黒い髪は
柔らかい春の光を受けて
ますます黒く輝いていた。
目に映る景色が、
かすかに頬に感じる風が、
あまりに優しくて
私は恋に堕ちてしまった。
ソウくんの全てが
大好きだった。
あまりに素敵だったから、
私はソウくんのことが
信じられなかった。
本当に私を好きなのかな、って。
あしながおじさんのように
高い身長。
スラリと伸びた
細すぎる手足。
クシャッと笑う時に
少し下がる眉。
たまらなくセクシーな
鼻にかかる話し方。
何もかもが美しく見えて
何か他の、意図があるんじゃないかって
思ってしまった。
我が家は一般的な家庭で
裕福な方じゃないけれど、
富裕層の子どもに産まれたら
こんな風に疑心暗鬼に
なるのかもしれない。
それで、
言ってしまった。
雨がスニーカーから
私のつま先までじわじわと侵食して
気持ちが悪かった、あの日。
「ソウくん、本当に
私のことが好きなの?」
そんな、たったひと言だけで
ソウくんには伝わった。
私の言いたいこと全てが、
どす黒い考えが、
矢のように彼の中心に
刺さってしまった。
彼は泣きそうな顔で
笑顔を作った。
「僕の状況じゃ
信じられないのは
仕方がないね。
でも本当だよ。本当に好きです」
抱きしめられて聴いた
その心臓の速い音と
熱い身体の震えが
全身を使って泣いているようで、
私はとてつもなく後悔した。
一生このことを
悔やみ続けるのかもしれない。
「ごめんね、ソウくん。
本当にごめん」
ソウくんの身体に回した両手に
力を入れて、
何度も謝る私の髪を撫でながら
ソウくんは囁いた。
"I,really,really love you,indeed."
(第ニ話に続く)
※第二話で終わります。
ありがとうございます!頂いたサポートは美しい日本語啓蒙活動の原動力(くまか薔薇か落雁)に使うかも?しれません。
