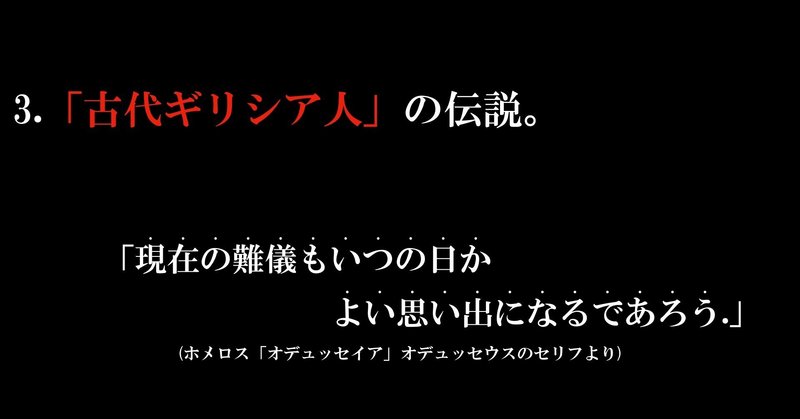
【②ギリシア人の伝説】ぼくたちは古代ギリシア人と友だちになれるか
※【①ギリシア人の神話】ぼくたちは古代ギリシア人と友だちになれるか、の続きになります。
古代ギリシア人にとっての伝説
前章では神話について書いたが、今回は伝説について書く。
では、神話と伝説は何が違うのだろうか。
辞書を引くと、
・神話…昔からつたえられている、神を主人公にした話。
・伝説…(その地に根付いて)事実として人々が言い伝える話。
となる。
ぼくも基本この定義に沿ってこの用語を使っているが、以前ぼくは古代ギリシア人の神話の特徴を以下のように書いた。
「この世界の構造を説明する道具として、神話は利用されていたのだ。」
つまり、神々の存在自体が世界の成り立ちの諸要素である、というのがギリシア神話の特徴なのであった。
さて、古代ギリシアにはかつて半神がいた。
半分神であり、半分人間であるのだが、彼らは「英雄」と呼ばれる類の存在である。
「古代ギリシア人の伝説」は、まさにこの半神=英雄の物語になるのである。
では神と英雄の大きな違いは何か。
それは神が不死であり、英雄は死を運命付けられた存在であるという違いである。
英雄は、神々と異なりこの世界を構成する諸要素などではない。
強大な力を持ちながら、あくまで生身の人間なのである。
伝説とは、英雄=人間の栄枯盛衰を描く物語に他ならないのだ。
古代ギリシア人にとって神話とは世界認識の前提であった。
それに対して伝説は、古代ギリシア人の自己認識の前提であると言えるであろう。
伝説に登場するあらゆるタイプの英雄たち、俊足のアキレウスや黄金の頭脳を持つオデュッセウス、非業の死を遂げることになるギリシア連合軍総大将アガメムノン、怪力の大アイアスたちは、古代ギリシア人の自己認識の投影なのだ。
もちろん、実際の歴史上の古代ギリシア人と英雄たちは多くの点で異なっている。
これから紹介する「トロイア戦争史」もあくまで伝説であって史実ではない。
しかし伝説の重要性は、それが史実かどうかという点ではないのだ。
英雄たちの事績を真実であると信じていた古代ギリシア人のメンタリティを理解することこそ、伝説の重要性なのである。
次章で紹介する「トロイア戦争史」は、古代ギリシア人にとって最大最高の教師であった大詩人ホメロスが紡いだ物語である。

ホメロスの作品は古代ギリシア文明がこの地上から滅び去るまで、初等教育の必修科目であった。
古代ギリシア人を自負する人間のなかで、ホメロスを知らない人間など存在しなかったといっても過言ではないほどなのだ。
次はこのホメロスの作品「イリアス」と「オデュッセイア」、およびその周辺の作品を取り上げることで、古代ギリシア人の自己認識の前提を探っていくこととしたい。
古代ギリシア人最大の伝説「トロイア戦争」
古代ギリシア人が実際にあったことだと信じていた「伝説」、その最たるものが「トロイア戦争」である。
紀元前1200年ごろに勃発したといわれるトロイア戦争は、当時ミケーネ文明下にあったギリシア連合軍と、小アジアの都市国家トロイ(イリオス)の10年に渡る戦いのことである。

ギリシア絶世の美女へレネが、トロイ王子パリスによって強奪されたことに端を発したと言われるこの戦争は、都市国家が乱立する紀元前5世紀前後の古代ギリシア黄金期において、かなりの程度人口に膾炙していたことは疑い得ない。
いわばトロイア戦争は、古代ギリシア人の常識であったのだ。
先述したとおり、このトロイア戦争を描いた紀元前8世紀の大詩人ホメロスは全ギリシアの教師とされ、ギリシア世界の初等教育において彼の作品は教材になっていたのである。
しかし肝心のホメロスはかなり謎に包まれた人物である。
生没年ははっきりしないし、出身地もイオニア地方(小アジアのギリシア人植民都市)のどこかであることしかわからない。
盲目であったとも言われている。
また、紀元前5世紀に黄金期を迎える古代ギリシア世界の時点で、すでにホメロスは謎の人物となっていたようだ。
このホメロスが紡いだ作品はトロイア戦争10年目の50日間を描いた「イーリアス」と、トロイア戦争の後日譚を描いた「オデュッセイア」である。
なお、トロイア戦争史としては、トロイア戦争前史、つまりパリスによるへレネ強奪などが語られる「キュプリア」や、「イーリアス」以後の戦争経過を語る「アイティオピア」「イリオスの陥落」、「オデュッセイア」の後日譚「テレゴニア」などの作品が梗概のみ伝わっている。
ここでは簡単に勉強会スライドを提示しておこう。トロイア戦争の全体を確認していただければと思う。








これらの作品はまとめて「トロイア圏叙事詩」と総称されるが、おそらくホメロスの作品は「イーリアス」と「オデュッセイア」のみだと考えられている。
ここで注目したいのは、ホメロスはトロイア戦争を俯瞰的に著述したわけではなく、あるシーンにポイントを絞って描いたという点だ。
「イーリアス」を読むと驚くのだが、トロイア戦争における名シーンがほとんど描かれていない。
多くの人がトロイア戦争と聞いて思い出せるシーンといえば、英雄アキレウスの死やトロイの木馬による奇襲ではなかろうか。
しかし「イーリアス」にそのシーンは一切出てこない。
「オデュッセイア」において間接的に語られるのみなのである。
さて、それはともかく、トロイア戦争は伝説としてのちの古代ギリシア人に多くの教訓を遺した。
いや、実はこの言い方には問題がある。トロイア戦争はあくまで伝説であるので、その骨子のみ残して多くの再解釈や脱構築が行われ、結果的に作り変えられていった。
それはおそらくホメロスの作品も例外ではないであろう。
つまり、当時の古代ギリシア人のメンタリティや時代感性が、逆にトロイア戦争に反映されているのだ。
トロイア戦争史を知ることは、トロイア戦争があったかなかったか/どのような戦争だったか、などという次元の問いには答えることができない。
しかし、トロイア戦争を通じて、トロイア戦争よりのちの古代ギリシア人のメンタリティを垣間見ることができるのだ。
「トロイア戦争」が投影されたもの
トロイア戦争は、ミケーネ文明下のギリシア連合軍が小アジアの城塞都市トロイ(イリオス)に攻め込んだ戦争である。
ミケーネ文明時代のギリシア世界は、紀元前8世紀以降のポリス国家乱立期の世界と同様に、小国家が乱立していた。
ただ、民主政的/寡頭政的ポリス国家とは異なり、各国それぞれ王家が統治する王権国家であった。
とはいえ古代ギリシア世界の共通認識において、ミケーネ文明下のギリシア世界は1000年前に実在した祖先たちに他ならない。
事実ベースではミケーネ文明はとうに滅びており、古代ギリシア人との関係性/継続性は不透明であるが、そのことは重要ではないのだ。
さて、このトロイア戦争の構図は、古代ギリシアの歴史を概観する上で非常に示唆的である。
古代ギリシアを語る上で、その地勢的条件を無視することはできない。
バルカン半島の先端に位置するギリシアは、東にエーゲ海を挟んで大帝国アケメネス朝ペルシアを隣国に持つ。
アケメネス朝ペルシアは地球上初の大帝国を建設した強大な国家である。
古代ギリシア人は、この大帝国は全世界の2/3を支配していると考えていたほどである。
古代ギリシア人は、このペルシアに対して憧れと侮蔑というアンビバレントな感情を抱いていたと思われる。
それが充分に顕在化するのは紀元前5世紀のペルシア戦争であるが、それはのちに取り上げることにする。
古代ギリシア人にとってペルシアへの憧れとは、莫大な富の集積地としてである。
何せ全世界の2/3を支配下に置くペルシアである。
西方には世界一の大富豪クロイソスが治めていたリュディアがあり、南方には大穀倉地帯エジプト、北方の黒海沿岸は木材などの資源が豊富であるし、東方は洗練されたインダス文明の領域である。
実際にペルシア王宮は華美な装飾物に彩られ、金銀財宝は溢れんばかりであった。
対してギリシアは主要な産業はなく、農業に適した土地も限られていた。
端的に言えば、大変貧乏であったのである。
古代ギリシア人は、このペルシアの莫大な富を少数のペルシア渡航者からの伝聞をもとに、憧れを募らせていく。
さて、話をトロイア戦争に戻す。
ホメロス「イーリアス」を読むと、小アジアの都市国家トロイは「黄金満つイリオス(トロイ)」と呼ばれている。
トロイは経済的にかなり富裕な国家として描写されており、むしろその富裕さが原因となって滅ぼされたとも書かれている。
ここには明確に古代ギリシア人から見たペルシアはトロイに反映されているのだ。
と、同時に古代ギリシア人はペルシアを侮蔑している。
この侮蔑感情もペルシア戦争以降、顕在化することになる。
というよりも、ペルシア戦争以前には無かった感情かもしれない。
古代ギリシア人は、ペルシアをたびたび「女性」と重ね合わせて侮蔑する。
前述したように、古代ギリシアにおいて女性の権利は著しく制限されていた男尊女卑社会であった。
そのため、ぼくたちが想像する以上に、ペルシアを女性と重ね合わせること意味は強いのだ。
ペルシアは富裕である。
だが、そのために暑さにも寒さにも弱く、身体は軟弱であり、同時に精神的にも女々しいのだ。
また皇帝支配は帝国臣民すべてが皇帝の奴隷であるということを意味する。
他方、我々ギリシア人は、暑さ寒さにも負けない頑強な身体と、市民皆兵の自由意志と、強大な敵に立ち向かう勇気がある。
古代ギリシア人のこのメンタリティは改めてペルシア戦争の章で記述するとして、ここで注意を促したいのは、ペルシアを女性的だと指弾していることである。
「神話」の章でも言及したとおり、仮想敵としての女性は、古代ギリシアの歴史において通奏低音に流れている重要なポイントである。
それは女性=ペルシア=トロイにも当てはめられている。
そして同時に想起されたい。トロイア戦争の発端は、まさに女性問題からであったことを。
続く
「シン・みのくま勉強会(読書会)」とは、

以下、誰でも参加できます。
・facebookグループ;【内容】イベント案内、勉強会アーカイブ公開
・X(旧Twitter)コミュニティ;【内容】イベント案内、参加者間コミュニケーションツール
問い合わせはこちら
・主催者(みのくま)→X(旧ツイッター)アカウント
一緒に学んでくれる方、もしくはウォッチだけの方も大歓迎です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

