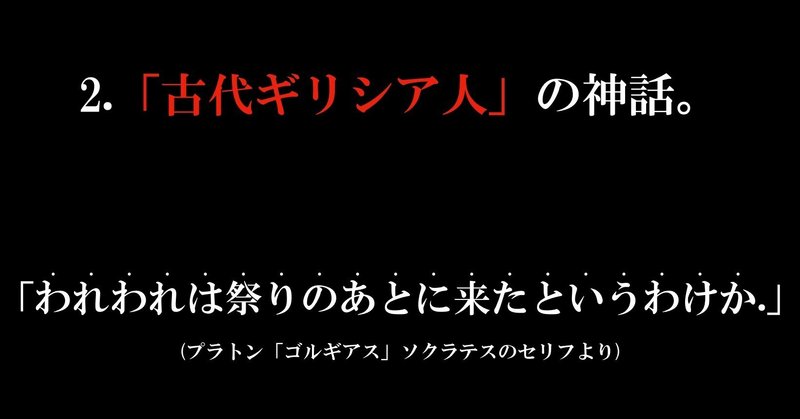
【①ギリシア人の神話】ぼくたちは古代ギリシア人と友だちになれるか
※【序章】ぼくたちは古代ギリシア人と友だちになれるか、の続きになります。
ギリシア神話とは何なのか
なぜ古代ギリシア人と友だちになるには神話を知る必要があるのだろうか。
それには幾通りもの答えがあるだろうと思うが、あくまでぼくの考えを書いておく。
古代ギリシア人にとっての神話は、例えば日本における古事記神代における神話とは違う、ある特徴があるように感じる。
それは、神話は古代ギリシア人にとって、あらゆる事象の構造を説明するものであったと思われるからだ。
例えば春夏秋冬の季節や雨や雷といった気象、地震や洪水といった天変地異、また人間の生殖行為や感情、運命や宿命といったことまで、古代ギリシア人は神話によって解釈した。
これは古事記とはまるで違う神話観である。
なぜなら、おそらく古代日本人は雷が鳴ったところで古事記を引用することはなかったろうと思う。
古事記はなぜ雷が鳴るのかを説明してはくれないからだ。
だが、古代ギリシア人は雷をゼウスの怒りとして神話から引用した。
古代ギリシア人にとって神話は生活にかなり密着したものであって、現代人にとっての科学と非常に近しい存在であったろうと思われる。
つまり、この世界の構造を説明する道具として、神話は利用されていたのだ。
また、ギリシア神話は古代ギリシア世界において常に再解釈されるものでもあった。
ギリシア神話に登場する神々は決まっており、またそのバックボーンもある程度定まってはいたが、旧約・新約聖書とは異なり、かなり柔軟に異文が作られることが常であった。
例えばギリシア悲劇は、ほぼその題材をギリシア神話から取っている。
しかし同じ題材でも作者によってかなりストーリーは変化する。
これは作者ごとに神話のどの部分を強調するかという世界観の違いを表すと共に、大胆な二次創作を受け入れる土壌が神話にあったということだ。
この辺りはかなり面白いところなので、また改めてギリシア悲劇を取り上げる際に記そうと思う。
このギリシア神話の柔軟性は、のちにイオニアのギリシア哲学者たちが自然科学を発達させる下地を作ることになる。

一般にイオニア自然科学は、無神論的な発想から科学を発達させたと思われがちだが、そうではない。
ギリシア神話の神々を代弁するという形式で自然科学を発達させたのだ。
これも同様に面白いところであるので、ギリシア哲学を単独で取り上げる際に言及する予定である。
話を冒頭に戻そう。
ギリシア神話を知ることの意義は、古代ギリシア人にとっての世界認識の前提を理解することに他ならない。
古代ギリシア人と友だちになるには、まずぼくたち現代人の世界認識の前提とは異なるということを、しっかり理解する必要があるのだ。
ギリシア神話の示唆するもの
とはいえ、ここで詳しくギリシ神話のディテールを記す紙幅はない。
そもそもぼくのような素人が手を出せる代物ではないのだ。
本来ならカオスやガイアによる世界のはじまりや、ティタン神族とオリュンポス12神の戦いについて書きたいところだが、それは作家や専門家にお任せするとして、ここではぼくの面白いと思う箇所を抜粋して記すこととする。

ギリシア神話の主神はゼウスであるが、その妻ヘラも有名である。
ヘラは嫉妬深く激烈な性格で、夫ゼウスが不倫するたび不倫相手に情け容赦ない報復を加える女神として、かなり人口に膾炙している。
実際、ギリシア神話を読んでみると、ゼウスの不貞云々を抜きにしても、ヘラはかなり人間にとって厄災でしかないシーンが多い。
だが、実はヘラに限らずギリシア神話の女神たちは全体的に人間にとって負の神であるケースが多いのだ。
これは天照大神という女神を主神とする八百万の神を奉じる日本人には驚くことかもしれない。
しかし、どうやらこの女神の表象は歴史的な背景がありそうなのだ。
もともとギリシアを含む南東ヨーロッパにおいて、女神信仰は盛んであった。
いわゆる「大地母神(グレートマザー)」信仰が、旧石器時代〜新石器時代において主流であったのだ。
だが、のちにインド=ヨーロッパ語族系の民族がギリシアに流入してくることになる。
この民族はどうやら男神信仰であったようで、大地母神信仰の先住民族と対立関係にあったようだ。
結果としてインド=ヨーロッパ語族系が抗争に勝利し、大地母神信仰を男神信仰で上書きすることでギリシア神話の原形が作られた。
なかでも大地母神信仰においてかなり上位の女神であったヘラは主神ゼウスの妻として置かれることになったようである。
このような神話の上書きの証左として、オリンピックで有名な聖地オリュンピアが挙げられる。
オリュンピアは古代ギリシアではかなり重要な聖地で、のちにゼウス神殿が建立されるが、もともとはヘラの神殿があったのである。
ヘラ以外の多くの女神も婚姻、父娘、類縁関係に習合されていく。
だが、この不穏な歴史的背景がヘラや他の女神たちに負の神としてのイメージを付与しているようである。

実はこの女神問題は、そのまま古代ギリシア世界におけるジェンダー問題と密接に繋がっているように思われる。
なぜなら、古代ギリシア世界は、明らかに行き過ぎなほど男尊女卑社会であるからだ。
古代ギリシアにおいて、既婚女性は外出さえも許されていなかったし、当然ながら多くの社会的権利も制限されていた。
アリストテレスを筆頭に、名だたる知識人による女性ヘイトは目を覆いたくなるほどである。
また、ギリシア神話やトロイア伝説(後述)に登場する人間の女性たちは、端的に言えばトラブルメーカーとして描かれる。
女性が戦争の原因になることは一度や二度ではないのである。
ぼくは、この古代ギリシアにおける女神/女性の描かれ方は、どうにも無理をしているようにしか思えない。
「一生懸命」、「がんばって」女性を貶めているように見えるのだ。
それは、この古代ギリシア世界の歪さ/不自然さ/不安定さを露呈しているように感じる。
と、同時に、これは「裏返し」なのだ。
つまり古代ギリシアの男性たちは、女性を過度に恐れている。
いや、もっといえば「女性的なもの」を恐れている。
彼らが恐れている「女性的なもの」とはなんだろう。
そして、かれらは「女性的なもの」から何を守ろうとしているのだろう。
次はこの問いを胸に秘めつつ「古代ギリシア人の伝説」という観点でアプローチしてみよう。
続く
「シン・みのくま勉強会(読書会)」とは、

以下、誰でも参加できます。
・facebookグループ;【内容】イベント案内、勉強会アーカイブ公開
・X(旧Twitter)コミュニティ;【内容】イベント案内、参加者間コミュニケーションツール
問い合わせはこちら
・主催者(みのくま)→X(旧ツイッター)アカウント
一緒に学んでくれる方、もしくはウォッチだけの方も大歓迎です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
