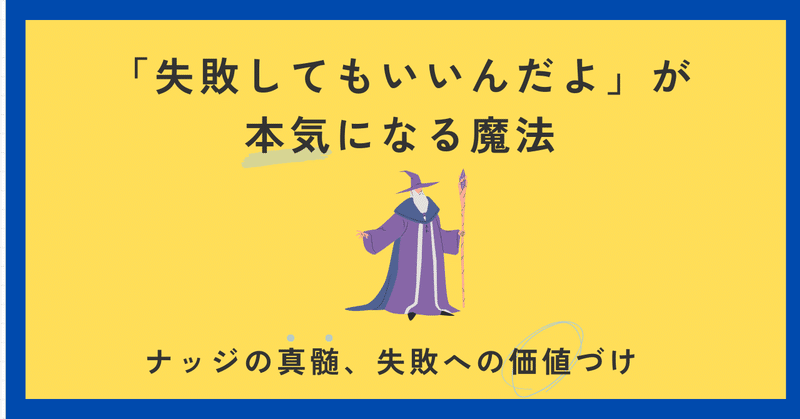
ナッジの真髄〜「失敗していいんだよ」が本気になる魔法〜/教育×行動経済学
教室でよく聞く「失敗していいんだよ」

「間違っていいから挙手してごらん?」
「失敗していいからやってごらん!」
よく教室で聞かれる「失敗」にまつわる言葉。
私は以前よくこの言葉を言っていました。
もちろん、誰も挙手しませんし、
やってみようともしませんでした。
当たり前です。
なぜなら私自身失敗が怖かったですし、
講演や研修で講師が時折出す難解な問いに、
すすんで挙手するなどあり得ません。
よくよく考えれば分かることでしたが、
子どもに
「失敗や間違いはとっても大事なんだよ!」
などと、よく薄っぺらい言葉をかけていました。
「人前で挙手をする」と「間違っていい」の分離

まず前提として、
「間違っていい」を理解していることと、
「人前で挙手をする」は
同義ではありません。
「間違うことが大切」であっても、
「人前で挙手することが大切」ではありません。
「人前で挙手をする力」を育てたいのならば、
別の体験と習慣を、
「間違うことが大切という思考」を
理解させたいのであれば、
別の体験と習慣を
用意しなければなりません。
私(教師)にとって待ち望んでいる
答えを絞り出すための、
その場限りの
「間違っていいんだよ」は、
子どもに「間違いへの恐怖」を
無闇に助長してしまっていたように
今では思います。
「失敗」をも価値づけるナッジ

今までnoteで紹介させていただいた
・あいさつナッジ
・そうじナッジ
・サポートナッジ(課題のある子どもサポート)
では、
「失敗」を自己評価できただけで
認める声がけができます。
そこで叱責はしません。
そして子どもが困っていれば
「失敗と気づいた、明日は何か変わるかもね」
「応援しているよ」
「何か先生にできることはあるかな?」
「こういうアイデアはどうかな?」と
自然と伴走者の形をとることができます。
「自分を客観視し、どうしていくか」
その過程に対して、
フィードバックをひたすら重ねていきます。
(フィードバックの詳細はお配りしている資料か、noteをご覧ください)
「失敗していいんだ」
「失敗も成功までのプロセスなんだ」は
初めてそこで子どもの腑に落ちます。
本音を話すと、
究極結果など
どうでもいいとすら思っています。
(本当はいけませんが)
しかし、児童自立支援施設から合わせて
実践2年目、結果は100%向上しています。

決してナッジを過信しているわけでは
ありません。
上記の条件が揃っている中で
上手くいかない時がきた場合は、
必ず分析していき、
ナッジの質をより高めていきたいと
思っています。
上手くいかないとき(失敗)を
待ち望んでいる気持ちさえあります。
勉強よりも簡単に「失敗」の価値を学べる生徒指導

勉強は最終的に理解が進まなければ、
充足感を得ることが難しいと思います。
もちろん自由進度学習やけテぶれ、
近日ご紹介しようと思っている授業ナッジで、
「失敗」の価値を学べるように
導くことは可能です。
しかし、
「そうじ・あいさつ・毎日の課題」は
程よい難易度でありながら、少し頑張れば
充足感を得られやすいものです。
失敗を含めたプロセスに価値があることを
伝えやすいものになっています。
「失敗していいんだよ」が本気になる魔法
気になった方はぜひ、
教室ナッジの他の記事をご覧ください。
ではまた次の記事で。
そうじナッジ↓
サポートナッジ↓
あいさつナッジ↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
