
あいさつナッジ〜強制ではない挨拶のもたらすパワー〜/小学校/指導
あいさつ指導であり、あいさつ指導でない
強制的な指導を一切入れることなく、
あいさつが飛び交う学級をつくる
「あいさつナッジ」。
そうじナッジも同様ですが、
これは、正直にいいますと、
あいさつ指導であって
あいさつ指導ではありません。
あいさつの価値や効力について
よく語りますが、
本人たちにとっては、
「誰からも強制されることなく、
できなかったことが徐々にできるようになる」
というプロセスに
価値を感じることができます。
自己効力感の生成と向上
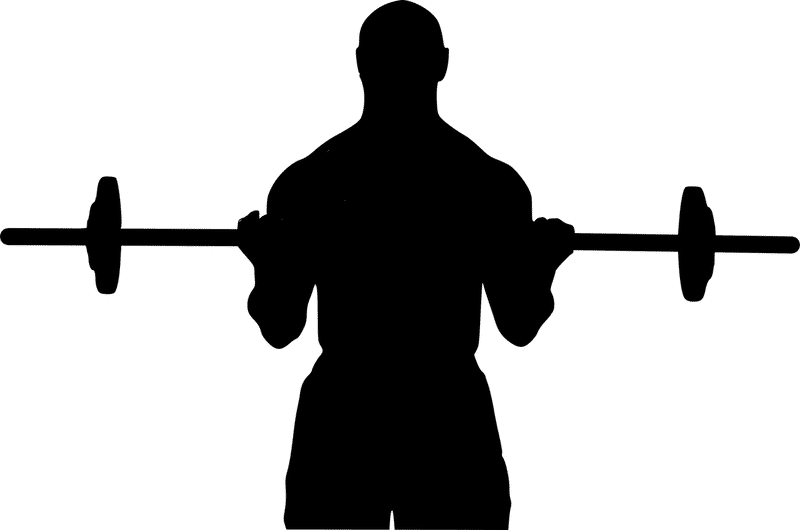
ナッジは、
自由意志の中で、
ゆるやかに意思決定者に判断や意思決定を
自由に行わせる余地を残しつつ、
よりよいと考えられる選択を
後押しするための工夫を指します。
これが、学校教育の中で
「自己効力感」を生成する上で
非常に相性が良いものとなります。
「自己効力感」とは、
「自分ならできる」
「きっとうまくいく」と思える感情をさし、
その気持ちが強い程、
「自己効力感が高い」状態だといえます。
一方で、話題によく上がる自己肯定感は、
自分自身の存在を肯定できる・認められる力です。
できるかできないかは関係なく、
できてもできなくても
自分を受け入れることを自己肯定感といいます。
もちろん、
自己肯定感を上げられるに越したことはないですが、
児童自立支援施設の勤務を経て、
それは非常に困難なことであると学びました。
そもそも、生育歴含め、
大人でも困難を極めるものだと思います。
「ありのままでいい」という
自己肯定感をあげることも
もちろん重要ですが、
「やればできる」「自分を信じる」という
自己効力感も同様にあげていくことが、
学級経営における
「不登校」へのアプローチの一つ
にもなると私は考えています。
誰でもできるのかもしれないナッジ

ナッジはその性質上、
自由意志を尊重するため、
「ゆるやかに促している」意識をもつこと
がポイントになります。
教師にとっては
強制的に正解を選択させたい気持ちを
「ガマン」する必要があります。
これはよく勘違いされやすいのですが、
「放置」とは全く異なります。
教師は、
「ゆるやかに成長するため」に
今の環境や声かけが適しているのか
常に考える必要があります。
つまり、教師の
「目的意識(何を大切にしているのか)」
「在り方」
「信念」
などが重要になってきます。
この辺りが、
けテぶれや自由進度学習と
リンクしている思います。
生徒指導におけるナッジと
非常に相性が良いと感じています。
よって、
「誰にでもできる」のは
間違いありませんが、
あいさつナッジをしておきながら、
「あいさつせんかい!!」と
声を荒げていてはできません。
単発ではない、習慣の計り知れない強さ

習慣のパワーに関する本が
多く出版されていますが、
まさにあいさつナッジは
毎日行うもの。
このパワーは物凄いものがあります。
毎日、
自由意志が尊重されている中で、
意思決定と行動繰り返すことで、
「あいさつに対する姿勢」は
見違えるように変化します。
挨拶が苦手な子どもに対しては、
安心安全な場が担保されるよう、
私のように大人になっても
声が小さい人がいることを伝え、
共感することを忘れません。
いつか挨拶しようと思える日がきた時の
準備をしていてね、
と伝えます。
今までの経験上ではありますが、
すぐに全員、
心を許している
誰かしらには挨拶ができるように
なると思います。
そこをぜひ価値づけてあげてください。
ではまた次の記事でお会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
