
漢字とひらがなのバランス/作家の僕がやっている文章術143
文章は難読漢字を使わないで書きます。
漢字は常用漢字を使い、それ以外の言葉はかな文字で書きます。
小説家志望のA君は、私に弟子入り志願を申し入れた青年です。
A君の許諾を受けて、彼の書いた原稿をここに紹介します。
漢字表記に着目して読んでみてください。
<文例1>
道路をすり足で散歩する老人を横目に畦へ曲がる。
今日は暖かく風もない。
思ったが遠くで鳥よけの黒ビニールが風に靡いていた。
畦をのぼるとアームを伸ばした車両が土手を塞いで配線工事をしていた。
スーパーで弁当を買って、荒屋が並ぶ、日陰が多く日向には笊に大根が晒された曲がりくねった路地を抜けると梨直売所の脇。
国道を跨いで浜に。

文章のクオリティは問いません。
表記に、難読漢字が使われていることに着目します。
漢字をかなに改めることを、出版界では「ひらく」と呼びます。
出版界の基本ルールに従って、難読漢字をひらいてみましょう。
<文例2>
道路をすり足で散歩する老人を横目にあぜへ曲がる。
今日は暖かく風もない。
思ったが遠くで鳥よけの黒ビニールが風になびいていた。
あぜをのぼるとアームを伸ばした車両が土手をふさいで配線工事をしていた。
スーパーで弁当を買って、あばらやが並ぶ、日陰が多く日なたにはざるに大根がさらされた曲がりくねった路地を抜けると梨直売所の脇。
国道をまたいで浜に。

執筆をする際には、多くの人がワープロ(ワードプロセッサ)を使うのではないかと思います。
変換候補に漢字が登場すると、つい漢字をそのまま使ってしまう人も少なくありません。
しかし常用漢字を使って、記事や創作文章を書くのが基本のルールです。
となるとA君の原稿に書かれている「あぜをのぼる」は「あぜを上る」が正しい表記になります。
どれが常用漢字で、どれが使うべきではない漢字なのか分からないうちは『記者ハンドブック』などの辞典を活用して、判別すればよいでしょう。

書き慣れてくると、漢字で書くべき表記と、かなにひらくべき表記の判断ができるようになります。
創作文章を書く人にありがちなのが、難読漢字をわざと使ってあたかもそれが、自己表現であるかのように、錯覚してしまうケースです。
陶酔と言いかえても通じるかもしれません。
A君にも、その傾向が見受けられました。
難しい言葉を書けば、文学である。
それは思い込みです。
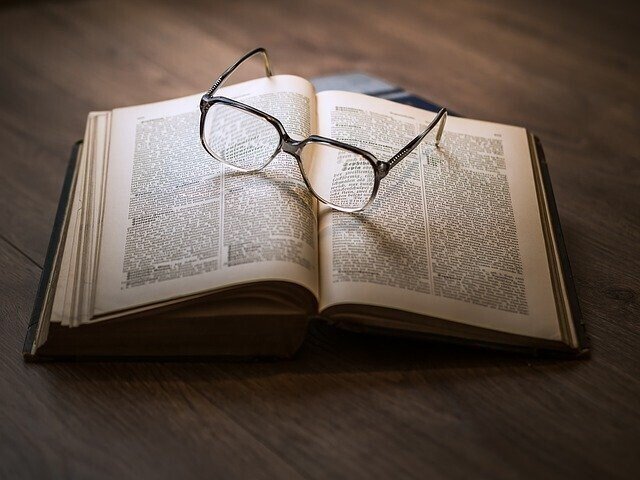
A君は、ひらくという表記のルールを覚えたので、読みやすい原稿を書けるように成長しています。
読みやすい表記であっても、読むにたり得る内容が書いてあれば、文学として成立します。
記事にも同じことが言えます。
読むにたり得る内容を的確に伝えためには常用漢字と、かな文字をバランス良く配置する必要があります。
使うべきではない漢字はひらきます。
表記のルールを守って原稿を書き続けると、ワープロの変換候補は記録され、蓄積されて、的確な表記が変換候補として提示されるようになります。
まず読みやすい文章を書く。
そのためには、漢字は常用漢字を使い、それ以外の言葉はかな文字にひらいて表記するルールを徹底しましょう。
サポートしていただけると、ありがたいです。 文章の力を磨き、大人のたしなみ力を磨くことで、互いが互いを尊重し合えるコミュニケーションが優良な社会を築きたいと考えて、noteを書き続けています。
