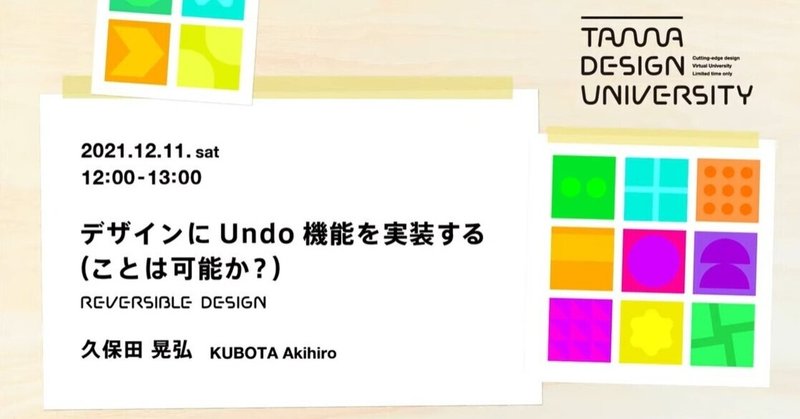
多摩デザイン大学「可逆デザイン」久保田 晃弘さん
昨年通った多摩美術大学が、期間限定「多摩デザイン大学 / Tama Design University」を開校しているので、受講しています。
この問いを頭に置きつつ、学んでいこうと思います。
「我々は新しい世界をどうデザインできるのか?」
我々は今、環境をはじめとした様々な課題や、テクノロジーによる急減な変化と向き合っています。その状況の中でどうデザインするかの前に、何をデザインしていくべきなのかを問い直していくことが重要ではと考えました。
▼講義詳細
多摩美術大学が、誰もが参加できる“デザインの大学”を期間限定開校。50の新たなデザイン領域を知る、講義プログラム公開
東京ミッドタウン・デザインハブ第94回企画展「Tama Design University」12月1日(水)〜12月26日(日) 会期中は講義プログラムを毎日開催。聴講無料。
▼講義一覧HP

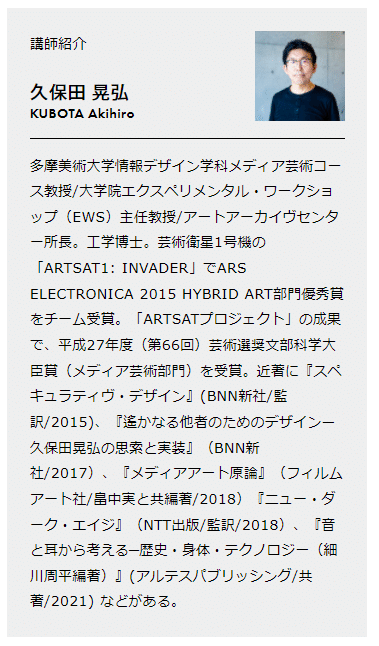
■テーマ
可逆デザイン「可逆デザイン - デザインにUndo機能を実装する(ことは可能か?)」
可逆=もとに戻りうること。もとの状態に戻りうること。ということで、さまざまなパターンのご紹介があります。
不可逆なことをするとエネルギー消費が伴うが、可逆な場合エネルギーは消費しないそうです。
ランダウアーの原理(1961)の解釈
・情報は必ず何らかの物理メディアで記録される。
↓
・情報と物質(物理メディア)、情報処理と物理法則の間には対応関係があるのではないか?
↓
・情報的に不可逆な演算を行うと、エネルギーの消費、即ちエントロピーが増大する
・情報を消去する際に、エネルギー消費が伴う。
・可逆な演算の場合、エネルギーの消費はない。
・不可逆な演算の際に最低限必要とされるエネルギーは情報の消去量によって推定することができる。
このあたり、理解が難しかったのですが、より詳しく知りたい人には下記が参考になるとのことです。
ファインマン計算機科学 第5章「可逆計算と計算の熱力学」
次に可逆デザインとはなにか、とのことですが、戻せたり、捨てなかったり、アクセス可能にしておくということが要件として挙げられます。
可逆デザイン(Reversible Design)
デザインにおけるフィードバック(と可逆ということは異なる)
・インタラクション
・リサイクル/再利用/再資源化
・ユーザーやマーケットからの反応
・ものにつくられるものづくり(存在論的デザイン)
戻せるデザイン
時々刻刻変化するデザインオブジェクトの状態を元に戻したり、戻した後にまた先に進める事。
可逆デザイン:デザインプロセスにおける不要なものを捨てない
≒非破壊的デザイン
(近代デザインにおけるシンプリシティーやミニマリズムの横行に疑念)
プロセスとしてのデザイン:デザインに「完成」概念は不要である。
デザインとアクセシビリティー
アクセス可能=可逆 アクセス不可能=非可逆
可逆デザインを実践するということは、デザインの対象や過程をできるだけ「アクセス可能」にすることに他ならない。
可逆デザインのためには、机の上は片づけない、データは決して捨てないことが重要だとおっしゃてましたが、わたしは机は片づけたいし、データはどんどん捨てる派です(笑)
そして、もっと気付いて、変えられるものは変えていきましょうともおっしゃっていました(また講義のなかで「気づきが大切」とでてきました・・!)
因果は認知的である。
・世界はさまざまな事象のネットワークである。
・その中には、可逆なものと、非可逆なものの両方がある。
・その中には、人間が気づくものと、気づかないものの両方がある。
・その中には、人間が変えられるものと、変えられないものの両方がある。
・気づいたもののうち、変えられそうなものごとを、原因とみなすことが多い。
・気づいたもののうち、変えられなさそうなものごとを、結果とみなすことが多い。
・本当は変えられるのに、そのことに気づいていないことが多い。
・変えられないものごとは、そもそもあまり気づかない。
・変えられるものを、変えられないと思い込んで諦めない。
・変えられるものに、もっと気づくようにする。
・ものごとを、なるべく変えられるようにしておく。
ほかにも、身の回りにある、巨大すぎて全貌が把握できないハイパーオブジェクト(ex 気候変動や、インターネットなど)
未来から見て現在を書くこと(予言としてのデザイン≒スペキュラティブデザイン→課題について考えるきっかけを提示する、問題提起)
遺伝子組み換えのPINKチキンプロジェクト
ユッカマウンテンプロジェクトなど多数ご紹介いただきました。
デザイン考古学についての考え方は下記。
デザイン考古学(デザインアーカイヴ学)
・デザインを反復可能にする=デザインを如何にして繰り返すか。
・反復によって、デザインプロセスの生(不可逆性)はどうなるのか?
・アーカイヴとは、過去にアクセス性=可逆性を(部分的に)実装するひとつの方法である。
・そのためにはあらゆるものをできる限り選択せずにアーカイヴしなければならない(何がアーカイヴされないのか?)
まとめとして、
可逆デザインとは、
1.可逆なデザイン=捨てないデザインの実践(自由意志)
2.可逆性をいかにデザインするか?=デザイン考古学(アクセス可能性)
で、締めくくり。
■所感
「可逆」という単語に初めて向き合った気がします。ここまで可逆、非可逆を考えたことなかったです。
なんでもかんでもアーカイヴするのはどうかと思いますが、アーカイヴし、アクセス可能としておくことは、未来の人類に役立つのかも?と思えました。
そういえば、noteもアーカイヴ資産ですね。インターネットおよびnoteの運営がなくならない限り、10年先も見返すことができそうだなーと思いました。10年先のわたしは今のわたしをどう思うのでしょうか。
未来を楽しみに、たまには未来から現在に思いを馳せ、生きていきたいと思います^^✨
最後までお読みいただき、ありがとうございます!スキ💛コメント、とても嬉しいです💛
