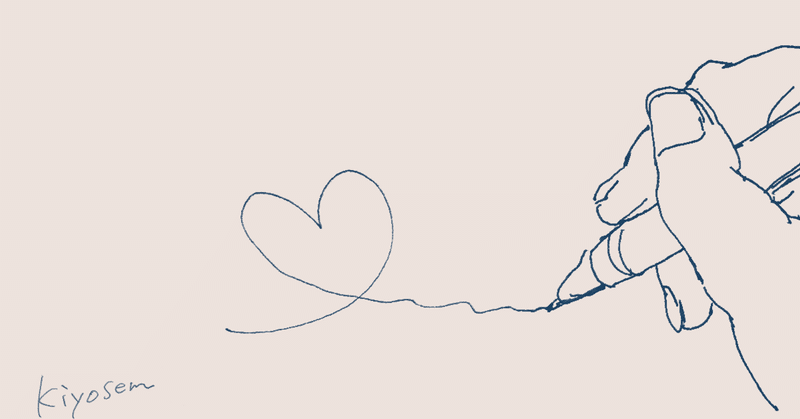
【読書感想文】私はナルシシズムでした|愛するということ
愛について考えてみたくなって、手に取った本。厳しく、スパルタな愛する技術を学ぶ書籍だった。2014年2月に放映された、100分de名著の内容も交えて、自分のための読書感想文とする。
"人を愛そうとしても、自分の人格全体を発達させ、それが生産的な方向に 向かうように全力で努力しないかぎり、けっしてうまくいかない。特定の個人への愛から満足を得るためには、隣人を愛せなくてはならないし、真の謙虚さ、勇気、信念、規律がなくてはならない。"
人格発達に通ずる活動に日頃意識を向けている方だと思うが、『愛する技術』の能力開発は大いに伸びしろがあると感じた。さらに、私はナルシシズムなのだなと気付くことになる。
愛は技術である
この本は、『愛は技術である』という前提に立っている。
◆2つの思い込み
1)愛の問題を、愛する能力の問題ではなく、愛される問題として捉える
2)愛の問題とはすなわち対象の問題であって能力の問題ではない
愛、それは人間の実存の問題にたいする答え
孤立こそがあらゆる不安の源であり、人間の最も強い欲求に通ずる。孤立を克服し、孤独の牢獄から抜け出したいという欲求。
私自身、深い部分に『孤立』『孤独感』というものを見ている。紐づく感情として『寂しさ』『悲しさ』のようなものを味わっており、特に扱うことを苦手に感じている感情?だ。
"つながりの切望は人の根源欲求"
昨年末頃から、しきりに『つながり』という言葉を用いているが、これは私だけの話ではなく人の根源欲求なのだと知る。
孤立したくないという欲求がこれだけ強いものであるので、他人と異なることへの恐怖、集団から離れる恐怖は大きいものとなる。
ゆえに、"自分以外の人間と融合したいというこの欲望こそが、人間のもっとも強い欲望"とされる。
"成熟した愛は、自分の全体性と個性を保ったままでの結合である。愛は、人間のなかにある能動的な力である。"
愛は能動的なものであり、なにより与えるものである。もらうことではない。
こういったGIVEの考え方は、なんとなく贈与論にも通ずるような気がしている。与えることに喜びを感じる、というもの。精神的にケチってはいけない、と100分de名著のなかで鈴木晶氏は言う。
関係性における愛
幼稚な愛は「愛されているから愛する」という原則にしたがう。成熟した愛 は「愛するから愛される」という原則にしたがう。
未成熟な愛は「あなたが 必要だから、あなたを愛する」と言い、成熟した愛は「あなたを愛している から、あなたが必要だ」と言う。
ここで、愛することって難しいなと思った。
母親からの母性愛で無条件に愛され、その後、父親から愛受けることが重視されていく。規律、父親の期待通りに動くなど、条件付きの愛を獲得することに必死になっていく。
その後の成長過程で、愛は受け取るものから、愛するものにシフトしていくというが、そんな体験はあっただろうか。
現在のメディア、広告は、むしろ愛されることばかり語る。人は愛されることを重視した考えで、他者に関わってくる。資本主義社会において、愛は商品化している。(もうすぐ来たるバレンタインはとても良い例)
すなわち、本来の愛から遠ざかっている。
とすれば人の成長過程において、いつ、愛する技術を学ぶプロセスがあったんだろう。
愛の修練
愛する技術を身に着ける条件:愛する技術の習得に最大限の関心を抱く
愛する能力の前提条件:ひとりでいられる能力
愛する技術を身に着けていくなかで、大切な要素のひとつに『集中』がある。”集中の欠如をいちばんよく示しているのが、ひとりでいられないという 事実”である。
集中力を磨くには、本当を語っていないくだらない会話を避ける、悪い仲間を避けることが大切だと語る。集中することとは、全身で現在を生きることである。どんなことにも集中すれば、覚醒がおきる。
自分に対して敏感でないと、集中力は身につかない。また、何事にも潮時があるので、やみくもに急いでも集中力、さらに愛する技術は身につかない。
人が死ぬまでの間に、人を愛する技術は身につくのだろうかと心配になるくらい、修行のような内容。それが率直な感想。
"愛を達成するためにはナルシシズムを克服しなければならない"
ここでのナルシシズムは、自分の内的世界が真実、正だと捉えること。私が〇〇なのだから、あなたも〇〇できるはず、という考え方だ。
暴露すると、私はナルシシズムである。この辺りの想像力、共感力が乏しい。ここが最も刺さったパート。
人間関係が広がることで、固有の繋がりは薄くなり、いつでも一方的にやめられる。間接的な人間関係はナルシシズムでもできる。ただ、直に会うのは近すぎると感じる。
100分de名著で鈴木晶氏が語っていた内容。まさに、である。人と向き合うこと、深く繋がることへの恐れがある。回避性愛着障害にも通ずるものがある、のかもしれない。
この点に、自分の愛する技術が磨かれる伸びしろを感じる。
"愛の技術の習練には、「信じる」ことの習練が必要"
"自分を「信じている」者だけが、他人にたいして誠実になれる。重要なのは 自分の愛にたいする信念である。"
"つまり 自分の愛は信頼に値するものであり、他人のなかに愛を生むことが できる、と「信じる」ことである。"
愛と傷つくことは、表裏一体。自分の愛という信念を否定されるかもしれない。それでも、嘘がなく、自分に正直になる信念を持ち続ける。
相手の心に愛が生まれるだろうという希望を自分に委ねる。それが自分自身の愛に対する信念である。(100分 de 名著より)
信念を持つには勇気がいる。そして、信念と勇気の習練は日常生活から始まる。自分がどんなときに信念を失い、どんなときにずるく立ち回り、どんな口実で正当化しているか。
人は意識のうえでは愛されないことを恐れているが、ほんとうは無意識のなかで、愛することを恐れているのだ。
これはきっと、自分の信念が否定されるかもしれない、そういう勇気が持てないことへの恐れ、のような気がした。だとすれば、わかる。
人を愛するということは、なんの保証もないのに行動を起こすこと
こちらが愛せばきっと相手の心にも愛が生まれるだろうという希望に全身を 委ねることである。
とはいえ、しんどくなるのは何故だろう?と思った。
以下、ハヤカワ五味さんの動画で語られていた内容。
与えることで満足していいはずだが、しんどくなるのは、許容値を超えた与え方をしているのかもしれない。
自分が与えることで、自分自身に返ってくる愛が足りないのかもしれない。なるほどね。前提として、自分自身も愛する対象に含めよ、とされているので、犠牲を伴う贈与は異なる質感になっていくのかもしれない。
まとめ
・1人でいられる能力こそ愛する能力の前提条件
・愛を達成するためには、ナルシズムを克服しなければならない
特にこのふたつが、自分のなかで愛という印象を変えるエッセンスとなりそうな予感がある。
私は元来、自己肯定感が低い方だと自認しているが、愛されることは生き延びることであり、孤独感を急速に癒してくれる印象がある。
ゆえに、孤独感をすべて他者、それも特定人物であるパートナーからの愛で癒そうとしてきた。そういうものの見方をするメガネ、レンズを持っていたのだと知る。
長い目で愛する技術を磨いていきたいし、なによりも自分で自分を愛することを学んでいきたいと感じた。
そのためには1人でいられること(20分以上の瞑想を推奨されたが苦手なので、ボディスキャンを再開していこうかな)、意思をもって能動的な行動の割合を増やすことを日常の些細なシーンから作っていくのが良さそう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
