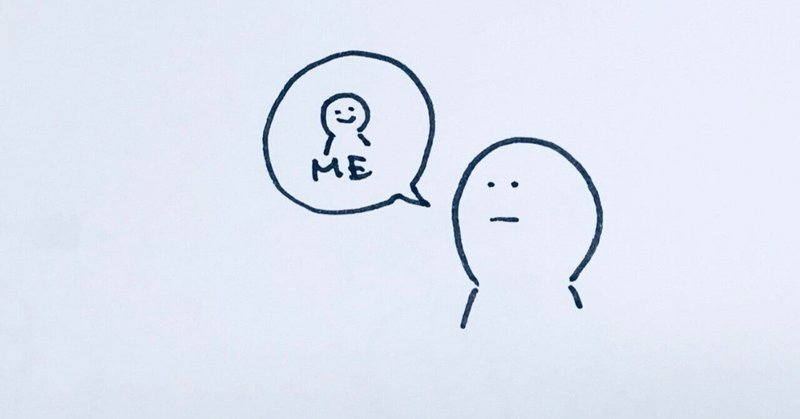
すべての起点は「顧客」から
✅ 3C分析で、自社の立ち位置を確認する
✅ ファイブフォース分析で、自社にとっての脅威を確認する
✅ ポジショニングマップで、自社サービスの立ち位置を確認する
どのフレームワークも重要ですが、それだけでは十分ではありません。
どんな時でも、サービスの相手である顧客が求めているものと合致しているかを意識する必要があります。
以前は
プロダクトアウト
… 市場や顧客視点よりも、企業側の理論を優先する考え方
が主流でしたが、
今は
マーケットイン
… 市場や顧客ニーズをベースにして、サービス提供していく考え方
が多く受け入れられています。
どんな業種であっても…
どんな職種であっても…
どんなポジションであっても…
ビジネスとして対価を得るためには、顧客のニーズに応え続けていく必要があります。
今回は、
✅ どのように顧客を設定するか?
について、考えていきます。
※ 今回は、以下の本を参考にしています。
勤めている会社の役員に勧められて読んだのですが、
これまでのマスを相手にした分析とは違うのが印象的でした。
すぐに実践できる内容が多く、おススメです。
「顧客」がいるのは、自社のソトだけではない
マーケティングは、製品企画や営業だけのものではありません。
総務・人事・経理・情報システムといった管理部門であれば、社内の人が「顧客」に当たります。
人事部門であれば「社員が社内研修制度を活用すること」が目的になったり、情報システム部門であれば「社員がグループウェアを活用すること」が目的になったりします。
顧客が決まれば、自然と戦略が浮かんできます。
あくまで「顧客」が先で、それから「戦略」です。
後述のロイヤル顧客に売上・利益が集中しているので、優先度が設定されることで、意識せずとも効率の良いマーケティングが実行できます。
「顧客」をセグメントに分けることから始める
営業手法を改善し続けるよりも、自社のサービスを必要としている顧客を探し当てる方が、みんなが幸せになれます。
マーケティングとは、究極的には「売り込まなくても、顧客側から『買いたい』と言ってもらう仕組みを作ること」が目的です。
顧客を分類する際は、自社サービスを知っているか/知らないかという「認知」の軸と、どれくらい使っているか(購入しているか)という「頻度」の軸を利用します。
① ロイヤル顧客
… 自社サービスを知っている かつ 利用頻度 高
② 一般顧客
… 自社サービスを知っている かつ 利用頻度 中~低
③ 離反顧客
… 自社サービスを知っている かつ 以前は使っていた
④ 認知・未購買顧客
… 自社サービスを知っている かつ 使ったことがない
⑤ 未認知顧客
… 自社サービスを知らない
顧客が分類できれば、各セグメントでどれくらいの売上・利益が上がっているかが把握できます。
(当然ですが、現状の売上・利益は①②で構成されています。)
ロイヤル顧客の「行動」「心理状態」を分析する
各セグメントの顧客が分かれば
次は、ロイヤル顧客が
✅ どのように自社サービスを知ったか?
✅ 他に、どのサービスを検討していたか?
✅ なぜ、その中で自社サービスが選ばれたか?
✅ なぜ、自社サービスを継続・リピートしようと思ったか?
を確認していきます。
ここでは、
△ ロイヤル顧客数社の「抽象化」された内容を分析
ではなく、
◎ ロイヤル顧客1社1社の行動・心理状態を「具体的」に分析
していくことが大切です。
複数社を並べて確認できるように、
共通のステップ
共通のフレームワーク
で見ていきましょう。
きっかけから「再現性」を見つけ出す
✅ 自社サービスを知った「きっかけ」
✅ 自社サービスを選んだ「きっかけ」
✅ 自社サービスをリピートした「きっかけ」
が分かれば、それを別の顧客で再現できるかを考えることができます。
ビジネスの基本は
「ルール」を見つけて、
その「ルール」を他の顧客で「再現」させること
です。
他の顧客で「再現」できることを確認できれば、より多くの稼働を掛けたり、より多くの費用を掛けたりして成果を「スケール」させることができます。
すべての起点は「顧客」から
非効率に思える部分もあるかもしれませんが、自社サービスの中心となる顧客に焦点を当てることで見えてくる景色があるはずです。
いただいたサポートは、より良い記事を書くためのインプットに使わせていただきます。
