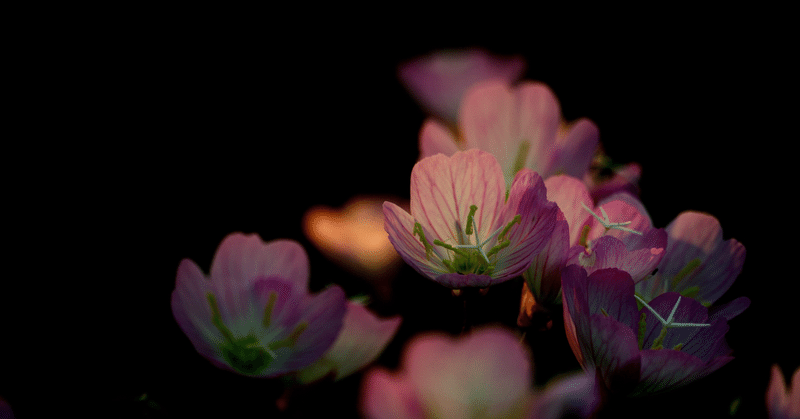
【勝手に現代語訳】三遊亭円朝作『怪談牡丹灯籠』第10話(全22話)
十
さて、かの伴蔵は今年三十八歳、女房おみねは三十五歳、二人の貧乏所帯でしたが、萩原新三郎のおかげで、何とか暮らせておりました。あるときは、畑を耕し、庭や表の掃き掃除などをし、女房おみねは萩原の宅へ参り煮炊き、すすぎや洗濯、おかずを拵え、お給仕などをしております。萩原も伴蔵夫婦には孫店を貸し、店賃なしで住まわせて、時々小遣いや浴衣などの古い物をやって、家来同様に使っていました。伴蔵は怠け者で、おみねは独りで内職をして、毎晩八ツ九ツまで夜なべをしておりました。
ある晩のこと、ところどころ穴のあいている蚊帳を吊り、伴蔵はござを敷いて独りで寝て、足をばたばたやっております。蚊帳の外では女房がしきりに夜なべをしていますと、八ツの鐘がボンと聞こえ、世間はしんとしております。時々、清水の水音が高く聞こえ、秋の夜風の草葉にあたり、陰々寂寞と世間が一体にしんといたしましたから、このときは小声で話してもよく聞こえるもので、蚊帳の中で伴蔵が、しきりに誰かとこそこそ話をしていることに、女房は気がつきました。行灯の下影から、そっと蚊帳の中を覗くと、伴蔵が起き上がり、ちゃんと座り、両手を膝についています。蚊帳の外に誰かが来て話をしているようですが、なんだかはっきりとはわかりません。どうも女の声のようですが、おかしいことだと、焼きもちの虫がグッと胸へ込み上げてきます。ただ、おみねは、自分はもう若くない、三十五にもなるのだから、と表向きは、嫉妬することもできません。あんまりな人だと思っているうちに、女は帰ったようです。何も言わず黙っていましたが、翌晩もまた女が来てこそこそ話をしております。こういうことがちょうど、三夜のあいだ続きましたので、女房ももう我慢ができません。ちょっと鼻が尖がり、鼻息が荒くなりました。
「おみね、もう寝ねえな」
「ああ、馬鹿馬鹿しい。こっちは八ツ九ツまで夜なべをしてさ」
「ぐずぐず言わないで、早く寝ねえな」
「えい、人が寝ないで稼いでいるのに、あんたは何をしているのさ。馬鹿馬鹿しい」
「蚊帳の中へ入んな」
おみねは腹立ちまぎれに、蚊帳をまくって中に入ります。
「そんな入りようがあるものか。なんて、入り方だ。突っ立ったまま入られちゃ、蚊が入ってしようがねえ」
「伴蔵さん、毎晩、お前のところへ来る女、あれはなんだい?」
「何でもいいよ」
「なんだか、はっきり言いなさいよ」
「何でもいいじゃねえか」
「お前はよかろうが、わたしゃ、つまらないよ。お前のために寝ないで、あくせく働いて稼いでいる女房の前も構わず、女なんぞを引きずり込まれては、私のような者でも我慢できないよ。わけを教えてくれたっていいじゃないか」
「俺も言おうと思っているんだが、言うとお前が怖がるから言わねえんだ」
「なんで怖がると思うんだい? お前が『かかあがいるから女房にできない』と言ったら、『そんなら、女房を捨ててしまえ』とかその女が何とか言ったんだろう。理不尽な女が女房のいるところへどかどか入ってきて、話なんぞをしやがって。もし刃物三昧でもする了見なら、私はただでは置かないよ」
「そんな者ではないよ。話をしても手前、怖がるなよ。毎晩、来る女は萩原様に、めちゃくちゃ惚れて通ってくるお嬢様とお付きの女中だ」
「お前はこんな貧乏所帯で、そんな浮気をしているのかい。それじゃ、お前がそのお付きの女中とくっついたんだろう」
「そんなわけじゃないよ。実は、一昨日の晩、俺がうとうとしていると、清水の方から牡丹の花の灯籠を提げた年増が先へ立ち、お嬢様の手を引いてずっと俺のうちへ入ってきたんだ。なかなか人柄のいいお人だから、俺のような者の宅へこんな人が来るはずがないと思っていると、その女が俺の前へ手をついて、『伴蔵さんとはお前様でございますか』と言うから、『わっちが伴蔵でごぜえやす』と言ったら、あなたは萩原様の御家来かと聞くから、『まあ、家来同様でございます』と言うと、『萩原様はあんまりなお方でございます。お嬢様が萩原様に恋焦がれて、今夜いらっしゃいと確かにお約束を遊ばしたのに、今はお嬢様をお嫌いになって、入れないようになさいますとは、あんまりなお方でございます。裏の小さい窓に御札が貼ってあるので、どうしても入ることができませんから、お情けにその御札を剥がしてくださいまし』と言うから、『明日きっと剥がしておきましょう』と答えた。二人は『明晩きっとお願い申します』と言ったら、すっと消えて帰った。それから、昨日は一日畑仕事をしていたが、つい忘れていると、その翌晩また来たんだよ。『なぜ、お札を剥してくださらないのですか』と言うから、『うっかり忘れやした。きっと、明日の晩、剥がしておきやしょう』と言って、それから今朝畑へ出たついでに萩原様の裏手へまわって見ると、裏の小窓に小さいお経の書いてある札が貼ってあるが、何をしてもこんな小さいところから入ることは人間にはできるものではねえが、かねて聞いていたお嬢様が死んで、萩原様のところへ幽霊になって逢いに来るのがこれに違いねえ。それじゃ、二晩来たのは幽霊だったかと思うと、ぞっと身の毛がよだつほど怖くなった」
「ああ、いやだよ。ふざけでないよ」
「今夜は、よもや来やしないと思っていたら、また来たんだ。今夜は俺が幽霊だと知っているから怖くて口もきけず、油汗を流して固まっていて、押さえつけられるように苦しかった。そうすると『まだ、剥がしてくださいませんねえ。どうしても剥しておくんなさいませんか。わたくしはあなたまでお怨み申します』と、おっかねえ顔をしたから、『明日はきっと剥します』と言って帰したんだ。それなのに手前にとやかく、こう焼きもちを妬かれては、つまらねえよ。俺は幽霊に恨まれる覚えはねえが、札を剥せば萩原様が喰い殺されるか、憑りつかれて殺されるに違えねえ。俺はここから引っ越してしまおうと思うよ」
「嘘をおつきよ。なんぼなんでも人を馬鹿にする。そんなことがあるものかね」
「疑るなら、明日の晩手前が出て挨拶をしろ。俺は真平だ。戸棚に入って隠れてら」
「そんなら本当かね」
「本当も嘘もあるものか。だから、手前が出なよ」
「だって、帰るときには駒下駄の音がしたじゃないか」
「そうだが、たいそう綺麗な女で、綺麗なほど、なお怖いものだ。明日の晩、俺と一緒に出な」
「本当なら大変だ。わたしゃ、嫌だよ」
「そのお嬢様が振袖を着て髪を島田に結上げ、とても人柄のいい女中が丁寧に、俺のような者に両手をつくんだ。瘦せこけたなんだか淋しい顔で、伴蔵さんあなた……」
「ああ、怖い」
おみねは恐怖のあまり、大きな声を出してしまいました。
「ああ、びっくりした。俺は手前の声で驚いた」
「伴蔵さん、ちょいといやだよ。それじゃ、こうしてやりな。私達は萩原様のおかげで、どうにか暮らせているのだから、明日の晩、幽霊が来たら、おまえが一生懸命になって、こう言いな。『誠にごもっともではございますが、あなたは萩原様に恨みがございましょうとも、わたくしども夫婦は萩原様のおかげで、こうやって暮らせているので、萩原様に万一のことがありましては、夫婦の暮らしが成り立ちませんから、どうか暮らせるようにお金を百両持って来てくださいまし。そうすればきっと剥がしましょう』と言いなよ。怖いだろうが、お前は酒を飲めば、強気になるだろう。私が夜なべをして、お酒を五合ばかり買っておくから、酔っぱらって、そう言ったらどうだろう」
「馬鹿を言え。幽霊に金があるものか」
「だから、いいんじゃないか。金をよこさなければ、お札を剥さない。金もよこさないで、憑りついて殺すなんてわけのわからない幽霊はいないよ。それに、お前に恨みはない。もし、お金を持って来れば剥してやってもいいじゃないか」
「なるほど。あのくらい、わけのわかる幽霊だから、そう言ったら納得して帰るかもしれねえな。うまくいけば、百両持って来る」
「持って来たら、お札を剥してやりな。お前、考えて御覧。百両あればお前と私は一生困りゃしないよ」
「なるほど。こいつは、うまい話だ。きっと持って来るよ」
欲というものは恐ろしいものです。明くる日のこの夫婦は、日の暮れるのを待っていました。日が暮れると、女房は「わたしゃ見ないよ」と言いながら戸棚へ入るという騒ぎです。
段々と夜も更け、伴蔵は茶碗酒でぐいぐい飲んでいます。酔っぱらって、幽霊と掛け合うつもりでいると、そのうち八ツ(二時)の鐘がボーンと不忍池に響いて聞こえます。女房は暑いのに、戸棚へ入り、ぼろを被って小さくなっています。伴蔵は蚊帳のうちで構えて待っていると、清水のもとからカランコロン、カランコロンと駒下駄の高い男が聞こえてきます。いつもと変わらず、牡丹の花の灯籠を提げています。伴蔵は朦朧としつつも、生垣の外まで来たなと思うと、ぞっと肩から水をかけられるような恐怖に震えました。三合呑んだ酒も無駄になってしまいました。ぶるぶる震えていると、幽霊が蚊帳のそばへ来て、伴蔵さん伴蔵さんと呼ぶ声が聞こえます。
「お出でなさい」
「毎晩参りまして、御迷惑なことをお願い申して、誠に恐れ入りますが、まだ今夜も御札が剥がれておりませんので、入ることができません。お嬢様がむずがり、わたくしが誠に困っているのです。どうぞ、わたしたち二人を不憫だと思われるのであれば、あのお札を剥してくださいまし」
伴蔵はガタガタ震えながら、なんとか答えます。
「ごもっともさまでございますけれども、わたくしども夫婦の者は、萩原様のおかげで、ようやくその日を送っている者でございます。萩原様のお体にもしものことがございましては、私共夫婦が困ります。どうぞ、のちのわたしたちの暮らしが困らないように、百両の金を持ってきてくださいませんか。そうしてくださるなら、すぐにお札を剥がしましょう」
伴蔵は言葉を発するたびに冷たい汗を流し、やっとの思いで言い切りました。両人は顔を見合せて、しばらく首を垂れて考えていましたが、お米が切り出します。
「お嬢様、それ御覧なさい。この方に恨みもないのに、御迷惑をかけて済まないではありませんか。萩原様は心変わりをされたのだから、あなたが慕う気持ちは無駄でございます。どうぞ、きっぱりあきらめてください」
「米や、わたしゃ、どうしてもあきらめることはできないよ。百両のお金を伴蔵さんに差し上げて、お札を剥がしていただいて、どうか萩原様のおそばへやっておくれよ」
お露はそう言いながら、振袖に顔を押しあてさめざめと泣いています。それが実に物凄いありさまなのです。
「あなた、そう仰しゃいますが、どうして、わたくしが百目の金子を持っておろう道理はございませんが、それほどまでに仰るなら、どうか才覚をして、明晩持ってまいりましょう。伴蔵さん、御札のほかにもありますよね。萩原様の懐に海音如来様です。あの御守りがあると、おそばへまいることはできませんから、どうかその御守りも昼のうちにあなたの御工夫で盗んで、ほかへ捨ててくださいね。できましょうか」
「へいへい、御守りを盗みましょう。百両はきっと持って来てくださいね」
「お嬢様、それでは明晩までお待ち遊ばせ」
「米や、また今夜も萩原様にお目にかからないで帰るのかい?」
お露は泣きながらお米に手を引かれて、すうっと出てゆきました。
◆場面
萩原新三郎の店子
◆登場人物
・伴蔵…萩原新三郎の店子
・おみね…伴蔵の女房
・お露…飯島平左衞門の娘、幽霊、萩原新三郎に恋焦がれている
・お米…お露の女中、幽霊
◆感想と解説
この章は「お札を剥がしてほしい」と頼んでくる幽霊に、生きている人間が百両持ってくるように持ち掛ける、というコミカルなシーンなのですが、ここでの夫婦のやりとり、伴蔵の発言が後半の伏線になっていますので、よく覚えておいてください。
第11話に続きます!
次の場面は飯島邸、お國の計略によって、孝助が大ピンチとなります。
チップをいただけたら、さらに頑張れそうな気がします(笑)とはいえ、読んでいただけるだけで、ありがたいです。またのご来店をお待ちしております!
