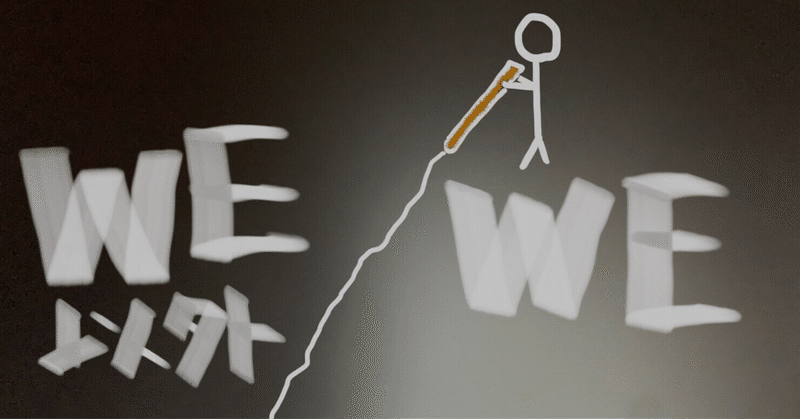
低所得家庭の子どもを排除する教師たち
以下は、西田芳正著『排除する社会・排除に抗する学校』(大阪大学出版会 2012)の6章の内容を要約したものです。
本節では、教育社会学者である西田芳正による「排除する学校・教師」という視点を整理したいと思う。そこから導かれるのは、学校や教師がむしろ積極的に、「貧困・生活不安定層」を学校から排除するような構造である。学校教育においては、教師は生徒に比してより大きな権力を持たざるを得ず、そこを前提にしなければ教育関係を築いていくことは不可能であることは、前節までの諏訪の議論で確認された。しかし、そこには当然「暴力性」も前提されており、さらに西田の研究では、その暴力性が「特定の階層の子ども」に集中した結果、その子どもたちを排除することに繋がることが指摘されている。では、以下に西田の研究を整理していこう。
まず、西田は「平等化装置」として期待されていた学校を取り上げる。第2次世界大戦以降の教育拡大に伴って学校には多くの子どもたち通うようになった。子どもたちは、学校で長期間の教育を受けることで、安定した職業に就くことが可能となり、それは「生まれ育った家族の階層的位置、親の職業」によって「子どもの人生が決まる」というそれまでの常識を打ち破るものであった。つまり、学校教育は平等化を推進する装置として大きな期待が寄せられていたのである。しかし、1960年代以降の欧米の調査によって、「上層の子どもは高い教育達成を遂げ、下層の子どもは低い教育達成に留まる」という傾向が繰り返し確認されると、学校は「平等化の装置」というよりも「(不平等の)再生産の装置」として捉える研究が蓄積されていく[1]。
西田は、「親の階層的位置が子どもの世代に引き継がれるのは何故か」という問いに対して、複数の視点から考察している。
① 経済的要因
子どもが長期間にわたって学校教育を受けるためには、学費の支出、学習塾などの費用、さらに、在学中の生活費負担(ここには就労していれば得られたはずの収入を放棄するという面も加わる)等、多大な経済的負担が必要となる。日本は先進国の中でも教育費の自己負担が突出して高く、進学を決める要因として「親の経済力」は最大の要因となっている。
② 文化的要因
ヨーロッパでは、階級間の家庭などによる文化差が、そのまま教育達成の違いをもたらすような「文化的再生産論」の研究が蓄積されてきた。例えば、階級間の言語スタイルの違いに着目したバーンスティン、家庭にストックされた文化資本が生活の中で身につけられ、学業成績につながる過程を解明したブルデューの研究などがある。
③ ①と②を踏まえた耳塚の調査
耳塚は、2007年に首都圏近郊の都市の小学6年生とその保護者を対象とした学力調査、生活調査の結果から以下の結論を導いている。
「だれが学力を獲得するのか(中略)親の富(学校外教育費支出、世帯所得)と願望(教育期待)が子どもの学力を規定していると言う意味で」、日本社会でも「選抜は業績ではなく、富を背景とした親の願望が形づくる選択次第だというのである」。
さらに、耳塚の調査によれば、「家庭の収入と子どもの学力の間に明確な関連」が示されている。そして、学習の土台となる文化的環境でも不利な低収入家庭の子どもは、長時間勉強しても成績はそれほど伸びず、条件に恵まれた子どもは勉強しなくてもそれを上回る成績をおさめているのである。ここからはわかるのは、「勉強の出来、不出来」は努力の差ではなく、環境・条件の違いによるということである。
次に西田は、(不平等の)再生産の担い手としての教師に注目し、その先行研究をいくつか紹介する。
① ベッカーによる「クライアント問題」(1952年)
アメリカの社会学者であるベッカーは、教師が直面するクライアント問題に着目する。人間相手の仕事において、対象であるクライアントが仕事の遂行にとって不都合な特性を持つ場合、その仕事に従事する者は困難に直面することになる。それがクライアント問題である。
学校においては、「中産階級出身の教師」と「下層出身の子ども」との間で対立が生じ、教師は困難さを覚える。「学習習慣がない、正しく育てられてない、教育を受けることに無関心」な下層の子どもたちに勉強を教えることは、教師にとっては確かに困難であり、そこに多大な労力が割かれることになる。そしてそれは、教師に不快感を抱かせて、結果的に適切な対応もできず、下層の子どもをその位置に留め、不平等の永続化に寄与してしまうことになる。
② リストによる「予言の自己成就」(1970年)
ベッカーにおける研究では、教師はまだ「受け身」として対応することになるが、リストはむしろ、積極的に不平等を創り出す存在としての教師を見出す。リストは、幼稚園教師によって学年の初めになされる「子どものグループ分け」に注目する。そこで基準となるのは、IQなどの知的能力ではなくて、中産階級出身の成功者である教師は、自らの階級において望ましいとされる特性を持つ子どもを「成功する」グループとして選び出し、そうすることで、下層出身の子どもはあらかじめ「劣った」グループにまわされてしまうのである。こうした客観的裏付けのない誤った期待に基づいて、教師は異なる形で子どもを扱う。
教師は、上層の子にはたえず注目し、注意深く享受するのに対して、下層のグループには指導そのものが少なく、「座っていなさい」などの統制的なものが主となる。結果として、上層の子の成績は伸び、下層の子は授業に参加しなくなる。結果として、そうした子どもの姿を「のろまでやる気がない」と見なし、さらなる統制を加える。当初の主観的なグループ分けが、結果的に「予言の自己成就」として機能することになるのだ[2]。
③ シコレル・キッセによる「階層的バイアス」(1963=1985年)
シコレル・キッセは、高校の進路指導を扱った研究をしている。教師は、生徒の能力別集団への配分過程を研究するなかで、それが「生徒の能力・成績」という要因によって機械的になされるのではなく、「生徒の生育歴・性格・風貌などの要因も含めた、教師の複合的な解釈・判断とそれに基づく指導」によってなされると指摘する。ここに「階層的なバイアス」が入り込んでしまう。例えば、中流以上の家庭の生徒の場合、テストの成績が悪くても「もっとできるはず」として判断され、低収入家庭の生徒の場合はそうした配慮はなされず、成績が良い場合も「この子にしてはできすぎ」と低い評価をされることがわかった。
上記①、②、③の研究は、再生産の現実に関心が向けられ始めた時期(1950〜1970年)のものだが、近年(2000年前後)でも同様の知見が確認されている。
④ ハーグリーブスの研究(2000年)
「ほとんどの教師と、マイノリティグループに属している多くの保護者との間には、社会文化的距離があることが明らかにされ」、「保護者としてのあり方を評するときには白人中産階級の規範を用いて」非難する教師の姿が明らかになった。
⑤ レヴィン&リーフェルの研究(1997年)
「ほとんどの教師や管理職は中産階級の出身で、貧困にまつわる個人的な経験をもっていない。貧しい地域に住んだこともない」、そのために、貧困やひとり親家庭の問題を認識しづらいのである
⑥ テス・リッジの調査(2002=2010年)
イギリスの90年代末の調査によれば、貧困家庭の子どもたちが学校内部で疎外と排除を経験していることが明らかになっている。教師との関係も疎外と排除をもたらしており、「教師は自分を目の敵にしている」と思うという回答が貧困層の子どもで高く、教師については、子どもたちの家庭背景を理解できず、教育費未納などを家庭の教育姿勢の問題に帰着させる傾向が指摘されている。
以上の研究は欧米のものである。翻って日本では、「階層や不平等問題」と「学校教育」の関連を扱う研究は少なく、教師を再生産の担い手とみなす研究もほとんど見られない。そこで西田は、関連するテーマの調査研究の結果を検討する。
① マイノリティへの差別
被差別部落で行った生活史調査では「特殊学級というところへ、地区の子どもを全部、先生は切り捨てて編入させていたんじゃないかなあと思います」という言葉があった。他にも「モノがなくなったらまっさきに地区の子どもが疑われた」などの声もあった。
② 貧困層への否定的まさざし
高度経済成長期以前の時期の1950年代の調査を2つ紹介している。
一つ目は、籠山京のものである(1953年)。籠山は一般家庭、貧困家庭、保護家庭の学童を比較し、学籍簿の社会的行動の記録を分析した。「この記録で判ることは、教師の眼に映る社会態度・生活態度が、一般と保護及び貧困ではまるで違っているということである。保護及び貧困では『友達なくひとりぽっち』、『暗い性質』、『乱暴』、『消極的』といった記録が特に多い」。
二つ目は、三宅和夫のものである(1957年)。三宅は、ホワイトカラー、ブルーカラー、日雇のグループを比較して、次のような傾向を明らかにしている。すなわち、高階層の子どもは学級内で高い位置を占め、教師と親密な関係をもち、優位的な立場から教師や生徒に要求する傾向にある(「もっと宿題を出して」「できない人にも当てて」と教師に要求し、一方で他の生徒には「きまりを守れ」「もっと勉強しろ」と要求する)。これに対して低階層の子どもは教師と疎遠な関係しかもてず、「いっしょに遊んでほしい」、「手をあげたらあててほしい」といった劣位的立場から切実な要求を教師にしているのである。
③ 教師が直面するクライアント問題
②はいずれも50年代から60年代の知見である。これらは今日において、その状況は変わっているのか。教師に対するインタビュー調査を数量的に分析した近藤邦夫の研究を見てみよう(1994年)。
教師が子どもを捉える視点は、生活態度、学習態度、集団の秩序を守る態度に関わる「子どもが『きまり』を守れるか否か」という視点と、「子どもが学習能力があるか、学習意欲があるか否か」という視点の2つに集約される。さらに、クラス内で自分と「ウマが合うー合わない」子どものグループ分けと、子どもの基本的生活態度がよいか悪いかという評価がほぼ対応していたケースも報告されている。これはつまり教師による評価は「(中産階級である教師自身と)価値観が近いかどうかで、評価が決まる」ということを示唆している。
このような構造の背景には、なかなか思うように事が運ばない教室の日常経験がある。「落ち着いて勉強に取り組み、クラスの秩序を乱さず、教師の言うことをよく聞いてくれる子ども」と「そうでない子ども」という見方が教師の中で強まり、教師の期待に応えてくれる前者の子どもたちには好意が湧き、期待や感情を逆撫でする後者の子どもたちには苛立ちが募る、と言うプロセスを近藤は推測している。これは、そのまま先述のベッカーによる「クライアント問題」が、教師の子どもたちへのまなざしを規定している事がわかる。
④ 教師の出身階層
教師には安定したホワイトカラー出身の者が多いため、低階層の生活は劣ったものと映り、また、劣ったものだと決めつける見方もある。だから、そのような地域の子どもの生活を理解することは困難ではないかという低階層出身の教師からの指摘もある。
[1] 最近だと、松岡亮二著『教育格差』(ちくま新書 2019)が新書大賞に選ばれるなど、「格差問題」が再び世間の注目を集めている。
[2] これに似た研究として、アメリカの教育心理学者のロバート・ローゼンタールによる「ピグマリオン効果」がある(ローゼンタール 1964)。これは別名「教師期待効果」とも言われる。ちなみに、これの逆の効果を「ゴーレム効果」と呼ぶ。
