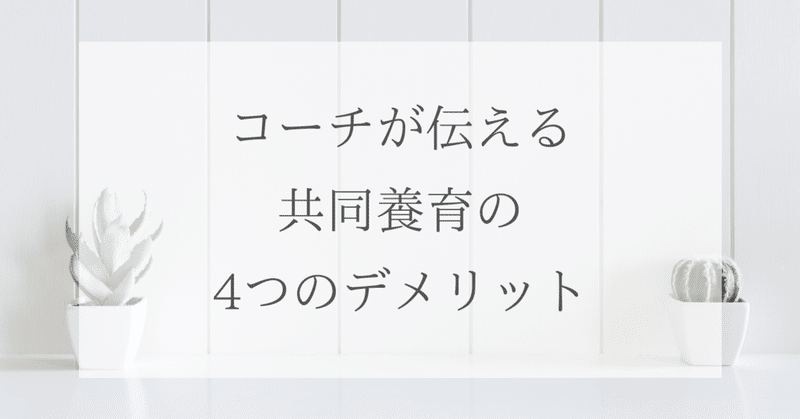
コーチが伝える共同養育の4つのデメリット
私が社会に伝えたい「共同養育」
前回のメリットに引き続き、(かなり時間が空いてしまいましたが…!)
今日はその共同養育のデメリットについて書いてみたいと思います。
共同養育の形態によってメリットとデメリットは変わってきますので、ここでは両親が積極的に子育てに関われる環境での共同養育について書いています。
また、現在の日本では「共同親権」への動きからも共同養育のメリットばかりが注目されがちですが、デメリットもあることを踏まえ課題を研究していきましょう。
メリットの記事はこちら⬇️
◆共同養育のデメリット◆
①子どもの気持ちの行き場がない
これは両親が高葛藤の場合にありがちなのですが、両親が自分の親としての立場を確保するあまり子どもが板ばさみになってしまうことがあります。
例えば子どもがもう一方の親の元から帰ってきた場合、どの程度あちらでの出来事の話を聞いてあげられるでしょうか?
長期休暇の計画、あちらの家でできることとこちらの家でできることの違い。
子どもは親のその時の言葉よりも、反応をよく感じています。
両親にとってはどちらも同等に子育てに関われるメリットの一方で、両親の関係性や共同養育に対する姿勢によって、子どもにとっては気持ちの行き場がないということも懸念されています。
つまりは共同養育を知り、共同養育ができる親になる、必要性が出てきます。
②進学や宗教について合意ができない
親がどこまで子どもの将来を管理するか、これはそれぞれだと思いますが、子どもの進学や宗教について拘りのある親は揉めてしまう原因の一つだと考えられます。
普段からお互いが頻繁に子どもと接していれば、こう育ってほしい、これを学んでほしい、などの思いは出てくるもの。
これについては主にどちらの親に決定権があるのかを事前に決めておくと良いでしょう。
単独親権制の中では法律上は親権者になります。
ただそもそもどちらの親も、進学も宗教も子どもにとっての目線で考え対話をすることを心がけたいものです。
子どもは親の所有物ではないので、道を用意するばかりではなく、その子が考え選択できる状態にするのも親の務めでもあります。
特に決定権のない非親権者である親は、子どもの心を聴き、子どもが自分の将来を考える力をサポートしていきましょう。
決して同居親の意向を否定したりしないよう心がけましょう。
③両親の居住の自由が限られる
半々や週末などの交替監護な共同養育をするには、子どもの生活圏内に住む必要が出てきます。
そうでなくても親が子どもを行き来させるのに負担にならない近距離であることは必須です。
そのため、自分の仕事や都合などに合わない不便な場所になってしまいかねないこともあります。
特に小さな田舎町などでは、仕事も限られたり、賃貸物件が少なかったりなどの問題のほか、ご近所さんの離婚した親への偏見や噂などがしばらくは付いて回ってしまいます。
が、数年経てば慣れます。
(経験談)
海外では子どもが住む家に両親が通って来ると言うケースもあります。
コロナにより働きかたも見直されるようになった日本でも、親が子育てと働き方をさらにちょうどよくできる社会になっていってほしいところです。
④DVやモラハラな相手とずっと関わらなければならない
おそらく社会が共同養育を懸念する一番の不安はここなのではないでしょうか。。
共同養育がなかなか浸透しないのも、こういった問題を孕んで離婚した元夫婦が多いという背景もあるでしょう。
DVやモラハラは、その程度や、子どもとの関係性を十分考慮しなくてはならないものだと考えます。
場合によっては共同養育ができないケースもあるでしょう。
共同養育をしていても、特にモラハラの場合は教育や普段の生活に関しことごとく文句を言ってくる可能性は十分に考えられます。
そうなると①〜③のデメリットがさらに強調されるということもあり得ます。
こういったケースの場合は支援機関を利用するなど、子どもとお互いがケアされながら子育てをしていく仕組みが必要になってきます。
DVやモラハラの形も様々なので一概に共同養育が良いとは言えませんが、できるだけ安心安全に親子関係を築き、子どもが自分の親を知りながら育つ機会を奪わないよう制度と仕組みづくりが求められているのが現状の課題であると考えています。
まとめ
以上、私が考える共同養育のデメリットを書いてみました。
見解はこれまでの経験とコーチとしてのものです。
実は私、共同養育にデメリットと言われるものはそんなにないのでは?というのを実感しているところなのです。
それはなぜかといえば、
デメリットというのは改善していけるものだからなのです。
共同養育という子育てをするビジョンを持った両親であれば、何より子どもの成長を中心に考えていくことができる状態にあることが前提であるので、今考える以上に現場はドライで建設的なのかもしれないとも思うのです。
そして実際私が行っている共同養育も、両親間はドライかつ建設的に行われ、私の娘父との間に円滑なコミュニケーションのできる関係性があるわけではありません。
かといって、激しく揉めたりお互いの子育てや生活に対し注文を付けたりというものでもありません。
(娘の名誉のために詳しくは書きませんが、とても高葛藤な相手であったことは確かです。)
それはお互いの子育てを疑わないということでもあります。
そして娘を大切にしているからこそ。
コミュニケーションもほとんどなく、かつては疑いしかない娘父で直接確認したわけではありませんが、今の形を認めて行ってくれていることが何よりの証拠なのだと確信しています。
もちろん必要最低限な業務連絡的なものはありますので、そこさえしっかりできていたら、あとは娘の意思を尊重し、親はそこをできる限りサポートしていくに過ぎないのです。
それでも何か課題にあたった時は、どうすることが最善なのかは常に考えていく。
実はそれは、婚姻中も離婚後も変わらないのではないでしょうか?
強いて言えば、婚姻中の子育てはそもそも相手との関わりと子どもの意思を尊重したものだったのでしょうか?
共同養育は改めて子育てを通じ、子どもと自分の幸せを考える手段です。
そしてその幸せは日々成長させ創っていくものなのです。
なので、もしもデメリットがあるとしたら、、、
それは共同養育をしても子育てに向き合えない両親が与える子どもへの影響でしょう。
私たちはここを考え続けていかなくてはなりませんね。
心を育むことに、絶対などないのだから。
見方が変われば、デメリットもメリットに。
メリットもデメリットに。
物事は常に表裏一体だからこそ、考えること。
子どもの心と対話をしより良い子育てをしていきたいものですね。
読んでくださり、ありがとうございました。
個別のご相談はこちらから⬇︎
子どもの心と対話する親子のコミュニケーションはこちら⬇︎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
