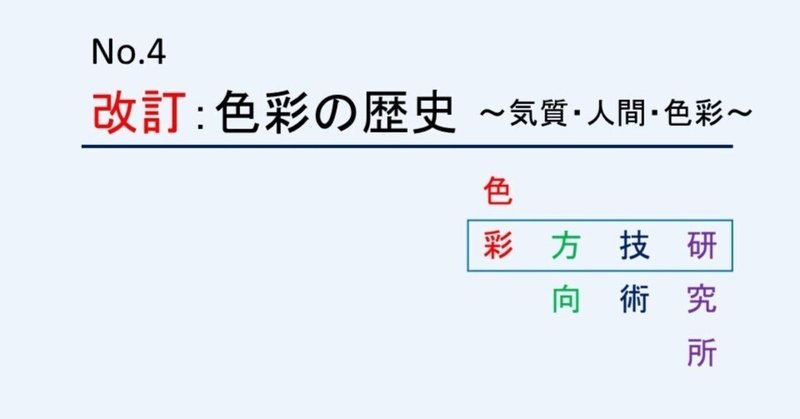
世界の表現「色彩の歴史」~No.4 気質・人間・色彩~
前回からの続きです。前回はゲーテがニュートンを批判した理由とそれぞれの違いを明確にしました。一応今回で「色彩の歴史」は終了となります。次回は「彩方技研にどうして気質・色彩がいるのか?」ということを話したいと思います。

前回より、色彩に関して2つの解釈と理論を知ることが出来ましたが、これは「見え方」に着眼して発展させたものでもあります。物体の色がなぜそもそもその色をしているのか?
どうしてヒマワリは黄色なのか?赤ではだめなのか?
というようなことに関してですね。ゲーテはこっち側にも進んでいき、独自の色彩論を展開していますが、それをさらに発展させた人物がいます。

発展させた人物は気質の歴史の最後にも出てきた「ルドルフ・シュタイナー」です。ゲーテも気質の歴史に出てきて、その後にシュタイナーが続いています。改めてどこかで「ルドルフ・シュタイナーについて」のまとめを出さなければならないと思っています。彼は神秘思想家、教育者、哲学者でありましたが、そもそもはゲーテ研究者でした。
気質や色彩を見ようとするのであればゲーテとシュタイナーの関係性についてより詳しく見ていく必要がありますが、これは簡単に「わかったぞ!」と出来る領域ではないことは彼らの残した書物を見てもらうのが一番早いです。

歴史的にシュタイナーはニュートン、ゲーテの後の人物です。おまけにシュタイナーは「理系」でもあります。これら2つの理論をしっかりと照らし合わせていき、理論的に色彩論を完成させています。
ただ単に色と言えば赤、青、黄色のようなものを想像しますが、彼が言う色彩とはつまり「色は世界の意味を表している」という存在になります。これだけでは「こいつ、何を言っているんだ?」と言われそうなので例を出します。

遺影の写真は本人ではありません。本人の色彩(像)です。当たり前の話ですが遺影があるということは本人はもうこの世に存在していません。ですが遺影を見たときに「本人を心の中に私たちは投影します」
つまり、遺影という色彩は「この世に存在していない人や時代を見せる色」または「過去の色」であるということが言えます。近代では写真というものがあるので掴みにくくなっていますが、徳川家康などの歴史上の人物で写真が無い場合、私たちはその絵姿を見て「これが徳川家康で戸幕府を開いた人だ」ということを認識して学習します。
ここから先、イメージをしてもらいたいのですが、大抵の人はさっき述べた通り、徳川家康の絵姿を小学生の時に見たことがあると思います。なのでこの場で急に徳川家康の絵を出したら多くの人が「ああ、徳川家康じゃん」と思います。そうすると付属して「江戸時代」が出てくるのは分かると思います。
これは書かれている物理的な色に対して、描かれていること以上の背景を私たちは無意識に、勝手に心の中に投影することが出来る証でもあります。これがニュートンの光学ではなく、ゲーテから発展させたシュタイナーの色彩論が導き出した色彩の本質であり、色彩の秘密です。

歴史の流れを整理したのが上の図になります。このような色彩の本質や秘密に彼が迫ることが出来たのはどちらか片側だけの理論だけは無く、両方を総合的に考えたうえで、シュタイナー自身が解き明かした「世界観」という物を色彩の世界とつなぎ合わせたからこそです。

それまでただ単純に現象として捉えていた色ですが、シュタイナーの色彩論によってそれらが「意味するもの」「表したい世界」を映し出しているということが分かるようになります。ルドルフ・シュタイナーは残した著書「色彩の本質◎色彩の秘密」という本にこんな言葉を残しています。

これは論理的に考えた時、世界の成分を理解することが出来れば、何かを作ることも表現することも自由自在でそれは可能である。ということです。何せ人はそもそも自然を利用してものづくりをしてきたのですから。。

そのため、ゲーテから繋がるシュタイナーが提唱した気質は色の本質を付け加えることで以下のような色分けをされています。

4大元素で「火」に該当する「胆汁質」色は赤色です。胆汁質の人間はリーダーシップやまとめ役に最適ですが、一方で怒りやすくなるため熱を発します。

4大元素で「土」に該当する「憂鬱質」色は青色です。外身からは全く分からないこの気質の人は「考えや行動が」全く理解できないことが多いです。それは輝きが内包されているため、それがうまく表現できないからです。

4大元素で「水」に該当する「粘液質」色は緑色です。粘液質の人たちはやや特殊な存在で、マイペース=自分のリズムを強く持っています。言い換えると「生きるということの力が強い」人たちになります。

4大元素で「空気」に該当する「多血質」色は黄色です。多血質の人たちは流行に敏感かつ、非常に魅力的な人間が多いです。とにかく動くことが彼らにとっては心地よいことになります。
この色が当てはめられた理由も根拠ももちろんあるのですが、これ以上詳しくやるためにはどうしても
「シュタイナーの世界観を探りにいかなければならない」
ということになります。
ただ、シュタイナーの世界観は非常に独特で複雑でこみ入った話になります。なのでとりあえず現象的な物から取り組んだ方が入りやすいと私は考えていますし、もし興味があってそれ以上を知りたいという方が居れば、それはメンバーシップの方でやろうと今のところ考えています。
次回の予定について
次回は気質・色彩の考え方がなぜ必要なのか?ということを書いた記事「彩方技研(株)「仮」の基盤理念について」を今年中に上げたいと思います。そして年明けから「シュタイナーの世界観に基づいた色彩現象」を出来る限り現象的に説明した物をアップしていこうと考えています。
気質の歴史、色彩の歴史共にかなり駆け足で書いてきてしまったので、年末年始の休みを利用して暇な方に読んでいただければいいなと思っています。
・メンバーシップ「彩方技研(株)「仮」」について
まだ会社ではありませんが、いずれは会社にしていこうと考えています。
このメンバーシップは「気質・色彩」を含ませて構築していく一枚の絵画のようなものを目指そうかなと考えております。
分かりやすく言えば「芸術」の分野です。
物語、絵、漫画、作曲、作詞、ダンス・・・
様々な表現方法がありますが、そういったものを組み合わせて何かの作品を作っていければなと考えています。
また、単に気質や色彩の世界を少し覗いてみたいという方、例えば○○を気質的に、色彩的に分析したらどうなりますか?というような質問でも構いません。
初月は無料です。その後は月100円となっています。
よろしければどうぞ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
