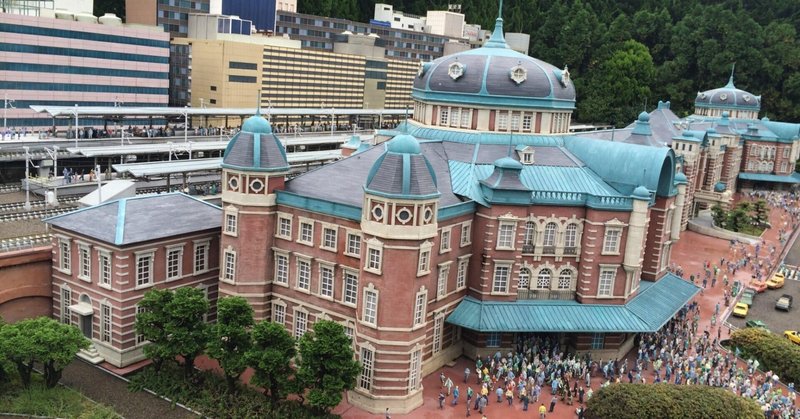
アラフィフ女性、ヒサンな転職活動のリアル⑧日本の「労働生産性」は高められるのか?
タイトルに「転職活動」を謳っていながら、今回も実際の転職活動について書いていないのは、実際の活動内容があまりにも地味だから。
エージェントに相談しつつ地道に進めております。。。
さて、今回は「日本の労働生産性」について考えてみたい。
というのも、「日本の労働生産性が低いのは、敬語を駆使して、バカ丁寧なメールを書いているからだ!」と、何かと主張している知人がいるから。
それを聞くたびに、「そうかもね」と笑いながら相槌を打っていたが、もちろん敬語のせいではなかろうし、「そもそもどの程度、低いのか」まったく知らなかったので、調べてみることにした。
なお、「労働生産性」とは、簡単に説明すると、「労働者一人当たり(または一時間あたり)の成果」、つまり「働いた人や時間に応じて、どれだけの成果を上げられたか」、ってことです。
労働生産性が低いと何が問題?
「労働生産性が高いというのは、無駄なくテキパキ働くってことでしょ? のんびり丁寧に働いた方が個人にとっては幸福なんじゃない?」と、考える人もいるかもしれない。
しかし、端的に言って、労働生産性が低ければ利益も少ないので、企業は少しでも利益を上げるために、従業員に薄給で長時間労働を強いることになる。
つまり、労働生産性の向上と、ライフワーク・バランスを取りながら豊かな暮らしをすることは、密接に関わり合っているのだ。
そもそも「日本の労働生産性」ってそんなに低いの?
とはいえ、そもそも日本の労働生産性は本当に低いのだろうか?
だいぶ前から「デジタル化による効率化」も進んでいることだし、近年は向上しているのではないだろうか?
そう思ってググってみると、「2021年 OECD諸国の労働生産性の国際比較」という資料が見つかった。
そして、残念ながら、本当に低かった。
2021年の日本の労働生産性は、OECD加盟国38ヶ国中、一人当たり28位、一時間あたり23位。米国の6割程度の水準である。
欧米先進諸国の中で最下位。ポーランドやエストニアといった東欧諸国と同レベルだ。
ちなみに一人当たりGDPは38ヶ国中23位。1996年には5位だったが、そこから年々低下している(なお、一人当たりではなく国全体のGDPはまだ世界3くらいである)。
じゃあ、どうしたら労働生産性は高まるの?
労働生産性が低いのは分かった。重要なのは「どうすれば高められるのか」だ。企業レベルでは、例えば以下のとおり、すでに多くの取り組みがなされている(導入が進んでいるのは大企業が中心で、中小企業ではどの項目も進んでいないようではあるが)。
①業務効率化の推進(ITツールの導入など)
②働きやすい職場づくり(テレワークや、育児・介護と仕事の両立を図れる社内制度の整備)
③長時間労働を防止し、個人的なスキルアップの機会を与える
いちばん大切なのは人を育てること
ただし、日本の経済状況の低迷ぶりを見ると、もっと大掛かりな取り組みが必要となる。具体的には、AIやロボット、ブロックチェーンなど、革新的な技術を利用した事業を生み出したり、画期的な雇用や就業のあり方を導入したりといった、「イノベーションの創出」だ。
社員の個人的な努力よりも画期的なIT設備を導入する方が、そして、一企業の取り組みよりも国策として制度を整備した方が効果的なのは、言うまでもないからだ。
しかし、技術的にも社会的にも、日本から新しいものが創出される気が全然しないのはなぜだろう(個人の意見です)?
大掛かりなイノベーションといっても、起こすのは人だ。
だが、多様性に乏しい日本では柔軟な発想をする優秀な人材がそもそも育ちにくい。日本ではベンチャー企業が生まれにくく、企業内で新規事業が育ちにくい原因の一つもそこにある。
心配なことは色々あって、例えば、博士課程に進む若者が減少している。博士号を取得しても就職に有利にならないという、これまた日本特有の事情が大きな理由の一つ。
さらに、影響力の高い論文数においても、日本は中国や欧米に遅れを取っている。
つまり、イノベーション創出に貢献してくれそうな人材が、欧米や中国と比べて、圧倒的に育っていないのだ。
加えて、少子高齢化に歯止めがかからず、若者は減少の一途をたどっている。
なんだか、世を憂えるお年寄りモードになってきたので(笑)、
今回はこのあたりで終わりにしておく。
結論としては、労働生産性のような大きな問題においては、さまざまな要因が複雑に絡み合い、それに伴う課題をクリアするまでに途方もなく時間がかかる場合が多い。
でも、個人には何もできないかと言えば、それは違うと思う。
すべての根底には「個人の意識」があり、個人の意識改革こそが、今求められているに違いないからだ。
「短く働いて、豊かに暮らせる社会」の実現は夢物語なのだろうか?
それを実現するための「個人レベルの取組み」について、これからも考え続けていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
