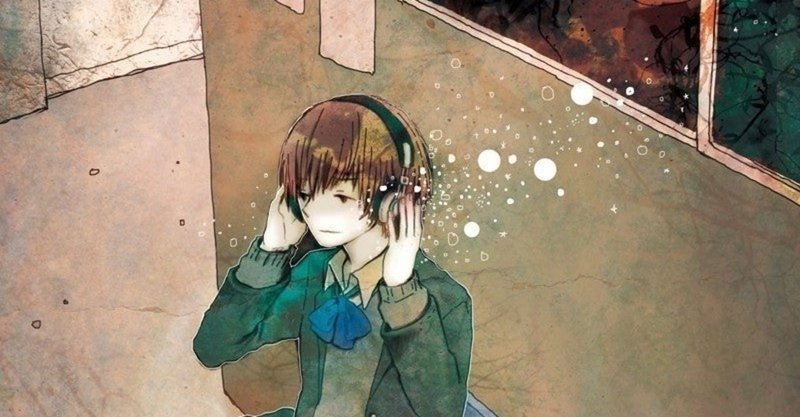
ドラマの中に「私」がいた――『17.3 about a sex』第2話感想
はじめに
――ドラマの中に「私」がいた。
正確には、私と似た性質の、アセクシュアル(※1)の少女が、これまでにないくらいリアルに描かれていた。今まで、アセクシュアルの人物を描かいた創作物にはいくつか触れてきたが、実写作品には出会ったことがなかった。そんな中、アセクシュアルを描写しているドラマ『17.3 about a sex』の存在を人づてに知り、実際に視聴してみた。今回は、アセクシュアルの人物が主軸となる第2話「そもそもセックスってしなきゃダメ?」の感想を書いていきたい。たった30分のドラマではあるものの、場面ごとに語りたいことが多すぎて、かなりの長文になりそうな予感がする。
※1 アセクシュアル・・・性的指向のひとつで、他者に性的に惹かれないことを指す。「性行為や性的魅力をそれほど重視しないこと」と定義する場合もある。
ドラマ概要
『17.3 about a sex』は2020年9月からABEMA SPECIALで配信されていた全9回のオリジナルドラマである。タイトルとなっている数字「17.3」は、性行為の初体験年齢の世界平均である17.3歳に由来している。
このドラマは1話完結型で、初体験、セックス、生理――と様々なトピックを取り上げ、青春恋愛物語と絡めながら、少女たちが“性”と向き合っていく物語だ。“性”に関する話題がタブー視されがちな日本で、女子高校生をはじめとする若年層をターゲットとして性体験や性教育をドラマの主題に取り上げるのは、きわめて革新的な試みと言えるだろう。
主人公は、咲良・紬・祐奈の仲良し女子高校生3人組である。彼女達は放課後のファミレスで、毎日のようにおしゃべりに興じている。「17.3」の意味を知った日を境に、彼女らの“性の価値観”が大きく揺らぎ始める。第2話「そもそもセックスってしなきゃだめ?」は3人組のひとりである紬にスポットを当てて展開する。
次の項から第2話の感想を述べていくが、ドラマの詳細にも言及するため、事前知識なしでドラマを楽しみたい方には、ドラマを視聴してからもう一度この記事に戻ってくることをおすすめする。
第2話内容紹介
「そもそもセックスってしなきゃダメなわけ?」
第2話は紬のこの問いかけからスタートする。セックスする理由を尋ねる彼女に対して、友人の咲良と祐奈は「人類繁栄?楽しいし!」と、あっけらかんと回答する。この答えに納得がいかず、紬が「自分はセックスしない」と述べると、二人は「もったいない」「人生損してる」と言いつのる。そのまま会話を続けていると、紬は思わぬ人物と再会する。その人物は、紬の幼なじみの康太だった。連絡先を交換したその晩、康太から映画に誘われた紬は、咲良たちに後押しされ、康太と映画に行くことに決める。
康太と恋愛映画を鑑賞した後、物語は急展開を迎える。映画の感想を言い合っている途中で、紬は康太から突然キスされ、「付き合ってほしい」と告白されるのだ。紬は茫然自失となって帰路に就き、道ばたで嘔吐してしまう。
後日、康太との出来事を咲良たちに話すと、「行って良かったじゃん!」と喜ばれ、紬が抱いた不快感や戸惑いには共感してもらえない。それどころか、「自分で映画デートOKしたのに、キスされて文句言ってるの?」と、紬に問題があるかのように返されてしまう。
自分は男友達と映画を見に行っただけなのに、男と女が二人きりで出かけたら、それはデートなのか。その先には、もはやキスやセックスしか存在しないのか。紬は他人が語る「恋愛のあたりまえ」に反発を抱き、席を立つ。
「絶対恋したら楽しいとか、普通はセックスするとか、
ほんと地獄。私さ、病気だから。もうほっといて」
咲良たちが普通で、「恋愛のあたりまえ」を理解できない自分がおかしいのではないか、と「恋愛できない 病気」で検索した紬は、「アセクシュアル」について説明したサイトに辿りつく。次の日、アセクシュアルに関する本を図書館で探すものの、めぼしい本は見つけられない。そんな紬に、静物の城山先生が声をかけ、生物室へと招く。城山先生が紬に差し出したのは、『見えない性的指向 アセクシュアルのすべて』という本だった。
城山先生は、恋愛にもセックスにも興味がないと吐露する紬のあり方を肯定し、アセクシュアルというセクシュアリティについて説明し、アセクシュアルの人々の中にも多様な生き方があることを教える。先生との語らいを通して、紬は、アセクシュアルについて、自分自身について理解を深めていく。城山先生の冗談めかした言葉が紬の心を軽くする。
「付き合ったらキスとかセックスとかしなきゃダメって、
そんなルール、馬鹿みたいじゃない?」
生物室の外では、咲良が先生と紬の会話を盗み聞きしていた。紬が抱える悩みを知り、咲良は自分の何気ない言葉が紬を傷つけ、あの怒りに繋がったのだと理解する。そして、咲良は紬に対して謝罪し、「紬のことをもっと知りたい」「友達、やめないでくれる?」と問いかける。「やめるなんて言ってないじゃん」。紬と咲良は和解を果たし、抱擁を交わす。
さらに、紬は康太の告白に対して、自分がアセクシュアルかもしれないことを明かし、恋愛関係にはなれないと告げる。そして、それでも構わないなら、また映画を見に行こう、と「恋人同士の紬と康太」ではなく「ただの紬と康太」として新たな関係を築こうと提案する。康太は紬の告白と提案を受け入れる。
物語終盤、舞台は再び放課後のファミレスへと戻る。いつもの3人組で会話しているが、祐奈の手には『見えない性的指向 アセクシュアルのすべて』がおさまっている。アセクシュアルについて知った祐奈が紬に対して謝ると、紬は誰だって自分の感覚しかわからない、他人の考えを知る良い機会になったと穏やかに返答する。――もしかしたら、セックスのない愛だって、あるかもしれないじゃん?――えッそれってロマンチック――、そんなやりとりと共に物語はエンドロールを迎える。
「私がおかしいの?」――紬と恋愛の隔絶
全体として、第2話「そもそもセックスってしなきゃダメ?」は、ひとりの少女のアセクシュアルの自覚と、周囲との軋轢の解消を、丁寧かつすっきりとまとめている良作だと感じた。アセクシュアルについて知る入門編として、多くの人におすすめできると思う。
特に、紬が感じる周囲とのずれや疎外感は、自分自身、とても共感できるものだった。「セックスしない」「恋愛しない」と言うと、決まって言われるのが、「もったいない」や「良い人に巡り会えたら変わる」「人生損してる」という言葉である。その度に、セックスしない現状に、恋愛をしない生活に満足している自分は、欠陥品なのか? 不幸せで哀れまれるべき存在なのか? と苛立ちや失望にも似た感情が芽生える。
ちなみに、私はチーズと生クリームが嫌いなのだが、それを伝えると、やはり「もったいない」「人生半分損してる」と言われる。その理論でいくと、私の人生の楽しみは半分どころか欠片も残っていないことになる。いずれにせよ、他人の尺度で自分の幸せを測られ、決めつけられるのは、居心地の悪いものである。第2話は、紬が自分の幸せを測る、オンリーワンのものさしを見つける物語とも言える。
この作品では、紬が感じる周囲とのずれが、映像的にも丁寧に描かれている。まず、私の目を惹いたのは、紬が様々な場面で身につけている黒いヘッドフォンである。教室で、廊下で、街中で――、周囲の音を遮断するように、身の回りにあふれる恋愛や性愛から距離を取るように、紬はヘッドフォンを耳から離さない。このヘッドフォンは、紬が周囲の人々から感じている疎外感の象徴とも言えるだろう。
紬と他者を隔てるヘッドフォン以外にも、紬と恋愛のコードとの隔絶を示す描写が随所にある。康太とのやりとりでは、その隔絶が露骨に現れている。
まず、康太はLINEで「大人っぽくなった」と紬にメッセージを送る。すると紬は「年取ったからね」と返す。ここで、康太が伝えたかったのは、自分は紬が大人っぽくなった、美人になったと感じている、異性として、恋愛対象として意識しているということだろう。しかし、思春期の男と女=恋愛という公式を持ち合わせない紬にとっては、自分が成長したように見えるらしい、という事実しか読み取ることができない。
さらに、康太は「今付き合っている人いるの」と問い、紬に恋人がいないと知ると、「全然関係ないけど、映画行かない?」と誘う。視聴中、この「全然関係ないけど」に対して、思わず「関係なくないだろ」と突っ込みを入れてしまった。康太としては、恋人の有無を確認することで、自分が異性として意識していることをアピールし、さらに二人きりの外出に誘うことで、相手が自分を恋愛対象として見ているか(脈アリか)を確認する意図があったはずだ。対する紬は友人たちの言動から、恋愛的な文脈をぼんやりと察するが、彼女が映画の誘いを了承したのは、あくまで友人として康太と映画が見たかったからであって、恋愛関係になることを受け入れる意図はまったくなかった。
映画鑑賞当日の、紬の服装にも、紬と恋愛の隔絶を示す演出がなされている。待ち合わせ場所に現れた康太は、紬の服装を見て、何かを言いよどむ。紬が着ているのは、彼女の私室に飾られていた、有名ロックバンドのTシャツである。デートだと思って来てくれているなら、女の子らしい、かわいい服装をするはず。――ひょっとして、オレ、男として意識されてない? そんな康太の声が聞こえてくるような一場面だった。紬からすれば、お気に入りのバンドTシャツを着ただけで、それ以上の意味などない。しかし、恋愛のコードを通して、彼女の意図は勝手に解釈される。
ところ変わって、映画館の場面では、前にもまして画面内にカップルが映りこむようになっている。映画館のチケット売り場で、廊下で、劇場内で、至る所に男女のカップルや夫婦が配置されている。この構図は、紬自身はそう思っていないが、周囲から見れば、紬と康太は映画館デートを楽しむ恋人同士に見えることを暗示しているようにも感じられる。ポップコーンに伸ばした手が触れ合う場面など、初々しいカップルの一幕そのものだろう。実際には、どぎまぎしているのは康太だけで、紬は何とも思っていない。ひょっとしたら、タイミング悪いな、くらいに思っているかもしれない。この落差もまた、一種の隔絶である。
そして、紬と恋愛の隔絶が決定的に示されるのが、康太と映画の感想を語り合う場面である。「面白かったね」と語りかける康太に対して、紬は「微妙」と返す。紬には、ラブシーンの登場人物たちの心の動きがまったく理解できなかったのだ。――なぜ、彼らは情熱的にハグやキスを交わすのか? ヒロインが夫ではなく、12年ぶりに再会した男を選ぶのはなぜ? 紬の疑問に、康太は「そういう流れだから……」としか返せない。この場面で、紬は自分の当たり前と、他人の当たり前が決定的に違うことを突きつけられる。
映画鑑賞のエピソードで興味深かったのは、紬が映画のラブシーンについて「まったく理解できない」と感じている点である。私もアセクシュアルを自認しているが、紬と私は少し違う。自分の場合、恋愛をメインテーマとする作品は好んで鑑賞しないものの、登場人物の恋愛における心の動きはある程度納得できる。これは、私が恋愛感情を持ちうるか、恋愛を実践できるかとは、まったく別の問題である。私は、過去の読書や鑑賞の経験値によって、「こういうシチュエーションになったら、こういう感情が発生して、こういう行動をとる」という流れを予測しながら、創作物の中の恋愛を捉えている。まさしく、康太の言う「そういう流れ」である。恋する登場人物に感情移入することは難しいものの、「そういう風になるのね」と他人事として楽しんでいる。そのため、恋愛感情を抱かないことと、恋愛感情を理解できないことの間には少々距離があるように感じている。
とはいえ、ドラマとして、紬のアセクシュアリティを強調するには、彼女が恋愛映画にまったく共感できないとした方が、より効果的である。上記のように、映画デート(?)をめぐる一連の流れには、紬と恋愛のコードを中心に回る世界のずれが、様々な演出・描写を通して表現されている。
この記事を読んでくださった方から、紬が恋愛映画を好きではないのは、単純に映画の趣味に合わないからであって、彼女のアセクシュアリティに直結するわけではないのでは?というご指摘をいただいた。確かに、全てを彼女のセクシュアリティが要因だと解釈するの、は些か乱暴な論かもしれないとハッとさせられた。ドラマ全体を見ると、紬の性質を強調する描写として働いていると考えられるため、上記の文章には加筆せず、追記に留めておく。(11/27追記)
「『変』って誰が決めるの?」――ドラマの中の救い
アセクシュアルに関する本が見つからず、悩んでいる紬に、飄々と声をかける城山先生。彼女は第2話における救世主である。先生が紬に差し出すのは、ジュリー・ソンドラ・デッカーの『見えない性的指向 アセクシュアルのすべて』(上田勢子訳、明石書店、2019年)という専門書だ。この本は、現在、日本語で読めるアセクシュアルに関する文献の中でも、最も詳細かつ丁寧にアセクシュアルについて解説する一冊と言っても過言ではない。
ちなみに、紬が図書室で手に取って戻したのは、おそらく『セクシュアリティの戦後史』(小山静子他編、京都大学学術出版会、2014年)である。この本は戦後日本の異性愛や同性愛の歴史について述べた論文集だが、私の読んだ限りでは、アセクシュアルを主題とした項はなかったと記憶している。残念ながらこの本は、アセクシュアルについて知りたかった紬のお眼鏡にはかなわなかった。
閑話休題。『見えない性的指向 アセクシュアルのすべて』は、自身のセクシュアリティに悩む私自身を救ってくれた一冊だ。紬が、インターネット検索で出会った「アセクシュアル」という単語を知っただけで満足して終わり、にするのではなく、より正確な情報を求めて図書室に訪れること、さらに、現実に存在するアセクシュアルの専門書を登場させること、これらの描写からは、制作陣の誠実さが読み取れると思う。私は、アセクシュアルという単語に辿りつき、専門書に出会うまでにそれなりの時間を要したが、このようにドラマが取り上げてくれることによって、アセクシュアルに関する情報を求めている人が少しでも救われるのではないかと思うと、とてもうれしい。
城山先生のアセクシュアルに関する説明も、非常に丁寧で、誠実だ。先生は、キスにもセックスにも興味がないという紬に対して、それは病気ではなく、セクシュアリティの一種だと説明し、彼女の不安を和らげる。先生の誠実さは、「アセクシュアルにもいろんなタイプの人がいる。一概には言えない」という内容のセリフに表れている。
アセクシュアルは、端的な言葉では定義づけできない、幅広い意味を持った概念である。英語圏では、他者に性的に惹かれない性的指向を指す。ドラマの中では性的指向と恋愛的指向の差異について詳しく説明されることはないが、アセクシュアルは、他者に恋愛的に惹かれるが、性的には惹かれないロマンティック・アセクシュアルや、恋愛的にも性的にも惹かれないアロマンティック・アセクシュアルなど、多様なあり方を包摂している。
城山先生は「パートナーがいる人もいる」という補足説明によって、アセクシュアルを自認するからと言って、生き方がひとつに限定されるわけではないことを示唆している。「『変』って誰が決めるの?」と問いかけるお茶目な城山先生の姿に、彼女のような大人が、悩んでいた頃の私のそばにいてくれたら、どんなに幸せだっただろうと感じた。
咲良や康太など、周囲の反応も、疎外感に苦しむ紬の心を救う。咲良は、紬がアセクシュアルであることを知った後に今までの言動を謝罪し、「紬のこともっと知りたい」と告げる。康太は、紬から恋人とは違う関係を築こうと提案されると、今度は紬が好きだと言っていた「SFの派手なやつ(映画)」を観に行くか?と尋ねる。二人は、紬がアセクシュアルであることを受け入れた上で、アセクシュアルという自分とは異なる種族の人間と見なすのではなく、自分の目に映る「紬という一個人」と向き合おうとしている。彼らのように、誰もが相手の生き方やあり方を尊重する世界だったなら、私たちはもっと息がしやすくなるかもしれない。
視聴後のひっかかり
先ほども述べたように、第2話はアセクシュアルについて誠実に説明していて、アセクシュアルの入門編ともいえる作品だと思う。しかし、少しだけひっかかりを感じる部分もあった。
まず、ドラマの中では性的欲求を持つこと(セクシュアル)と恋愛感情を抱くこと(ロマンティック)を明確に区別して説明していない。作中では、アセクシュアルが、より広義の意味の概念(アロマンティック・アセクシュアル+ロマンティック・アセクシュアル+etc...)として用いられる場面と、他者に性的に惹かれない性的指向を示す言葉として用いられる場面が混在している。
この揺らぎは、アセクシュアル=恋愛感情を抱かないという誤解を助長しかねないものである。厳密には、恋愛感情を抱かない性質はアロマンティックという言葉によって表される。後述のnote記事でも指摘されているが、このドラマにはアロマンティックの不可視化という問題が潜んでいる。30分未満のドラマにそこまで詳細な解説を求めるのは酷かもしれないが、定義の扱い方の重要性を考えさせられた。
また、ドラマの内容とED曲『ONE STEP』の歌詞の乖離には、少し笑ってしまった。まるりとりゅうがによるポップな恋愛ソング『ONE STEP』のサビの歌詞は以下の通りである。
ONE STEP
踏み出せる君は 誰より輝いてるよ
恋する乙女たち
今こそ幸せな花 咲かせようよ
恋愛に興味がない自分がおかしいのではないか、と悩む少女が主人公の物語にもかかわらず、異性愛の素晴らしさを礼賛する曲が主題歌となっている点には、痛烈な皮肉を感じる。早くも第2話でED曲を変えるわけにはいかないなど、制作側の都合もあるだろう。また。聞きたくなければ歌の部分をスキップすれば良いだけの話である。しかし、この第2話と主題歌の乖離には、世間の異性愛規範や恋愛規範、性愛規範の根強さを感じざるをえない。
ここまでの文を見ると、私が世の中のすべての恋愛ソングを蛇蝎の如く嫌っているように見えるかもしれないが、私も恋愛ソングは人並みに聞いて楽しんでいる。仮に、第2話が独立した映像作品として発表される場合は、このED曲にはならなかっただろうな、と思うのみである。
終わりに
ここまで、『17.3 about a sex』第2話「そもそもセックスってしなきゃダメ?」について自分が感じたことをつらつらと書き連ねてきた。30分のドラマに対して、ここまでの長さの感想が書けたことに、我ながら驚いている。それだけ、現実世界で、創作物の中で(ことに恋愛がテーマの作品の中で)いないものにされがちなアセクシュアルが、ドラマの主題として取り上げられたことがうれしかったのかもしれない。これからも紬が、恋愛や性愛にあふれた世界とどう向き合っていくのか、追いかけていきたいと感じた。咲良や康太が、紬のアセクシュアリティを、彼女の新たな側面として受け入れたように、「私とあなたは違うけれど、共に在る世界をつくろう」という風に、世界が進んでいくことを願ってやまない。
最後に、私が『17.3 about a sex』を視聴するきっかけとなった、羽田ゆきちさんのnote記事のリンクを以下に添付する。私とはまた異なる視点から展開される感想をぜひ読んでほしい。
私は、アセクシュアルを自認しているが、アセクシュアルは私そのものではない。私を構築する属性や傾向の一部、いわば個性だ。この記事を、アセクシュアルという個性を持つ、一人の人間の感想として受け止めていただけたら、幸いである。
(11/27 一部修正・加筆)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
