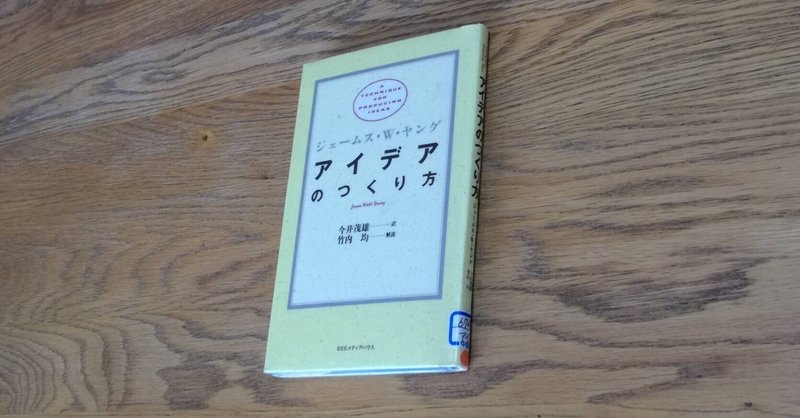
【読書録5】ジェームス・W・ヤング「アイデアのつくり方」を読んで
原書は、1940年代に出版されたかなり古い本である。私自身も読んだのは、少し前のことである。改めて、その時のメモを基にして記載していきたい。
『60分で読めて一生残る内容』というのは偽りのない本。
アイデアのつくり方
この本の内容は、「あなたは、アイデアをどうやって手に入れるのか?」という問いに対する著者の経験からの解。
解は、以下の通り非常にシンプル。
(1)アイデアとは、既存の要素の新しい組み合わせ
(2)既存の要素を新しい一つの組み合わせに導く才能は、事物の関連性を
見つけ出す才能。
従って、この解を公開したところで、実際に信用する人は少なく、また説明は簡単至極であるが、実際にこれを実行するのは、最も困難な知能労働が必要で使いこなすことは難しいから問題ないとのこと。
ではどうやったらそれができるか。それは技術で誰でもできる。
手順は、以下の5つ
➀資料を収集すること
・集める資料は、特殊資料と一般的資料
言い換えると、この事例に関連する業界などの特殊知識とリベラル
アーツ、学問的な理論などの一般的知識が必要ということ
・これは、生涯にわたる長い仕事であるとのこと
・著者は、カードに記載するのなどしてファイルしておくことが必要と
している
➁心の消化過程
その集めた資料を咀嚼することが求められる
③孵化段階。問題を放置するとも言っている
「そこでは諸君は意思の外で何かが自分で組み合わせの仕事をやるに
任せる」
➃アイデアの誕生。ふとした時にアイデアが出てくるひらめき見たいなもの
⑤アイデアの具体化
特に、➀➁の過程は、非常に納得。まさに『知の探索』。いろんなものを吸収して、それが意外なところで結びつき、法則性を生み出す。インプットは、大切。そしてそれを継続していくこと。
すごい解説
またこの本の面白さ、すごさは、竹内均さんの解説。(解説の方が長い?)
【印象に残ったところ】
・事物の新たな関連性を見つけ出す才能を、別の言葉で言うと「美的直観」(ポアンカレ)これまで無関係と思われていたものの間に関係があることを 発見すること。
・パレートの法則、デカルト、中庸は、一緒のことを言っている。重要なことに集中する。そのためには、それ以外のことには時間を浪費しない。
デカルトによれば、人々はそれぞれの人生の大目標をもっており、その実現に全力を注いでいる。しかしその一方で人々は、日常的な生活を生きなければならない。この場合に、その日常的なことがらの一つ一つについて熟考するのは面倒なことであり頭脳と時間の浪費でもある。こういう場合には、最も常識的で最も穏健な意見に従うのが良い。
どうでもよいことについては中庸の道を選ぶことによって我々は自分自身の人生の大目標に全力を集中しえる。
それを一言でいえば、「小事省事」(椎名悦三郎)
会社の中で、何か変革をしようとしてもなかなか進まないのは、ほかの部署の方からすると、プライオリティが低く、「穏当な道」(中庸の道)を選ぶためなのかな?となぜか納得。
最後の重要な事項という箇所も気に入った。
方法論や道具にこだわりすぎずに「直ちに仕事を始めよ!!」
➀好きなことをやり、➁それで食べることができ、③その上でそれが他人のためにもいささかの役に立っている人生が自己実現の人生であり、理想の人生。
方法論や道具は、あくまでそのためのもの。「直ちに仕事を始めよ!」
「実行するは我にあり!!」
一日一日を大切にしていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
