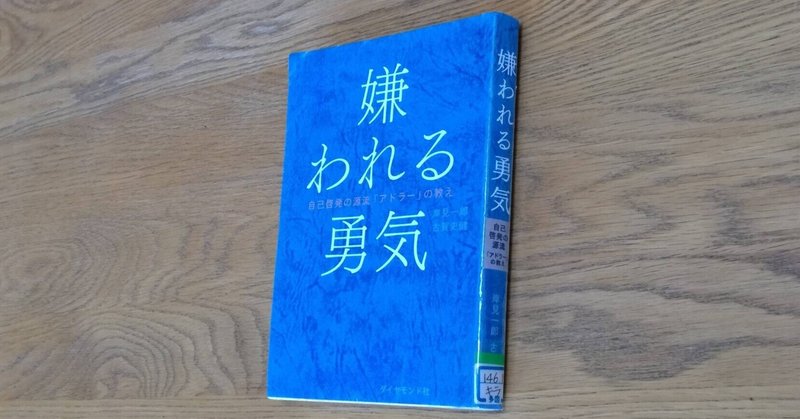
【読書録15】「禅」と「アドラー心理学」~岸見一郎・古賀史健「嫌われる勇気」を読んで~
先週の「嫌われた監督」に続き、「嫌われ」続きである。だが、そこに特に深い意味はない。
しばらく前のベストセラーであるが、今までタイトルから書いてあることを勝手に想像して、手に取らないでいた。
少し前に、著者の一人である古賀史健氏の著書「取材・執筆・推敲 書く人の教科書」が話題になっており(私は未読)、その古賀氏の本であることを知ってはじめて読んで見た。
「いま、ここ」を真剣に生きる
「世界は、どこまでもシンプルであり、人は今日からでも幸せになれる。」と説く哲学者と納得のいかない青年の対話形式で進んでいく。
読んでいて、「禅」について特段詳しいわけではないが、禅僧との問答であるかのような錯覚に何度か陥る。
「いま、ここ」を真剣に生きる。
人生とは、いまこの瞬間をくるくるとダンスするように生きる連続する刹那である。人生は、「線」ではなく、「点」の集まり
人生における最大の嘘は、「いま、ここ」を生きないこと
これまでの人生に何があったとしても今後の人生をどう生きるかについて何の影響もない。
ありのままの自分を受け容れる勇気を持つ。肯定的な「あきらめ」
「変えられるもの」と「変えられないもの」を見極める
「あきらめ」=「明らかに見る」の意味がある。物事の真理をしっかりと見定める
自らの生についてあなたにできるのは、「自分の信じる最善の道を選ぶこと」
一方で、その選択について他者がどのように評価を下すのか?これは他者の課題であり、あなたにはどうにもできない。
「いま、ここ」、「あるがまま」など、素人ながら「禅」を想起させる。
その他、ちりばめられた名言、「自己啓発の源流」と呼ばれる考え方について見ていきたい。大上段に構えたタイトルを付けてしまったが、私が印象に残った点および私の雑感についてのメモである。
人は、自らが意味づけした主観的な世界に住む
本書は、こんな書き出しから始まる。
人は、誰しも客観的な世界に住んでいるのではなく、自らが意味づけを施した主観的な世界に住んでいる。
井戸水は、年中10℃であるが、それを飲んだ人は、夏は冷たく、冬は温かく感じる。それは、どう人が意味づけるかと一緒である。
人は常に「変わらない」という決心をしている
そして、哲学者は言う。
性格や気質、ライフスタイルは、自ら選んだものであり、選びなおすこと可能である。
人は、いろいろと不満はあったとしても、「このままのわたし」でいることの方が楽・安心のため、「変わらない」ことを選んでいる。 「勇気」「幸せになる勇気」が足りない。
これまでの人生に何があったとしても今後の人生をどう生きるかについて何の影響もない。
確かに、そんな面はあると素直に受け止める。人からどう思われるかにとらわれ、その時その時の判断をしてきた結果が今をつくっている。今を変えるには、それ相応の「勇気」が必要である。でも「勇気」があれば今後はいかようにでも変えられる。
健全な劣等感とは
そして、勇気が持てない理由に「劣等コンプレックス」があるとする。それを理解するのに、「(健全な)劣等感」と「劣等コンプレックス」の違いを理解しなければならない。
人は誰しも「優越性の追求」(向上したいと願うこと、理想の状態を追求すること)という欲求をもつ。
「劣等感」は、それの対になるもの。理想に到達できていない自分に対し、まるで劣っているかのような感覚を抱くことこれらは、健全で正常な努力と成長への刺激となる。
それに対して「劣等コンプレックス」とは、自らの劣等感をある種の言い訳に使いはじめた状態のことである。例えば、わたしは、学歴が低いから成功できないなど。これは、「見かけの因果律」である。本来は、なんの因果関係もないところにあたかも重大な因果関係があるかのように自らを説明し、納得させてしまう。
「見かけの因果律」に陥るのは、ライフスタイルを変える「勇気」を持ち合わせていないからである。
「劣等コンプレックス」に似たようなものに、「優越コンプレックス」というのもあるそうである。自分が優れているかのように振る舞い偽りの優越感に浸ることを指す。例えば、著名人と懇意であることをアピールすることや 10本の指すべてにルビーやエメラルドの指輪をすることなど。
それらを自慢する人がいるとすれば、それは劣等感を感じているから。不幸自慢も同様であるという。確かにそういう人は結構いる。
それに対し、
健全な劣等感とは、他者との比較のなかで生まれるのではなく、「理想の自分」との比較から生まれる。今の自分よりも前に進もうとすることにこそ価値がある。
とする。
対人関係の軸に「競争」があると、人は、対人関係の悩みから逃れられず、不幸から逃れることができない。誤りを認めること、謝罪の言葉を述べること、権力争いから降りること。これらは負けではない。
他人との比較からは、何も生まれない。
たしかに、他者と比較しがちである。私も他者を見て、自分の恵まれなさ至らなさに落ち込んできたものである。
先日、TVで林修先生の森岡毅氏へのインタビュー見ていると
林修「自分の強みを活かせと私もよく言うが、『自分は、得意なものは何もないのでどうすればよいか』と聞かれるがそれに対してどう答えるか?」 森岡「それは、他者と比較するから。自分の中で好きなことを「動詞」で見つけると、強みは見つかる」
という場面があった。
「動詞」とは、「鞄」が好き「サッカー」が好きではなく、「(鞄を)デザインする」ことが好きとか「(サッカー)で作戦を立てる」ことが好きなことを動詞のレベルまで掘り下げること。そうすると、何が好きか、何が強みかは必ず見つかる。その強みを磨くのが重要ということであった。ハッとさせられる指摘であった。
他者の課題を切り分けよ
さて本書に戻ろう。
哲学者は、「我々は他者の期待を満たす為に生きているのではない」と承認欲求を否定する。そして、「課題の分離」をすることが重要であるとする。
この「課題の分離」というのが、この本の中核的な考え方である。
「課題の分離」とは?
自分の課題と他者の課題を分離し、他者の課題には踏み込まず、自分の課題に専念するという考え方
では、「誰の課題か?」はどう決まるのか。
それは、その選択によってもたらされる結果を最終的に引き受けるのは誰かで決まる者であるという。
例として、「子どもの勉強」を挙げる。勉強をしないことによる結果を引き受けるのは子供であって親ではない。従って、「子どもの勉強」は、子どもの課題である。親の課題ではない。ただこれは親は、放任するというのを意味するものではない。子供が何をしているかを知ったうえで、見守る。本人の課題であることを伝え、勉強したいと思ったときにはいつでも援助する用意があることを伝えるのが正しい態度であるという。
自らの生についてあなたにできるのは、「自分の信じる最善の道を選ぶこと」一方で、その選択について他者がどのように評価を下すのか?これは他者の課題であり、あなたにはどうにもできない。
「馬を水辺に連れていくことはできるが、水を飲ませることはできない。」
人は変えられない。自分を変えるのは自分しかいない。
そして本書のタイトルもこの文脈ででてくる。
「嫌われることを恐れるな」
他者の評価を気にかけず、他者から嫌われることを怖れず、承認されないかもしれないというコストを支払わない限り自分の生き方を貫くことはできない。
人生の意味
哲学者は、「人生の意味は、あなたが自分自身に与えるもの」であるという。
では、何でもいいかというと、「自由なる人生の大きな指針」はあるとする。それは、「他者に貢献すること」
そして、最後にこう締める。
あなたにとっての人生の意味「いま、ここ」を真剣に踊りきったときに明らかになる。「わたし」が変われば、世界は変わる。
共同体への所属感覚
最後にモヤモヤが残った部分も振り返っておこう。
自己への執着を他者への関心に切り替えるためには、「共同体感覚=社会への関心」が必要であるとする。
共同体のなかに自分の居場所があると感じられること「ここにいてもいいのだ」と感じられること=所属感を持っていることが人間の基本的な欲求である。
そして
所属感とは、ただそこにいるだけで得られるものではなく共同体に対して、自らが積極的にコミットして得られるもの
共同体へのコミットには、「わたしはこの人に何を与えられるのか?」すなわち他者貢献が必須の要素であるという。
所属感とは、生まれながらにして与えられるものではなく、自らの手で獲得していくもの「共同体感覚」=他者を仲間だとみなし、そこに自分の居場所があると感じられること
人は、「自分には価値がある」と思えた時にだけ勇気を持てる
人は私は共同体にとって有益なのだと思えた時にこそ自らの価値を実感できる。
確かに共同体・コミュニティへの所属感というのは、根源的な欲求であり、大切な感覚であり、所属感を得るには、「コミット」(その共同体への貢献、他者貢献)が必要であるというのは理解できる。
一方で、哲学者は、「他者貢献」と「承認欲求」を明確に区別する。
他者貢献は、貢献感を持てれば良い。実際に役立っているかどうかは他者の課題なので、求めるべきではない。それを求めることは「承認欲求」であるとして否定する。幸福は、貢献感から来るという。
そのように切り分けて考えられるか?貢献感を持つ以上、フィードバックはどうしても求めたくなるのではないか?相手の役に立たないことを貢献と言えるのか?
正直、ここはモヤモヤが残ったところである。
最後に
本書は、人間の認知や生き方の根本を問う内容であり、まだまだ掘り下げて考えてみたい。そして、古今東西、「人間どうあるべきか」について掘り下げると結局は、本質的なところで行きつく先は、変わらないのかなとも考えた。
もう少し掘り下げて考える材料として、本書の続編である「幸せになる勇気」や本書の著者である岸見一郎氏のギリシア哲学の本なども読んでみたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
