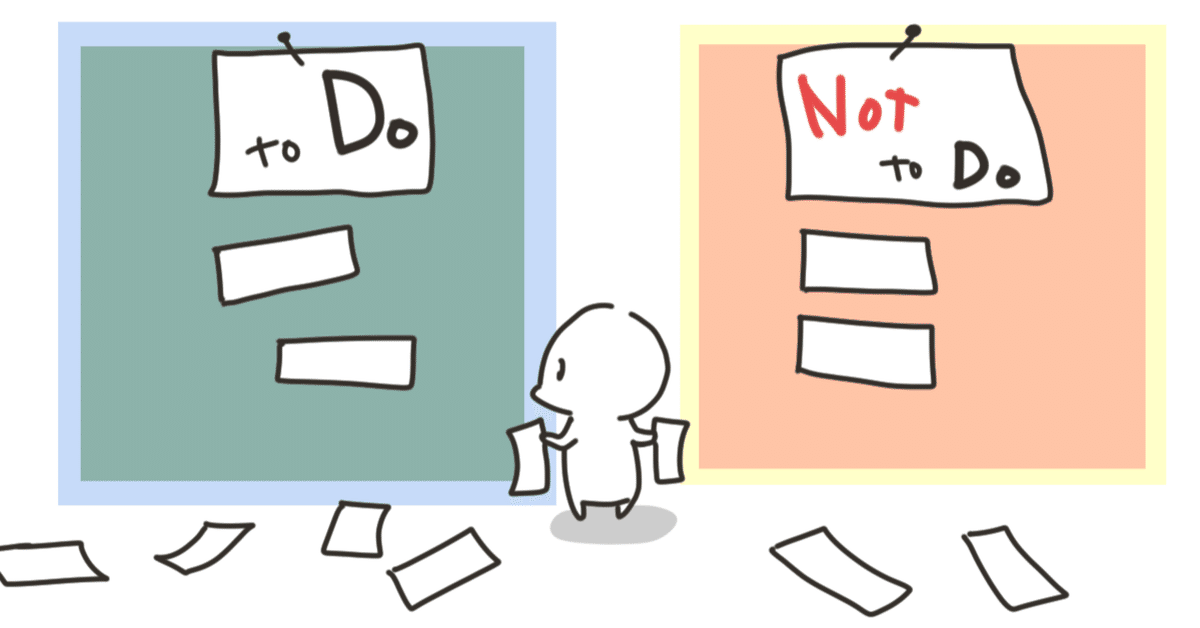
誰の都合なん?<440/1000>
【ラジオ体操742日目】
【ニコチンレス生活463日目】
こんにちは。
効率を上げるために何をしたら(やめたら)いいのかを考えるのは好きだけど、効率の良さを得ることでお客さんを不便にさせることは許すことが出来ない偽善者コマリストです。
今日は『”楽”を追求するあまり、本質を失ってしまう恐怖』というテーマで書いていきたいと思います。
少しでも効率よく進めるためには、どうするのが良いか。
そんなことを日頃から考えながら仕事をしているという真面目な方が多いと思います。
業務の効率化を進める際には、新しいものを追加するのではなく、今やっている”何か”をやめることから始める場合が多いはず。
ところが、やめようとしている"何か"が何のために存在しているのかという部分を検討せずして進めてしまうと、あとで痛い目に合うことが多いわけで・・・。
今日は、効率化や改善を推進することは素晴らしいことではあるが、その結果、誰にデメリットが生じるのかという視点を忘れるとこれから厳しくなるよね~というお話です。
良かれと思ってやった結果、悪い状態を引き寄せてしまうって、悲しいですよね。。
改善の原則

まずは、一般的な知識として知っておいたら少しだけドヤれるフレームワークを書いておきます。
それは、業務効率をあげたり、生産性を改善する時に参考になるもので、改善の4原則と呼ばれています。
その名も、
『ECRS(イクルス)の原則』
#ハンバーガーの中にあるやつ
#それはピクルス
このフレームワークは、もともと製造業における業務改善のために生み出されたものだと言われていますが、その起源についてはどこを探しても見つかりません笑
とはいえ、私がこの言葉を初めて聞いたのは13年前なので、少なくともそれ以上前から存在している割と古いものだと思います。
この原則は、
Eliminate・・排除
Combine・・結合
Rearrange・・交換
Simplify・・・簡素化
この4つの言葉の頭文字をとったもので、業務改善を進めていくためには、これらの項目をこの順番に進めていくのが良いとされています。
『排除』は、今やっている業務をやめられないか検討すること。
『結合』は、2つ以上の作業を1つにまとめることが出来ないかを検討すること。逆に1つのものを2つ以上に分割できないかということも同時に検討するのが良いとされています。
『交換』は、仕事の順序や使用する道具の配置を変えることが出来ないかを検討すること。順序の変更だけでなく、並列で処理できないのかということも検討するのが良いとされています。
『簡素化』は、作業を簡素化したり、自動化することが出来ないかを検討すること。
簡単に説明してみましたが、やはり重要なのは、『やめること』から最初に検討するという部分です。
やめることに勝る効率化は無いということですね。
#そりゃそうだよね
この原則は、かなり昔からあるものなんですが、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められるようになったことで再び注目を集めているようです。
#原理原則
#不変
効率の悪い仕事を何とかしたいと考えている人は、是非参考にしてみて下さい。
誰の為の改善か

ここまで、業務改善や効率化を進めていく上で参考になる原則の紹介をしてきましたが、今日の本題はここからです。
国内のほぼ全ての会社において、業務の効率化や改善はすすめられているわけですが、一歩間違うと会社としての信用を失いかねない事態を招くことに繋がります。
前半に書いてきた通り、業務改善を進めていく際には『やめること』を最初に検討するわけですが、この時にやってしまいがちな判断があります。
それは、やめることによって発生するメリットとデメリットだけを基準に判断してしまうということ。
一見すると、何が問題なのか分かりづらいですが、『業務そのものの存在理由』を考慮していないということに問題があります。
例えば、富士山に登るということを考えた場合、効率を追求するのであれば山頂まで自動車で乗り入れ可能にしたり、ロープウェイを設置するという打ち手が考えられます。
この時にメリットとデメリットだけを考えると、
(メリット)
・登山者が早く山頂にたどり着ける
・富士登山が身近になる
・登山客が増加する
・物販等の業者を介入させられる
(デメリット)
・ゴミの量が増える
・投資が必要になる
・人件費がかさむ
こんな感じでしょうか。もちろん時間をかければもっとたくさんのメリット・デメリットを出せると思います。
#ブレスト
#人数をかけたい
では、こういったデメリットを考慮しても、登山客増加による大幅な収益増加によって、デメリットを補うだけの効果が見込まれると判断した場合、この改善は実行すべきか?
もちろん答えはNOですよね。
車やロープウェイで山頂まで行けてしまったら、富士登山そのものの価値が大きく下がることになるはずです。
一見、効率は悪いかもしれませんが、自分の足で歩くという行為があることで富士登山の価値が維持されて、登山客に選ばれているわけです。
#あらためて言わなくても
#当たり前のこと
とはいえ、一定の効率化は推し進められていて、5合目までは自家用車で行けるんですけどね。
この富士山の例のように、業務には【必要なムダ】というのが存在しています。
これを排除してしまうと、結果的にはお客さんに負担をかけたり、自社の価値を下げたりということに繋がりかねません。
また、業務効率化だけでなく、トラブル発生を防ぐ手段を検討する時にも、こういったことは起こりがちです。
入会する時には、基本的に全ての登録がオンラインで完結出来るのに、退会時には対面でしか対応しない。
こんなサービスって結構多いですが、これは対面での退会というハードルを作ることで退会率の減少を防ぐ改善の結果です。
#心理効果を狙ってる
#気分悪い
だけど、これってお客さん側に負担を強いている状態なので、まったくもって優しくないし、健全なサービスとは言い難いですよね。
#これで儲けている会社も多いけど
#何か嫌だ
こういった細かい部分が積み重なると、お客さんから信用を失っていくことになるので、ファンが減少して、トータルで損することになりかねません。
改善や効率化が、独りよがりのものになっていないか?
改善や効率化が、目先の効果だけを狙ったものになっていないか?
今一度、しっかりと検討して、業務改善をすすめていくようにしたいですね。
じゃ、またね~!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
