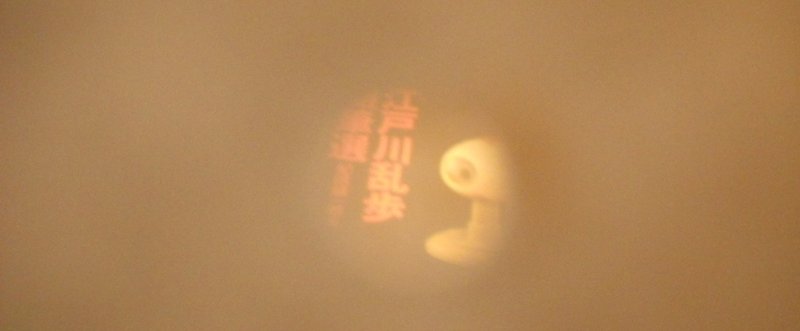
文豪のぞきシリーズ・江戸川乱歩
推理・探偵小説で有名な江戸川乱歩であるが、その名前のもととなったエドガー・アラン・ポーは死ぬほど大好きなのにも関わらず、私は乱歩の作品は二次創作しか読んだことがない。推理ドラマや、アニメは結構好きだが、小説となるとなぜか構えてしまう。そういう風にして、私はどんどんと読書の垣根を上げていってしまっているのだが、古本屋で、乱歩の随筆選なるものを見つけてしまったので、胸がときめいた。
出会いのきっかけは、大切である。何事にもきっかけがなければ、始まらないのだ。そういう風にして、私は江戸川乱歩の書いたものを生れて初めて読むこととなった。
小説はフィクションであるが、随筆は違う。大衆向けに書かれたいわゆる日記みたいなものだと思っている。自分の意見や思い出話をつらつら書き綴り、まさしくその書いた人間の頭の中をのぞいている気分になる。だから好きなのだ。もともとノンフィクション物は大好きで、よく読むほうだった。本当のことが大好きなのだ。幼いころから本当に起こった、事実は小説よりも奇なり、の世界が大好きだった。
この「江戸川乱歩・随筆選・紀田順一郎編」は、ちくま文庫から1994年に発行されている。解説を読んで紀田順一郎さんの事がちょっと気になって調べてみたのだが、インターネットとは本当に便利である。こういう時に気になったことは瞬時に自分の目の前に現れるのだから、まったくもって図書館等に行く手間が省けていいものだ。紀田さんは、小説家でもあり、評論家でもあり、翻訳家でもあるそうだ。わくわくするような評論を沢山出されているので、今度探してみようと思う。
私は、江戸川乱歩の名前を知ってはいたものの、推理小説家という印象しかなかったのだが、実は業績の三割近くが随筆なのだと知って軽く驚きを覚えた。そしてこの本の一番初めに載っている随筆が、「乱歩打明け話」という同性愛についてなのであるから、私は激しくうれしくなって、心がひらひらするのを感じた。しょっぱなからこんなのを持ってくるとは、やりますな。
この打明け話、乱歩が三十三の時に書いたものであるらしいが、出だしはなぜ貿易商になったかであるが、その後二十三あたりまで童貞であったという話になり、中学時代の同性愛のまねごとの話にすり替わっていくのである。
”それが実にプラトニックで、熱烈で、僕の一生の恋が、その同性に対してみんな使いつくされてしまったの観があるのです。少しばかり甘い話なんです。”
まねごとと書いてあるくせに、一生の恋が使いつくされてしまったのである。そんなのがまねごとであるはずがない!当時は、女々しいことが大禁物だった時代である。それにもかかわらず、稚児さん役と呼ばれる柔弱な男子にいろいろな奴らが言い寄るのである。これも当時流行っておった、恋の真似事というのであろうか?乱歩の通う中学ではこんなことがなかなか盛んであり、浮き名が立つらしい。しかし、汚らわしい関係というものではなく、ほとんどがプラトニックなものだったらしい。体の関係や、言葉を交わすこともほとんどないという関係だったが、ラヴレターのやり取りは盛んだったらしく、乱歩も大分貰ったそうだが、たった一人断り切れず返事をした美少年がいたそうだ。彼とは同級生で、夏休みの休暇中に先生に連れられて、お寺で二、三週間なり泊まり込みで、体を鍛えるような事があり、そこでほかの生徒たちの計らいにより、毎晩二人きり同じ蚊帳の中で布団を隣同士に並べ眠るのだが、覚悟を決めていた乱歩に対し、相手は怖気づいたのか、ナイフをちらつかせ距離を取ろうとするのだ。これは、もう同性愛に対して抵抗のない乱歩と、本当にまねごとだった相手の温度差だなあと思えてきた。しかし、これがその使いつくされた一生の恋の話ではなかったというのである。
本題に入るまでの話が長いはずなのに、実に面白く、読んでいて飽きない、まさしく乱歩は小説家でもあるが、紀田さんが書いているように、乱歩はエッセイストなのだ。
そして本題の乱歩の初恋の話なのだが、この男も中学の同級生で、乱歩と同じような柔弱な美少年だったらしく、喋ることもままならず、出会ってもはにかむ間柄というプラトニックな関係で、しかし、恋文、ラヴレターはお盛んで、そのくだりが実に興味深い。
”そりゃもう、ずいぶんだらしのないことを書いたものです。その文句のあるものは今でも覚えているが、中に「君を食ってしまいたい」なんてものもあった。うわべだけでなく、心からプラトニックにそんなふうに思っていた。どちらが稚児さんというわけでなく、双方対等の立場で、男女のごとく愛し合った。実行的なものを伴わないからこそ、そんな真似ができたのです。”
数え年で十五の少年が、「君を食ってしまいたい」としたためる世界なのである。なんと夢のようであろう。常に受け身であった乱歩は、その少年に触れられることをいつも待っているのであるが、そのくだりの描写が、乙女の世界のそれよりも恋い焦がれる世界で、ガラス玉に閉じ込められた性別のない、淫乱であり無垢な意識を持った人形を眺めているような感覚に陥った。そしてついに秘め事のようにこっそりとお互いの手を握り合うのだが、それが彼らの間で起きた最上のもので、くちづけさえ交わさなかったのだが、この気持ちはその後誰に対しても、どんな女性に対しても味わったことがないらしい。
そのあぶくの様な短い恋は、相手の口当たりに薄ひげが生え、乱歩の頬にニキビができるころ、いつとなく疎遠になり、彼は中学を終えずに、病気でこの世を去ってしまうのである。まさに悲恋である。悲恋であり、美しく、純粋であり、大々的でもある。乱歩いわく、恋とは性的関係を伴わないもので、性的関係が伴う恋は、不純な偽物らしい。それが私にもよく納得できる。思い出の中の淡い恋は、たいてい美しく、人間はその思い出だけを大切に抱きしめて生きていたいものだ。誰にも侵されず、汚されることのないように。自分だけのひそかな秘密のように、ただその思い出だけで心の中をあの時の木苺のような甘酸っぱさが幻のように蘇れば、それだけでいいという事もあるのだ。
乱歩は実に惜しげもなく、普通の人間であれば心の中に閉じ込めておきたいようなことも、沢山書き残してくれている。それは冒頭の同性愛についてもだが、次の「恋と神様」なんてもう最高である。実にのぞき甲斐のある話である。八歳の恋心というか、性への朧気な目覚め、そして秘め事や妄想。妄想は誰も傷つけないので、私は大好きだが、時々暴走してしまうので、大人になってからは恋愛の妄想だけしかしないと決めている。八歳の乱歩少年の妄想は、好きだった女の子が、乱歩一家が引っ越した後、その家に女の子一家が引っ越してくるというものだ。その妄想は暴走し、乱歩少年は家のあちこちに、引っ越してきた少女に充ててメッセージを残すのだ。八歳の少年が、家の柱に”アナタノタメ二ナラ、ワタシハヨロコンデシニマス”というようなことを書いて回るのだ。なんというか、江戸川乱歩は真正マゾだったのかもしれないな。国宝級な純粋さを持ち備えた真正マゾだ!
さて、乱歩も他の大半の作家と同じように、自分自身の恐怖の対象を作品に取り入れていると思うのだが、皆さんは幼いころ、何が怖かっただろうか?幼いころは、他の人が大抵どうでもいいようなものを怖がることがあるが、乱歩の恐怖は少し面白くて、幻想的だ。しかも、恐怖の中にあえて美を見出すところなんてすごく乱歩らしいと思った。
まず初めに「映画の恐怖」、乱歩はフィルムの中であんなに小さかった人間が映写機を通してスクリーンに映し出されるときに、あまりにも大きくなるのに恐怖するのだ。マクロへの恐怖。自分の顔が凸面鏡では滑らかに見えるのに、凹面鏡に変わったとたん、月面のようにでこぼこの顔になる、それも乱歩の恐怖であり、スクリーンに大写しになり、大勢の人間の前に見られる恐怖。そして、映写機の不具合で突如制止するスクリーンに映し出されていた人間たち。今まで動いていたものが突然静止してしまう恐怖。それを乱歩は、生物が瞬時に化石化する、と書いてある。それに遭うと、乱歩は映画館から逃げ出したくなったそうだ。
”活動写真の発明者は、計らずも、現代に一つの新しい戦慄を作り出したと云えないでしょうか”
「映画の恐怖」に続き、「声の恐怖」、「レンズ嗜好症」、「透明の恐怖」のエッセイで乱歩の恐怖がつづられる。「声の恐怖」「透明の恐怖」はどちらも見えないものへ対しての恐怖であるが、乱歩は空気より大きな透明物はない、目に見えないものが恐ろしいとすれば、空気ほど恐ろしいものはないはずだ、と書いてあり、空気こそが全ての自然災害における根源であり、それを我々の祖先は神の怒りだとかと考え、信仰に繋がったのだと。信仰が恐れから始まったのは、納得ができるし、人間幸せだったら縋ったりしなくてもいいのだ。
見えないものといえば、透明人間だが、一つ私にも恐ろしかったというか、不思議だった体験がある。私の故郷は九州の大分なんだが、母が他の故郷が三重町という、今は名前が変わって豊後大野市とかになったそうで、結婚する前、連れが日本に遊びに来た。その連れをいろんなところに連れまわして、日本を満喫してもらって、祖父の家に寄ったついでに、三重町周辺を見て回ったんだが、内山観音を見た時の話。
山の上に般若姫と呼ばれる大きな像が立っていて、車を停めて、山を登り、その像を目指して歩いた。着いた所は意外と開けていて、私と連れの二人以外誰もいなくて、思い思いにふらふらしていたんだが、般若姫の像(というか建物)の後ろに行くと、入り口のドアが開いていたので、気になって中を覗き込んでみた。中は薄暗くて、空洞になっていて、入れるのかなあ?と思っていたら、いきなりすごい強さで背中を押されたのだ。うわあ、びっくりしたなあ!と思って後ろを振り向いたら、誰もいないのだ。私はてっきり連れがいるんだろう、ぶっ飛ばしてやる、と思って振り向いたのに、誰もいない。そうか、突き飛ばして、一目散で逃げたんだな、と思って、もうやめてよ!と叫んだら、ありえないほど遠くから連れの声がする。辺りを見回しても、誰もいない。慌てて怖くなり、連れの声のするほうに走っていき、今背中押したでしょ?やめてよ!と怒ってみたのだが、連れはきょとんとしている。あれは今考えても、何だったんだろうかと、不思議に思う。しっかりとした、力で押されたのだ。あの時、般若姫の中に入ってしまっていたら、どうなっていたのだろうか?うろ覚えなのだが、下に降りるには階段があったような気がするが、確かではない。
しかし少し面白い話で、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%90%8D%E9%87%8E%E9%95%B7%E8%80%85%E4%BC%9D%E8%AA%AC
このリンクを参考にしてもらうとわかりやすいと思うのだが、般若姫は、夫に会いに行くために一人船に乗り、そこで嵐にあい死んでいる。一人悲しく死んでいった般若姫の怒りが、連れと楽しく過ごしていた私にぶつかってきたのじゃないかと思えてくる。しかし、実体のないものに触られるというのは、不思議で、恐ろしい。
私は、作家や芸術家の書いた随筆とか作品に、精神障害のことなんかを見つけるとうれしくなって、ああ私だけじゃないんだ、と気が楽になるのだが、乱歩の随筆の中にもいくつか、彼のおかれていた精神状態についての記述があった。
乱歩は中学生の頃憂鬱症のような病気(たぶん鬱病だろう)にかかっていて、閉じこもっていたことがあったらしい。その時に考えていたことといえば、宇宙の広さ、地球の小ささ、そして自分の存在は虫けらのようにちっぽけだ、ということ。私も、よく宇宙の広さや、地球の規模を考えて憂鬱になったし、何億分かの一の確率で生まれてきた私の存在は、その生まれてこなかった私よりも優れているのだろうか?なんて考えたりして、生まれてこれなかった私に涙を流した。生まれてこれるはずだったけれど、生まれなかった無数の存在に恋い焦がれ、理不尽だとさえ思った。
自分の生まれてくる遥か前に存在して、沢山の本を残し、歴史に名前が刻まれているような人間も、似たようなことを考えていたり、悩んだり、恐怖の対象があった。そういうことを少しでものぞき、知ってしまうとますますその人の残したものが気になってくる。乱歩は「蒐集癖」という短い文の中で、自身の蒐集癖について語っている。乱歩は古本収集が趣味であったが、もう一つ驚くべきものを収集していた。乱歩は、自分について記載されたありとあらゆる物を余すことなく収集するほど、自分が大好きだったのだ。
”人々はなぜ他人の物ばかり集めて自分のものは顧みないのであろう。自分が一番可愛いのだから、自己蒐集こそ最も意味があるのではないか。自分のものを集めるのには自分こそ最適の立場にあり、最も正確を期することもできるわけである。自分のものはほうっておいて、他人の作った、学問的にも大して意味のないマッチのペーパーや料理屋の引札なんか集めている人の気がしれない。”
これで最後にするが、乱歩の少年時代、活字に魅せられたことが克明に描かれていて、私も小さいころ絵本作家になることが夢で、本格的に文章を書く喜びに目覚めたころの事とかを思い出した。それもある出会いが関係していて、いくら人間嫌いとかいう時期があったとしても、人間という生き物は、他人の関与なしにはほとんど生きられないので、まず自分を肯定して、他人を許せる寛容さと、認めてあげれる強さを身につけなければ、泥沼にはまってしまうな、なんてことを思ったり、だからといって、病んでいない私は創造力のかけらもないし、生きていればいいのよ、とにかく、とかいうふうな声もする。
乱歩も様々な職業を転々とし、貧乏時代もあったそうなので、それにも勇気づけられた気がするし、この随筆選を手にとって本当に良かったと思えてきた。これから、「D坂の殺人事件」を読みます。ポーも読み返してみたくなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
