
物語と科学-Maggie’s Tokyo Ep.4-
前回記事:コロナ禍がもたらした変化 -Maggie’s Tokyo Ep.3-
がん患者やその家族、近しい人々が疲れ切ってしまった時、羽を休めに訪れるサンクチュアリ、病院でも自宅でもない「第二の我が家」、マギーズ・センター。訪れた人々は少し非日常的で素敵な空間に身を置き、心を落ち着け、スタッフとの対話により頭と心を整理する。マギーズ・センターは、がんとともに生きて行くための様々なサポートを無料で提供する英国発祥のキャンサー・ケアリング・センターだ。
物語と対話による医療

近年、医療はEBM(Evidence-based Medicine エビデンス・ベイスト・メディスン 根拠に基づいた医療)という新しい診療理念が重視されるようになった。EBMとは、1991年に登場し、北米を中心に広まり、日本にも90年代後半より浸透してきた医学用語である。
それまでの医療は個々の医師の有する医学的知見はもちろん、直観や経験に頼る部分が大きく、担当医により診療内容が大きく異なることも珍しいことではなかった。それに対し、EBMは最新の臨床研究に基づいて統計学的に有効性が証明された治療を選択することにより、安全性が確かめられた効果的で質の高い医療を誰もが受けられるようにするという観点から生まれた医療の在り方だ。
しかし、「科学的根拠に基づく」からといってどのような病にも効果的な治療ができるという訳ではない。根拠となるデータが不足している病気、がんのように治療が困難な疾患、死に至る病、精神疾患などEBMを適用できない場合もある。そのため、EBMで有効とされる医療技術を患者に応用するか否かは、患者の病状や副作用を考慮し、患者の価値観や意向を尊重し、医師の技量や経験を活かして決定することが望ましい。 こうした考え方から、EBMを実践してきた英国の開業医から提唱されたのがNBM (Narrative-based Medicine: 物語に基づいた医療)である。Narrativeは「物語」を意味する。患者が対話を通して語る病気になった理由や経緯、病気についてどのように考えているかといった「物語」から、医師は病気の背景や人間関係を理解し、患者の抱えている問題に対して全人的(身体的、精神・心理的、社会的)にアプローチしていこうとする臨床手法である。
EBMとNBMは対立するものではなく、むしろ、互いに補完するものといえる。医療には、サイエンスに基づく医学的知識だけでなく、固有の価値観を持った患者一人ひとりとの対話や向き合う姿勢など、人間性や感性が求められる。しかし多忙を極める日本の勤務医が診察に使える時間は限られており、一人ひとりの患者と向き合いNBMを実践するための十分な時間を確保することが困難な現状がある。来訪者と対話し、信頼関係を築くことを重視するマギーズ・センターの活動は、全人的治療に必要とされる「物語」を補完する役割として、医療に大きく貢献しているといえるだろう。
心を耕し、つながりを作る

マギーズ・センターはザハ・ハディドやフランク・ゲーリー、日本からは黒川紀章と著名建築家が設計を手がけており、数々の建築賞を受賞することで世界中の人々がマギーズ・センターを知るきっかけを作っている。それは、病気や怪我をしなければ健康について特段意識しないように、普段は医療について無関心な多くの人々が文化的なアプローチからマギーズを知るきっかけにもなっているということだ。マギーズ東京では、このように関心のなかった人々にもマギーズ・センターの活動を伝え、つながりを作り出す様々な取り組みがなされている。

例えば一昨年には、日本音楽財団の協力のもと、チャリティ・コンサートを開催している。本公演のチケット売り上げは全てマギーズ東京への寄付金となる。観客数は公演1回につき2000人ほどという。音楽好きだがマギーズ・センターを知らない人がマギーズの活動を知るきっかけに、また一方で、音楽に関心はないがマギーズ・センターの活動に興味のある人がコンサートに行くという相互作用が生まれている。設立から3年間は日本財団からマギーズ東京への事業助成があったが、その関係で日本音楽財団とのつながりができ、チャリティ・コンサートがスタートすることとなった。クラシック愛好家はコンサートに満足したことはもちろん、チケットを購入することでマギーズ東京への寄付となり、図らずも社会貢献の一助となることに意義を感じる人は少なくない。また、マギーズ・センターの活動自体を知るきっかけともなる。一方、マギーズ東京の来訪者や医療者など、クラシック音楽をコンサートホールで聴く習慣のない人たちもこのチャリティ・コンサートが契機となり、生演奏に感銘を受け、音楽の素晴らしさを改めて知る体験になったという。
ちなみに、がんの痛みのコントロールにおける音楽の効果は広く研究されている。がん患者に音楽療法を用いることで、入院患者の痛みのコントロール感覚の向上、ウェルネスと患者の健康面の促進、痛みの軽減と免疫力の向上、不安の軽減、心理・身体症状の軽減などの効果が論文で報告されている。癒しとウェルネスに対する音楽と音楽療法の効果に関するいくつかの臨床研究では、音楽が不安を軽減し、リラックスにつながることが分かっている。
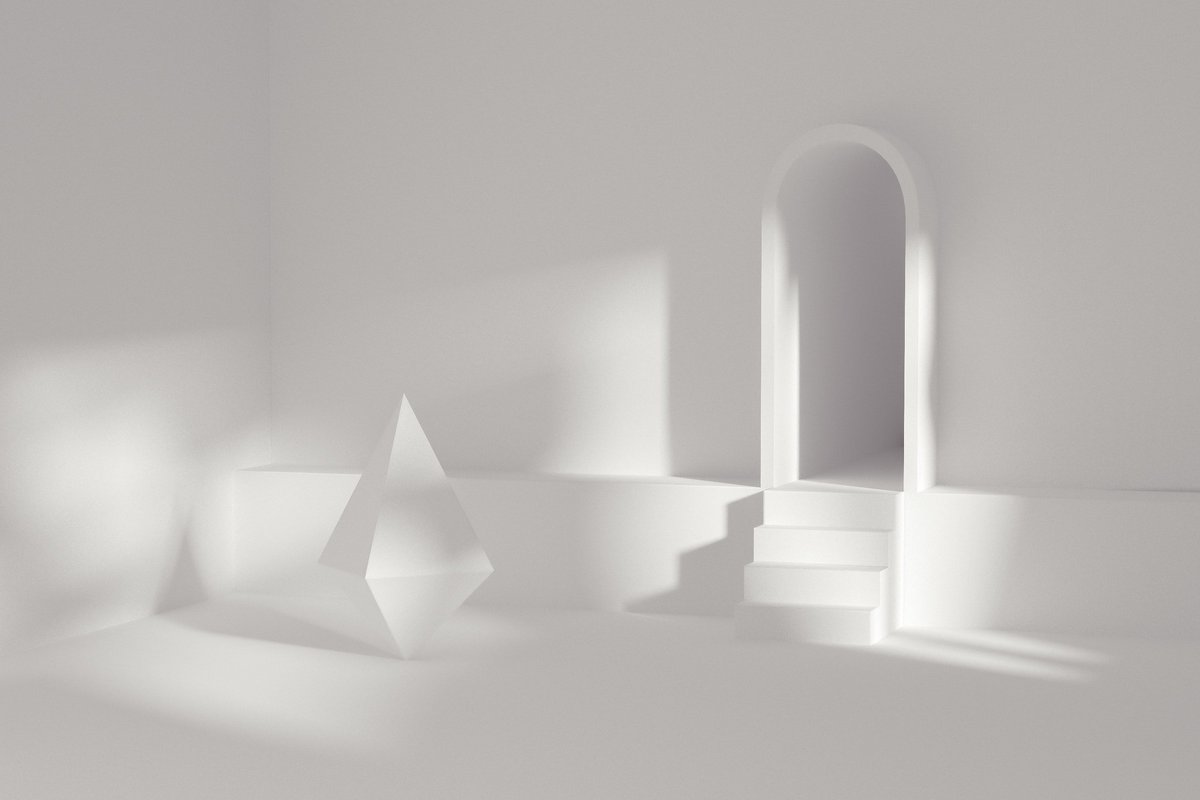
マギーズ東京の建築・アート担当の佐藤由巳子さんは、日本建築家協会(JIA)で研修のプログラムを作っている。また、佐藤さんやマギーズ東京を建築監修した阿部さんが幾つかの大学で講義をしている関係で、ここ数年、芝浦工業大学、東京工科大学、日大、東京都立大、早稲田など6つの大学の建築科の修士課程の学生たちにマギーズを紹介し、例えば「もしマギーズをこの場所に建設した場合、どのような新しいデザインがあるか?」というテーマで、庭と合わせてプランを考えるオープンスクールが行なわれている。プログラムに参加する大学院生は50人近くいるが、その中には家族にがん患者、もしくはがんになった経験のある学生もいるという。今や2人に1人はがんになる時代、こうしたプログラムに参加する時点でマギーズ東京の活動に興味を持つ何らかの動機があるということだ。
また、マギーズ・センターにとって大切な要素である庭は、単に美観維持に努めているだけでなく、地域の人たちに協力してもらい「たねダンゴ」を植え、NPOコミュニティガーデンの指導のもと庭づくりに取り組んでいる。マギーズ東京の利用者と地域の小学校の親子がこの花畑活動を通じて、命の大切さや、病気を患う人への理解、そしてマギーズの普及活動の機会となっている。

がんを患ってマギーズ東京に来た人たちが花畑に咲いた花を摘んで花束にして持ち帰ることもあれば、地域の人たちがボランタリーで作ったラベンダースティックを来訪者が持ち帰ることもあるという。そして時には、地域の子供たちと一緒に「たねダンゴ」を植える交流も生まれる。植物の成長の様子を通りすがりに見かけるだけで、自分も元気になるようだと話すマギーズの利用者もいるという。この活動に協力するNPO法人の人々も、植物やこのような植物に触れる活動が人の心を癒す効果があるという状況を伝え、地域行政にフィードバックしている。
Culture(文化)とCultivate(耕す)はともに「Colere」(「耕す」の意)というラテン語が語源だ。土や植物に触れることも文化に触れることも、心を耕す行為なのである。
その他にも、2018年にスタートしたナイト・マギーズでは、江東区と品川区からの委託事業で月2回開催している。区のがん対策の一環としてがんの夜間相談窓口事業をマギーズ東京に委託し、夜間スタッフの人件費を計上してナイト・マギーズを運営している。例えば品川区はマギーズ東京からは少し距離があるものの、特に仕事に復帰し、夜間にしか相談に来る時間が取れない人などが利用できるという利点がある。区民や在住、在勤に加え、区内の病院に通院している人が対象であるが、対象外の人も利用できる。
こうした行政との連携は、日中の活動では対応しきれない働き盛りの世代をカバーできるうえ、江東区報や品川区報といった公的な広報誌にマギーズ東京の名前が掲載されることで、マギーズ東京の信頼度も向上するといった利点がある。
がんに限らず、私たちは自らの死に直面すると、砂時計の砂がサラサラと落ちてゆくように残された時間を急に(それは生まれた瞬間に始まっているという自然の摂理を頭では理解していたとしても)突きつけられたような気持ちになるだろう。
マギーズ東京では、より多くの人々に訴求するため、様々な出会いや試行錯誤を経てつくり出された多様なプログラムがある。そこには多くの人にこの活動を届けたいという想いがある。
私たちが「がん」によって人生の大きな岐路に立たされたとき、投げやりにならずに病と向き合い、これからの人生の歩き方について自らで思考し選択していくための環境を提供してくれる場所なのだ。
参考文献:
「患者の心理社会的背景への配慮:Narrative Based Medicine」斎藤清二
「EBM エビデンスに基づいた医療とは」公益財団法人長寿科学振興財団
取材協力:マギーズ東京
Special Thanks: Masako Akiyama
Illustration: Dayoung Cho
Text & Photo: Riko
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
