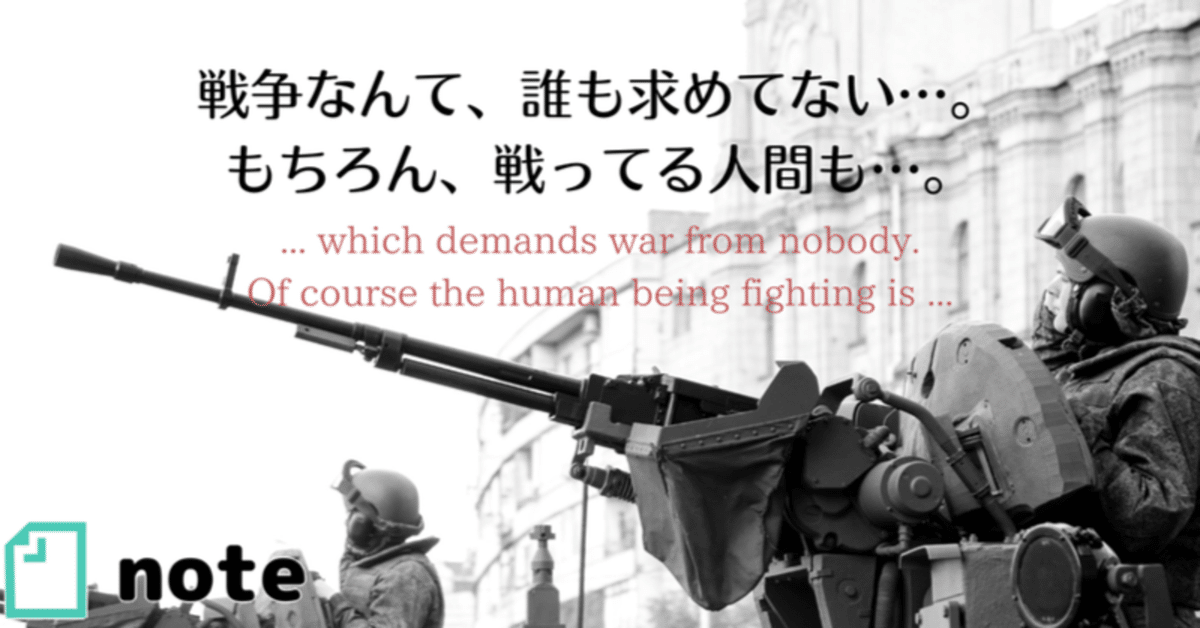
毒の付いた鎖(3)
そういうわけですので。
じっとキムラはぼくを見ていた。その目はどこか怯えているように見えた。次にぼくが何を語るのか。そればかりを警戒しているようで、少しだけおかしかった。
「キムラさん、ぼくは分からないんだ」
その言葉に対する驚き方は、決して正常な反応とは言えないものだった。だが、その目だけは真っすぐにぼくを見据えていた。
「なにが、分からない」
「何で国は自分たちにとって不利益な情報をぼくたちに流したのかな?」
拍子抜けしたのかそれともまだぼくを警戒しているのか。キムラはゆっくりと言葉を選びながらぼくの問いに答えを返した。
「この国がそういう国だから、じゃないのか?」
「そうかな? そんなにお人好しかな?」
「判断はできないな。私はあくまでも首都軍の人間で、国の目的などは分からん。だが、国民に対して利益ある情報を流すことは国の仕事の一つだと私は思う」
「じゃあなんで取り締まりなんてしているんだろうね」
「それも、私には判断が出来ないことだ」
「そう、そうなんだよね」
ぼくは彼に初めて同意した。だが、それは称賛でも何でもなかった。あくまでもその言葉に対しての同意。彼の奥底にある心理への同意。
「どういうことだ」
「ぼくたちにはどうせ判断できない。そう思わせたいんだよ」
「なぜ」
「そっちの方が国にとって都合が良いから」
全くキムラは理解が出来ない、という顔をしていた。
「じゃあなんだ、人々を怒らせることが目的だったというのか?」
「ぼくはそう思う」
「何のために」
「人と人を争わせるために」
「どうして」
「あなたたちを価値あるものとするために。首都軍をね」
「そんなことを国がして何のメリットがあるというんだ?」
「平和が無料だったはずのこの国に平和で金をとるために」
「ばかな」
信じられない、という顔の奥に生まれていたのは、微かな疑念。まるでどこか心当たりでもあるかのように。
「だが、そんなことをして何になる?」
「今って、色んなところから色んな情報が流れてくる時代だよね」
「例えば?」
「ワクチンの情報、マスクの情報、それに色んなイデオロギー。色々な情報」
「それがなんだというんだ?」
「今は一瞬にして自分の信念に同意してくれる存在に会える。だけど、その反対も同じだよね?」
「確かに、それはそうだな」
「今は誰とでも仲間になれて、そして誰とでも敵になれる」
「そうすると、どうなると?」
何を話しているんだ、というキムラの顔が少し面白い。ぼくはますます話を続ける。
「小さなコミュニティが生まれるよね。そしてそのコミュニティはそれぞれがとても強固な絆で繋がっていたとする。では、それらを傷つけようとするものが外から来たらどうなる?」
「……争い、か」
どうやらキムラは納得してくれたようだった。
私より半分も生きていないであろう少年に、今気圧されていることだけは分かった。ヒロイハヤトの仮説には、一つとして裏付けがない。その根拠となり得るものが無いにも関わらず、荒唐無稽なその論理を私は信じようとしていた。いや、彼が信じさせようとしていたというのが正しいのかもしれない。そこにある妙な説得力と、疑うことなく真っすぐに向けられた目。その奥に潜んでいた暗い目。私は彼に恐怖を覚えた。彼には全てが見透かされていて、その上で何を話しても一つとして隙がない。
思い返してみる。今この世界で起きていることは何だろうか、と。それはワクチンを打つかどうかということによって生まれた争い、様々な考えの違いから生まれる人と人が面と向かわないからこそ生まれる争い。自らの考えと異なる考えを照らし合わすことなく暮らすことができる世界。そして、自らの考えと同じ考えの人物とだけ暮らすことができる世界。日常で肩と肩がぶつかっただけで起きる喧嘩が、人と人を介さないだけでいつでもどこでも出来るようになった世界。疑念が生まれる。だからこそ、苦し紛れに彼に問うた。
「だが、君の意見がもし本当だとして、果たしてそこにいったい裏付けがどこにある?」
問うてみると、彼は初めて目を見開いた。それは今まで見せていた暗さとは違う少しばかりの光が入っているような気がした。
「それは、誰かがぼくの意見を信じるかどうか、ってことかな?」
「そうだ」
そう、彼が立てた仮説や意見はあくまでも彼の感想に過ぎないと切り捨てることは十分にできる事だった。人によってはそうする人間も居ることだろう。だが、この仮説にはどこか妙な説得力があった。
治安が悪化すれば、警察や軍という存在が介入する口実を作りやすくすることができる。そうすれば、政府は少なくともある程度は人々をコントロールすることが可能となる。そして、そのためには人と人とが繋がりやすい世界を創り出してしまうことはナンセンスだ。むしろ人と人とが断ち切られる、あるいは様々な考えの下で仲たがいさせあわよくば争いを起こさせることができれば理想的だ。
だが、これまでだって様々な考えの違いなどで争いとなる火種はいくつもあったはずだ。それでも争いさえ起こらず平和な国であったのも事実だ。だが、いつでも生身でないという理由の中で誰とでも手軽に。そうした確実にくすぶりつつあった争いの理由を爆発させるのに都合が良かった。それまで様々な人の良心によって組み立てられていたこの国の治安そのものを変えてしまうような。人と人とが考えの違いだけで争いを巻き起こすような火種を。それがこのウイルスの騒動そのものだったというのか。だからこそ、ヒロイハヤトはこう答えた。
「そんなことはどうでも良いんですよ」言葉が、トーンが変わった。「多分そうだ、っていうぼくの結論なんですから」
「それで満足なのか?」
「まあね」
ひどく達観していると思った。彼は罪そのものでさえも、大したものではないと考えているようでもあった。
「もし、君の意見が真実だとすると」彼は顔を上げた。少し色が白く感じたのは気のせいだろうか。「ウイルスは偽物であったかどうかではない、そこは重要ではないと?」
「うん、正解」
「マスクの有無やワクチンを打ったか打たないかは問題ではないと?」
「ですね」
「つまり、こうなるように誰かがシナリオを描いていた?」
「安っぽい脚本だけどね」
ははっ、と彼は嘲るように笑ってから私を見た。
「だとしても、誰も君の言葉に耳を傾けないだろう」
「ね、ぼくもそう思います。だから期待していないんです」
目を見開いた。次は、私が。
あと二つくらいですかね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
