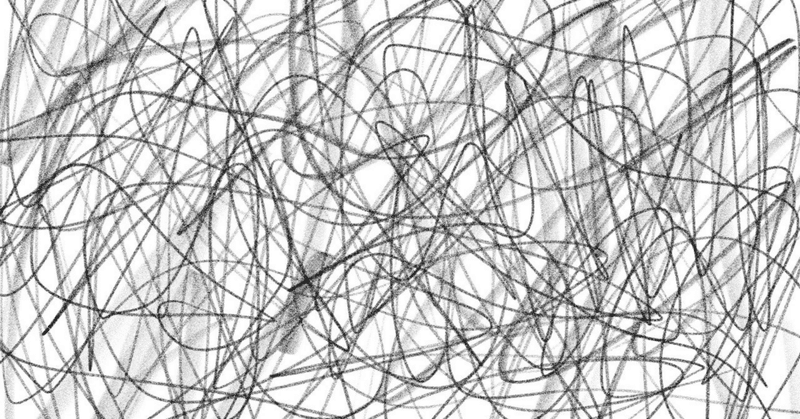
お勉強は楽しくない
息子5歳の時に発達障害グレーゾーンと診断されてからの話。
子どもの成長スピードは個人によってペースが異なるのだから、楽しむことを第一に、焦らずじっくり基礎固めが正解だったんだな、ということ。
市の施設での検査の結果、アウトプットの能力が低いと評価された息子だが、小学校入学までに何とか人並みに読み書きができるようにして自信をつけさせてあげたいと、私は考えた。
そこで、年長に進級してから公文に通わせることにした。
6歳上の娘も就学前から4年生まで公文に通い、そこそこの進度に進み、ご褒美のキーホルダーや盾をいただいたりしていたこともあり、同じ教室に通わせることにした。
公文は寺子屋のように長机が並んでおり、子どもたちは各自の課題を自習するスタイルだ。前方に先生が座り、課題を終えた子どもたちの教材の丸付けをしている。息子は先生の対面の幼児用の小さな机に着席した。
ところが...娘が年長だった時と全く様相が違うのだ。まず、座る姿勢を保っていられないし、5分と椅子に座っていられない。
同じ学年の子どもたちは静かに課題をやっている中、ウロウロしだす。机の上の鉛筆をバタバタと床に落とす。消しゴムの消しカスを集める小さなちりとりがお気に召し、そればかり触って遊んでいる。そのうち、眠い...と言い出し、机の狭間の通路に仰向けになり、本当に眠り出した。これには娘の面倒を見てくださってきた先生も苦笑。それでも辛抱強い先生は「初めは皆んなこんなもの。特に男の子はよくあることだから、これからゆっくり慣れていけば良いわよ。」と言ってくださった。
私も保育園の先生に指摘されてからも、息子はちょっとユニークなぐらいで、そこまでと思っていなかったので、この状況を目の当たりにしてさすがにショックだった。
息子より小さな子どもたちが足し算をしているのを尻目に、まずは鉛筆を持つことからのスタート。ただ点線をなぞって線を書いていく、というもの。
でも、全然できない。鉛筆を転がして遊ぶことに忙しいからだ。そのうち書き出すが、心細い線を描くか、鉛筆の芯が折れるほど、紙が破れるほどの力をかけて殴るようにぐるぐると描く。点線はほぼ無視。一枚書いては教室の中をブラブラお散歩して、また気まぐれに一枚書く、という感じ。毎回、2時間かけて5枚進むのが関の山だった。
娘は同じ時期に足し算をやっていたのに...同じ自分の子どもなのにこの違いは一体何なんだ?と思った。
結局、息子には就学前までは、
・姿勢を保つこと
・椅子に5分間は座っていられること
・程よい筆圧でかけること
・真っ直ぐに線を書けること を目標にした。
もしもお名前が書けるようになれば万々歳だ。
とはいえ、正直ビハインド感が半端なく、焦っていた。
しかし、今思えば“鉛筆を持ってお勉強させる”ことに対し、そんなに拘る必要はなかったのだ。
息子は体幹を保つことが苦手だった。発達障害傾向のある子によくあることらしい。
筋力は結構あるのだが、常にゆらゆらしていてビシッと立っていられない。
子どもは体の中心から末端へ発達していく。
だから、鉛筆を持たせる以前に、たくさん遊んで体幹を鍛えることを優先した方が正解だったのだ。
また、指先を使う細かい作業も苦手で、公文もそうだが、折り紙やお絵かきをやらせようとすると集中力が続かず、嫌がった。
ただ、今思えば誤解していたな、と思う。
息子は細かい作業が嫌いなのではなく、それを長時間続けることが嫌なだけだった。
短い時間ならば純粋に楽しんでやれていたのだ。
それなのに、楽しませることよりも、長時間座ってちゃんと書くこと、周りの子と同じようにじっとして“鉛筆を持ってお勉強する”ことを、息子に要求していた。
一足飛びに公文でお勉強をやらせようという私の判断は、今思えば大切な基礎固めをすっ飛ばしていたと思うのだ。
というわけで、息子にとって公文は“苦悶”の時間だったろうと思う。
公文はコロナによる緊急事態宣言が発令された2年生の春、教室がお休みになってしまったのを機に辞めたが、息子にとって“鉛筆を持ってお勉強する“ことは、苦痛以外の何物でもない”楽しくないもの“となってしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
