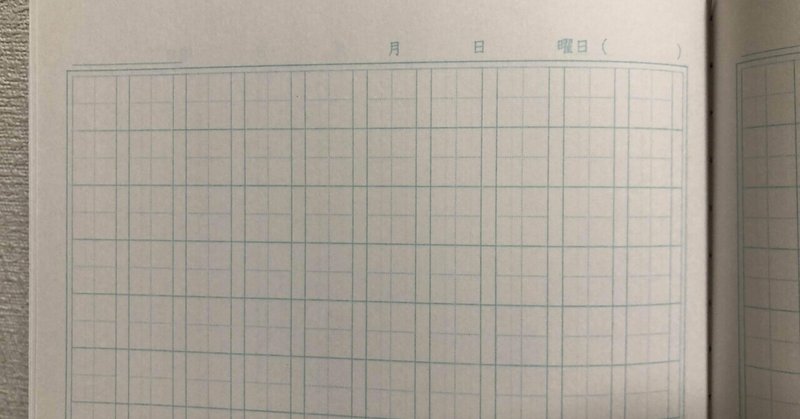
優しい踏み台
就学前に発達障害グレーゾーンと診断された息子であったが、無事小学校に入学した。
こじんまりした穏やかな環境の私立の保育園から、地域でも学童数の多い小学校に入学し、一気に交友関係が広がった。
保育園の指導により、これまで息子はお友達には「くん」「ちゃん」付けで呼称していたが、すっかり息子も呼び捨てで声をかけられるように。
体の小さい息子はかわいがられる、というか いじられ系と化し、頭二つ分背の高い同級生や年上の子たちと登校するようになった。
いじられつつも、息子は割とヒューマンスキルは高めなので、交友関係はそこそこ順調そうだったが、お勉強と生活習慣の方は「やっぱりなぁ...」という感じだった。
まず、お勉強。
就学前から公文でがんばった甲斐があって、入学時点でお名前とあいうえおは書けた。
が、解読困難なことしばしば。そして、発達障害の診断をした施設の先生の予告どおり、漢字の書き取りには本当に苦労した。
本来、横棒が2本のところ、3本も4本も増えてしまう。
視力は悪くないはずなのだが、本人には本当にそのように見えるのだそうで。
本人としては精一杯きれいに書こうとしているのだと思うが、なかなかクセ強めのフォントで、同級生の書くスピードの3倍くらいかかっていた。
小学校では毎学期末に漢字のまとめテストがあるのだが、小4までは毎回惨憺たる結果だった。
あまりに酷かったので、単身赴任で不在だった夫には到底情報共有できなかった。
それでも、ゆっくり書く時間がとれる作業はまだ良い方で。連絡帳や授業のノートをとるといった、書くことが主目的で無い作業には、さらに苦労していた。
毎度、連絡帳は何が書かれているのか?本人ですら解読不能だった。宿題の内容も次の日何を持っていくのか?も不明、ということがしょっちゅう。というか、日々そうだった。
学校に問い合わせたり、お友達やママ友に確認するも、毎度というわけにはいかない。
時には失敗することも、字をきれいに書けるようになりたいという意欲を引き出すことにつながらないかな?と考え、あまりうるさいことは言わずに様子を見るに留めた。
なので忘れ物は、漏れなく毎日複数発生。
そこに不器用さからくる生活習慣のままなら無さも重なり、息子の机やロッカー、ランドセルの中身は常にカオスだった。
本人はあまり気にしていない様子だったけど。
授業のノートをとる作業の方は、結局、克服できたのは小5の終わりになってからだった。
少なくとも小4までは、学校のノートをまともに取れていなかったと思う。
マス目や行は無視。各ページに断片的に走り書きが書かれているだけで、ページも飛び飛びで、まともな記録にはなっていなかった。
ガヤガヤした教室の中で、先生の指示を聞きながら、黒板の文字を読み取り、ノートのマス目通りに書き写すって、実は高度な判断と処理が行われて成り立っている。
息子は興味が移ろいやすいので、お友達にちょっと話しかけられたら、そちらに意識が向かってしまうし、複数の作業を同時並行で処理することが苦手なので、先生の話を聞きながら文章を書いたりするのも難易度が高い。
授業を聞く姿勢を保ち、座り続けるのも難しいので、どうしても気が逸れて遅れをとってしまって、そのうちがんばることもくたびれてしまい、授業に関心が向かなくなる、という感じのようだった。
なので授業参観に行くと、一人、体を捻って後ろの私たち保護者の方ばかり見ていた。ニコニコと。
息子だけ、先生の授業の進行や挙手しているお友達とは、別の世界で生きているように見えた。
担任の先生とは発達センターから情報共有がなされていることもあり、息子の状況を細かく把握する面談を定期的に行なってもらった。
中学年までは本人のやる気が削がれないように、漢字テストはごく甘めに採点してもらっていた。
他にも工作や絵画など、苦手な授業では手厚く面倒を見る配慮していただいた。
担任の先生やサポート役の先生は、優しい踏み台を息子の足元に置いてくださっているかのようだった。
息子の自己肯定感を下げないようにするために。
というわけで、息子の小学校中学年までの生活は、表面上はそこそこ穏やかに進んでいたと思う。
ただ、同学年の子どもたちとの能力の差はなかなか埋まらなかった。むしろ開いているようにも思えた。
中学年にもなると、受験を意識する子どもたちは、進学塾へ通い出す。上の娘は3年生から塾へ通い出していた。が、息子はそれ以前の問題で躓いているので、ほぼ諦めの感情で彼を見ていた。
息子は無邪気で愛嬌がある子なので、かわいくてたまらなかったが、これからこの先、この子どうなるんだろう...将来お仕事に就くことができるのだろうか...その前にちゃんと進級していけるんだろうか...小学校だってついて行けるか怪しいのに...と、悲観的なことばかり考えていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
