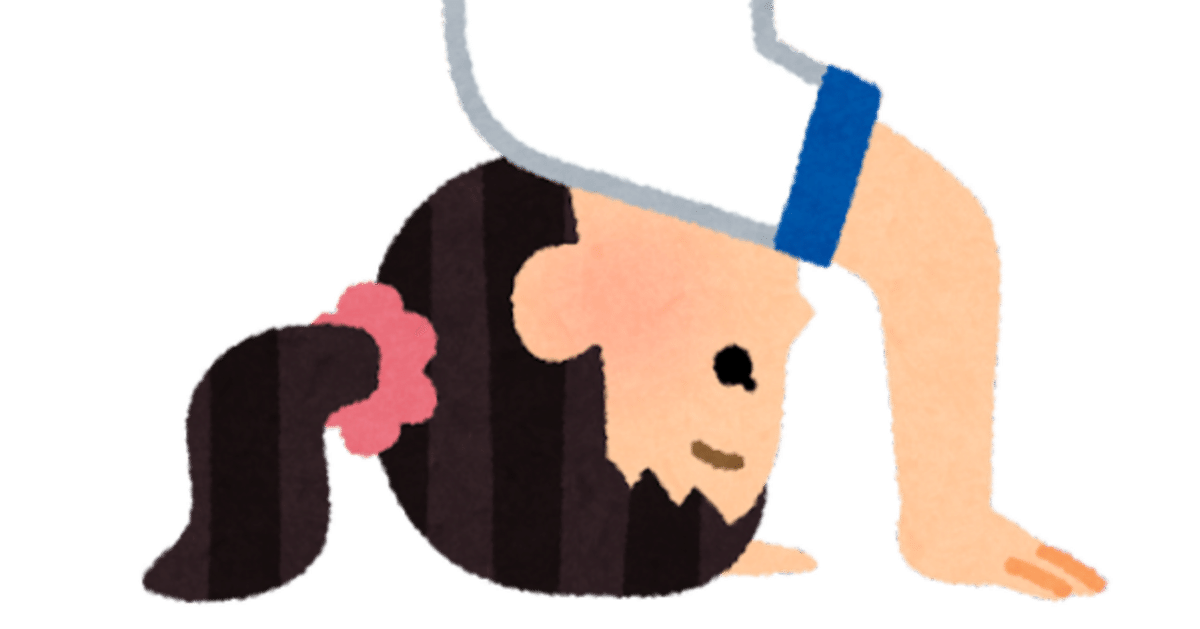
分数の計算ができるようにさせるためなら「教室の後ろで逆立ちさせようが全くかまわない」……
教育長は小学校の分数の計算の指導法について悩む教師たちに語った。「「教室の後ろで逆立ちさせようが全くかまわない」、そうしてでも生徒に達成させなくてはいけない……」(p29)
これは、ある本からの引用です。
いったい、いつの時代のことでしょうか?
実はこれ、今から30年以上も前にアメリカの教育哲学者、ネル・ノディングスが自著に上げたエピソードです。
ノディングスは、1957年に起こったスプートニクショック以降、アメリカ連邦政府がロシアの技術がアメリカに勝ることを恐れるあまり、学校教育の大規模化と効率化を急速に進めてきたことに危機感を抱き、1992年『学校におけるケアの挑戦』によって「大胆とも思われる学校革新の提言」(佐藤)1)を行いました。
今から30年以上前の提言ですが、私には現代の日本にも当てはまる面があるような気がします。
さすがに「逆立ちさせても」という教育長はいないでしょうが、残念ながら「どんな手段を使ってでも学力を向上させよ」という考え方は、日本にもあります。
例えば、「全国学力・学習状況調査」の順位に過剰に反応して、あらかじめ過去問をやらせるなどテストの回数を増やし、点数を上げようとする自治体が出てきてしまうのもそのためでしょう。
ある中学校では、自治体独自で行う統一テストや「全国学力・学習状況調査」を含めて、3年生に対して一年間に13回ものテストを実施しているそうです。
夏休みを除いても月に約1.8回のテストを実施していることになります。
恐らくそうしたテストは入試の関係で2学期中盤から後半に集中するでしょうから、その時期になると月に3、4回実施されてもおかしくありません。
しかも、そうしたテストの結果が高校進学に用いられる調査書の評定に大きく影響するわけですから、生徒たちのストレスはかなりのものでしょう。
こんなに多くのテストは、子どもたちを「逆立ち」させても、と言った冒頭の教育長と何が違うのかと思ってしまいます。
そうした中では、生徒の声はスルーされます。
「なんで、将来使わん勉強をして、高校に行くために無駄なテストを受けなければいけないの?」
「……勉強って高校に行くためにするもんなのかな?」
と、涙ながらに語る生徒たちの声は、まともに聞かれることはないのです。
本当は、そういうことをじっくり考える時間が最も必要なのに。
これは、教師にも同じことが言えます。
教師は決して生徒をテストで追い込みたいとは思っていません。
ノディングスは、そうした教師の気持ちを次のように代弁してくれます。
教師たちは(見かけ上)「授業の手段の選択において専門家としての判断を活用する自由をもっていたが、目的に手をつけることは許されていなかった。こんな制約は専門家の指標にそぐわないものであり、これらの教師はそのことを憤慨している」
『学校におけるケアの挑戦 もう一つの教育を求めて』ゆみる出版、29頁
もっと探究的な授業展開がしたい、独創的なアイデアで生徒たちの興味・関心を喚起したいという願いは、テストづけを強いられる状況にあっては実質的に許されていないのと同じです。
中には「学校に殺される」と職員室で叫んだ先生もいるそうです。
ノディングスは、「学校は、ケアリングを教育の中心目的として「第二のホーム」になるべきであり、ケアの諸領域を教育内容としケアする者とされる者との関わりを基盤として成立するケアリングを教育の方法にすべきである」(佐藤)と主張しました。
学校は勉強するところです。
しかし、その勉強はあくまでも教師と生徒がケアし合う信頼関係の中で行われなければならないはずです。
「一人の人格をケアするとは、最も深い意味で、その人が成長すること、自己実現することをたすけることである。」
1)ネル・ノディングス著/佐藤学監訳(2022 初版2007)『学校におけるケアの挑戦 もう一つの教育を求めて』ゆみる出版、p337(監訳者の佐藤氏による「訳者あとがき」より引用)
※この本は、教師に勇気と希望を与えてくれる最高の一冊です。少し分厚いですが、それほど内容が難しいわけではないので、ぜひご一読を。
参考資料:『教育』No.908(2021)旬報社、教育科学研究会編集(寄稿された現職の教諭の教育活動に影響を与える可能性に鑑み、具体的な頁数や寄稿のタイトル等は差し控えました。また同じ理由で、内容に影響しない範囲で一部修正を施しています)
