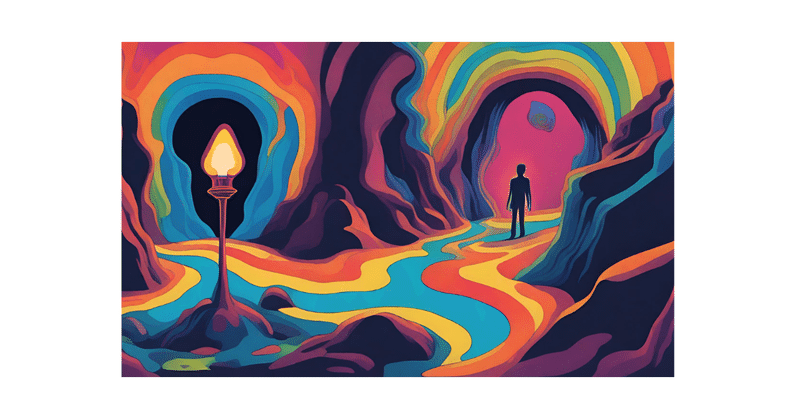
黄金をめぐる冒険⑨|小説に挑む#9
黄金を巡る冒険①↓(読んでいない人はこちらから
目を開けると世界には既に闇がはびこっていた。
そう形容したくなるほど静かで、真っ暗な夜が僕を囲っていた。
実に奇妙な感覚だ。
僕らは食事を終え食器を綺麗に片付けた後、簡単に身支度を整えて家の外へと出た。玄関の扉を開けると、目の前にはいつもの無機質なコンクリートの廊下ではなく、ひらけた暗闇が広がっていた。
彼女は当然扉の外は暗闇ですよと言わんばかりに僕の顔を見て、では向かいましょう、と僕をその闇の中へと押し出した。
本当に押し出されたわけではなく、彼女の言葉が幾らかの質量を持って空気の塊となり僕の背中をもわっと押し出したのだ。
僕はよろめきながらも、雲も星も風も無い中、人を支えるだけの大地だけはしっかりと存在していたことに心底ほっとした。何度か踵でがつがつと地面を叩き、その足場の確実性を確かめた。足から伝わってきた感覚で地面はごつごつしていて固い物質でできているということが分かった。
急にカッカッチという音が聞こえて、彼女の顔がぼんやりと現れた。
その一瞬は、ゆらゆらと弱々しい種火が彼女の顔を不鮮明に灯し出し、辺りの暗闇はキャンパスに塗られた真黒な絵の具となって、印象派の絵画のように美しくそこに完結していた。
「足場が不安定なので気を付けてください」
一つの美しい絵画が消滅し、彼女はマッチの火をランプの灯りに移した。
その儚さが、また美しかった。一つの事象の消滅によって、儚さと美しさの相関性が見事に証明されていた。
僕は茫然とし、ひどく昔にこの美しさを感じたことがあったような気持ちを思い出した。あくまで気持ちだけ、深層心理というべきか、心の奥のざわざわとした感覚的な記憶とはまた別の何か。体は何かを覚えている、だが僕の脳がその記憶を、体験を現像することを拒んでいる、そんな感覚だ。
僕はおそらく求めている。過去を、彼女を思い出すことを。だが同時に、それは開けてはいけないパンドラの箱のような気がした。
意識の外で回路が切り替わる。
その場所には一つのくすんだ褐色の扉があった。ぼくは扉の前で立ち尽くしている。この奥にはおそらく、ぼくの忘れている”何か”がある。とても開けたい欲望を覚える。飢えや渇きに近い欲望だ。
真黒なドアノブに手をかける。背徳感が一種の心地よさとなってぼくの顔を得体の知れない怪物に変え、真黒なその丸玉を握る力が次第に強くなっていった。
かけた手を右に捻ろうとしたそのとき、カッカッチという音がまた聞こえた。音の出所の方へ顔を向けると、そこに美しい印象派の絵画が浮き上がっていた。描かれていたのは幼い少女がマッチに灯りを点けている様子だった。少女は温かさと儚さとの二面性を含んだ目でぼくを見ていた。
そして方向を持たない声で、誰かが僕の意識を震わせた。
「まだその時じゃない」と。
空気の疎密を媒介とせず、ぼくの内側から流れてくるその言葉は、少女の声でもあり、同時に老人の声でもあった。
誰かが僕の肩を大きく揺らした。ぼくの意識はぐらんぐらんと揺れ、褐色と暗闇が部分的に曖昧に混ざり最終的には暗闇だけが残った。肩を揺らしたのは彼女だった。
「大丈夫ですか? しっかりしてください」
彼女の顔はランプの灯りでオレンジ色に染まっていた。
僕は頭を振り意識をしっかりとさせ、大丈夫、先に進もうと彼女に伝えた。
彼女はいつの間にかランプを二個持っていて、一つを僕に渡してくれた。ランプで辺りを照らしてみると、どうやらここは洞窟の中のようだった。地面はでこぼこはしているがある程度平らで、横壁は大きな曲線を描き上部で一つに融合していた。道幅は二人で並んで歩いても十分な幅があり、円状というよりは楕円状になっていて大男でも通れそうな造りだった。
僕らのすぐ横にはランプ掛けが壁に取り付けられていた。おそらく人が通れるように作られた洞窟なのだろう。後ろを照らしてみると、先ほど跨いだばかりの家の扉は既に消えていた。扉の行方は全く分からないが、もう戻れないということだけは理解できた。
「ここは一体どこなんだろう?」
僕はある程度状況が飲み込めたところで(飲み込むしかない状況であったからだ)彼女に尋ねてみた。
「ここは”世界の末端”へとつながる洞窟です。大昔にとある男女がこの場所を見つけたと、私は組織にそう教えられました」
「組織? それは最初に電話で話していた『炒飯』のことかい?」
「ええ、ですが『炒飯』とは組織の一要素に過ぎません。組織の目的は、『失われた感覚』を世界に取り戻すことです。古代、世界にはもっと多くの言葉と感覚が備わっていたとされています。例えば、『宗教』、『戦争』、『国境』という言葉があったそうです。他には『恨みや妬み』、『顕示欲』など、今の私たちでは到底理解できない感情や意識が多くあったと言われています。
「『炒飯』もその一つ、ということだね」
「その通りです。組織の研究だと、それらは争いの原因を生む言葉だったことが解っています。そして何かしらの方法でそれらの言葉と感覚自体をこの世界から消してしまったのです。いや、消してしまったというよりは、変えてしまった、という方が正しいかもしれません」
変えてしまった? 現実でそんなことが可能なのだろうか?
いや、あまりにも非現実的すぎる。
でも僕には、彼女の言っていた言葉を理解できる気がする。あくまで部分的に。何より『炒飯』という言葉にはどこか『ノスタルジア』を感じる。
「詳しいお話は、道中でお話ししましょう。ここから先はとても長い道のりですし、お話しする時間は多分にありますから」
そう言って彼女は真っ直ぐ洞窟の奥を見つめて歩き出した。
僕も頷き、彼女の隣を歩き始めた。
第九部(完)
二◯二四一月
Mr.羊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
