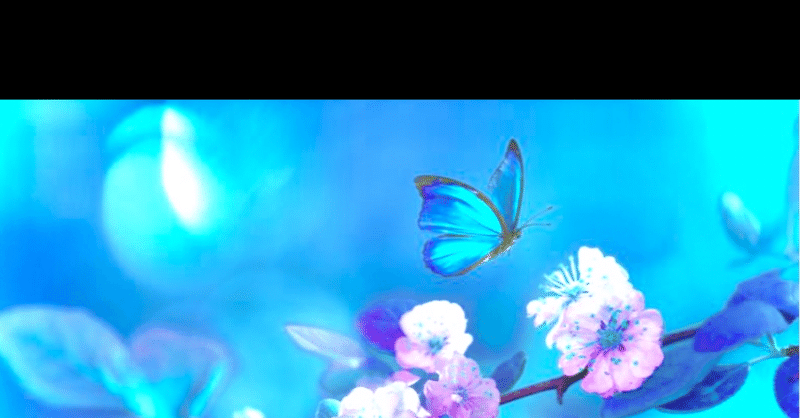
“本能寺の変”には『黒幕』がいた――。
戦国最大のミステリー“本能寺の変”の『真実』と、信長の隠し子が辿る戦乱の世の悲しき運命……。
幾つ屍を越えようとも、歩む道の先には骸の山が…
- 運営しているクリエイター
#義昭
『敵は、本能寺にあり!』 【第二章『桔梗咲く道』】 第六話『機を見るに敏』
―1565年―
傀儡には下らず直接統治に拘る将軍 足利 義輝を桎梏と感じる三好氏は、清水寺参詣を名目に集めた一万の軍勢を率い、突如として完成間近の二条城に押し寄せる暴挙に出た。
義輝が暗殺されたのを機に、其の弟 義昭は興福寺に幽閉される。
そんな義昭を“次期将軍に”と推す義輝の旧臣 藤孝らは彼を奪還し、越前の大名家へと亡命。
其れは偶然にも、浪人となった光秀が保護を許された“朝倉家”のも









