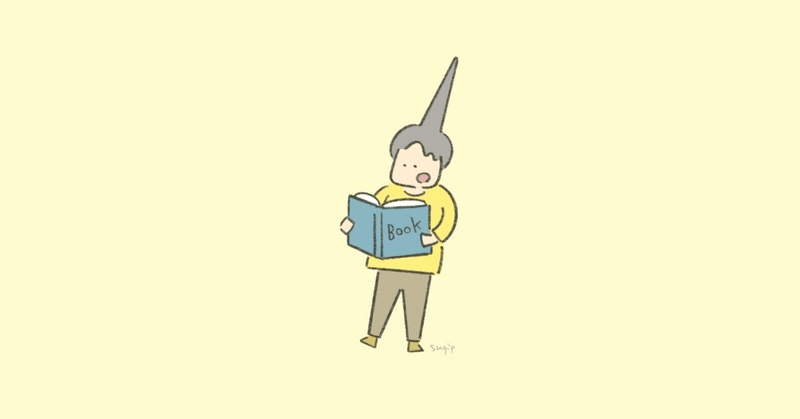
雑感記録(22)
【"つながる"ことの困難さ】
最近、ちょこちょこ本が読めるようになってきて、今まで積んでいた本も次第に消化出来ています。……「消化出来ている」という表現は些か、自分で書いていてどうかとは思うのですが、それなりに読めてきているということです。
ここ数日は都築響一さんの『ヒップホップの詩人たち』を読んでいます。
これ結構面白くて、ラッパーたちのインタビューがメインで、その都度都度でその人たちの曲のリリックが引用されています。普段は音と共に聴いているから、文字面だけで深く読んだことはなかったので非常に新鮮でした。
個人的には最初の田我流が最高でした。同郷ということもあるでしょうが、何かこう「つながり」みたいなものを感じたのです。「一宮」「山梨県」「甲府」といった聞きなれた言葉、僕の身体と密接に結びついている言葉とでも言えばいいのでしょうか。それを見て、読んだだけで僕は勝手に「この人とつながっている」、いや厳密には欲望なのかもしれません。「この人とつながっていたいんだ」と感じたのでしょう。
深沢七郎の『甲州子守唄』を読んだ時も、どこか「つながっている」という感覚がありました。大学に在学中の時、僕はよくこれを読み返していました。まあ、一種のバイブルみたいなものとして読んでいました。
これまた何と言えばいいのか、いい言葉が見つからないのですが、「ポケットに故郷を」みたいな感覚なんでしょうかね。少し引用してみますね。
「えらく、今朝は、繭糸市場へ行くじゃアねえか」
と、徳次郎は怒るようなでかい声で話しかけた。
「お天気がいいから、急いで持って行くら、どこの家でも」
と、母親は家の中でのろのろと返事をするのだ。
「帰り(けえり)は、ゼニを背負って、ホクホクで帰るら、みんな」
母親は他家のマユが通るのを眺めても嫌な気がしないらしいので、徳次郎もちょっと気が軽くなった。
「ああ、持って帰る(けえる)らよ」
と、徳次郎の言いかたも静かになった。
「火事にちげえねえ」
「東京ずらよ」
「東京が焼けてるずらよ、震災の時と同じ方向だ」
土手に出て東の空を眺めている人たちは騒いだ。
「おかしいことを言ってるジャン、ねえ、よく聞いてるジャン」
そう言ってチヨは出て行った。チヨもオカアと同じような気がしているらしい。暑い日で土手はしーんとしていて空襲警報のサイレンの音も飛行機の音もしない。徳次郎が帰ってきた。家の中へ入ってくると、
「戦争は負けただとオ」
と言っただけである。負けたと言っても戦争はやっていくのでまさか、戦争が終ったのだとはオカアは思わなかった。それでもさっき「戦争はおしまいだ」と言っていたので
「戦争は、それでもまだやって行くずら」
とオカアは言った。
とりわけこの語尾が懐かしさを感じていました、大学生当時は。今ではもう地元に戻っていますから、毎日聞いているのでさほどのノスタルジーは湧かないのはちょっと寂しい気もします。
大学の友人に1度この『甲州子守唄』を読ませたんですが、「会話文が入ってこない」ということを言っていました。これを聞いたときにより「つながってる」感覚というのを感じた気がします。
『甲州子守唄』と僕は「甲州弁」という共通言語でつながった。ということなのでしょうね。でも、それって本当につながっていることになるんですかね?たまたま、共通言語を持っていたから自身が「分かる」という感覚になっただけなのかもしれない。先程も書いたように「分かりたい」「つながりたい」という欲望なのかもしれない。
僕がマッチングアプリを使用していて感じている「つながり」の虚構性についてもまた考えてみたいなあと思います。
東浩紀さんの『弱いつながり』を購入して読んでみようと思った、そんな今日この頃でございます。
よしなに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
