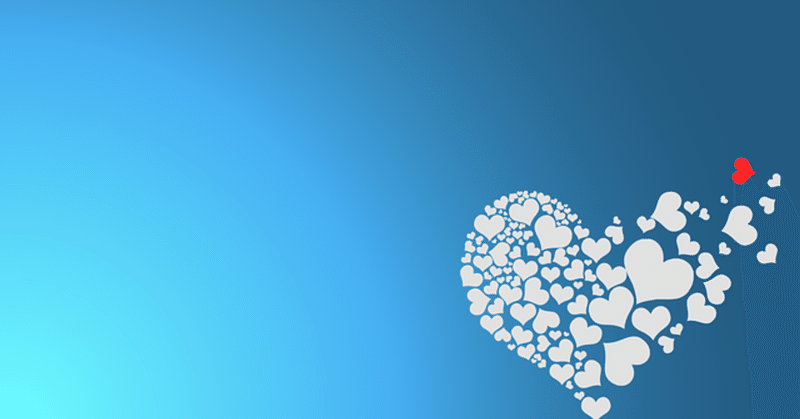
【高齢期リハ】原因不明の慢性痛
訪問リハビリでは内科、整形外科的に問題がなく診断がつかなくても痛みを訴え続ける人がおられます。
痛みはその方にしかわからない、主観的で生活の幅を狭める非常にやっかいなものです。
たとえば
訪問リハビリ開始時に痛みを100点満点で1000点と表現していた方が現在は60点、70点と答えられるも「痛くてどうしょうもないんです。」と訴える方。
趣味の話をしていると全然痛みを気にしていないようにみえるが、「今、痛みを感じてなさそうですね。」と尋ねると途端に痛みの訴えを強める方。
買い物や家事ができてきた方に「段々と痛みをコントロールできてきましたね。」と話すと「痛いんです。こらえてやってるんです。」と訴える方。
その方たちに共通する特徴は
1.過去の痛みと現在の痛みを比較できない、つまり前よりも良くなったという感覚が湧きにくい
たとえば「前はもっと痛かったけれども今は前ほどではない(痛みの自己評価点数が下がっている)」「前よりもたくさんのことが生活上できている」と客観的な評価をセラピストが説明・フィードバックしても
「今も変わらず痛いんです。前がどうとかは覚えていないし、思い出せない。」と答える方がおられます。
「今、苦しい、辛い、それだけ」という想いが強いんでしょうね。
もう一つの特徴は
2.「痛みがあるけど一所懸命にがんばって生活している」ということを周囲に理解してほしいという気持ちが強い
痛みを感じているのは当人だけ。
「できますね。」「大丈夫そうですね。」と声掛けすると
「なんでわかってくれへんの!」という怒りや
「誰もわかってくれない」という孤独感
「これからどんどんひどくなるんじゃないか」という不安感
「生活を送れなくなるんではないか」という心配
が当人の心理にはあるのではないかと考えられます。
このような方に対しては
決して否定せず
痛みを感じているという事実に共感を示すことが大切と最近、よく思います。
もし痛みを感じているその人を否定をしてしまったら余計に痛みの訴えが強くなるかもしれません。
わかってほしい、理解してほしい気持ちが強くなるためです。
まずは痛みを感じている当人に理解を示し共感する。感情の安定が何より大事かと考えられます。
ただ、痛みに注意を向けすぎると強める恐れがあるためこれがまた難しい。
そこから
どうすれば楽になるのか
横になる
音楽を聴く
散歩をする
温める
風呂に入る
姿勢を変える
など
痛みに対するセルフケア方法を
一緒に考え自分で痛みを生活の中でコントロールしていく、あるいはコントロールできると自信をつけることが重要と考えられます。
できたこと、痛みを感じていない瞬間があることに気づいてもらうことで「あ、わたし、これをしても大丈夫。」「こうすれば痛くない」「生活の中で休む時間をつくれば大丈夫」と痛みに対するセルフケアの習得や自己イメージや生活を変えられ改善する方もいらっしゃいますが
そうでない方もいらっしゃるということはセラピストとしてしっかりと心に留めておかければならない、と最近よく思います。
痛みは大変やっかいでプライベートなものだけに作業療法士として丁寧にアプローチしなければ。
最後まで読んでいただきましてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
