
【初心者向け】発声器官について【無料】
どうも、れーむです。
今回は基礎事項編として発声器官について示していこうと思います。
なぜ発声器官について知るべきか
一言で言うと
ボイトレという試行錯誤するのに
発声の仕組みや発声器官の働きを知らないと
どういうアプローチでトレーニングを行えばよいか分からないため。
以前の記事で述べたのですが、
歌が上手くなるには基本的には『試行錯誤』を行う必要があります。
<中略>
試行錯誤のためには『声の調整の仕組み』を知る必要があるのです。
<中略>
その声の調整の仕組みを把握するためには
そもそもの発声の仕組み、メカニズムまでさかのぼって理解する必要があるのです。
ゲームで例えると、
装備のカスタマイズを考えたりコンボを考えるのに
装備の詳細や技の有効範囲等を知らないと
うまくいかないのと同じです。
したがって当記事では発声器官の役割や動き方など示していきます。
上気道および下気道
発声器官は大きく分けて下図のように上気道と下気道に分かれます。

下気道は主に呼吸に関わる筋肉の「肋間筋」と「横隔膜」が該当します。(上図参照)
「横隔膜」は腹式呼吸において
「肋間筋」は胸式呼吸においてよく使います。
呼吸法については別記事にまとめる予定ですので割愛します。

基礎医学教育研究会(KIKKEN)Lab内の図より引用

基礎医学教育研究会(KIKKEN)Lab内の図より引用
上気道は発声に関わる「声帯」と、
調音に関わる「鼻腔」「口腔」「咽頭」が該当します。
「声帯」は靭帯や筋肉からなる組織です。(後述)
「鼻腔」「口腔」「咽頭」は音を響かせる体内の空洞です。
もう少し詳しく見ていきましょう。
喉頭部
上気道のうちの声帯付近を喉頭部といいます。(下図参照)

喉頭部で重要なのは「声帯」と「仮声帯(かせいたい)」です。
仮声帯の本来の働きは声帯を異物から守るシェルターですが、
がなり声やデスボイス等特殊な発声で使用します。
特殊発声において別記事でまとめる予定ですので仮声帯については割愛します。
声帯について詳しく見ていきましょう。
声帯
声帯の構造と動きは以下の通りです。
構造

声帯の構造図です。粘膜、靭帯、声帯筋からなります。
声を出すのに必要な組織です。ふるえる声帯同士がぶつかることで音が生じます。
その動き方やふるえる部位の違いで声の特徴が変わります。
声帯の長さ、声帯間の距離と厚みの違いによります。
これらを筋肉でもって調整して声色を変化させます。
動き
地声では声帯筋が弛緩して近づき、声帯筋も動きます。
声帯全体がふるえることで強い鳴りが生じるといわれています。

Wikimedia Commons内の図より引用
裏声では声帯筋が緊張して遠ざかり、声帯筋は動かず粘膜のみがふるえます。
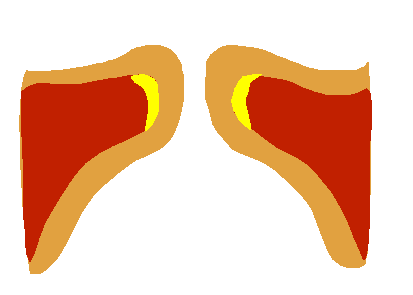
Wikipedia内の図より引用
では、こういったふるえ方はどのように調整されているのでしょうか??
複雑な声帯の調整筋肉を見ていきましょう。
内喉頭筋
声帯を調節する筋肉を内喉頭筋といいます。
内喉頭筋は種類が多くややこしいですが、役割で分けて考えると理解しやすいと思います。
役割
内喉頭筋の役割・機能は大きく分けると3つにわけることができます。(下図参照)
「声帯伸展」「声帯緊張」「声帯閉鎖」の3つです。
「声帯伸展」は声帯の前後方向の伸び縮みに関与し、音程調整で働きます。
「声帯緊張」は声帯の固さに関与し、音程調整で働きます。
「声帯閉鎖」は声帯の開閉に関与し、発声自体に重要です。

各機能や動きについてみていきましょう。
動き
まずは声帯の開閉の動きについてです。
下図は声帯を開いたときと閉じたときの図です。

声帯は閉じている状態で音が出ます。
反対に開くと音が出なくなります。
この声帯を開く動きに関与するのが「後輪状披裂筋」です。
ボイトレではあまり注目されることのない筋肉です。
下図は声帯を閉じるための筋肉をまとめた図です。

声帯を閉じる動きに関与するのが「横披裂筋」「外側輪状披裂筋」「声帯筋(内側甲状披裂筋)」です。
3種類の筋肉が上手く関わることで声帯を閉鎖させることができます。
つまり、声を出すのに重要な筋肉と言えます。
「外側輪状披裂筋」は下図のように勾玉のような形の披裂軟骨を回転させることで声帯どうしを近づける働きがあります。
この外側輪状披裂筋だけでは声帯の閉鎖は不完全で隙間ができます。

ヴォイス・リハビリテーション内の図より引用
そこで「横披裂筋」がさらなる閉鎖のサポートに加わります。
下図のように勾玉のような形の披裂軟骨どうしを近づけることで閉鎖をサポートする役割があります。
この「外側輪状披裂筋」と「横披裂筋」が働くことで声が出せるようになります。
裏声(ファルセット)の発声の状態です。
しかし地声のような強い鳴りは得られません。
これでもまだわずかな隙間ができ、声帯間の距離が遠いからです。
上述の声帯の項目で声帯間の距離の違いで声に違いが出ると述べましたね。

ヴォイス・リハビリテーション内の図より引用
地声の状態のように声帯間をさらに近づけるには「声帯筋(内側甲状披裂筋)」が関与します。
上述の声帯の項目で声帯自体も筋肉とその他で構成されていると述べましたね。
この声帯筋は声帯の厚みと固さを調整する役割があります。
声帯筋が収縮すると声帯が薄くなり、固くなります。
逆に弛緩すると声帯は厚くなり、柔らかくなります。
弛緩させて声帯が厚くなることで声帯間をさらに近づけることができ、地声のような強い鳴りが得られます。
また声門の完全閉鎖(息が通らず無声となる)も可能となります。
このように声帯を閉鎖させる筋肉が複雑に調整されることで声の切り替えが可能となるのです。
また声帯は伸び縮みします。
下図は声帯を伸ばすための筋肉の図です。

声帯を伸ばす動きに関与するのは「輪状甲状筋」です。
声を出すためというよりは高音方向に音程調整するのに重要な筋肉です。
「輪状甲状筋」は上図のように収縮すると声帯をピンっと引っ張る働きがあります。
これにより声が高くなります。
低音発声ではあまり働かなくても発声できますが、
高音発声では非常に重要な働きをします。
常日頃裏声のような高音発声で話すことがないため、
あまり鍛えられていないことが多く、
この輪状甲状筋の筋力およびコントロール力が低いことで高音発声が上手くいかないということが多いですね。
実際、根拠として以下が報告されています。
Bernard Roubeauらによると、
上昇/下降グリッサンド歌唱中の輪状甲状筋等の筋電図活動を低音~高音の全声域で記録した研究で、中音域以上で輪状甲状筋がアクティブだったことを受けて周波数制御の主力は輪状甲状筋であると述べている。
参考文献
Roubeau B, Chevrie-Muller C, Lacau Saint Guily J. Electromyographic Activity of Strap and Cricothyroid Muscles in Pitch Change. Acta Otolaryngol. 1997 May;117(3):459-64.
Fabian Untereggerらによると、
49名のプロ女性歌手の話声位F0→そのオク上F1→さらにオク上F2での運動解析した研究で、
F0→F1で輪状甲状筋収縮による輪状軟骨の後方傾斜により声帯が伸長し、
F1より上の音域では、輪状甲状筋収縮に加えて外側輪状披裂筋収縮によっても声帯が更に伸長すると述べている。
加えて、訓練された歌手は輪状甲状筋収縮によりF0からF1への1オクターブピッチ上昇を可能としているとも結論付けている。
参考文献
Unteregger, F. et al. 3D analysis of the movements of the laryngeal cartilages during singing. Laryngoscope. 2017 Jul;127(7):1639-1643.
高音発声において鍛えるべき筋肉と言っても過言ではありませんね。
内喉頭筋の3種の役割の最後1つは声帯の緊張です。
下図は声帯筋緊張と音程調整のまとめ図です。

声帯の緊張・弛緩に関与するのが「声帯筋(甲状披裂筋内側)」「甲状披裂筋外側」です。
これらも音程調整するのに重要な筋肉です。
「声帯筋(甲状披裂筋内側)」は機能解明不完全ですが、収縮で声帯を緊張させ、張りを強くする働きがあります。
これにより音程が上昇します。
「外側甲状披裂筋」は収縮で声帯筋を短縮し、弛緩させる働きがあります。
これにより音程が下降します。
このように解明不完全ですが
甲状披裂筋は内側外側で正反対の機能を有していることがわかっています。
このように内喉頭筋は声帯の調整に関与しています。
外喉頭筋
また声帯でなく喉頭部全体を調整する筋肉も間接的ですが歌唱に関与します。
最後に喉頭部の位置を調整する「外喉頭筋」について役割と動きをみていきましょう。
役割
外喉頭筋の役割・機能は大きく分けると2つにわけることができます。(下図参照)
「喉頭挙上」「喉頭下制」の2つです。
「喉頭挙上」を担う筋肉は嚥下の補助に関与し、喉頭部(喉仏あたり)を持ち上げて喉頭蓋を倒して気道の完全閉鎖に必要です。
「喉頭下制」を担う筋肉は喉頭の挙上を抑制するのに関与します。

各動きについてみていきましょう。
動き
下図は各外喉頭筋の位置関係と力の向きをまとめた図です。

上図のように喉頭部は喉頭挙上筋群により吊り上げられたように位置し、
喉頭下制筋群に下から支えられています。
ちょうど綱引きしているような関係でどちらが優位に働くかで喉頭部の位置が決まるというイメージです。
喉頭部が高い位置にある状態を「ハイラリンクス」といいます。
一方、喉頭部が低い位置にある状態を「ロウラリンクス」といいます。
「ハイラリ」などと聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。
ではこの喉頭部の位置が歌唱にどう関係するのか見ていきましょう。
下図はハイラリンクスとロウラリンクスについてまとめた図です。

ロウラリンクスでは喉頭が下がることで咽頭が開いています。
これにより強い咽頭腔共鳴がかかり非常に響く声となります。
歌声も迫力が出たり、声量が出たり、太くしっかりした声の印象となります。
一方ハイラリンクスでは喉頭が持ち上がることで咽頭が狭くなり、共鳴がかかりにくいことで声の響きが悪くなります。
したがって喉頭が締め付けられて声帯を傷めやすかったり歌声も詰まったような声の印象となり聴き心地が悪くなります。
以上からハイラリンクスは歌唱においては良くない状態とされ、
反対にロウラリンクスは歌唱において理想的な状態とされています。
しかし、高音発声では声帯伸展強化のために喉頭挙上筋群が強くはたらくことでハイラリンクスに移行しやすくなります。
したがって高音発声時には意識的にハイラリンクスとなるのを抑えてロウラリンクスに近づけることが求められます。
ではどのようにすれば喉頭部を上げ下げできるのでしょうか?
もう少し見ていきましょう。
下図は舌の根本である「舌根」に注目してハイラリンクスとロウラリンクスについてまとめた図です。

喉頭部を意識的に動かすには舌根を動かします。
上図のように舌根を下げるとロウラリンクスを維持でき、
舌根が上がるとハイラリンクスとなります。
つまり声の豊かな響きのためには舌根を下げることを意識して歌う必要があるのです。
一般的に喉をあくびの状態で歌うといわれるのがこのためです。
その具体的な方法については別記事にまとめようと思いますので割愛します。
ちなみに歌唱時の外喉頭筋の活用に関してまとめると下図となります。

上図のように外喉頭筋は輪状甲状筋による声帯伸展を助けます。
ファルセット(弱い裏声)に比べヘッドボイス(強い裏声)の方が
ハイラリンクス抑制のために喉頭下制筋群が強く働く必要があります。
このように外喉頭筋は声帯の働きを間接的にサポートするのです。
今回は発声器官について解説しました。
ボイトレメニューについては別の記事にまとめようと思います。
見ていただきありがとうございました(*- -)(*_ _)ペコリ
よろしければスキボタン、フォロー、コメント、シェアいただけると励みになります👍
質問要望などはコメント欄にお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
