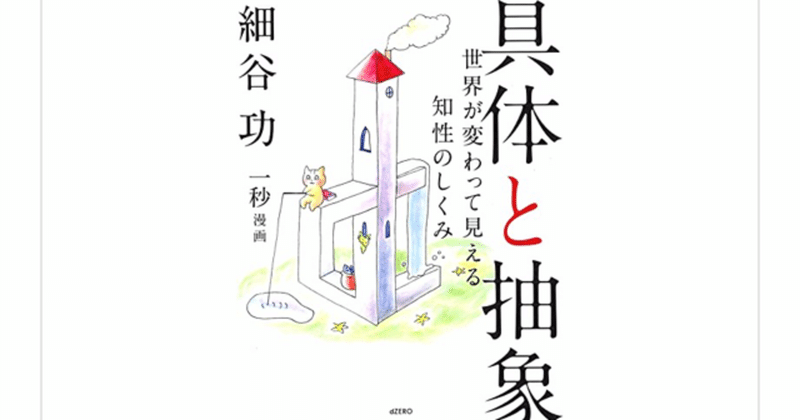
細谷功氏の本、6冊から学んだこと。
いわゆる抽象思考について書かれている本は意外にも少なく、その代表格といえば細谷功さんではないでしょうか。
Kindle unlimitedにも数冊ありますが(お得ですね)、いくつか読んだものから気になる箇所をクリップ。
その内容に項目を付けて順番を入れ替え、かんたんなコメントを付けてみます。
抽象化について
その①
抽象化とは、複数の具体的な事象に高次の共通点を見つけて一般化することです。そこで見つけた共通点を基にして一見まったく異なるように見えるものをつなげることで新しい発想を生み出すことができるようになります。
ここでいう「高次の」というのが本書でいう「メタ」の視点ということになります。
『メタ思考トレーニング 発想力が飛躍的にアップする34問 PHPビジネス新書』(細谷 功 著)より
抽象化する手段として、高次な共通点を見い出す、つまりメタ視点が必要ということ。その共通点をつなぐことで新たな発想が生まれる。
その②
抽象化とは複数の事象の間に法則を見つける「パターン認識」の能力ともいえます。身の回りのものにパターンを見つけ、それに名前をつけ、法則として複数場面に活用する。これが抽象化による人間の知能のすごさといってよいでしょう。
『具体と抽象』(細谷 功 著)より
言葉、数字こそ抽象化そのものであり、人間の知能のすごさ。紐解けばパターン認識だと。
人はいつからパターンを見出せるようになったんでしょうかね。
その③
人間は個々の経験を抽象化・一般化し、継承可能な知識として蓄積することで知的能力を高めてきました。「一般的であるが役に立たない」ことの象徴として時に「教科書的」という言葉が使われますが、まさに教科書を作って再現可能な言語として結晶化することで、学習が可能になったのです。
『自己矛盾劇場 ―「知ってる・見えてる・正しいつもり」を考察する』(細谷 功 著)より
継続可能な知識として蓄積した結晶が教科書だとすれば、たしかに抽象化ですね。
教科書=抽象化したもの、というつながりは持っていませんでした。クリップ。
その④
そもそも「具体的」という「抽象度の高い言葉」を相手に投げかけ、相手がその要求(具体的に言うこと)を「具体的にイメージできない」にもかかわらず、「具体的に言えと、何度言ったらわかるんだ?」などと、繰り返し要求するのは、もはやお笑いの域に入っているようにも見えます。
『自己矛盾劇場 ―「知ってる・見えてる・正しいつもり」を考察する』(細谷 功 著)より
言葉はそもそもが抽象的。それなのに“具体的”への拘泥は、もはやお笑いの領域だと。ここはなかなか気がつけないのではないかなあ。
ただ、言葉は抽象的であるという前提を持っているだけでも、一歩前進かもしれません。戒めも込めてクリップ。
アナロジーについて
その①
要はアナロジーというのは、「ざっくりと」理解したり大きな方向性を考えたり、仮説を考えたりするのに向いている思考法であり、厳密な証明を論理的に積み上げるのに向いている思考法ではないということになります。
『メタ思考トレーニング 発想力が飛躍的にアップする34問 PHPビジネス新書』(細谷 功 著)より
松岡正剛さんをきっかけとして、アナロジーの重要性を多少なりとも感じていて。ただ論理とは相性が合わないってことも、頭に入れておかないと。
本書には「アナロジーと論理は対義である」とまで書かれていますね。
その②
アナロジーとは、「抽象レベルのまね」です。具体レベルのまねは単なるパクリでも、抽象レベルでまねすれば「斬新なアイデア」となります。ここで重要になるのが、第5章で述べた「関係性」や「構造」の共通性に着目することです。
『具体と抽象』(細谷 功 著)より)
むずかしいけれど、この領域は大好物です。構造レベルでのモノマネは、パクりではなく、むしろ斬新なアイデアになる。
ガブリエル・タルドの『模倣の法則』とかは、そういうことを言ってるんだと認識しています。パロディ大好き!
あと構造寄せのモノマネにはゾクゾクします。タモリさんの寺山修司の思想モノマネとかはまさに。
その③
アイデアの豊富さというのは、いかに新しいアイデアを異なる世界から借りてくるかに依存しています。陳腐なアイデアしか出てこない人は、狭い世界や業界の中、あるいはすでにヒットしている類似商品から発想するからです。なるべく目を「遠く」に向け、目に見えないものの類似性を探すことで、いくらでもアイデアは出てきます。
『メタ思考トレーニング 発想力が飛躍的にアップする34問 PHPビジネス新書』(細谷 功 著)より)
アイデアについてときどき「飛ばす」という表現があると思います。ムーンショットというワードも昨年、学びました。飛ばして、共通点を探す。これもアナロジー。
不可逆性について
その①
ルールや理論、法則は、大抵の場合は具体的に起こっている事象の「後追い」の知識だったはずです。ところが、一度固定化された抽象度の高い知識(ルールや法則等)は固定観念となって人間の前に立ちはだかり、むしろそれに合わない現実のほうが間違いで、後付けだったはずの理論やルールに現実を合わせようとするのは完全な本末転倒といえます
『具体と抽象』(細谷 功 著)より)
ルールは抽象的。その固定された観念は後付けにも関わらず、人を縛りつけるおそれがある。まさにそう。
この後から、“不可逆”というワードが出てまいります。
その②
一つ目の非対称性は、「抽象化の不可逆性」です。これは先に述べた「具体と抽象の往復」とは趣旨が違います。抽象化とは一種のパターン化、法則化ですが、人間はよくも悪くも、一度法則化・ルール化してしまうと、そのパターンが変化しても、覚えた法則やルールを疑うことなくいつまでも使い続けるということです。
『「無理」の構造 ―この世の理不尽さを可視化する』(細谷 功 著)より
一つの事例があります。いちど作ってしまった信号はなかなか外すことはできない。いや、たしかにそう。
後付けの観念に「規則だから、ルールだから」と従うのだけど、時間の経過とともに、それらはどんどん増えていく。なかなか無くせないのは、抽象化の不可逆性が関係している。
その③
二つ目の非対称性は、いわば具体と抽象が「マジックミラー」の関係になっているということで、抽象レベルを理解している人には具体が見えるが、具体しか見えていない人には抽象レベルは見えないということです。
『「無理」の構造 ―この世の理不尽さを可視化する』(細谷 功 著)より)
抽象レベルを理解している人と見えてない人。かみ合わないことには原因がある。さらに見えている人は(たとえばマジックのタネ明かしを理解してしまうと)その前の見え方にはぜったいに戻れません。そりゃそうか。
企業目線のこと
その①
オープンイノベーションを実施する上での「障壁」も企業と個人の構図は同じであり、参考になるだろう。これまで日本企業がよくも悪くも特徴としてきた「自前主義」というのがそれである。
これは、NIH(Not Invented Here)シンドロームという言い方で表現されるものであるが、要は他人の開発したものは信用できないという考え方であり、オープンイノベーションが進まない主要原因となっている。
『アナロジー思考』(細谷 功 著)より
自前主義という悪い特徴にネーミングがあること自体、知らなかった。NIHシンドローム。
その②
イノベーションを起こすためには、顧客の声を抽象化して、先回りした商品を考える必要があるが、先の「ソウゾウ力」のない社員にはこれは無理である。
『会社の老化は止められない――未来を開くための組織不可逆論』(細谷功 著)より
顧客の声をそのまま応えるのではなく、抽象化して先回りしましょう。ふに落ちました。
その③
超優良企業の特性のうち、もっとも重要なもののひとつが、放っておけば次第に複雑になっていく自然の傾向に逆らって、あえて物事を単純化しつづけることの大切さを熟知していることだろう
『会社の老化は止められない――未来を開くための組織不可逆論』(細谷功 著)より
ベンチャー時代は風通しの良い環境でイケイケドンドンだった。しかし成熟するその過程で抽象化されたルールやしきたりもどんどん増える。
ここに企業の不可逆性がある。優秀な企業は不可逆性を理解しているから、あえて単純化させることを好むんですな。
自己目線のこと
その①
自己矛盾には三つの特徴があります。
①自ら気づくことはきわめて難しい(が、他人については気づきやすい)。 ②気づいてしまうと、他人の気づいていない状態が滑稽でたまらない。
③他人から指摘されると「強烈な自己弁護」が始まる。
『自己矛盾劇場 ―「知ってる・見えてる・正しいつもり」を考察する』(細谷 功 著)より
「具体的」という抽象化された言葉を使うことをはじめ、矛盾はたくさんあるんでしょうね。せめて自己弁護だけはしないように気をつけます。
その②
人生は「不公平」にできています。だから「努力は無駄で意味がない」のではなく、だからこそ、与えられた「公平ではない環境」の下で、努力することに意味があるのです。そして努力の成否は「他人と比べて結果がよかったかどうか」ではありません。比較対象は、「努力しなかった自分」です。
『「無理」の構造 ―この世の理不尽さを可視化する』(細谷 功 著)より
理不尽さを一度受け入れた上でポジティブに生きる、肯定する。ここでも諦観の要素を感じます。
成功の反対は失敗ではなく、アクションしないこと。成功と失敗は紙一重ですぐそばにある。図解してくれているので、わかりやすいです。
いやー、細谷功さんの本、めちゃ好きみたいです。
以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます...!本に関することを発信しております。
