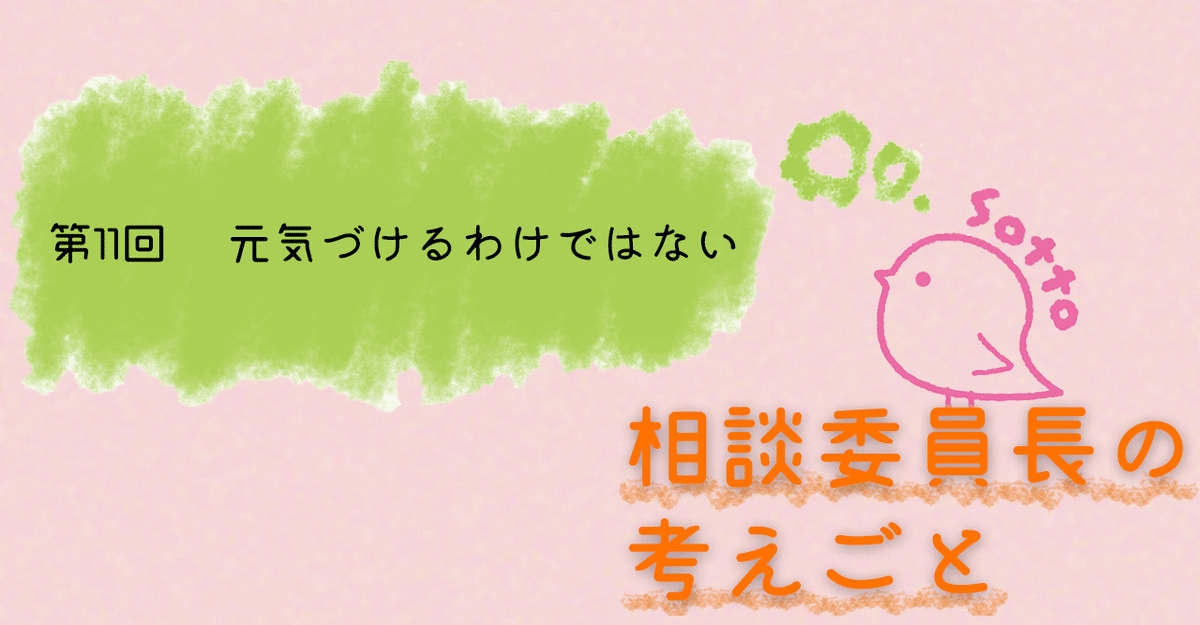
相談委員長の考えごと 第11回~元気づけるわけではない~
私たちは、NPO法人京都自死・自殺相談センター Sottoです。
京都で「死にたいくらいつらい気持ちを持つ方の心の居場所づくり」をミッションとして掲げ活動しています。
HP: http://www.kyoto-jsc.jp/
Sottoが行っている活動は幅広く、根幹となる電話・メールによる相談受付に加え、対面の場での居場所づくり活動、広報・発信活動などがあります。
各活動は委員会ごとに別れ、日々の活動を行っています。
今回から、電話相談を担当する「相談委員会」の委員長である「ねこ」さん(もちろんあだ名です)の、Sottoの活動を通して考えることを月刊連載としてお届けします。
Sottoの立ち上げ当初から活動に関わり、Sottoの文化を形づくることに貢献し、現在は電話相談ボランティアの養成を担当しているねこさん。
そんな立場から、Sottoの活動や、死にたいという気持ち、人の話を聞くということなど、様々なことについて考えることを語ってもらいます。
この連載が、読んでくださる皆さんにとって新しい気づきを得たり、死にたいくらいつらい気持ちについて理解を深めたりするような、そんなきっかけになれば幸いです。
第1回はコチラ→相談委員長の考えごと 第1回~死にたい気持ちについて~
前回はコチラ→相談委員長の考えごと 第10回~うまいとかへたとか~
相談委員長の考えごと 第11回~元気づけるわけではない~
これまでの連載では、相手の立場で発想すること、気持ちを汲むことについて言葉を替えながら書いてきました。
前提として触れていなかったかもしれませんが、話を聞くというのは、必ずしも相手を元気づけるためにそうするわけではありません。
だから、指導するわけでもなければ、機嫌をとるわけでもありません。慰めるのとも少し違います。
わかってもらえなさなどの孤独を解消するための一手段なのですが、労う、いや、適当な言葉に言い換えるのは難しいですね。
ニュアンスが難しい話ではありますが、いわゆる[傾聴]をかじったことのある方なんかは、よく、アドバイスをしてはいけないと習っていたりするかと思います。
しかしどうしてそう言われたのか理解が曖昧だったり、曲解していたりするために苦労しているような印象を受けることがあります。
これはアドバイスすること自体が悪いのではなく、端からアドバイスしてあげようという態度や心構えが、相手には押し付けがましく感じられ、不快にさせてしまうからです。
また、必要以上に褒めるなども、自信をつけさせようという意図があるかもしれませんが、相手の変化を期待してあるべき姿を強いるという意味では、それ自体やはり自分本位で、本当に優しい関わりだとは言えません。
理屈の話をどれだけしてもわかるようなわからないような感じかとも思うので、今回は具体的な話もしてみます。
以下は、メールで相談をされたという想定で研修用に作った例題です。
たとえばあなたが相談員なら何とお返事をするでしょう。
死にたくなります
「世の中は新型肺炎で大騒動だが、自分には休校になるような子どももいなければ、急遽中止になって困る催しや予定もない。
トイレットペーパーや納豆が売り切れるなど、デマなんかも広がっていて不安だが、情報の精査をするにも相談相手もなく、こういうときに本当に孤独なのだと思い知る。ずっとそう。
考えれば考えるほどみじめで、ひとり野垂れ死ぬ前に自殺したほうが良いように思えてしかたない。助けてください。」
困ることがないのはいいことじゃないか、先のことは結局誰にもわからないし、気にするなと言いたくなるかもしれません。
感染が不安ならと予防を徹底するように知っている対策を教えるでしょうか。
別のことを考えさせようと気分転換の体操や散歩を促しますか?
とりあえず大丈夫と言って聞かせるようなことも思いつくかもしれませんね。
気持ちを汲むというのは、何を、どんな気持ち(苦悩)を伝えようとしているのか。
言葉の選び方や言い回しから、わかってほしいだろうニュアンスを想像することです。
すくいとるというイメージかもしれません。
想像というのは、自分だったらどうかということではなく、文字通り、相手なりに言葉を尽くして表現している感情そのものをみようとすることです。
なんだか説明すればするほど意図からはずれる気がしなくもないですが、考えるのではなく感じるのだと言うと、有り体ではあるものの真理に近く思えます。
ただ、図星を言い当てるのが目的ではありません。
わかろうとしてくれていると感じられるかどうかが大切です。
本文から感じられるのは、不安、寂しさ、あたりでしょうか。
細かい状況に言及する必要はありません。余計な詮索も無用です。
作文自体は個性や趣味によるところが大きいので、10人いれば10通りできるものですが、複数の文案を比べるときなどは何について(どんな気持ちについて)言及しているかを見ます。
また比喩的な表現は、それこそ趣味が合わないとかえって白けてしまうので避けたほうがいいです。
以下は、必ずしもお手本というわけではありませんが、返信の一例です。
返信の文案
「いつ何が起こるかわからないようななか、誰にも頼れないのは心細いことでしょうし、不安にもなりますね。
それに考え始めると止まらない悩みや心配事を思えば、思いつめたり死ぬことがよぎったりするのも無理もないことかと思います。
気持ちの支えになれたらと思っていますので、ひとりで抱えきれないようなときはいつでも相談してください。」
返信には正解があるわけではなく、さらに、作文は好みによるところもあるので、自分ならこう書くのにと思うところもあるかと思います。
また、伝えようとしていることについてどう感じたかを都度言葉にしているので、仮にこれを暗記したところで今後役に立つことはないかと思います。
考え方として重要なのは、感じた不安や寂しさをどのように受けとろうとしているかです。
たとえば「〇〇です」と言われたら「△△ですね」と返す、というようなマニュアルはありません。
なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、練習すればできるようになります。
自己責任、結果がすべて、そういう世知辛い世の中です。どれだけ苦労をしてきたか、傷ついて、報われない思いか、そういうことを気にかけて受けとってもらえる場所はなかなかありません。
だからこそ、Sottoの活動に意義や役割があるのだと思います。
相談者を元気づけようとしなくても、やりとりのなかで人との関わりやそのあたたかさを支えに感じられたとき、つらさがやわらいだり、まるで元気をもらったような感覚になるのかもしれません。
今回はここまでにしましょう。
相談委員長 ねこ
つづき⇒第12回「気持ちを話したところでどうなるの?」
マガジントップ「相談委員長の考えごと」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
