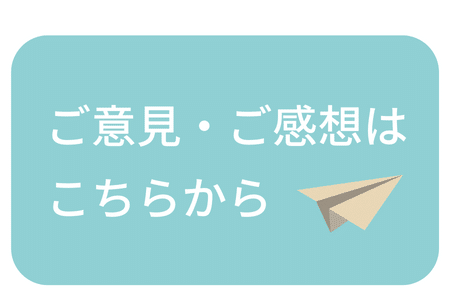偶然を追いかけたら忘れられない物語に出逢った話
信じられないような偶然の連続が、もたらしてくれた物語がある。
11月に公開した、以下のリンクのウェブ記事だ。
長年、音信不通で人嫌いだった関西出身の男性が、なぜか札幌市で孤独死した。その背景を姉が追ううち、天涯孤独だと思っていた弟に、大切な人と生活を営んでいた過去が浮かび上がったというストーリーである。
実はこの話、私が記者としての仕事をこなす過程で出会ったものではない。確率で考えれば到底あり得ないような偶然が何度も重なって、私の胸に飛び込んできた物語だった。
そう、それは飛び込んできたのだ。
知らない人に会ってみる旅
話は、コロナ禍真っ盛りの秋にさかのぼる。
私は当時、何か面白いことがしたいなーと漠然と思っていた。毎日の仕事がワンパターンに感じられる。会う人はいつも同じようなタイプばかりになっている。なんだか日々に精彩が乏しい。
………有り体に言えばそういう気分で、誰にでもあるようなスランプにコロナ禍のストレスが重なったのだろう。
そんなときに出会ったのが、花田菜々子さんの『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』という本だった。手に取ったら夢中になり、書店で買ったその夜から明け方までノンストップで読み続けてしまった。
読了後、嘆息した。嗚呼、私もこの本のように、仕事抜きで知らない人とたくさん会ってみたい。
でも、どうしたら自然に人と出会えるのか?しかも、このコロナ禍に。さすがに出会い系サイトで探せば、男女の出会いを求めているとしか思われないだろう。巣ごもり期間が長すぎたせいか、いつの間にか人との出会い方を忘れてしまっていたようだった。
少し考えて、面白がってくれそうな友人に電話してみた。
すると彼も退屈続きだったのか、電話口で興味津々の様子だった。「ほんなら友達を一人、紹介してみよか?その人からさらに友達を紹介してもらって、その次の人にもそうしてもらって・・・って、わらしべ長者みたいに延々と会っていけばおもろいんちゃうか」
さらに「偶然性があったほうがおもろいっしょ」と、サイコロの目に従って次に誰と会うかを決める方法まで勧めるのだった。「1と2の目が出たらAさん、3と4が出たらBさん・・・」というように、候補となった複数の友人に1~6の数字を割り当て、出た目に従って紹介してもらうというものだ。
特にこだわりのなかった私は、彼の案をまるまる採用してみることにした。

それから非番の時に、ひたすら未知の人と会っては話す日々が始まった。
最初に会ったのは友人から紹介してもらったインストラクターの女性で、難波の喫茶店で待ち合わせた。なんとなく世間話を交わしつつ、「どうして今の仕事を?」などとこれまでの人生を尋ねていく。
すると相手も当然、私が何者なのか、なぜこんな奇特なことをやっているのかと興に乗って聞いてくる。話し始めて一時間もすると、打ち明け話をし合った後のように、ちょっとした連帯感の中にいた。
話が尽きたところで、ポケットから東急ハンズで買ってきたサイコロを取り出す。戸惑われながらもテーブルの上で振ってもらい、出た目に沿って友人をつないでもらった。
そんなふうにして私は、不動産鑑定士、主婦、エステ経営者、書道家、元政治家と、サイコロの目が指した人々とひたすらに出会っていった。
皆、別れ際に「ようわからん企画だったけど、話せて良かった」と言ってくれるのが印象的だった。家族にも話したことがないという昔話を開陳し始めた人もいた。人は、初めて会う人にこそ話せることが、けっこうある。
そして出逢った物語
そんなふうに出会ったうちの一人が、司法書士の増田正子さんだった。
事務所を訪れると、増田さんは「なんかようわからへんけど、まあ座り」と言ってペットボトルのお茶を出してくれた。
私はいつものように、増田さんの個人史について突っ込んで聞き始める。

話が一段落したところで、「仕事は記者なんやろ?普段はどんなテーマを取材してるん?」と増田さんが尋ねてきた。私はそのころ、孤独死した身元不明の女性を追いかけるノンフィクションを執筆していたところで(後に毎日新聞出版から『ある行旅死亡人の物語』として出版した)、「最近だと、孤独死について取材していましたね」と応えた。
すると、増田さんは驚いた様子で言った。「わたしもなあ、ちょうど孤独死の事案に関わったばかりなんやけど。これが忘れられへんような話やってん」。
それから増田さんが語り出したのが、冒頭の記事の、札幌市で孤独死をした男性の物語だ。
男性の姉から、弟と連絡が取れなくなったと聞いたときの嫌な予感。札幌の警察とのやりとり。荒れ果てた男性の自宅。見つかった数多くの手紙………増田さんは次第に感情的になっていったのか、話の流れは蛇行気味になり、言葉は行きつ戻りつした。ようやく語り終えた時には、目元が赤く腫れていた。
一息して、増田さんは言った。「それでこの話をな、洋子さん(亡くなった男性のお姉さん)と、何かしらの形で書き残せたらなって話しててん」

その言葉で私は目が覚めた。増田さんの語りに、完全に引き込まれていた。
彼女が語った、亡くなった男性と女性が雪道を並んで歩く光景が、ありありと目に浮かぶ。
この話は、ここで自分一人が聞いて終わりにすべき物語じゃないだろう。たとえ裏付けのために札幌まで行かなきゃいけなくなったとしても、取材して記事にすべき話だ。そう、強く思った。
それに、巡り合わせの不思議さにも心を打たれた。
孤独死の物語を抱えた女性のもとに、孤独死をテーマに取材していた記者が突然、現れる。それも計6回のサイコロを振り続けた挙げ句、だ。運命めいた偶然のはたらきを感じてしまう。
私は、記者としてこの物語を引き受けることに決めた。
偶然を手放さないこと
取材を進める一方で、私の胸には次のような根本的な問いが浮かんだ。
はたして、偶然とは何だろう?
合間に調べると、偶然を研究した戦前の哲学者の九鬼周造が、以下のように定義していたことを知った。
偶然の「偶」の字は人偏でありますが、之繞(しんにゅう)に書いた遇うという字と同じ意味でありまして、二つのものが遇うことを意味しているのであります。配偶の偶であります。我と汝とが出逢うということが偶然の根本的な意味であります。
なるほど、そういうことか。偶然は、出会いの火花。原子と原子の衝突。誰かと出合い頭にドンとぶつかるときの、ヒリヒリするような痛みでもあるだろう。
そう考えると、わざわざサイコロなど振らなくても日常生活は偶然に満ちていることに改めて目が行く。そしてその偶然の一つ一つが、いつか芽吹く種子なのかもしれない。

出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」
では私たちは、偶然に遭遇した際、どのような態度で向き合えばよいのだろうか?例えば今回、私が巻き込まれた巡り合わせのような事態に際して。
九鬼周造は主著『偶然性の問題』を、「遇うて空しく過ぐる勿れ」という言葉で締めくくっている。九鬼哲学研究者の宮野真生子は、以下のように噛み砕いて説明する。
「遇うて空しく過ぐる勿れ」とは、この日常が決してありふれたものではなく、つねに偶然を抱え込んでいること、だからこそ、そのときにあらわになる偶然を逃してはならないというメッセージだった
この日常は、背後にある無数の歯車が一つでも異なる動きをすれば、まったく違ったものでもありえたはず。だからこそ、偶然が露頭のように姿を現したとき、黙って通り過ぎてはいけないと言うのだ。偶然を手放すことなく、引き受けること。それが哲学者からのメッセージである。

私は取材を続けた。北海道に行き、増田さんらの話の裏を全て取った上で、新たに関係者を割り出して追加取材もできた。結局、紆余曲折あって1年近くかかったものの、11月になってようやく記事を公開することができた。
「出逢わない」という出逢い
先日、亡くなった男性(雅樹さん)の姉である洋子さん宅に、借りていた資料や遺品を返却しに行った。
出迎えてくれた愛猫のぺる(♂)は、取材を始めて初訪問した1年前の夏と比べて丸々としていた。1.5倍ぐらいは大きくなっている気がする。あの日は、洋子さん宅でインタビューしていたところ、途中で安倍元首相が銃撃されたニュース速報が流れ、慌てて会社に戻るはめになったのだった。

洋子さんはコーヒーを淹れながら、私が語る取材の顛末に耳を傾けた。弟が共に暮らしたという女性はどんな人物だったのか。どんな環境で生まれ育ったのか。私なりにたどり着いた結論を、淡々と伝えた。
一通り聞き終えた洋子さんは、独り言のように二度、つぶやいた。「会いたかったなあ。会いたかったなあ」。それから私の方に向き直って、続けた。「生きていれば、私と同じ歳やからね。雅樹のこととか、会って話してみたかったなあ」。
私は、今や「会いたかった」とつぶやくほかない洋子さんの気持ちに、強く心を揺さぶられた。
洋子さんは確かに、亡くなった女性と会うことはなかった。にもかかわらず、洋子さんの中に女性は大きな位置は占め、こんなにも生き生きと息づいている。今まで感じたことのないであろう感情が、生起している。
そうか。「出逢わなかった」死者とのつながりもまた、出逢いの変奏たりうるのかもしれない。
逢ったこともない死者に触れて、心の内に火が灯る。何かを受け取る。痕跡が残る。
洋子さんの胸中においても、亡くなった女性の存在と、彼女を通じて初めて知ることができた弟の優しい一面とが、永遠に刻まれたようだった。
冬が来るたびに、私もこの一連の巡り合わせを思い出すのだろう。そんな気がする。
武田惇志(たけだ・あつし)=1990年名古屋市生まれ。2015年入社。横浜、徳島支局を経て大阪社会部。著書に『 ある行旅死亡人の物語 』(伊藤亜衣との共著 )。同書で第13回広島本大賞(ノンフィクション部門)受賞。