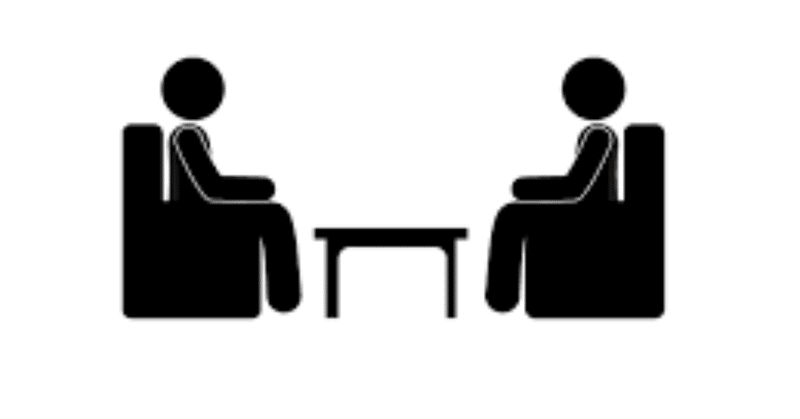
錯覚の春夏冬 ♯3(ウサギノヴィッチ)
どうも、ウサギノヴィッチです。
今日は錯覚の春夏冬の三回目です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「お先に失礼します」
永井が定時にあがるとそのまま副都心線を使って、池袋に向かった。今日は、編集者との打ち合わせだった。永井は編集者と毎月一回打ち合わせをして次回作を見てもらっていた。地下鉄に乗っている間、彼はカバンから今まで出来上がった分のプリントアウトした原稿を読んでいた。とりあえず、短時間の間に見つかった粗をなるべく潰していく。できるなら完璧なものにしたい。渋谷からの短い時間を使った。優先席でもお構いなしに座った。自分はある種優先されるべき人間だし、たった二十分弱の乗車時間なのだから許されると思っていた。彼は自分がどう見られているか気にはならなかった。そのマインドが功を奏しているのか、彼が乗ると席を必要とする人は現れなかった。彼は自分の作品を読みながら、編集者の反応を期待していた。自分の努力はきっと報われる。間違いなくそうだ。そう思う反面、自分が小説を書くということは、結局、プロになっても自尊心を満足させるという行動なんだと思ってしまう。西早稲田の駅に着いたときに車内の電光掲示板を見る。「そろそろか」と普段めったに言わない独り言が口から出た。原稿をカバンに仕舞い、スマートフォンで現在時間と連絡が来てないか確認する。編集者から連絡が来ていて、北口のルノアールで待っている旨があった。永井は、大きく息を吐いて、まるでこれから採用試験を受けるかのような緊張感を持ちながら、編集者に会うのだった。彼の隣に座っていた初老のサラリーマンが訝しげな目で見た。彼はその視線には気づかなかった。
池袋の駅に降りると、人がごった返すというほどではないにせよ、帰りのラッシュで、仕事で疲れた人が酩酊しているような状態で若干左右にフラフラと地下の通路を歩いていた。永井は大学を卒業し、初めて社会人になったときに思ったことがある。それは、社会人になって上司や同僚の人は夢があるのだろうかということであった。みんな会社に飼い殺されて、大きい夢、たとえば世間で有名になることなど、野心みたいなものがないのか、そういうことを考えると一緒に働いている人のことが怖くなってしまった。この人達は仕事をするマシーンなんだ。ただただ、月曜日から金曜日までを働いて、土曜日と日曜日は休むんだと思ったら、自分たちとは違う生物のように感じられた。ただ、それも年を重ねるごとに永井も社会にとりこまれていって、いつしか歯車の一つとなっていた。そのことに関しては、友人などによる周りの環境が起因しているのかもしれない。ただ、彼の心の中で消えなかったのは、自分は「小説で有名になる」ということだった。その気持ちは社会の歯車になっても柔軟に対応していく。最初は、仕事が小説を書く邪魔をする、ということだったが、段々と、執筆をどうやって生活の一部として取り入れていくかということを考えるようになった。今、永井は、理想は早朝に書くことだが、早朝覚醒が邪魔をして書くことはできない。ゆうとは会わない日にコーヒーショップで小説を書いていた。待ち合わせ場所に向かう足はどこか重いながらも自信に溢れた一歩一歩をコンスタントに刻んでいた。永井は普段は音楽を聴いていた。ガレージパンクを中心に聴いていて、歩くリズムがエイトビートのスネアドラムの叩く音とシンクロしていた。そのことは彼の中では無意識の中で起こっていることだった。北口の階段を上る。下りてくる人たちがなにかを喋っている。外国人だ。しかも、中国人か韓国人だ。彼らの話ぶりはなんであんなにも怒ったような表情なのだろうか。すれ違う刹那、外国人は永井の方を見て彼が聞いてる音楽が漏れているのが気になってしまった。彼らの会話はそこでプツリと途切れた。永井は階段を上がり終わり左に折れる。東武デパートに沿って歩く。少し行くと向かいに目的地のルノアールがあった。ここも階段をのぼる。彼は普段運動不足で、家と会社の往復くらいで、駅もエスカレーターを使う。激しい運動と呼べるものは一切していない。しようとは思っている。たとえば、ランニング。でも、一度始めてしまうと継続させないといけないという強迫観念にかられる。それが怖くてメンタルに悪いのでやらないようにしている。そういう悪い理由で。お店の階段をのぼるきると来客を告げるチャイムが鳴った。そのときには彼は肩で息をしていた。
「お客様、一名様ですか?」
永井はそのときの精一杯の力を使って首を横に振ってから言った。店内を見渡す。そんなに首を振ることはない。だいたい二十五度。目的の相手は窓際でパソコンのキーボードを叩いていた。
「待ち合わせなんで」
指をさして編集者の方へと歩いていく。何度も会っているのに緊張して右手と右足が同時に出てしまうことがあった。編集者は永井が近づいていっても気づかない。椅子のところに来て、「佐藤さん」と永井が声をかけると、呼ばれた編集者は顔をあげた。黒縁のメガネをかけていて、黒髪がボサボサの男性だった。
「やぁ、お待ちしてましたよ。ちょっと待ってくださいね。メールだけ送っちゃいますから」
永井は椅子に腰掛けてバッグに入れていた原稿を取り出した。それから、店員を呼んでアイスコーヒーを頼んだ。待ってる間は原稿を読み返したが、足が若干震えていた。待っていることにイライラしていたのもあるかもしれない。お腹が少し痛かった。永井の気持ちを知らずに、佐藤は彼のペースで仕事をやっていく。待っていたのは十分とちょっとだったのだが、一時間待たされたような気分だった。佐藤がマウスをクリックして、水を一口飲むと、「お待たせしました」と言った。永井は固唾を飲み込んだ。
「今回出来上がった分をお願いします」
「はい」
永井が原稿を渡すときに賞状を渡すみたいにあまりにも仰々しくなってしまった。向こうはそんなことは気にしてなかった。クリアファイルからプリントアウトした原稿を取り出して読み始める。
永井は窓の外東武デパートの外壁の溝を眺めた。
打ち合わせは、まあまあだった。ダメなところはダメだったし、良いところは良かった。まるで健康診断のような結果だった。
「ところで永井さん、千住さんの新刊知ってます?」
佐藤は冷めたコーヒーに口をつけてソーサーに戻したときにカップと擦れる音が鳴るのを待ってから言った。
「文芸誌に載せてたやつですね。知ってますが、今度本になるんですか?」
「はい、そうなんですが、それが込み入った状況になりまして……」
「実は、今日、千住さんが亡くなりました」
店内がストップモーションになったように感じた。四月馬鹿にしては遅い。思考回路はショート寸前。今すぐ会いたいよ。ゆうに。でも、永井の目には涙なんか溜まらなくて、むしろ乾いているような気がする。次の言葉が出こない。何を言えばいいのか、正解も不正解もないのかもしれないが、安い感じの言葉しか出てこない。この間の考えているのがおそらく数秒単位だった。そして、驚いたことに、永井のモノは千住の死を聞いて隆起しようとしている。二年間なかった感覚を再び味合うのは、どこかこそばゆい。いくら不謹慎だとしても、自分の状態を優先したいし、生理的な現象なのだからしょうがない。
千住公平は、永井のライバルだった。いや、ライバル視を勝手にしていた。先にも書いた通り、万年賞にノミネートされるだけで結果が出ない作家だ。それでも、永井には追いつけない作家だし、彼と同じ同人界隈というフィールドにいたのだから、いやでも目に入ってしまう。何回かニアミスをしたことがある。その中で一番近況だったのは、千住が永井の隣のブースに買いに来たときだった。永井も隣のブースの人を知っていた。同人歴が長い男性で、ネット中では有名だった。千住は小走りにその男性のブースのもとに来て「すみません、ください」と言った。赤のチェックシャツに、チノパンだった人の良さそう男がいた。それが千住だというのはすぐにわかった。男性は一部千住に売った。そのあと、他愛もない話をしていた。最近、なにを読んでるんですか? オススメはありますか? 売り上げはどうですか? そのやりとりをピンポンをやっているのを見るように首を行ったり来たりしながら、永井は見ていた。応対している男性も千住が苦手なのか、永井が見ているのがやりにくいのか、話しづらそうだった。
「また、ブースに伺いますね」
話をそこそこに男性が切り上げて、千住は去っていった。その後ろ姿を永井はずっと追いかけていた。
そのあとの話なのだが、千住のブースの前を何回か通り過ぎることがあった。見たくないものほど、目がいってしまう。彼のブースには仲間がいて、若いノリがあった。そのブースだけクラブのノリというか、クラスのカースト上位の人間が集まっているような、つまり繰り返しになるが「若い」というか、同人誌即売会ではないような感じがした。それは永井の考えが古すぎたのかもしれない。ブースではおとなしく座って、客が来てもあまり出しゃばらずにいる。旧態依然たる出店者の思想の持ち主だったのかもしれない。だから、千住たちみたいに、客が自分たちのブースの前を通ると押し売りと言っては言い過ぎかもしれないが、はたから見るとある種の必死なアピールをしてくるさまを見ていると、永井はうんざりしたし、恥ずかしくなったし、敵意が芽生えた。しかし、三時くらいに前を通ったときには彼らのブースはだれもいなくなっていて、テーブルの上には椅子が乗っていた。「完売したんだ」永井の嫉妬心は今すぐにでも、そのテーブルを破壊しそうになる勢いがあった。たった一滴の透明な理性が、暴走を食い止めていた。それ以来、そこを通ることはなくなった。
そのときのことは度々思い出される記憶となって古いフライパンにこびりついた焦げのように残っている。
敵対していた千住公平が死んだ。永井にとっては、勝手にライバル視していた人間がいなくなったことが悲しくて虚しい気持ちになるが、その反面いい気味だと思ってしまう。作家として良い結果が出なかったことで気持ちがせいせいしている。これで芥川賞なんか獲られたら、自分の中では消化不良を起こしかねない。このときの永井の顔はどういう表情だったかというと、あまりにも中途半端だった。最初はドキッとした反応をしていた。自然だった。話が進むうちに永井の黒い心が出てきて笑いにも似たものになった。それは勃起にも関わってくる。だれかを抱きたい。久しぶりに湧いた性欲に自分を抑えることができなかった。なんなら風俗でもよかった。どうせゆうに会うのは、まだ先なのだから、それくらいしてもバレないし、このチャンスを逃したら、今度はいつこの状態になるかわからないと思った。
「大丈夫ですか? 永井さん」
佐藤の目は深い井戸を覗き込むようなで永井を心配していた。
「すいません、あまりにもショックだったので、つい自分を見失っていました。あの人とは同人のときから知っていたので、あまり直接的な面識はないですが、同郷の好じゃないですけど、一緒に頑張っていけたらいいなと思っていましたので」
「そうでしたか」
佐藤は視線をパソコンの画面に移す。それを確認して、自分の演技が相手に伝わったのだと感じる。急いでいるわけではないが、時間が気になりテーブルの影に左腕を伸ばしシャツを少しめくる。
「始めづらいですが、始めますか」
佐藤はパソコンをカバンに仕舞ってそう言った。永井が時間を確認すると八時を回っていた。ゆうの仕事の時間だったので、彼女のことをすこしだけ考えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
