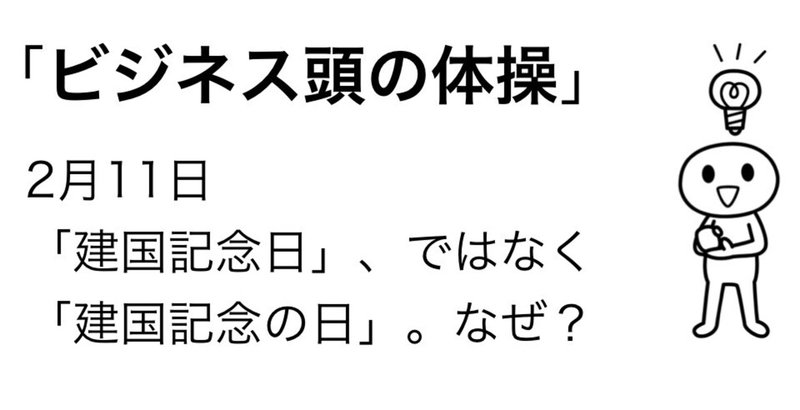
2月11日 建国記念日に「の」が入った理由は?
今日は何の日?をビジネス視点で掘り下げ「頭の体操ネタ」にしています。 今日の「頭の体操」用質問例はこちら。
→意見の対立が激しい場合の合意点の見出し方にはさまざまある。9回も廃案になった「建国記念の日」の成立経緯に学ぶことがあるとすればどんなことだろうか?
“建国をしのび、国を愛する心を養う”国民の祝日。
1966(昭和41)年から国民の祝日になった「建国記念の日」です。
あまり深く考えたことはなかったのですが、「建国記念日」ではなく「建国記念の日」なのですね。
戦前もあったこの祝日の由来が「紀元節」であり、天皇制を強化する策の一つとして、戦後になってこの祝日はGHQの指示により廃止されました。
その後復活の動きがあり、1957(昭和32)年以降9回の議案提出・廃案を経て、1966(昭和41)年に、日附は政令で定めるものとして(つまり日付は未定のまま)国民の祝日に追加されたのです。
日附は内閣の建国記念日審議会でも揉めましたが、10人の委員のうち7人の賛成により、2月11日にするとの答申が1966(昭和41)年12月8日に提出され、翌日政令が公布され現在の形になりました。
「建国記念日」ではなく「記念の日」なのは、建国された日とは関係なく、単に建国されたということを記念する日であるという考えによるもの、とされ、当時の意見の対立が伺えます。
他国では、同じように建国を記念する日はありますが、ほとんどは、はっきりとこの日に国ができた、と分かる日付があるものです。
例えばアメリカであれば、「独立記念日」ですし、元植民地であった国であれば、やはり、独立した日が明確です。
しかし、日本の場合は「この日にできた」という明確な日付がわからないのです。もともとの「紀元節」というのは、神武天皇が即位された日、という日本書紀に書かれている日付なのですが、そもそも真実かわからないです。なにせ紀元前660年の話ですから…
と、ここで、アメリカの占領が終わった日、というのは明確ではないか?と思ったら、すでに安倍前首相が1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約発行が「主権回復の日」にあたるとして、2013年の閣議で決定し、政府主催の式典を行なっていました。
ところが、私も反省なのですが、このサンフランシスコ講和条約時点では、沖縄、奄美群島、小笠原諸島はまだ主権を回復していないのです。当事者からすれば、日本から切り捨てられたという日なのに、首相が「主権回復の日」として式典を、というのですから、厳しい反応がありました。
事実、当時の琉球新報では、同じ4月28日を「屈辱の日」として報じています。
自国の歴史、押さえるべきところはきちんと押さえておきたいですね。
→「県民の日」を決めていない県も多い。これだけ議論がある建国記念の日、なくす、という発想はないだろうか?その場合何が問題になるだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。 過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
