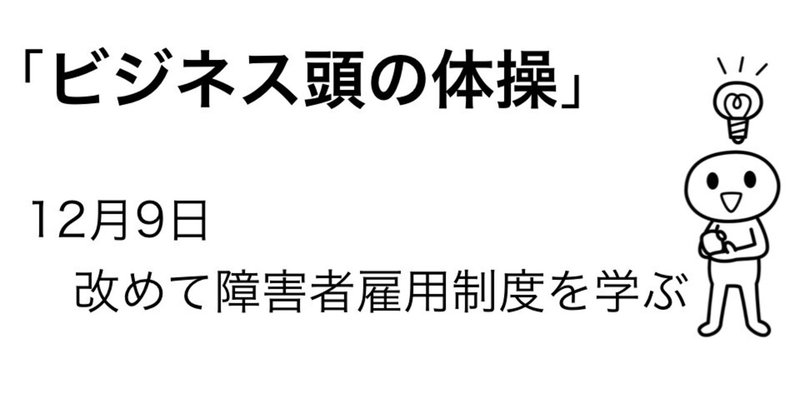
12月9日 改めて障害者雇用制度を学ぶ
視野を広げたい、が、どうしても自分が携わっている仕事中心になってしまう…
そんな問題意識をお持ちの方に、その日にちなんだ過去の事象をビジネス視点で掘り下げています。普段の仕事や興味の範囲を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
→部分は、頭の体操する上での自分に対する質問例、です。
国際障害者年の1981(昭和56)年のこの日に開催された総理府(現内閣府)主催の中心記念事業「広がる希望の集い」で制定された「障害者の日」です。
1975(昭和50)年のこの日に国連総会で「障害者の権利宣言」が採択されたことに由来しています。
障害者雇用、分かっているようでよく分かっていません。これを機会に色々と調べてみました。 (参考資料:戦後我が国における障害者雇用対策の変遷と特徴)
<戦後から割当雇用前まで>
日本の障害者雇用は、戦後、復員してくる軍人や引揚者の中に重度の障害を負った人たちに対するものから始まり、主としては職業指導の実施と雇用する事業主への支援が行われました。
傷痍軍人を戦中から採用していた事業主の代表としては「早川電気分工場」があり、「シャープ特選工業株式会社」の前身です。
その後、1949年12月に身体障害者福祉法が制定されますが、主となったのは、いわゆる手に職をつける職業訓練でした。これは、通常の職業安定行政によって身体障害者の雇用を促進することは困難だったことに加えて、通勤などが困難な障害者のために自営業として営めるものにしようというという意図がありました。
<割当雇用の始まり>
1952年6月の官公庁各省次官会議申し合わせにおいて、公共職業安定所に登録された身体障害者から採用をすること、特に公共職業安定所は職員定員の3%を目標とすること決めました。
このことが日本における割当雇用の最初になります。
なお、当時、労働省が調査を行ったデータによると、官公庁の雇用率は0.69%、民間事業所が0.65%となっています。
<〜現在まで>
その後もさまざまな努力や法整備などにより、障害者雇用は徐々にですが改善しています。昭和52年からの推移を厚生労働省の資料から以下に引用します。

なお、昨年6月1日時点の統計(厚生労働省「令和2年 障害者雇用状況の集計結果」)では、
☑️ 民間企業が法定雇用率2.2%に対して2.15%
☑️ 公的機関が同2.5%に対して国が2.83%、都道府県か2.73%
等
となっています。

→「ダイバーシティ」などと言われるが自社の障害者雇用の現状はどうなっているのだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
