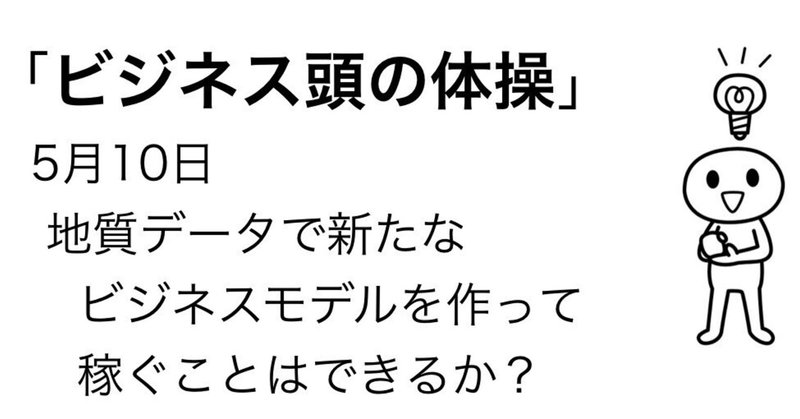
5月10日 地質データで新たなビジネスモデルを作って稼ぐことはできるか?
はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
→蓄えられた地質データや技術で新たな需要(例えば観光など)を喚起することは可能だろうか?その場合、どのようなビジネスモデルが考えられるだろうか?
地質関係の組織・学会が2007年に制定した「地質の日」です。
1876年のこの日、アメリカの地質学者ライマンらが日本初の広域的な地質図「日本蝦夷地質要略之図」を作成し、また、1878年のこの日、地質の調査を扱う内務省地理局地質課が設置されたことに因みます。
地質。
ブラタモリよく見るのですが、必ず地質ネタが絡みます。
やはり、その地域の成り立ちを紐解いていくとその土地、つまり、地質や地形の影響は避けられないのでしょうね(タモリさんが好きだ、というのは間違いなくあると思いますが)。
地震国、火山国である日本では、古くから国が地質について情報を集め分析し活用してきました。
今回はその一部をご紹介します。
おそらく最も広く使われているのが、地質調査総合センターだと思います。
同センターは国として行なうべき「地質の調査」を実施するための組織で、明治15(1882)年 に前身の地質調査所が創立されて以来、地質にかかわる研究を行なっています。
ちなみに、5月10日地質の日についても専用サイトを開設しています(下)。
公開されている情報は地質に限らず、衛星データや海洋地質構造データ、重力データベースなど実に多種多様です。
地質という意味では、「地質図Navi」があります。
日本全国の地質を色分けした地図データです。下は淡路島になります。同じ島ですが、様々な地質があることが分かりますし、中央構造線がはっきりと見て取れます(すいません、詳しい解説はできません…)。

もちろん縮尺は変えられるし、同時に様々な地図データ(Googleの航空写真も選択可能)と重ねて表示することも可能です。
お住まいの地域なんか見てみると面白いかもしれません。リンクは以下になります。
次に表面だけでなく、地中深くまで地質を知りたい、という場合(あんまりないでしょうけど…)に利用できる、その名も、国土地盤情報検索サイト「KuniJiban」です。
国土交通省、国立研究開発法人土木研究所および国立研究開発法人港湾空港技術研究所が共同で運営し、土木研究所が管理しているものなのですが、全国各地で実施したボーリング(地中の地質を調べるために、地上から筒状のものを打ち込んで引き上げることで、その直下の地質がどうなっているかを調べるもの)結果を公開しているのです。その地点の数はなんと約14万強!(下表)

サイトを開くと、以下のような地図が表示され、ボーリングした箇所が分かるようになっています。

見たいところを選択すると、その地点のボーリング結果(ボーリング柱状図)が表示されます。以下は例として渋谷駅直下のボーリング柱状図の一部です。

地表から1.5mまでは埋土で、その下は砂と礫が交互に登場し、岩は17m以上掘らないと出てこない、などということが分かります(すいません、本当はもっといろいろ情報が読み取れるかと思います)。
最後に、先程の地質データをAR技術によって「新たな地質体験」ができるアプリ「ジオ・ビュー」が開発中でその社会実装トライアルの模様が以下に公開されています。
概要としては目の前の風景をスマホで写すと、そこに該当部分の地質データが重ねて表示される、というものです。
なかなか興味深かったのでご興味があれば(3分弱の動画です)。
→こうした地質データや技術で新たな需要(例えば観光など)を喚起することは可能だろうか?その場合、どのようなビジネスモデルが考えられるだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
一昨年7月から投稿し続けており、だいぶ溜まってきました。
以下のマガジンにまとめていますので、よろしければぜひみてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
