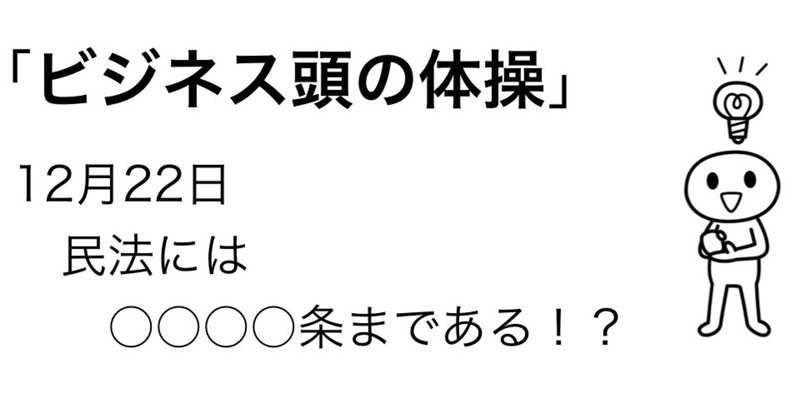
12月22日 民法、身近な法律だが、自分の生活や仕事にどんな関係があるだろうか?
今日は何の日?をビジネス視点で掘り下げ「頭の体操ネタ」にしています。
今日の「頭の体操」用質問例はこちら。
→民法、身近な法律だが、自分の生活や仕事にどんな関係があるだろうか?
1947(昭和22)年のこの日、「民法」の第4編と第5編を全面改正する改正法が公布されたのを記念した、「改正民法公布記念日」です。
家父長制の家族制度が廃止され、戸籍が夫婦単位となりました。
民法、私法関係の原則となる法律ですから、通常、仕事や暮らしで最もお世話になっている法律です。
が、詳しく知っているか、というとあんまり…だと思います。
2020年4月に大きな改正があって、身近なところでは保証人に関する部分に影響があったので、お仕事でも書類や規定の見直しなどをされた方もいらっしゃるかもしれません。
本当にさわり、ですが、その構造をこの機会に勉強してみました。
テキストばかりで退屈だと思いますので、ご興味ない方は飛ばしてください。
(出典:ハンドブック企業法務)
① 民法の概要
民法は私法関係の原則となる法律。全ての取引の根幹となる法律といっても良いもの。
民法は大きく分類すると「財産法」と「家族法」とに分かれており、条文は1050条にもなります。
② 総則(第1編)
総則は、民法全般にわたる共通項が規定されている部分。
具体的には、まず、私法関係の主体となる「人」と「法人」が規定され、次いで、対象となる「物」、さらに「法律行為」が定められ、「期間」、「時効」が規定されています。
③ 物権(第2編)
物権は、「本権」と「占有権」に分かれていて、「本権」がさらに「所有権」と「制限物権」とに分かれ、「制限物権」がさらに地上権などの「用益物権」と抵当権などの「担保物権」とに分かれています。
仕事上では、「所有権」と「担保物権」との関係、「担保物権」には「留置権」、「先取特権」、「質権」、「抵当権」の4つが規定されている、という程度は押さえておくと良いそうです。
④ 債権(第3編)
債権は、「総則」、「契約」、「事務管理」、「不当利得」、「不法行為」から構成されています。
「総則」「契約」は民法の中でも最重要の分野とされています。
まず「総則」では、契約に関する規定が定められています。
例えば、損害賠償、連帯保証人、債権譲渡、債務の弁済などに関するものです。
次に「契約」では、契約の成立、効力、解除が規定され、加えて、「売買」、「賃貸借」、「雇用」、「請負」、「委任」、「和解」などの契約が列挙されています。
最後に「不法行為」では、違法な行為により発生した損害の賠償の請求についての規定があり、仕事上では、使用者責任(従業員の不法行為について使用者が責任を負うもの)が重要です。
また、今回の改正では、保証人の保護の拡充、債権譲渡・危険負担・解除・賃貸借が特に重要とされています。
⑤ 親族(第4編)
家族関係が定められており、「総則」、「婚姻」、「親子」、「親権」、「後見」、「補佐及び補助」、「扶養」の7章があります。
⑥ 相続(第5編)
「相続人の範囲」や「相続分」についての定めがあります。
→民法、身近な法律だが、自分の生活や仕事にどんな関係があるだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
