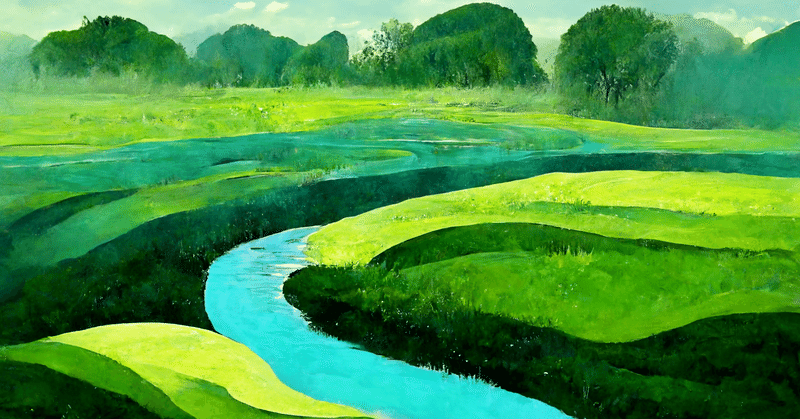
むかしむかし
このページのお話は、桃から生まれた桃朗と竹から生まれた竹姫の物語です。続きができたらこのページに追加していきます。細かな構想はありません。更新しようと思った日にその日の分を書きます。目次は更新した日です。だいたい深夜に更新するので「第●夜」という目次になっています。日付を超えていることが多いので、カレンダーの日付としては実際には翌日だったりします。不定期更新です。誤字脱字単語間違い等はあとでこっそり修正することがあります。
この物語はフィクションです。実在の人物・団体・事件・地名・呼称などにはいっさい関係ありません。昔話・童話・逸話・伝奇などのパロディを含んでいます。
第一夜 2021/11/5
むかしむかしあるところに、お爺さんとお婆さんがいました。
お爺さんは竹林へ散歩に行きました。お婆さんは川へ散歩に行きました。ふたりは仲良しでしたが、好きな散歩コースの趣味はあいませんでした。
お婆さんが川沿いを散歩していると、大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。
おやこれは大変。川にいるタニシが潰れてしまう。お婆さんは桃を捕獲しました。お婆さんは大きな桃をひとりで持てるくらい足腰が丈夫でした。
桃を家に持ち帰ったお婆さんは、鉈で割ってみました。すると、男の赤子が出てきました。
いっぽうお爺さんは、竹林で光る竹を見つけました。
おやこれは大変。竹林の夜が明るくなってしまう。お爺さんは光っていた竹を引っこ抜いて家に持ち帰りました。お爺さんは竹を引っこ抜けるくらい足腰が丈夫でした。
お爺さんが家に帰ると、ちょうどよくお婆さんが鉈を使い終わったところだったので、その鉈で竹を割ってみました。すると、女の赤子が出てきました。
お爺さんとお婆さんは大喜び。男の子と女の子に桃郎と竹姫と名前を付けて大切に育てました。
年月が過ぎ、桃朗と竹姫は元気にすくすくと育ちました。
第二夜 2021/11/6
ある日、四人が暮らす家に訪問販売の魔女がやってきました。
お爺さんとお婆さんは、それぞれの散歩コースへ出かけようとしていたところでした。桃朗と竹姫は、まさかりを担いだ金郎君のところへ遊びにでかけていて留守でした。
「これは魔法のきびだんご、こっちは魔法の鏡。今なら魔法の毒リンゴもおまけに付けるよ」
訪問販売の魔女の商品はどれもこの世のものとは思えない不思議な雰囲気のものばかりでした。
お爺さんとお婆さんは、もうすぐ十歳になる桃朗と竹姫への誕生日プレゼントを選ぶことにしました。
訪問販売の魔女は商品の説明をしました。
魔法のきびだんごは、犬と猿と雉を家来にできるよ。
魔法の鏡は、この世で最も美しいものを教えてくれるよ。
魔法の毒リンゴは、王子様と結婚できるよ。
魔法の柿の種は、栗と臼と蜂と牛糞を仲間にできるよ。
魔法のつづらは、たくさんのお化けや虫や蛇を入れることができるよ。
お爺さんとお婆さんは仲良く首を傾げました。どれもこれもいつ使えばいいのかわかりませんでした。
訪問販売の魔女は、商品の使用上の注意を長々と説明したあとで、つまりはね、と言いました。
「正しく使わないと、正しい結果にはならないよ」
お爺さんとお婆さんはどれを選べばよいかわからなかったので、訪問販売の魔女が最初にお勧めした魔法のきびだんごと魔法の鏡を買うことにしました。今ならおまけに魔法の毒リンゴをつけてもらえるからです。
訪問販売の魔女はほくそ笑んだ顔を隠しながら言いました。
「まいどあり」
お爺さんとお婆さんは、お金を払おうとしましたが、訪問販売の魔女はおそろしい顔とおそろしい声でそれを遮りました。
「そんなものじゃ売ることはできないよ。外に立てかけてあったホウキをもらっていくよ。文句は言わせないよ」
お爺さんとお婆さんは震えながら「ホウキは一本で良いのですか」と聞きました。
訪問販売の魔女は「ありったけもらおうか」と言いました。
ホウキは三本ありました。お爺さんとお婆さんは三本のホウキを訪問販売の魔女に差し出しました。
「最後にいちばん大事なことを伝えるよ」
訪問販売の魔女はもったいぶって言いました。
「いろいろと説明をしたけれどね、絶対に覚えておいてほしいことはひとつだけだよ」
お爺さんとお婆さんは固唾をのんで訪問販売の魔女の言葉を待ちました。
「クーリングオフはきかないよ。これだけは忘れるんじゃないよ」
お爺さんとお婆さんは仲良く首を傾げました。
第三夜 2021/11/12
十歳の誕生日、桃朗には魔法のきびだんごが、竹姫には魔法の鏡がプレゼントされました。
たいそう喜んだふたりは、一日中、プレゼントを眺めて過ごしました。
魔法のきびだんごの説明書には「常温で長期保存が可。非常食にもお勧め」と書かれていました。桃朗は、魔法のきびだんごを非常用持ち出し袋に入れました。
竹姫は、夜になっても魔法の鏡を放そうとしませんでした。魔法の鏡は手鏡の大きさだったため、布団の中にまで持ち込めました。
翌朝、お爺さんとお婆さんがそれぞれの散歩コースに出かけたのを見計らって、竹姫は「内緒の相談があるの」と桃朗に言いました。
「この魔法の鏡、ニセモノなの」
桃朗は「どうして?」と聞きました。
「だってほら、見ててね」と言って、竹姫は魔法の鏡に語りかけました。
「鏡よ鏡、この世で最も美しいものを教えておくれ」
すると、魔法の鏡は眩しく光りだしました。
そして鏡は言いました。
「この世で最も美しいものは、鬼が島にある『蓬莱の玉の枝』」
桃朗が鏡の中をのぞきこむと、それはそれは美しい盆栽が映っていました。銀色に輝く根元から金色に輝く幹と枝が伸び、枝には白く発光する真珠の実がたわわに実っていました。
「これは美しい」
桃朗は初めて見る盆栽に見とれました。
「ね、ニセモノよね?」
竹姫はかわいらしく首を傾げながら言いました。
桃朗は「どうして?」と聞きました。
「この世で最も美しいものは、私だもの」
竹姫はとても悲しそうな顔で続けて言いました。
「お爺さんとお婆さん、悪い訪問販売の魔女に騙されてしまったのかしら」
桃朗は口をパクパクするほかありませんでした。
「どうしたらお爺さんとお婆さんを悲しませずにすむかしら?」
竹姫は真剣な顔をして言いました。
「僕は、魔法の鏡は本物だと思う」
桃朗は勇気をふりしぼって言いました。
竹姫は、ハッとした顔をしてから、何度も大きく頷きました。
「そうね。さすが桃朗。頼りになるわ。魔法の鏡は、ちょっとだけ間違いをしてしまったのね。お爺さんとお婆さんは騙されてなんかいないのよ。よかった。『蓬莱の玉の枝』が無くなれば、鏡は私を映すということね」
桃朗は口をパクパクするほかありませんでした。
竹姫は真剣な顔をして「『蓬莱の玉の枝』を消し去らなければ」と言いました。
桃朗は一生懸命に考えてから聞きました。
「魔法の鏡は、一番と二番を間違えてしまったということ?」
竹姫は聖母のような微笑みをしてから言いました。
「誰にだって間違いはあるものよ。お爺さんとお婆さんが悲しむことになる前に、魔法の鏡を助けてあげればいいのよ」
竹姫は、お爺さんとお婆さん想いの良い子でした。
口をパクパクしていた桃朗は、『蓬莱の玉の枝』を探しに鬼が島へ行くことになりました。
第四夜 2021/11/13
桃朗は川の流れに沿って歩きました。
川はいつか海に辿り着くはずだからです。
鬼が島は海のどこかにあるはずだからです。
竹姫はお爺さんとお婆さんの家で留守番をしています。桃朗が鬼が島へ出かけたことを、お爺さんとお婆さんにばれないようにしなければいけません。
竹姫ならきっとうまくごまかしてくれることでしょう。桃朗にはひとかけらの心配もありませんでした。
桃朗が歩いていると、川辺に何かが倒れていました。
近づいて見ると、それは、大きな口に大きな牙、大きな耳、黒い毛の獣でした。
桃朗は、持ってきた非常用持ち出し袋から、魔法のきびだんごの説明書を取り出しました。
説明書には犬と猿と雉の絵が描かれています。
倒れている獣は、犬の絵の形とそっくりでした。
「もし、そこのおかた、気分でも悪いのですか?」
桃朗は犬に話しかけました。
「魔法のきびだんごを食べて僕の家来になりませんか?」
すると犬は、閉じていた目を重そうに開きながら、ぐったりとしていた首を持ち上げました。そして、ギラギラとした目で桃朗を睨みました。
「俺がおまえの家来だと?」
ぐるぐると地を這うおそろしい音が、その喉から聞こえてきました。
桃朗はびっくりして後ずさりしました。
しかし、よく見てみると、犬のお腹は不自然にゴツゴツと膨れ上がっていて、糸で縫われていました。
「怪我をしているのですか?」
桃朗が聞くと、犬は「なに、よくあることさ」と言いました。
桃朗は「どうして?」と聞きました。
「仕事だからさ」犬は言いました。
「俺の腹は石でいっぱいさ」
「どうして石を食べるのですか?」
桃朗は聞きました。
犬は、ふっと遠い目をしてから言いました。
「食べたのは六匹の子山羊だったんだがな、いろいろあって石が詰まっているのさ」
桃朗は一生懸命に考えてから聞きました。
「仕事だからですか?」
「そうだ」
犬は答えながら、首をぐったりと地面に倒しました。
「仕事って、大変なんですね」
桃朗は犬がかわいそうになりました。
「よかったら、魔法のきびだんごを食べませんか? 説明書によると、ひとつ食べるだけで力がわいてくると書いてあります。きっと、元気になります」
桃朗は犬に近寄り、口元に魔法のきびだんごをひとつ置きました。
犬はクンクンと匂いを確かめてから、がぶりと魔法のきびだんごを丸飲みしました。
すると、犬のお腹はみるみるうちに普通のお腹に戻り、縫いつけられていた糸がぽろぽろと落ちました。
犬はのそりと立ち上がり、ギラギラとした目を桃朗に向けて言いました。
「恩に着る」
桃朗は「よかったですね」と言いました。
「だが、家来にはならないぞ。俺は仕事に行かねばならんからな」
犬は言いました。
「そうですか」
桃朗は少し残念でした。犬のことを好きになりかけていたからです。
「もう仕事に行くのですか?」
「そうだ。次の仕事はあそこだ」
犬は遠くの草原を指さしました。
「あれはなんですか?」
桃朗は聞きました。
「藁の家と、木の枝の家と、煉瓦の家だ。中には豚が住んでいる」
犬は三つの家を見据えながら言うと、「じゃあな」と言って、桃朗に背中を向けて走って行ってしまいました。
「仕事、がんばってください」
桃朗は大きな声で言いました。
第五夜 2022/1/7
犬と別れた桃朗が川下へ向かって歩いていると、後ろから何かが走ってくる気配がしました。
「大変だ大変だ! 忙しい忙しい!」
白いふわふわしたものが、叫びながら桃朗の横を走り抜けて行きました。
あっけにとられた桃朗がその後ろ姿に目をやると、長い耳がぴょこぴょこと跳ねています。
魔法のきびだんごの説明書には、きびだんごをあげても家来になってくれない生き物リストが描かれていました。
その中の「ウサギ」という生き物にそっくりです。
ウサギは、突然立ち止まって頭を抱えました。
「もし、そこのおかた、気分でも悪いのですか?」
桃朗はウサギに走り寄りました。
「どうしようどうしよう。やることがいっぱいで、何からしたらいいかわからない」
ウサギは真っ赤な目をしていました。
「目がとっても赤いですよ。寝不足ですか?」
桃朗は聞きました。
「そういえば、とっても眠いよ」
ウサギは言いました。
「眠いときは眠ったほうがいいですよ。僕も休憩をするので、いっしょにどうですか? 僕が起こしてあげます」
川沿いから少し離れたところに、たくさんの葉っぱを茂らせた大きな木が一本ありました。
桃朗とウサギはその木陰で休憩をすることにしました。
ウサギは桃朗の膝を枕にしてすやすやと眠り始めました。
とても疲れていたようで、いたずらに揺すってみても、まったく起きる気配がありません。
ふわふわの白い体を撫でながら、桃朗がぼんやりとしていると、緑色で、四本足で、背中に堅そうなお椀を乗せた生き物が、川上からやってきました。
川沿いをゆっくりと進んでいきます。
魔法のきびだんごの説明書を見ると、「亀」という生き物にそっくりです。
亀は、のそのそとした足取りで、桃朗の前を横切って、海があるはずの川下へ歩いていきました。
第六夜 2022/1/15
ウサギはなかなか起きませんでした。
桃朗が声をかけると、「あと五分だけ……もうあと五分したら起こして……」と答えるだけで、起きようとしません。
それを繰り返していたら三時間が経ちました。
もう夕方です。ふわふわの毛を撫でるのが好きになった桃朗は、このままここで一夜を過ごすことにしました。
翌朝、まだ眠っているウサギを草の上に寝かせておいて、桃朗が顔を洗おうと川辺へ行くと、何かが倒れていました。
大きな口に大きな牙、大きな耳、黒い毛の獣でした。
黒い毛は、まばらでチリチリになっていて少し様子が違いますが、昨日、魔法のきびだんごをあげた、あの犬です。
「仕事帰りですか?」
桃朗が近寄ると、犬は苦しそうに唸っていました。
よく見ると、酷い火傷をしています。
「なんの仕事をしたのですか?」
桃朗は聞きました。
「煉瓦の家の煙突から落ちたら下に鍋があって熱湯で茹でられたのさ」
犬は遠い目をして言いました。
「仕事って、大変なんですね」
桃朗は、また魔法のきびだんごをあげました。
三つあった魔法のきびだんごは、あとひとつになってしまいました。
犬は、「ありがたい」と言って、魔法のきびだんごをがぶりと食べました。すると、火傷はみるみるうちに治り、黒い毛もツヤツヤになって生えそろいました。
毛づくろいをし、「腹が減ったな」と言った犬は、木陰で朝寝坊をしているウサギを見つけました。
「ほぉ。あれはうまそうだ」
そろりそろりと足音を忍ばせて、犬はウサギに近寄りました。
桃朗は葛藤しました。
お腹がすいたらごはんが食べたいのは当然です。
けれど、ふわふわの毛を撫でさせてくれたウサギのことも好きになっていました。
ハッとあることに気づいた桃朗は叫びました。
「ウサギさん! 起きてください! 五分はとっくに過ぎています!」
「う~ん、あともう五分だけ」と、言いながら薄目を開けたウサギは、犬の姿を見るなり飛び起きて、脱兎の如く駆け出しました。
川下に向かって走り去ったその姿は、あっという間に見えなくなりました。
犬は恨めしそうな顔をして桃朗に振り返りました。
「だって、僕は、昨日、ウサギさんに、『起こしてあげます』と約束をしていたのです」
桃朗はおずおずと言いました。
「先に約束していたものですから。……すみません」
「そうか。それなら仕方ない」
犬はあっさりと言いました。そして桃朗ににじり寄りました。
「おまえもうまそうだ」
第七夜 2022/1/29
「待ってください! 僕は美味しくありません。僕を食べても桃の味しかしませんよ」
桃朗は後ずさりしながら言いました。
一歩、二歩、動くことができたのはそこまででした。
桃朗は立ち竦んでしまいました。
棒立ちになった桃朗の胸に、犬の前足がかかっていました。
黒いしっぽが、桃朗の足に巻き付いていました。
ツヤツヤでフサフサに見えたしっぽは、思ったよりも硬い毛のようでした。
尖った毛先が、桃朗の膝裏とふくらはぎを、チクチクと刺しました。
あのウサギのふわふわとは違いました。
胸に置かれていた犬の前足が、桃朗の肩に這い上がりました。
「桃とはなんだ? 俺は好き嫌いは少ないほうだ」
犬は首を傾げながら、桃朗の首筋に鼻先を近づけました。
生ぬるい息が、桃朗の首から顔を撫でました。
声を出すためではない犬の呼吸が、桃朗に何かを伝えました。
「桃とは……」
絶体絶命を感じた桃朗の脳裏に、竹姫の笑顔が浮かびました。
「桃とは、川を流れていて、割ると中から人が出てくる果物です。美味しくないことで有名です。
なぜなら、栄養はすべて、中に入っていた人に奪われてしまうからです。だから果肉もスカスカで、味もそっけもありません。
僕は、そんな桃の化身です」
生まれて初めて、桃朗は嘘をつきました。
竹姫に教えてもらったとおり、本当と嘘を混ぜました。
「嘘をつくときは、本当のことも言わなければいけないのよ」竹姫はいつもそう言っていました。
目と鼻の先にある犬の目が、訝し気に桃朗を見つめていました。
竹姫はこうも言っていました。「本当の結果に、嘘の理由をつけるといいのよ」
それを聞いたときの桃朗は、いったいいつ役に立つのかと首を傾げました。
けれど今、今がその時であることを確信しました。
「僕の持っているきびだんごには、桃の魔法がかかっているのです。その証拠に、あなたの体を、二回も治すことができました。僕は、あとひとつ魔法のきびだんごを持っています。だから、あと一回、あなたの体を治せます」
桃朗は夢中で言いました。
「……なるほど。確かに二回、助けられた。……おまえは果物なのか? 俺は肉が食いたい」
犬は、桃朗の首筋にぴたりと付けていた鼻先を外して、桃朗の体から離れました。
前足をストンと地面におろした犬を見て、ほっと胸をなでおろした桃朗は、ふと、とてもいいことを思いつきました。
「僕を食べない代わりに、鬼が島へいっしょに行きませんか。鬼が島には金銀財宝がたくさんあるそうです。それを手に入れて、美味しいものをたくさん食べませんか」
第八夜 2022/2/4
鬼が島を目指して、海を目指して、桃朗と犬は川沿いを歩いていきました。
海に辿り着かないまま、太陽が空のてっぺんを通り過ぎて、夕方になりました。
桃朗はお腹がすきました。
海がこんなに遠いとは思っていなかったので、道中のごはんのことを考えていませんでした。
桃朗の隣を歩く犬は、かわいそうなくらいげっそりとしていました。
今にも倒れそうです。
魔法のきびだんごの力でなんとか歩いている状態でした。
このままでは、犬がまたいつ桃朗を食べようとするかわかりません。
しかし桃朗も、空腹のあまり、いざとなったら犬を食べようかと思い始めていました。
けれど、ひとりで鬼が島へ行くよりも仲間がいたほうがいいとも思っていました。
桃朗と犬の気持ちは同じでした。
相手に逃げられたら、追いかける元気がないことも同じでした。
だからいざとなったら相手を食べようとしていることがばれないようにしようと考えていることも同じでした。
「何か食べ物はないかな」
桃朗がきょろきょろとあたりを見まわしながら歩いていると、風に乗って甘酸っぱい匂いが漂ってきました。
前方左手、川から少しそれたところに、幹の細い木が群生していました。
「あの木に、果物がなっているのかもしれません」
それは葡萄の木でした。
近づいてみると、紫色の実がたくさんなっています。
葡萄の木の根元に、犬に似た形をした茶色い毛の小さな獣がいました。
何度も跳び上がったり、木の周りをうろうろとしたりしています。
魔法のきびだんごの説明書を見ると、「狐」という生き物にそっくりです。
「葡萄、美味しそうですね」
桃朗は犬に言いました。
「葡萄よりもそこの狐のほうがうまそうだ」
犬は言いました。
「……だが、今の俺では狩りは難しいだろうな」
空腹すぎて、のろのろとしか歩けないからです。
そうでなくても、一昨日は山羊を食べそこね、昨日は豚を食べそこね、今朝は寝起きのウサギを食べそこねて、自信喪失気味でした。
「とにかくまずは、確実に食べられるものを食べましょうよ」
「そうだな」
桃朗と犬の意見はまとまりました。
桃朗は狐に話しかけました。
「もし、そこのおかた、僕たちもその葡萄をとってもいいですか?」
狐は桃朗に気づくと、振り返って鼻を鳴らしました。
「手が届けばね」
桃朗は葡萄の実に手を伸ばしてみました。
届きません。
思い切り跳び上がってみました。
届きそうで届きません。
「やっぱりね」
がっかりした顔をして、狐は言いました。
「きっとこの葡萄は、酸っぱいよ。美味しくないよ。僕はもういいや」
「酸っぱくてもいいから食べたいです」
桃朗は言いました。
狐は首を傾げました。
「酸っぱくてもいいの?」
「酸っぱいくらいどうってことない」
犬はそう言うと、桃朗を背中に乗せました。
なるべく低い木の下で、桃朗は立ち上がって手を伸ばしました。
そして、なんとか三房の葡萄をもぎとることができました。
その様子を見ていた狐に、桃朗は「どうぞ」と一房を渡しました。
犬にも一房を渡しました。
みんなで仲良く一房ずつを食べることになりました。
手に持った葡萄からは、濃厚な甘酸っぱい匂いがします。
これならきっと、ちょっと酸っぱいだけでしょう。
「いただきます!」
勢いよく一粒食べたとたん、桃朗と犬は、涙を流しました。
狐の言ったことは本当でした。
「なんて酸っぱいんだ!」
喉が刺激され、ゲホゲホと咳き込みました。
桃朗と犬が酸っぱさに悶える様子を見ていた狐は、しばらく思案顔をしていましたが、おそるおそると一粒をかじりました。
するとどうでしょう。狐が大好きな味でした。
「甘い! 美味しい! とってくれてありがとう」
狐は大喜びでたいらげました。
桃朗は、「それはよかったですね」と狐に言ってから、「僕はこれよりもっと美味しくないんですよ」と、犬に言いました。
しかめっつらをしていた犬は、「そうなのか。それは食べなくてよかった」と言いました。
桃朗と犬は、酸っぱさと戦いながら完食しました。
第九夜 2022/2/5
「あー美味しかった! 本当にありがとう。そうだ! お礼をするよ! 願いをひとつ叶えてあげるよ」
得意げな顔で狐が言いました。
「僕は凄い妖怪だから、なんでもできるよ! なんでも言ってみて」
桃朗と犬は仲良く首を傾げました。凄い妖怪なら、どうして自分で葡萄がとれなかったのでしょうか。
きっと、たいした力はないのだろうと思いました。
「僕の袖がほつれてしまっているのを直せますか?」
右腕の袖口を見せながら、桃朗は聞きました。
「それは自分で直せるでしょ? もっと難しいことを頼んでよ」
狐は不満そうに言いました。
桃朗と犬は顔を見合わせました。
「じゃあ、僕たちをあの川の先にある海まで飛ばせますか?」
桃朗は聞きました。
「できるよ!」
狐は嬉しそうに言いました。
「どうしてその力を使って葡萄をとらなかったのですか?」
桃朗は聞きました。
狐は不思議そうな顔をしました。
「どうやって力を使えば葡萄がとれるの?」
それは桃朗にも犬にもわかりませんでした。
桃朗と犬と狐は仲良く首を傾げました。
狐はにこりと笑いました。そのしっぽが、逆立つようにしてむくむくと大きくなりました。そして、ぱさりと九つに割れて扇の形のようになりました。
「葡萄はとれないけど、海に飛ばすのはできるよ! いくよ!」
「あ、待ってください。それなら行き先は海じゃなくて……」
鬼が島がいいです。と、桃朗は言い直そうとしましたが、手遅れでした。
狐の毛の色と同じ茶色い風に巻き込まれたと思った次の瞬間には、桃朗と犬は海にいました。
第十夜 2022/4/4
桃朗と犬を海まで運んだ茶色い風は、くるくるの毛玉が転がるようにして高く舞い上がり、ふわっと膨らんだかと思うと空に溶けて消えてしまいました。
桃朗は砂に埋もれていた足を引っ張り上げました。
犬は、桃朗の背後で砂を掘って遊んでいました。
目の前には海がありました。
初めて見たけれど、桃朗はそれが海だとわかりました。
大きな看板があったからです。
桃朗のちょうど頭上にアーチ形の看板が浮かんでいて、「海へようこそ」と書かれていました。
桃朗はほっとしながら波打ち際に目を向けました。
竹姫から「海に着いたら船を探すのよ。船着き場があるはずよ」と聞いていたとおりでした。
船と思われる形をしたものがいくつかと小屋がふたつ並んでいる場所が見つかりました。
砂遊びに夢中になっていた犬を強引に引っ張って、桃朗は小屋へ向かいました。
ひとつめの小屋の看板には、「片道切符で乗船できる泥船」と書かれていました。
ふたつめの小屋の看板には、「切符のいらない鰐船」と書かれていました。
桃朗は犬に話しかけました。
「泥船と鰐船、どっちがいいと思いますか?」
犬は不機嫌な声で言いました。
「おまえが決めろ。決まるまで、待っていてやる。長くかかってもいいぞ」
桃朗にはわかりました。犬は砂遊びに戻ろうとしているのです。
自分だけ遊んで待つなんてずるいです。
桃朗は、しぶる犬を担ぎあげました。
実は桃朗もお爺さんとお婆さんのように足腰が丈夫でした。
「中に入ってみましょう」
桃朗と犬は、「片道切符で乗船できる泥船」と書かれた小屋に入りました。
すると、そこには、あの白いふわふわのウサギがいました。
第十一夜 2022/4/9
「いらっしゃいませ」と言ったウサギは、桃朗と犬を見ても、表情を変えませんでした。
似ているけど別のウサギなのでしょうか。
桃朗が犬に目くばせをすると、「わかってるぞ。襲わないぞ」と犬は面倒くさそうに言いました。
「切符の代金はいくらですか?」
桃朗はウサギに聞きました。
ウサギが答えた金額は、桃朗が持ってきたお金の何十倍もしました。
とても払えません。
泥船はあきらめて「切符のいらない鰐船」の小屋へ行こうと思った桃朗にウサギが言いました。
「ここへタヌキを連れてきたらお金はいりません」
桃朗は、魔法のきびだんごの説明書を見て、タヌキの形を確認しながら聞きました。
「タヌキを? どうしてですか? お友達ですか?」
「タヌキ汁にします」
ウサギは答えました。
つまらなそうにしていた犬の顔が明るくなりました。
「それは、俺たちも食えるのか?」
「もちろんです」と、ウサギは頷きました。
「泥船にご乗船のお客様にサービスでふるまいます。でも昨日、僕は仕事をさぼってしまって、仕入れに行けていないのです」
しょんぼりした様子のウサギは、赤い目をパチパチしながら続けて言いました。
「昨日は、不覚にも出勤途中で眠ってしまいました。それに、今朝も寝坊してしまいました。だから、今日のタヌキ汁が用意できていません」
どうにも、昨日出会って今朝までいっしょにいたウサギのような気がします。
桃朗が「僕のことを覚えていませんか」と聞こうとしたとき、ウサギがぼそりと言いました。
「僕のことをたぶらかした人に出会ったら、仕返ししなくちゃ」
桃朗の背筋に冷たいものが流れました。
犬とはまた違った恐ろしさをウサギに感じました。
桃朗はこのまま知らん顔をすることにしました。
「タヌキはどこに行けばいるんだ?」
やる気に満ち溢れた顔をしていた犬がウサギに聞きました。
ウサギは小屋の入り口の向こうを指さして言いました。
「海の底です」
桃朗はもういちど魔法のきびだんごの説明書を見ました。
タヌキには背びれも鱗もなさそうです。貝のようでもありません。
陸にいる獣にしか見えません。
涎を垂らしていた犬も同じように疑問に思ったようで、首を傾げていました。
一応、桃朗は犬に聞いてみました。
「海の底へ行ってタヌキを連れてくることはできるでしょうか?」
犬は残念そうに「無理だな」と言いました。
第十二夜 2022/7/24
桃朗と犬はふたつめの小屋に入りました。
「切符のいらない鰐船」の小屋です。
小屋の中には誰もいませんでした。
「すみませーん、誰かいませんかー。もしー」
桃朗が声をかけてしばらくすると、小屋の奥からウサギが出てきました。
「いらっしゃいませ」
「おや? 先ほどのウサギさんではありませんか」
「はい。ふたつの小屋は後ろでつながっています。ふたつとも僕の店です」
桃朗は目を丸くしました。
「お店をふたつも持っているなんて、すごいですね」
「えぇまぁ。それなりに。いろいろありまして」
なぜだかウサギは苦々しい顔をしていました。
「僕たちは海の底にタヌキを探しに行くのは無理なので、鰐船にしようと思うのです」
桃朗はなんとなく気まずくなって言いました。
「泥船の切符を買えなくてごめんなさい」
すると、ウサギは愛想の良い笑顔を見せました。
「泥船のお客様も、鰐船のお客様も、大切なお客様です」
桃朗はほっとして聞きました。
「鰐船は切符がいらないというのは本当ですか?」
「本当です」
「どうして切符がいらないのですか?」
ウサギは桃朗の全身を舐めるように観察すると、くすりと笑って答えました。
「切符の代わりに生皮をもらうからです。生皮は高く売れます。その中身も、まぁ、物によっては、高く買ってもらえます」
桃朗は首を傾げて聞きました。
「ナマカワって、なんですか?」
「知らなくて大丈夫です。お客様は、鰐船に乗って、今から教える暗号を言うだけでいいのです。あとのことはぜんぶ鰐に任せてください」
一瞬、ウサギの笑顔が竹姫の笑顔と重なりました。
桃朗は、そういう笑顔の竹姫に、しばしば騙されているのでした。
だから隣の犬に聞きました。
「ナマカワって、知っていますか?」
犬はギラリと目を光らせ、「知らないなぁ」と言いながら涎を垂らしました。
「……知っているのですね」
桃朗は犬を引っ張って小屋の外に出ました。
「涎が出ていますよ。ナマカワというのは食べ物ですか?」
犬は舌打ちをしました。
「せっかくのチャンスだったのにな」
桃朗が問いただすと、犬は不満そうにナマカワのことを教えてくれました。
「よく考えてください。あなたも餌食になるところでしたよ」
桃朗は少し怒って言いました。
犬は目を見開いて威嚇しました。
「俺が鰐ごときに負けると?」
「だってほら、あんなにいっぱいいますよ」
海辺には、鰐がウヨウヨといました。
犬はまた舌打ちをして、砂を掘り始めました。
「あぁ、腹が減った」
「それは同感です」
桃朗は途方にくれました。
太陽が海の向こうに沈もうとしていました。
ふたつの小屋の右手の丘には、蒲が一面に生えていて、ふわふわとした穂が風に揺れていました。
第十三夜 2022/7/30
ウサギの店を後にした桃朗と犬は、あてもなく砂浜を歩いていました。
「今夜はどこで眠ろう」
桃朗がぼそりと言うと、犬が猫なで声を出しました。
「俺の隣で眠るといいぞ」
犬の魂胆はわかりすぎています。
「僕は美味しくありませんよ」
冷静な口調で言い返してみたものの、桃朗は身の危険を感じていました。
一晩をこの犬と過ごして、無事に朝を迎えられる保証は、あまりなさそうだと思いました。
すっかりと夜になっているのに、思ったよりも明るい砂浜でした。
それもそのはず、今日は満月のようです。
涙ぐみそうになるのを我慢しながら、桃朗が満月の昇った空を見上げていると、犬が呻きだしました。
「ぐあぁあああぁぁぁぁ」
これまでに聞いたことのない低く太い声でした。
見ると、犬の様子はただごとではありません。
魔法のきびだんごで治したばかりの黒い毛皮がバリバリと音を立て引き裂かれていました。
そして、その体が二倍ほどの大きさになりました。
犬は、二本の足で立っていました。
その姿は、半分は犬、半分は人間でした。
変身した自身の体を確認するように見てから、犬は、「忘れていた。今日は満月か。仕事へ行かねばならん」と言いました。
「また仕事ですか?」
桃朗は驚いて目を丸くしました。
「ほとんど何も食べていないのに仕事なんて無理ですよ。今日は休んだらどうですか?」
「なぁに、仕事中に食べるさ。街へ行って乱暴狼藉を働く仕事だ。腹いっぱいに食ってやる」
桃朗よりも背の高くなった犬の目は、満月のように輝いていました。
「……これまでも、食べる仕事だったはずなのでは?」
「……それを言うな」
桃朗は考え直すように言いましたが、犬は聞く耳を持ちませんでした。
満月を仰ぎ見た犬は、「うぉぉぉぉおぉぉぉん」と長い遠吠えをしてから、「じゃあな」と言って、砂浜を囲う茂みに向かって駆けて行ってしまいました。
半分人間のようになった犬の背中を見送りながら、「あっ」と、桃朗は気づきました。
「そうですよ。犬がいなくなってくれて、僕にとっては都合が良いではないですか」
夜中に犬に食べられる心配が無くなりました。
引き留めてしまわなくて良かったのです。
桃朗は、非常用持ち出し袋から魔法のきびだんごを取り出しました。
これが最後のひとつです。
ひとつ食べるだけで力がわいてくるという魔法のきびだんごですから、食べたらきっと空腹もまぎれるのでしょう。
「でも」
桃朗は魔法のきびだんごを非常用持ち出し袋にしまいました。
「これは、僕が食べるためのものではありませんから。僕が僕の家来になっても楽しくありません」
第十四夜 2022/8/24
––翌朝
ピカピカと輝く大きな水面が、桃朗の目の前にありました。
ここは海で、砂浜でした。
岩に囲まれた少し固めの砂の上。大きな葉っぱを敷いて、大きな葉っぱにくるまって、桃朗は眠っていました。
瞼は重くて、いつもならまだ寝ている時間です。目が覚めてしまったのは、肩と背中と腰が、少し痛くなっていたせいでした。
あぁ、布団で眠りたいな。
あぁ、みんなに会いたいな。
あぁ、食卓を囲んで味噌汁が飲みたいな。
家を恋しがりながらも、桃朗は、初めて見る早朝の海に見とれていました。
絹の布のような朝靄が、ふわふわと揺れながら薄まって広がっていきました。海面を跳ねてくる朝陽は、まばゆい粒のようでした。
「なんと美しい……」
しかし、綺麗な光景は瞼の重さに勝てませんでした。
桃朗はあくびをしながら、葉っぱの布団にくるまりました。
ところが、寝入りばな、騒がしい音が聞こえてきて、桃朗の二度寝の邪魔をしました。
人の声でした。
朝靄が晴れ始めた砂浜には、桃朗と背格好がそう違わない子供たちがいました。
輪になって、緑色のものを囲んでいます。
子供たちの足の隙間から見えるあれは、あの緑色のお椀は、一昨日に川で見かけた「亀」ではないでしょうか。
「もしかして、……朝ごはん!」
ひらめいた桃朗は、葉っぱの布団を跳ね上げました。
子供たちは、とても楽しそうに亀を突いたり叩いたりしていました。
そして、「えいっ」という掛け声とともに、亀はひっくり返されました。
「助けてください。元に戻してください」
亀は、腹を空に向けたまま、手足をばたばたさせていました。
子供たちは口々に言いました。
「どうして自分で元に戻れないの?」
「どうして? どうして?」
「教えてくれたら戻してあげてもいいよ!」
ざぶーん、ざざざざ、ざぶーん。
波の音で、みんなが何を言っているのかわかりませんでした。
桃朗は、会話が聞こえるところまで近寄ってみることにしました。
「十秒以内に答えて! 十、九、一! はい時間切れー」
桃朗は、さらに近づいて声をかけてみました。
「もし、そこのかたたち、どうして『九』の次が『一』なのですか?」
亀を囃し立てていた子供たちが次々と桃朗のほうに顔を向けました。
桃朗には一瞬でわかりました。
どの顔を見ても、桃朗を歓迎していない顔でした。
しかし、食事にありつけるかは死活問題です。
歓迎されていないくらいで怯むわけにはいきません。
桃朗は、礼儀正しく挨拶をしなければと思いました。
「おはようございます。僕は桃朗といいます」
すみませんが、朝ごはんを分けてもらえませんか。
桃朗がそう続けようとしたとき、子供たちは、一斉に目を丸くしました。
そして、一呼吸おいて、「ぎゃー」と叫んで走り去ってしまいました。
いったい何事でしょう。
呆気にとられている桃朗の背後で、どさっと音がしました。
振り向くと、犬がいました。
血だらけで、体はぼろぼろ。小さな槍がたくさん刺さった犬が倒れていました。
大きな口は歪んで、大きな牙が剥き出しになって、荒い息をしています。
一見すると、おそろしい怪物のように見えますが、これは、犬が苦しんでいるときの顔でした。
桃朗はもう慣れたものでした。
「どうぞ」と言って、魔法のきびだんごを差し出しました。
「でも、これが最後のひとつですよ」
犬も慣れたものでした。
魔法のきびだんごを、大きなひと口で食べると、すぐさま元のツヤツヤの体に戻りました。
たくさんの小さな槍は、砂の上にぽろぽろと落ちました。
第十五夜 2022/11/13
お腹をすかせた桃朗と犬は、亀の丸焼きを作ることにしました。
犬は、焚火のための木と石を集めてきました。火打石も忘れずに探してきました。
桃朗は、ウサギの小屋の右手の丘に群生している蒲の穂を採ってきました。
平らな石を並べて焚火台を作り、その上に蒲の穂を置きます。
火打石で起こした火花を蒲の穂に飛ばします。
ところがなかなか着火しません。
「うぅむ。三匹の豚の煉瓦の家では、あんなに簡単に燃えていたのだが」
犬はもどかしそうに言いました。
「助けてください。元に戻してください」
焚火台の横でひっくり返ったままの亀が手足をばたばたさせながら大粒の涙を流し始めました。
「助けて助けて」と、悲痛な声が砂浜に響き渡りました。
喉が裂けそうな声を出して、亀は繰り返し懇願しました。
「助けてください。私にはするべきことが残されているのです」
桃朗がどうしたものかと犬を見ると、犬は、
「俺は丸焼きにはこだわらない。ナマでもいい」
と言いました。
桃朗は困りました。
丸焼きにするのも難しそうですが、ナマで食べるのはもっと難しそうに思いました。
突如、
「こらーっ!」
と、桃朗の背後で声がしました。
振り返ると、釣り竿を持った男が走り寄ってきて言いました。
「何をしているんだ! 亀を虐めるな!」
「いえ、僕たちは……」
桃朗は亀を虐めているつもりはありませんでしたが、うまく言葉になりませんでした。
あっという間に、亀は釣り竿の男に抱えられていました。
犬は唸りました。
「それは俺たちのものだ。返せ」
「この亀は、海の者。海に返すのが道理」
釣り竿の男は亀を抱えたまま海に向かって歩いて行ってしまいました。
桃朗も犬も、焚火の材料集めで最後の力を振り絞って歩きまわったものですから、追いかける元気がありませんでした。
しかし、亀は相変わらず「助けて助けて」と叫んでいました。
そして、波打ち際で下ろされた亀は、なぜか海に向かわず、のそのそと砂浜に戻ってきました。
その行先には、小さな砂山がありました。
亀は、砂山に登って言いました。
「いちばーん! また駆けっこでウサギどんに勝ったぞ! これで九十九連勝だぞ!」
砂山から下りた亀は、「ふぅ。任務完了」と言うと、海に向かってまたのそのそと歩いて行きました。そして、振り返ることもなく、波間に姿を消しました。
第十六夜 2022/12/15
「聞いてくれるか」
波打ち際で亀を見送っていた釣り竿の男は、桃朗たちに振り返りました。
そして独り言のように続けました。
「こんなことは初めてなのだ」
桃朗と犬は、首を傾げたまま聞いていました。
「もう何回も、何十回も、何百回も、何千回も、……数えきれないほど亀を助けた。しかし、……こんなことは、初めてなのだ。
砂浜で私は亀を助ける。すると亀は私を海底の煌びやかな城へと招く。
城では、うまい飯をたらふく食い、芳しい香りの酒を飲み、好きな時に眠り、好きな時に起き、竜の子供たちと遊び、毎日を愉快に過ごす。
そこは、時間の無い世界。どれくらいの時を過ごしているのかは、わからぬ。そして……」
——ぐううううううう
釣り竿の男が語っている最中に、桃朗の腹が大きく鳴りました。
「わぁっ、す、す、すみません」
桃朗は慌てて腹を押さえましたが、なおもぐぅぐぅと鳴り続けました。
恥ずかしくなって犬に助けを求めようとしたら、犬の腹も鳴り始めてしまいました。しかも、犬の口からは涎が滝のように流れ出ていました。
「……そなたたち、腹が減っているのか」
「……はい。……『うまい飯』、僕も食べたいです……」
——ぐううううううう
桃朗の腹の音はますます大きくなって止まりません。
釣り竿の男は、桃朗と犬の背後にある焚火台に気づき、なるほど、と頷きました。
「私はそなたたちの食事を邪魔してしまったというわけか……。すまなかった。私は亀を見ると、ああしてしまうのだ」
それから浜辺をぐるりと見渡して、ある一点で目をとめると、にんまりと笑いました。
「しばし待っておれ」と言って、ざくざくと波打ち際を歩いて行った釣り竿の男は、十馬身ほど離れた場所で屈んで何かを持ち上げました。
そして、桃朗と犬の元へ戻ってくると、「ほれ、これを食べよ。なぜかは知らんが、仲良くくっついておった」と言いました。
釣り竿の男が手に持っていたのは、シギとハマグリでした。
シギのクチバシが、ハマグリの殻にがっちりと掴まれていました。
シギとハマグリは、お互いに、「おまえが離さないからだぞ」と言い合っていました。
釣り竿の男は、焚火もらくらくと着火してくれました。
桃朗と犬は大喜びです。
まもなく、こんがりと香ばしい肉と磯のにおいが砂浜に漂い、桃朗と犬の腹を満たしました。
無我夢中の食事をおえた桃朗は、ふと気づいて言いました。
「何か、御礼をしたいのですが」
釣り竿の男は「礼などいらぬ。むしろ、こちらがしたいほどだ」と言いました。
しかし桃朗は竹姫の言葉を思い出して身震いしました。
——「タダより高いものはないのよ」
桃朗がどうしても御礼がしたいと食い下がると、釣り竿の男は言いました。
「では、その蒲の穂をひとつくれないか」
桃朗が採ってきた蒲の穂の束からこぼれ落ちた数本が、焚火台の陰にありました。
「この蒲の穂で、私は新たな人生を歩むのだ」
男は、蒲の穂を拾い上げると、空高く掲げました。
するとそこにアブが止まりました。
男は満足そうに頷きました。
「私にはわかる。これは蜜柑と交換できるのだ」
桃朗と犬は仲良く首を傾げて砂浜を出て行く男を見送りました。
去り際に男は言いました。
「私からも御礼をさせてくれ。すぐそこの岩棚には洞穴がある。その中にある玉手箱は、そなたたちにあげよう」
男の去った後には、釣り竿が残されていました。
第十七夜 2022/12/24
右を見ても左を見ても、箱、箱、箱。
釣り竿を残して去った男が示した洞穴の中は、黒漆の小箱で埋め尽くされていました。
奥から連なる小箱の壁は、手前のものほど艶がありました。
「いったいいくつあるのでしょうね」
小箱の壁はどこまで続いているのかわかりません。
何十、何百、何千、数えきれないくらいありそうでした。
桃朗は、入口付近に散らばっていたいくつかの小箱の蓋を開けてみました。
「……どれも、からっぽのようですが」
「あそこにひとつ、開いていない箱があるぞ」
犬の視線の先には、艶々の新しそうな小箱がありました。
赤い飾り紐が十字にかけられています。
桃朗が背伸びをしてその小箱をとると、辺りに金粉が舞いました。
「何が入っているのでしょうね」
「あいつは玉手箱と言っていた。きっと宝物だ。金銀財宝だ」
うずたかく積み上げられた小箱の壁を見上げながら、桃朗は首を傾げました。
「でも、こんなにたくさんの玉手箱の中身は、どこへ行ったのでしょうね」
「早く開けてみろ。金銀財宝を売ってうまいものをたくさん食べる約束だぞ」
犬が桃朗を急かしました。
玉手箱から金銀財宝が出てきてしまったら、犬は、鬼が島へ行かないつもりなのかもしれません。
それは少し寂しいと桃朗は思いました。
「待ってください。思い出しました。僕はこの箱を見たことがあります。
この中には、たくさんのお化けや虫や蛇が入っています」
桃朗は嘘をつきました。
お化けや虫や蛇が入っているのは、もっと大きなつづらです。
訪問販売の魔女の品書きに書いてありました。
犬は、じれったそうに「だからなんだ。開けてみよう」と言いました。
「開けないほうがいいです。僕はこの箱のことを知っているのです。訪問販売の魔女の品書きで見たものと同じ形の箱です。開けてはいけない箱です」
「この箱がそうだとは限らない」
「いいえ、ぜったいにそうです」
「似たような箱なんていくらでもあるだろう。おまえの勘違いかもしれない。それに、本当にお化けや虫や蛇が出てきても、何も困らない。それはそれで食えるかもしれないしな。だから開けてみればいい」
「いいえ、とても危険なお化けや虫や蛇なのです」
「やめておきましょう」と言って、小箱を元の場所に戻そうとした桃朗の袖を、犬が勢いよく引っ張りました。
その拍子に、桃朗の懐から非常用持ち出し袋が落ちました。
魔法のきびだんごはもう入っていませんが、説明書が入っています。
訪問販売の魔女の品書きは、説明書の裏表紙に書かれていました。
素早く、犬が袋を咥え上げました。
「返してほしければ小箱を開けろ」と犬が唸りながら言うと、牙の突き立った裂け目から魔法のきびだんごの説明書が顔をのぞかせました。
そして運の悪いことに、裏表紙が上になった状態で地面に落ちました。
嘘がばれてしまう。桃朗は青くなって説明書を拾おうとしましたが、間に合いませんでした。
犬は説明書を前足で押さえながら言いました。
「やはり、おまえの勘違いのようだな」
第十八夜 2022/12/31
犬は、品書きを舐めるように見てから桃朗に鋭い目を向けました。
「おい、これを見ろ。違うぞ」
桃朗が改めて見てみると、お化けや虫や蛇を入れるための大きなつづらは、品書きの上のほうに大きく描かれていて、とても目立っていました。
玉手箱とは似ても似つかぬものでした。
「あれれ、本当だ。僕の勘違いかな……」
ははは、と桃朗は笑ってごまかそうとしましたが、すぐに観念してうなだれました。
「すみません、僕はまだいっしょにいたくて……。この玉手箱には、お化けや虫や蛇は入っていないと思います」
開けてみましょう、と桃朗が玉手箱の赤い飾り紐に手をかけると、犬がまた袖を引っ張りました。
「違うと言っているだろう。こっちを見ろ」
犬が鼻先で品書きの左下を指しました。
そこに描かれていたものは、目の前の玉手箱と同じものでした。
「え? ――『未開封の玉手箱、高価買取』……?」
「そうだ。開けるにしても、買い取り価格を聞いてからだ。なになに? 買い取ってもらう方法は、――」
品書きの最下段には、訪問販売の魔女への連絡方法が小さな文字で書かれていました。
桃朗と犬は額を寄せ合って説明を読みました。
「えーと、『空がよく見える場所で、この品書きを燃やしてください。燃やすと煙が出ます。この連絡手段により火災報知器が誤作動しても当方は一切の責任を持ちません。安全な場所で周囲に充分な注意を払って燃やしてください』……なるほど。煙で知らせるのですね」
連絡方法の横には、訪問販売の魔女の似顔絵も描いてありました。
偽物に注意とのことです。
桃朗と犬はその顔をしっかりと目に焼き付けました。
「ところで、火災報知器って知っていますか?」
「知らん」
桃朗と犬は仲良く首を傾げました。
世の中にはわからないことがたくさんあるのだなぁと桃朗は思いました。
桃朗と犬は、洞穴を出て、砂浜の焚火台へ戻りました。
おぼつかない手つきではありましたが、カチカチと火打石を鳴らして、桃朗は三回目で火を付けることに成功しました。
「なかなかやるじゃないか」
犬が感心したように言いました。
桃朗は、照れながら「さっきの人に、火の付け方を見せてもらったおかげです」と言って、品書き付きの説明書を焚火に入れました。
すると、ひゅるるるると、虹色の煙がくねりながら空に伸びていきました。
それをポカンと見上げていた桃朗と犬の背後から、しわがれた声がしました。
「呼んだかい?」
振り返ると、黒服に身を包んだ訪問販売の魔女が立っていました。
桃朗は犬に耳打ちしました。
「でも、あの似顔絵よりも、目元と口元の皺がちょっと多い気がしませんか? 本当に本物か聞いてみましょうか」
犬は「うぉほおん」と大きな声を出して遮りました。
「余計なことを言うな。本物だ」
「僕、さっきの似顔絵、しっかり覚えていますよ。今度は勘違いじゃありません」
「皮膚の皺はな、増えたり減ったりするんだ。人物特定の役には立たない。おまえも人生経験を積めばわかるようになる。あれは本人だ」
犬がそこまで言うのなら本物なのでしょう。
桃朗は未開封の玉手箱を差し出しました。
訪問販売の魔女はたいそう満足した顔をして頷きました。
「こりゃあ、美品じゃ」
「買い取ってもらえますか」
「もちろんだとも。ほれ、これをやろう」
訪問販売の魔女が桃朗に手渡したものは、大判でも小判でも金銀財宝でもありませんでした。
「なんだそれは」
犬は牙を剥き出し、「高価買い取りと書いてあったはずだ。騙すつもりなら容赦しないぞ」と、威嚇しながら言いました。
ひょひょ、と訪問販売の魔女は笑いました。
「それは、魔法のうちでのこづちだよ。なーんでも願いが叶えられる。金が欲しけりゃ好きなだけ出してもらうがよい」
桃朗と犬は、魔法のうちでのこづちの説明書を受け取りました。
裏表紙は、これまた品書きになっていました。
訪問販売の魔女の似顔絵を見ると、さっき燃やした品書きにあった顔よりも皺が減っていました。皺は増えたり減ったりする。犬の言ったことは本当でした。
訪問販売の魔女は、「またごひいきに」と言って、ホウキに乗って飛び去ってしまいました。
魔法のうちでのこづちの説明書にはこう書かれていました。
――なんでも願いが叶ううちでのこづち
――けれど、願いは一度だけ
――よく考えてから願ってください
「なんでも……、一度だけ……」
桃朗は考え込みました。
犬は目をらんらんとさせて言いました。
「うまい食べ物をたくさん出してもらおう」
「いいえ、いいえ、待ってください。こういうときは、一番効果的な願いにしないと、もったいないです。僕の願いもあなたの願いも叶う効果的な願いにしなければ」
「効果的? どういうことだ?」
犬は訝し気に首を傾げていました。
「ほら、葡萄の狐さんへのお願いの仕方、あれはとてももったいなかったと思いました」
海へ行きたいとお願いしてしまったけれど、鬼が島へ行きたいと言えば良かった。と、桃朗はずっと後悔していました。
けれど、本当の本当の願いは、何でしょうか。
鬼が島へ行くのは、『蓬莱の玉の枝』を探すためです。鬼が島へ行くことは願いなのでしょうか?
「つまり、……つまり、何が一番の願いなのでしょう。一番の願いは……」
桃朗がどう願おうかと一生懸命考えていると、苛立った犬が言いました。
「もういい、俺が願いを言ってやる。うちでのこづちよ、我の願いを――」
犬が願いの呪文を開始してしまいました。
桃朗は考えがまとまらないまま、慌てて叫びました。
*
気が付くと桃朗は、眩い光の中にいました。
「こぉらぁーーーー! なんだぁおまえはぁ! 我らの畑になんの用だぁ」
暴風のような声が、辺りの空気を揺すりました。
ノッシノッシと地面を揺らして白い光の中から姿を見せたのは、頭に二本のツノのある大きな大きな鬼でした。
肌は岩石のようにゴツゴツとして頑丈そうです。
顔の半分くらいが口ではないかと思うほどに大きな口です。
手足の爪は、犬の爪がかわいく見えるほどに鋭く堅そうです。
そして、黒光りしている大きくて重そうな棍棒を持っています。
竦み上がった桃朗の後ろ襟を、鬼の大きな手がひょいと摘まみ上げました。
桃朗は宙づりになり、手足をばたばたとさせましたが、鬼はまったく気にとめません。
「お嬢、お嬢、コソ泥を捕まえました。どうしますか。煮て食いますか、焼いて食いますか」
桃朗は怖ろしさのあまり気を失ってしまいました。
*
頬をペチペチと叩かれて、桃朗は目を覚ましました。
ぼんやりした視界に、人の顔がうっすらと見え始めました。
「あーよかった。桃朗」
それはよく知る声でした。
目の前の人の顔は、竹姫の顔でした。
「あれ? 僕……、どこにいるの?」
桃朗は上半身を起こしてきょろきょろと見まわしました。
四方八方に、魔法の鏡で見た『蓬莱の玉の枝』が整然と並んで生えていました。
眩い光は、『蓬莱の玉の枝』の真珠の実から発されていたものでした。
「ふふふー。ここは、『蓬莱の玉の枝』の畑よ」
竹姫は楽しそうに言いました。
その隣には、さっきの鬼が行儀よく座っていました。
「お嬢の知り合いなら早くそう言ってくださいよ」
いったいどういうことなのでしょう。
桃朗が口をパクパクさせていると、竹姫が言いました。
「桃朗だけに任せっきりにするわけにはいかないもの。
私も、私ができることをしていたのよ。
あのね、桃朗が出発してすぐに訪問販売の魔女が来てね、事情を聞いてもらったの。
そうしたらね、『蓬莱の玉の枝』の試供品をくれたの」
竹姫は、目をぱちくりしている桃朗の手をとって畑を歩きながら話を続けました。
「悔しいけれど確かに美しかったわ。
この世から消してしまうにはもったいない美しさよ。
美しい者には美しさの価値がわかるものなのよね。
だからね、町の人に私とどっちが美しいかを聞いてみようと思ったの。
でもね、町へ行く途中で、『蓬莱の玉の枝』を譲って欲しいという人が現れてね、えーと、名前は忘れちゃったけど、どこかの偉い皇子様だったわね。なんでも、想い人にプレゼントしたいのだとか言ってたわね。
どうしてもと頼まれたから、仕方がないから譲ってあげたの。
そうしたらね、お礼に金銀財宝が届いたの。
おかげで、家中をリフォームできたのよ。
お爺さんとお婆さんは大喜びよ。
そこで私は思ったの。
『蓬莱の玉の枝』は、敵ではないの。
素晴らしい味方なのよ。
やっぱり美しいものは大切にするべきなのよね。
だから、訪問販売の魔女に相談したらね、苗を売ってくれると言われたの。
鬼が島から買った苗を自分で育てたものは販売していいって言われたの。
しかもこの鬼さんも来てくれたの。育成のコツをいろいろと教えてくれるし、どんな重いものでも持ってくれるし、とっても頼りになるのよ。
でもね、盆栽は鬼が島の専売だというの。
だからね、地植えにすることにしたの。
それでね、ここを『蓬莱の玉の枝』の畑にしたのよ」
桃朗には、何が「だから」なのか「それで」なのか理解できませんでしたが、相槌を打ちながら聞きました。
「あそこの辺りの枝は、もうすぐ出荷よ。こっちは植えたばかり。そっちは、ちょっと違う肥料をあげてみたところ」
歩きながら竹姫はいろいろと紹介してくれますが、桃朗には、いまいち違いがわかりませんでした。
しかし、鏡で見たのとはまた違う、実物の艶めかしい美しさに圧倒されていました。
畑を抜けると、そこは、お爺さんとお婆さんの家でした。
竹姫は、お爺さんとお婆さんの家の前の空き地を『蓬莱の玉の枝』の畑にしたのでした。
「それでね、さすが私なんだけど、育てるのが上手でね、鬼が島産の『蓬莱の玉の枝』にも劣らないほど美しく育てることができるようになったの」
「さすがです、お嬢は。もうすぐ本家から正式に認定証がもらえること間違いなしですよ」
後ろに付き従って歩いていた鬼が、誇らしげに言いました。
「すごいね……」
桃朗はやっとのことでひとこと声を出しました。
「あら、感動が少ないわね」
竹姫が、「桃朗ってこういう人なの。つまらないでしょ?」と鬼に同意を求めると、鬼は、「そうですね、つまらないっすね」と頷きました。
「でも桃朗が突然畑にいるからびっくりしたわ。3か月もいなくなっていたのに」
「3か月?」
思わず桃朗は聞き返しました。
「帰るのが遅くなるのなら、手紙くらい出してよね」
竹姫は拗ねた口ぶりで言いました。
「そんなに心配なんてしてないわよ。ちょっと気になっていただけよ。でも、3か月も連絡が無いなんて」
しょんぼりとした竹姫の肩に手を添えながら、鬼は、「薄情なやつですな」と同調を示しました。
3か月も経っていた? いったいどういうことなのでしょう。
桃朗は指を折りながら日にちを数えてみました。
今日は、出発してから3日目です。
竹姫にからかわれているのかもしれません。
しかし、確かに、たった3日で『蓬莱の玉の枝』の畑がこれほど豊穣なのは、不自然です。
そういえば、さっきから、少しの暑さを感じていました。歩いているだけで汗ばみます。出発した日は、まだ春の始めだったはずでした。
ふと思いついて、桃朗は、懐から、魔法のうちでのこづちの説明書を取り出しました。ひっくり返して裏表紙を見ます。
新しくなった品書きには、あの「玉手箱」が載っていました。
――訪問販売の魔女が独自のルートで極秘に入手した貴重な玉手箱
――開けると時をぐんぐん進める煙を出します
――使用済みの玉手箱でも、残留煙に注意
――効能が残っていることがあります
――未開封の玉手箱でも、漏れ出る煙に注意
――長く傍に置くのは危険
――不要になった玉手箱は高価買取いたします
桃朗は、あの洞穴でいくつかの玉手箱を開けたとき、少しほこりっぽいなと思ったことを思い出しました。
残留煙があったのかもしれません。
玉手箱の魔法がかかってしまったということなのでしょうか。
3か月経っているというのは本当なのかもしれません。
けれど実感はありません。
うーんと唸りながら桃朗は考え込みました。
「どうしてあそこにいたの?」
竹姫に聞かれて、桃朗は我に返りました。
「僕が、魔法のうちでのこづちに願ったからだと思う」
「何を願ったの?」
「『この世で最も美しいものの元へ』」
桃朗は、あのとき叫んだ言葉をそのまま言いました。
この世で最も美しいものは『蓬莱の玉の枝』。魔法の鏡がそう言っていたのだからそれを疑う余地はありませんでした。
だから、あのとき、桃朗は、犬より先に願いを言い切るために省略して言ったのでした。
「鬼が島の『蓬莱の玉の枝』よりも、美しいってことになるよね。竹姫は、すごいね」
育て方によるものなのか、時季的なものなのかは、わかりませんが、状況から察するに、竹姫の育てている『蓬莱の玉の枝』の中に、鬼が島のものよりも美しいものがあるということなのでしょう。
竹姫が目を潤ませて桃朗に飛びつきました。
「わぁ、嬉しい。やっぱり、私がいちばん美しいのね」
鬼は目を細めて「間違いないです。この世で最も美しいのは、お嬢で間違いない」と、デレデレしながら言いました。
何か勘違いされてしまったようです。
「あのね、僕は、竹姫の『蓬莱の玉の枝』の畑はすごいねって言ってるんだけど……」と桃朗が言うと、竹姫は「それもわかってるわよ」と弾んだ声で言いました。
さらに桃朗が訂正しようとしたとき、袖が何か引っ張られてつんのめりました。
そんな桃朗に気づきもせず、竹姫と鬼は、仲睦まじそうにお爺さんとお婆さんの家へ入っていってしまいました。
「余計なことを言うな」
引っ張られた袖の先を見ると、犬がいました。
「あなたもここへ来ていたのですね。お互い無事でよかったですね」
桃朗はそう言いながら、冷や汗をかきました。
魔法のうちでのこづちへの願いの途中で割り込んだことを恨まれているに違いありません。
ところが、犬は、「おまえの言ったとおり、俺の願いも叶ったぞ。ここの食い物はうまいなぁ。しばらくいてやってもいいぞ」と、上機嫌な顔をして言いました。
「本当ですか!」
嬉しさのあまり、桃朗は犬に飛びついて喜びました。
「僕も、お爺さんとお婆さんの作ったごはん、大好きです。ずっとここで暮らしましょうよ」
「ああ、だが、今日はそろそろ仕事へ行かねばならん。
3か月経っているらしいからな。
だいぶ休んでしまったことになる」
桃朗は不安になって聞きました。
「今日はいったいどんな仕事ですか?」
「森へ行って、赤い頭巾を被った少女に会う仕事だ」
「その仕事は、危険ではないのですか?」
「危険なわけがない。赤い頭巾を被った少女だぞ。安全に決まっている」
桃朗は胸をなでおろしました。
「そうですか。仕事、頑張ってきてください!」
桃郎は元気よく犬を送り出しました。
*
竹姫の育てた『蓬莱の玉の枝』は、評判が評判を呼び、たいそう高く売れるようになりました。
訪問販売の魔女は、定期的に訪れては、いろいろな魔法の商品を売ってくれました。お代は、『蓬莱の玉の枝』で作ったホウキでした。いたく気に入ったようで、お爺さんとお婆さんが内職で作った『蓬莱の玉の枝』のホウキを、いつもありったけ持って行きました。
鬼は相変わらず竹姫にべったりでした。
どうやら魔法の毒リンゴを食べたようですが、竹姫はそこのところを明らかにしようとしません。
犬は相変わらず働き者でした。
桃朗は、犬のために魔法のきびだんごをたくさん買えるように、竹姫の『蓬莱の玉の枝』の畑で一生懸命働きました。
そうして桃朗と竹姫とお爺さんとお婆さんと犬と鬼が幸せに暮らしていたある日、庭で日向ぼっこをしながら訪問販売の魔女の品書きを見るのが趣味になっていた犬が、桃朗を呼びました。
「重大な話がある」
犬の声はただごとではありませんでした。
桃朗はついにこの時が来たと覚悟しました。
魔法のきびだんごは桃の魔法ではありません。訪問販売の魔女の魔法の商品です。これまで、犬にばれないようになんとかごまかしながらやり過ごしてきましたが、品書きに書かれているので、いつかは犬にばれると思っていました。
桃朗は神妙な顔をして庭に出て犬の前に正座しました。
「ごめんなさい」
犬はキョトンとして言いました。
「なぜ謝る?」
「……魔法のきびだんごのことですよね?」
桃朗はおずおずと言いました。
犬は、品書きの魔法のきびだんごの紹介を一読してから首を傾げました。
「魔法のきびだんご? おまえの桃の魔法のきびだんごと似てるやつだな。ふむ。こっちのやつは犬と猿と雉に効くものか。これがどうかしたか?」
「騙してごめんなさい」と言う桃朗の言葉に被せるようにして犬は、「俺はオオカミだから関係ないな」とさらりと言って、品書きの欄外を指しました。
「それよりこれを見ろ」
「え? え?」
動揺したまま桃朗は犬の指した場所に目をやりました。
そこには小さな小さな小さな文字で、「特別魔法訪問販売法に基づく表記」と書かれていました。そして、訪問販売の魔女の住所が書いてありました。
――鬼が島一丁目一番地
「え? どういうことですか?」
「やつら、グルだったんだ」
犬は鋭い目をして言いました。
「え? どういうことですか?」
桃朗は犬が犬でなかったらしい衝撃からまだ抜け出せていませんでした。
「わからないのか?」と呆れた顔をして犬が言いました。
「訪問販売の魔女は、鬼が島の販売員だったんだ」
(おしまい)
