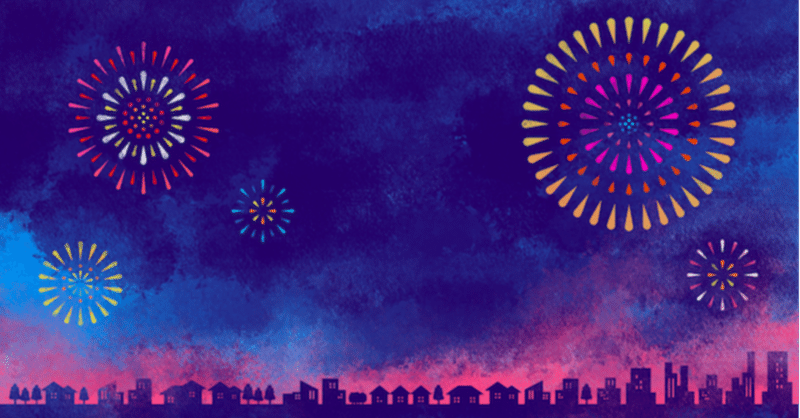
ショートショート 『月が綺麗ですね』
ドン、と花火の打ち上がる音の合間に、草むらの鈴虫がリリリ、とすだく。徹は空から目を落として、着なれぬ浴衣と合わせた草履を見つめた。どこからか蚊取りの匂いがぷんと匂う。
「刺されました?」
徹の横に座る女が訊く。徹はいいえ、と首を振ってまた遠くの空の花火に目を戻す。その徹の視線の先を見るように、女もついと細い頸を動かした。
この女——湯田幸子は、徹の何回目かの見合い相手で、釣書によると年は三十七であった。もう女としては盛りを過ぎようという年ではあるが、ほかならぬ徹も四十である。年についてあれこれ思うところはない。それに、若い折ならともかく、この年になって結婚相手に求めるものは、外から見えるものとは違う、別の何かであった。例えば性格や、互いの価値観。結婚をする上で、それは避けては通れない問題だろうと思っていた。
だから一週間ほど前に、『浴衣を着て、花火を見に行きませんか?』と、幸子から誘われたとき、徹は『花火ですか?』と、思わずオウム返しに聞き返した。幸子とはまだ一度顔合わせをしただけだったし、それに徹にとって、いい年をした男女が、それも浴衣を着て花火を見に行くなどということは、まったく徹の価値の外にあるものだったからだ。
それでも誘いを受けてしまったのは、この縁を簡単に手放したくなかったからか、これまでの経験からきっとまた何回か会って終わりだ、と諦めていたからか。別れを増やすだけの見合いを重ねるうちに、徹は自分が望むものを見失って自棄になっていたのかもしれなかった。きっと今回も外れだ。人混みの中、大人げなく揃って浴衣を着てそぞろ歩く——そういうことが好きな女性とやっていくことなどどうせ無理だろう、とあの時の徹は思っていた。けれど——。
徹は静かな空間に身をゆだねて、一つ吐息をついた。花火から少し離れた、影絵のような木立の向こうには、おぼろな月が浮かんでいる。その優しい光を横切って、薄い雲が通り過ぎていく。結婚か。徹は胸の中で呟いた。
愛するということ——かの夏目漱石は、『アイラブユー』を、『月が綺麗ですね』と訳したという。『月が綺麗ですね』。徹は、その言葉に自分の求める確かな価値のようなものを感じていた。その言葉には、こうして二人で夜空に見上げる月が、その清かな光が、それを見上げるあなたが綺麗なのだと、そんな思いが込められていると思えるからだ。そして、その言葉を分かち合い、その一言で、通じ合える男女は互いにとって理想の相手だろうとも思っていた。
『月が綺麗ですね』、その一言で通じ合える何か。徹はふと隣の幸子を見やった。その一言は、彼女にとっての、この花火大会への誘いであっただろうか。
「このお寺から花火が見えるなんて、地元の人間でもあんまり知らないんですよ」
花火を映した瞳で、幸子が徹に意味ありげに微笑む。「花火の日だけ、夜も解放をしてるんです」
寺の長い縁側には、ほかにもちらほらと人影が揃って空を見上げている。徹は黙ってうなづいた。
いい年をして花火など馬鹿馬鹿しい、などと彼女の誘いを断ってしまっていたら、徹が彼女の気持ちを知ることはなかっただろう。彼女は二人でただ花火を見たかったのだ。静かな、とっておきのこの場所で、共に花火を楽しんでくれる相手を探していたのだ。それがきっと彼女の求める価値だから。もしかして、自分は彼女に試されたんだろうか。そんな考えが頭をよぎって徹は苦笑いした。
「どうしたんですか?」
その苦さに気付いた幸子が、徹をゆっくりと振り向く。長い髪をきれいにまとめた彼女の後ろに、大きな花火が咲いては消える。そのたびに、幸子の顔に影が生まれて、徹を見つめる瞳だけがきらきらときらめいた。
「いいえ——」
徹は口元を緩めて、幸子を見つめ返した。幸子は臆することなく、教えてくれた。自分の好きなものを、自分の好きな場所を。そして、同時に自分に訊ねてくれたのだ。あなたはどうですか、わたしの好きなものを好きと言ってくれるでしょうか。わたしたちはうまくやっていけるでしょうか。
徹は彼女を見つめたまま、うなづいた。
「花火、とても綺麗ですね」
ぱっと、また一つ、ひときわ大きな花火が夜空に咲く。その光に、一瞬照らされた幸子の頬がさっと朱を刷いたように赤くなる。
「ええ——」
彼女はややあって恥ずかしそうに微笑んだ。
「とっても綺麗です」
ドン、と徹の鼓動に重なるように、花火がまた一つ、夜空に打ち上げられた。
『月が綺麗ですね 完』
読んでいただき、ありがとうございました🙏
その他の小説はこちらのサイトマップから、ご覧いただけます😃
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
