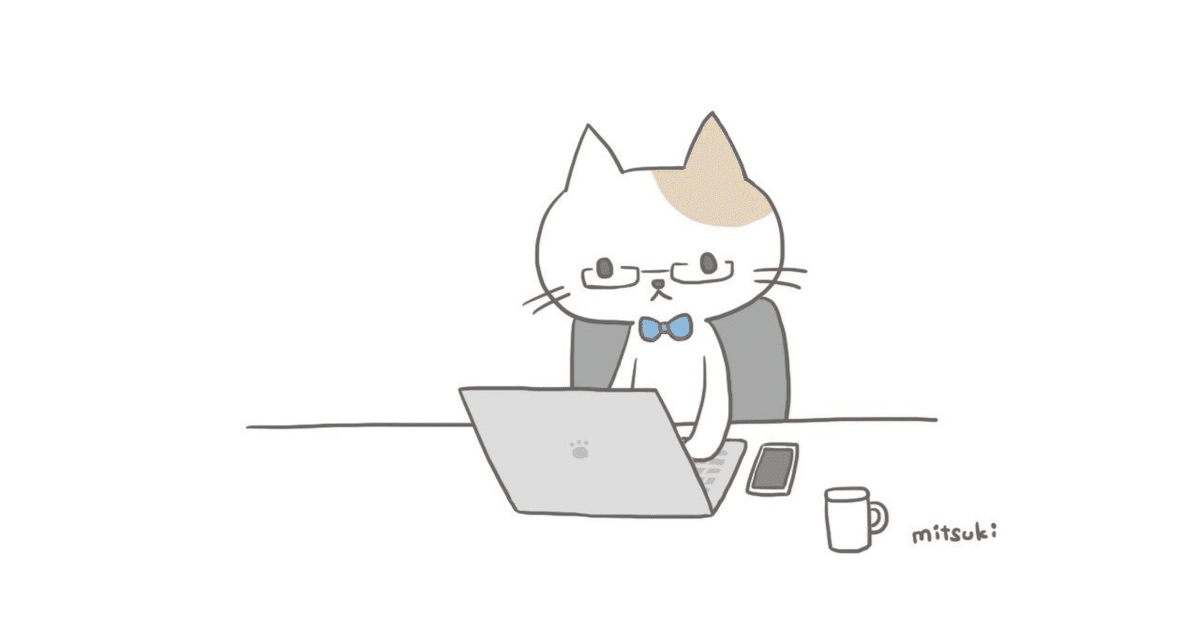
リモートワーク、フレックス制度の振り返りと次に向けて・・・
現職はコロナ前からリモートワーク、フルフレックス制度があり、社外の協力者も多いので当たり前に使う環境である。
日系メーカーから転職した当時は、出張が終わったのが13時だった時、でこれから帰社かな~と思ったら、社長から直帰であと続きは在宅でどうぞと言われ、びっくりしたのは懐かしい思い出。
個人としては、リモートワーク、フルフレックス制度は本当にとても働きやすい。特にワーママになった後はこの制度のおかげでフルで働けていると思っている。
しかし、管理職として働いていると、この制度は特に製造業、実際にモノを作る会社においては組織として効率的に回すのに足かせになる部分もあると感じることがある。
そして、次の仕事場ではリモートワークは週1程度、フレックス制度はないという。(やっていけるか不安)
そこで、フレックス制度、リモートワークがこれまでどれくらいメリットをもたらしたか、デメリットはどんなものかを振り返り、次の仕事場ではどう進めるかの頭の整理で本記事を書いてみる。
リモートワーク、フレックス制度のメリット
一言でいうと、自分の仕事を集中して自分のペースで進めることができる!こと。
具体的には、
保育園から呼び出しが来た際、途中で抜けてもまた夜復活して仕事ができる。旅先からも仕事ができる(しないけど)。打ち合わせが無くて今日は気分が乗らないな、昨日遅くまで働いたしな~となれば、今日は10時~15時まで仕事してあとは好きにしよう!ということもできる。
全ては自分次第でコントロールできるのはワーママにとって精神衛生上とても良い。
リモートワーク、フレックス制度のデメリット
現場との情報格差
現場(ラボ、製造現場)にいる者とリモートしている者の間で情報格差を生んでしまう。
特に管理職でリモートが多めの私は、現場の情報を収集するのに本当に時間がかかるし、全部を把握することは難しいし、そもそも情報があるということすら知らなかったという事態が発生する。(ただし、この問題は指示系統がおかしい、上の上が管理職をすっ飛ばし現場に直接指示を下すことが大きな要因でもある)
私が働いている業界が製造業であるがゆえに、モノづくりに関わる現場に多くの情報が集中する。
実際に手に取る製品が主役なのに、オンラインでは現物を五感で感じることができない。
IT関連だとまた違うかもしれないが、製造業ではフルリモートっていうのは限界がある気がする。
ふわふわな概念が一人歩きしてしまい、営業部、開発部、間接部門が同じ製品イメージを共有できていないため売れないし、売れるものも開発できないの負のループに陥っている部分があるなと感じる。
ブレストの難しさ
現職の製品はアイデア勝負なところがあるので、ブレストやディスカッションが重要だと考えている。
オンラインミーティングは報告、相談には使えるけどブレストはなかなかに難しい。
次の会社ではどうするか
次の会社ではフレックス制度がないらしい。知った時は今時ないの!?無理じゃない!?これから小1の壁もあるんだよ!?とひるんだ。Twitterを眺めると、日系企業はまだまだフレックスも中抜けもできない会社があると知る。
幸い在宅はできるようなので、在宅を挟みつつなんとかやりくりするしかない。しかしフレックスがないせいで、8時間働けない時は有給を切り崩すしかない。
保育園の呼び出しがあった時、その日は8時間働けなくても次の日以降9時間ずつ働いて月でトータル勤務時間合わせられた方が9時間稼働の日に残業代1時間もらうより健全な気がするんだけど。。
そもそも、次の会社にはワーママなんていなかったんだろうな、と察する。
また、効率的に働くには出社した方が良いことは身をもってわかっている。ただし、集中力が必要な書類作成、報告書作成、資料作成は在宅の方が良かったりするけど。
上の子が小学校まであと2年。その間に成果を出し裁量労働で働けるよう頑張るか、それとも無理といって転職したっていいかなと思っている。ただし、入社してからには成果をつかんでいく。
頑張ろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
