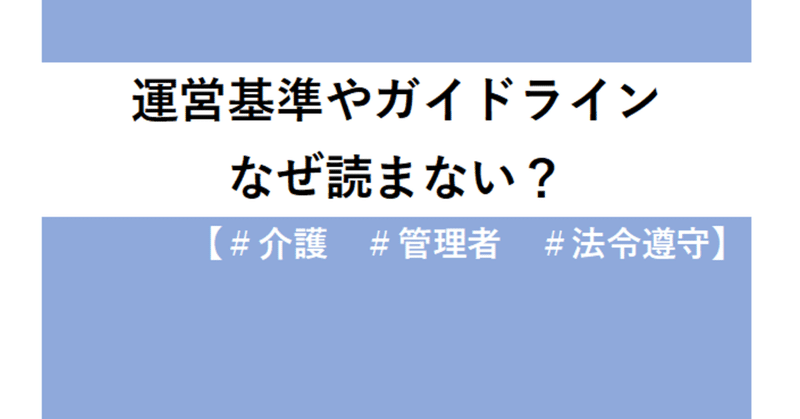
なぜ運営基準やガイドラインを「読みたくない!」と嫌悪するのか?
昨日の記事において、介護事業所や施設における管理者の本質的な役割は利用者の対応や人員調整といった現場業務だけではなく、法令や運営基準に目を向け、それに沿った体制を整備することにある・・・とお伝えした。
内容はキツめとなったが、現場業務が大変であることを承知のうえで、その現場を成立させるためにも、管理者は法令に沿った現場づくりに努めていただきたいと願って記事にした次第だ。
とは言え、管理者が法令遵守や事業所の整備に全く目を向けていないわけではないということも理解している。これらが自身の役割であることを承知のうえで、国や地域からの通知文などだって目を通しているだろう。事務員や運営法人に詳細把握を任せている方もいるかもしれないが、職員らへの周知や文書管理など直接的に整備するのは、結局のところ管理者となる。
この点を踏まえて、介護事業所の管理者と経営を担っているという立場から常日頃思っていることをお伝えしたい。それはこの手のテーマを同法人内の施設長や他法人の管理者と意見交換してみて思うことである。(もちろん、全ての管理者が以下のような現状ではないことは承知している)
まず、どの事業所や施設でも管理者や施設長も、現場対応に追われている中で法令遵守や事業所の整備に頭を抱えていることは共通している。この点については私も同感だ。
しかし、管理職という立場にある方々の中には「なぜその法令ができたのか」という社会的背景や必要性が曖昧なうえに、「運営基準にどのように明記されているのか」を確認しないまま、通知文を起点に「自分たちなりに」事業所の整備を進めようとしている人がいる。
もちろん、通知文にも概要は記載されているが、あくまでも概要である。社会構造や環境の変化、問題提起の起因となった事例や統計まで当然ながら事細かく記載されてはいない。また、感染症などの一般的・共通的な考え方や手技についてはガイドラインとして公開されているが、これも目を通さない人たちもいる。
こう言っては何だが、おそらく「面倒くさい」だけなのだろう。
先日、業務継続計画(BCP)についてオンラインセミナーの案内が届いたが、その講演内容の中に「基礎知識」という言葉があったところを見ると、感染や自然災害に対して「何を整備すればいいのか」以前に、それを成すための基礎知識やガイドラインも学習していない人が多いのだろう。
このように書くと、「ずいぶんと上から目線で物を言ってやがるな」と憤慨されると思うが安心していただきたい。私が管理・運営している事業所や施設においても整備はこれからであり、各管理職もガイドラインの出だしくらいは目を通しているレベルである。それ以前に上記のように法令整備における詳細や解説となると当方に相談してくるため、当面は「何を整備すればいいか」以前に一般的な仕事の進め方を指南することになるだろう。
とは言え、「整備が進んでいない事業所がある=まだ先延ばししてもいいだろう」と思って安心しないでいただきたい。BCPにおいては令和6年3月31日までの猶予期間があるとは言え、感染症のまん延(クラスターなど)や地震等で被災するレベルとなったときに、事業が継続できるように機能できる体制にしなければいけない。法令や運営基準で定められているものは全て法令遵守のためではなく、「自分たちの事業所を守るの体制整備」という認識でなければならないのだ。
しかし、ここでまた「進め方が分からない」という話に戻る。それ以前に法令が制定された社会背景や必要性は曖昧、法令の理解は浅い、ガイドラインにも目を通さない、これら文書を読むのが「面倒くさい」という始末。
だが逆に言えば、こういった法令遵守や整備を進めるための基本的な「情報」を知ること、理解することができれば良いという話でもある。
それはつまり、法令やガイドラインなどの文書を読むのが「面倒くさい」と思うことから脱却するということである。
それにしてもなぜ、このような法令やガイドラインなどの文書を、管理者の皆さんは毛嫌いするのだろうか?
もちろん私も好きというわけではないし、介護職員処遇改善加算といった算定要件に係る内容となると、もはや古代文字の解読のように思えてくる。しかし、それを読み込まないと話が進まないので幾度も確認するだけの話だ。
ここで日常的に法令や運営基準などに対して抵抗がない人と、上記のような「面倒くさい」と考えて整備の進行を先送りしている管理者との違いを考えてみたところ、次のような結論に至った。
法令や運営基準、ガイドラインなどを読むのが「面倒くさい」と嫌悪する人は、この手の文書を読むことに「慣れていない」だけ。
この手の話をすると、頭の良さや理解力だとか、文系理系だとか、読書量や文才だとかおっしゃる人がいるが、私はあまり関係ないと思っている。全く関係がないとまでは言わないが、私自身、介護に何も分からない状態で管理者になって法令や運営基準を目の当たりにしたときは、どこから見て、何をどう理解すればいいか分からなかった。事業所のキャリアのある人たちも分からないし、インターネットも含めて法令の読み方に関しての情報なんて一切ない中でひたすら読み込んできた。法令や運営基準の読み込みを”習慣化”して、自分の中で「これはこういうものだ」と体に馴染ませてきた。
すると次第に、条文の構造や準用文との兼ね合いなどが見えてきたし、自分の事業所にとって必要な部分だけを抽出するなど、効率的に読み進められるようになった。もちろん、解釈となると話は別だが、「面倒くさい」「何を書いているから分からない」「自分の役割ではない」と言って目を背けていたらこうはならなかっただろう。
このように書くと、まるで意識高い系みたいに思われるかもしれないが、別にそう思われても結構だ。ちゃんと習慣化として積み重ねた自信もあるし、それによって他事業所や他法人から相談を受けることもある。(さすがに細かい話へは「管轄の市町村へ質問したほうが良いです」と伝えるが・・・)
しかし、やってきたことは単純で、基本的に「ひたすら読む」だけだ。
確かに「ひたすら読む」と言っても一定のコツはあり、それはもはや「勉強の仕方」「読書の仕方」に発展するので本項では割愛するが、それでも「とりあえず読む」を何回もするくらいならば誰でもできるはずだ。私はただ、誰でもできることを人よりも多くしてきただけに過ぎない。
それに法令やガイドラインなどを読まない管理者の方々を責めるつもりもない。と言うのも、管理者に最近なった方々は法令などの知識や活用に理解をしているが、それは先達者の指導のたまものであり、またインターネットや書籍などの情報に恵まれていからだと思われる。
しかし、現場上がりで管理者や施設長になった方々はそうはいかない。特に「仕事はすべて現場で教わった」というタイプの管理者ならば、法令ベースで職場を整備するとか、ガイドラインに沿って対策を立てるとなると、頭ではわかるが行動に移せない、踏み込めないとなるのは仕方ないと思われる。
それでも、その一歩を踏み出さなければ始まらない。
何も運営基準の何条に何が書かれているかまで知る必要はない。目を通せばわかるが、契約時の説明や地域連携など大抵の項目はすでに日常でやっていることであり、それが単純に文章となっているだけの話だ。
もちろん、細かくて分からないこともたくさんあるだろうが、いきなり全てを理解しようとせず、はじめは「こういう文章が確かあったな」「法律ではこういう言い回しをするのか」くらいで良い。
まずは出勤してから業務日誌を確認する前、あるいは勤務終了前に運営基準やガイドラインを手に取ってみてほしい。そして最初は1分間でいいので、とりあえず眺めるところから始めてみてほしい。それを勤務するたびに習慣することで、法令や運営基準、ガイドラインなどを読むことに慣れていただければ幸いである。
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
