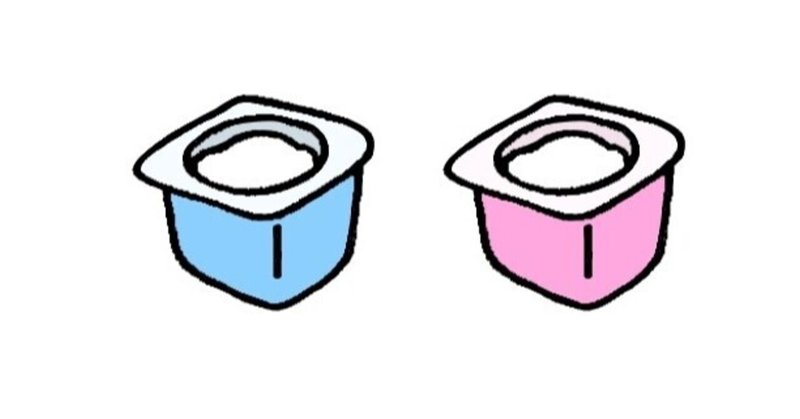
『ヨーグルト』
「また!ない!」
大声を上げて、冷蔵庫の扉を力いっぱい閉めた。
ドカンと大きな音がして、私の身長より高い冷蔵庫が揺れた。
中からはガシャガシャンと激しく瓶が当たる音と、ゴロンと何かが転がる音がした。
力加減を間違えた。
一瞬焦って黙った私に、リビングから「食べた」と声が聞こえた。
反省の色もない、落ち着いた低い声。
わざとだ。
怒りが湧き上がりながらも、冷蔵庫をそっと開けて被害状況を確認する。
ドアポケットから飛び出したスパイスの小瓶がいくつか、ラップのかかったお皿に突撃していた。幸い破損はないようだ。
牛乳パックも傾いていたけどこぼれてはいない。
全てを元の場所に元の形で戻して、今度はゆっくり冷蔵庫の扉を閉めると、私は無言で、怒りの足音を立ててリビングを出た。
帰宅の楽しみに取っておいた最後一つのヨーグルト。
それを無断で食べてしまう犯人の姿は見たくないし、同じ空気も吸いたくない。
たびたび繰り返されているからうっかりではない。絶対分かってやっている。
2階の自室に戻ると、破壊しない程度の力で音を立てて扉を閉めた。
その日の夕飯は親と食卓を囲まないように時間をずらした。
ーーーーーー
夕飯後、父は自室に入って読書をするか、PCに向かっているようだ。
知らないけど。
夜のリビングはドラマや音楽番組を見る私と母の空間になる。
母がスーパーで買ってきた4個パックのヨーグルトの一つを食べながら目当ての俳優が出ているドラマを見た。
ヨーグルトは私にとって、学校と塾で疲れた頭を落ち着かせるための精神安定剤のような役割がある。
その、大事な最後の一パックを父は知りながら断りもなく食べたのだ。
ドラマが終わると、私はヨーグルトの空きパックを流しに置いて、2階へと上がった。
参考書を広げる。
すっかりこじれてしまった気持ちと関係を修復する方法は思いつかない。
私は、この家を出るための有効な作戦を立てていた。
誰もが認める偏差値の高い大学、それも国立大学に合格すれば、進学という名目で両親を納得させることができる。
成績上位者に奨学金が出ることは確認済み。
キャンパス周辺の家賃相場と通学経路も調査して、アルバイトで生活をしていく算段も立てていた。
費用面も世間体も文句を言われる余地はない。
私はこの不穏な空気から早く抜け出したかった。
そのために、高校生活をかけて着々と計画を遂行していたのだ。
ーーーーーーー
受験日。
幸い親が進学について反対することはなかったが、それでも費用はなるべくかけたくない。
高速バスで東京に出て、在来線で受験会場の大学へと向かった。
最後まで模試の判定は良かった。
でも油断はできないし、過信もしちゃダメだ。
絶対に失敗したくないという意志が私を慎重にした。
受験の手応えは正直よく分からなかった。
周囲が落ち着いて見えて、私は逆に心がいつまでも落ち着かなくて、安心材料が見つからない。
学校を出て、駅へ向かう途中のコンビニに寄った。
万に一つでも体調に影響したらいけないと、昨夜から絶っていたヨーグルトを眺める。
コンビニに並ぶヨーグルトは、少し大きめで贅沢なサイズ。
母がスーパーで買ってくる4個セットのヨーグルトとは全然違った。
とりあえず今日の大仕事を終えたご褒美にはちょうどいい気がした。
冷蔵の棚に少しかがんで手を伸ばそうとしたその時、携帯が鳴った。
長い振動は、メッセージではなく着信だった。
画面には母の名前。
受験のタイムスケジュールは伝えてあったから、終わる時間を見計らってかけてきたのだろう。
ねぎらいの言葉でも伝えてくれるつもりだったのかな。
「もしもし」
電話から聞こえてくる母の声からは、尋常ではない事態が伝わってきた。
ーーーーーー
予約していた帰りの高速バスは捨てて、在来線で東京駅まで移動すると新幹線に飛び乗り、駅から病院まではタクシーを使った。
お金に糸目をつけず、自分にできる限りの最速の手段で病院に着いた。
父は、一番大変な山場は越えてICUから個室に移っていた。
移動中、大まかな事情は聞くことができた。
大通りの横断歩道に信号無視の車が突っ込み、歩行者が巻き込まれた。
いつも通りの駅を出て会社に向かっていた父は、真正面から車に跳ね飛ばされ、腹部を中心に重傷を負った。
母のショックと動揺も大変なものだっただろう。
緊急手術により、ひとまず命に別状がないことでようやく母は安堵と落ち着きを得ることができた。
私の受験が終わるまでの間、父も母も人生をかけた戦いを乗り越えていた。
病院に私が到着したことで、付き添いは私が交代し、母は身の回りの荷物を取りに自宅へ一旦帰ることになった。
父の口に装着された呼吸器が定期的に曇る。
布団がかけられて事故の傷を直接みることはできないが、その横から生えている大量の管に、父の身に起きた出来事の重大さを感じる。
表情のない顔には消えない深いシワが刻まれ、髪は半分くらい白髪になっていた。
いつの間に年を取ったのだろう。
何かの機械が動く振動音と定期的に鳴る電子音だけが響く病室で、私はまじまじと父を眺めた。
父の目が、一瞬きゅっとつむった。
目が開かないまま、まばたきのように弛緩と緊張を数回繰り返したあと、まぶたがうっすらと開いた。
「お父さん」
呼びかけた。
そばにいた看護師さんも、意識を取り戻した父の名を呼んで目を点検したり計器をチェックする。
作業の邪魔にならないよう遠慮がちに身を乗り出し「お父さん」と再び呼びかけた。
声は届いているようだった。
目を左右にキョロキョロさせて、私を見つけて目が止まった。
認識している。良かった!
「絶対安静ですからね」と念を押して、看護師さんが病室を出て行った。
父と2人でこうして目を合わせて向き合うのは一体いつぶりだろう。
「大丈夫?」と聞いてみると、軽く首を動かして頷くような仕草をした。
「お母さんは家に荷物を取りに行ったよ」
返事をしなくて済むように、要件を伝える。
大きな怪我を負ったが、命に別状がないことと、脳機能に傷害がないことは聞いていた。
こうして意識さえ戻れば、あとはゆっくり回復を待つだけだ。
寝ていればいいのに、父は私の方に顔を傾けたまま、何か言いたそうにしていた。
身体がゴソゴソと動いて、布団の端から手が出てきた。
動かして大丈夫なのだろうか。
みていると、父の指が私の横を指差した。
受験会場から直接来たため、カバンの口からは参考書と受験した大学の過去問題集がのぞいていた。
父が口を動かす。
透明な呼吸器がそのたびに曇る。
「なに?」
私は腰を上げて顔を近づけた。
す、ご、い。
一言ずつ区切りながら父は声を発した。
家を出るために、父の顔を見たくないために目指した大学だった。
誰にも文句を言わせないよう、偏差値の高い国立大学を選んだ。
そんな経緯なのに、誇りに思ってくれていた。
「結果はまだ分からないよ」
そう答えたが、父は穏やかな顔でゆっくり「だいじょうぶ」と口元を動かした。
さらに、何か口にした。
呼吸は苦しいだろうし、怪我を負った身体も痛むだろう。
聞き取れなくて首をかしげる私に、もっと近づくようにと指先をくいっと動かした。
父の口元に顔を寄せると、呼吸とともに小さな声で一文字ずつ言った。
み、て、き、た。
一瞬、何のことだか分からずに眉をひそめて父を見返した。
父は、ふっ、ふっ、と息を継ぎながら口元をにっとゆがめて笑っていた。
「見てきたって」
まるで合格発表を見てきたと言うような、父の冗談にここで気付いた。
その途端、込み上げてくる感情が抑えきれなくなった。
おかしてくおかしくて、私は声を上げて爆笑した。
呼吸が苦しくても笑いを止めることができなくて、上半身を痙攣させながら引き笑いのようにずっとくっく、はっはと笑い続けた。
同時に、大量の涙が溢れて出てきた。
溜まっていたすべての感情、不満と攻撃と疲労と不安と安堵が一気に流れ続けた。
私の様子を眺めながら父も、ふっ、ふっ、ふっ、と笑いを続けた。
絶対安静の身体が何らかの異常な数値を発し、警報音を聞いた看護師が病室に飛び込んできた。
ーーーーーー
父の冗談の真偽はともかく、その予言通りに私は志望校に合格した。
父は順調に回復し、3月半ばには退院して帰宅した。
自力で立って歩けるようになった父は、送迎を母に頼りながらもデスクワークでの職場復帰も果たした。
私の引越しの日。
まだ安静中の父がうっかり重い荷物に手を出さないよう母が厳重に見張る中、私は引越しトラックに荷物を積み込んだ。
夜は目当ての俳優が出ているドラマの最終回を見ながら一緒にヨーグルトを食べた。
父との関係がずっとこんなに穏やかだったら、この居心地のいい家を出ようとは思わなかったかもしれない。
そして、大した努力もしなくてすむ場所で安穏と生きていたかもしれない。
修復不能に思えるほどこじれた感情も、突然襲ってくる事故も、本人の意志とは関係なく遭遇してしまう。
起きないに越したことはないかもしれないが、避けようがなく逃げることもできない不遇の中にいるとき、私たちは可能な限りその場でできる事に一生懸命取り組むしかない。
私と父をこじらせたヨーグルトは、同時に私たちを繋いでいた。
ーーーーーー
春から新生活を始める者にとって、5月のゴールデンウィークは程よいタイミングでの休暇となる。
高速バスでも良かったのに、交通費を出すと言ってくれた親に甘えて新幹線で帰省した。
地元のローカル線に乗り換えて、実家の最寄駅で降りる。
目の前に広がる駅前の風景は、たった1ヶ月なのにもう懐かしいと感じる。
道中のコンビニに立ち寄った。
いつも母が買うスーパーの4個パックではなく、大きめのヨーグルトをカゴに入れた。
お財布に余裕がある分、気持ちが大きくなって、新発売のフルーツヨーグルトも追加した。
レジに向かおうとして、棚の陰から出てきた人影とぶつかりそうになる。
「あっ」と思わず声を出す。
ベージュのトレンチコートを着た父が「おっ」と、ほぼ同時に声を出した。
左手に持つカゴの中には、ヨーグルトが3つ入っていた。
ちょっと顔を見合わせて、2人で気まずく苦笑いをした。
別々にレジにならび、それぞれヨーグルトが入ったビニール袋を片手に下げて、自宅に向かった。
「で、お前はどれを食べるんだ」
父が聞いてきた。
「教えたら、お父さん、それを食べるつもりでしょう」
そう返すと「バレた」とにやりと笑った。
おかしくなって私は笑いが込み上げた。
そしてあの日のように、涙腺も少し刺激されて目頭がツンとしてしまった。
父は、ふっ、ふっ、と途切れるように笑った。
呼吸が苦しいのではなく、元々そういう笑い方をする人だった。
終
この記事が受賞したコンテスト
スキやシェア、コメントはとても励みになります。ありがとうございます。いただいたサポートは取材や書籍等に使用します。これからも様々な体験を通して知見を広めます。

