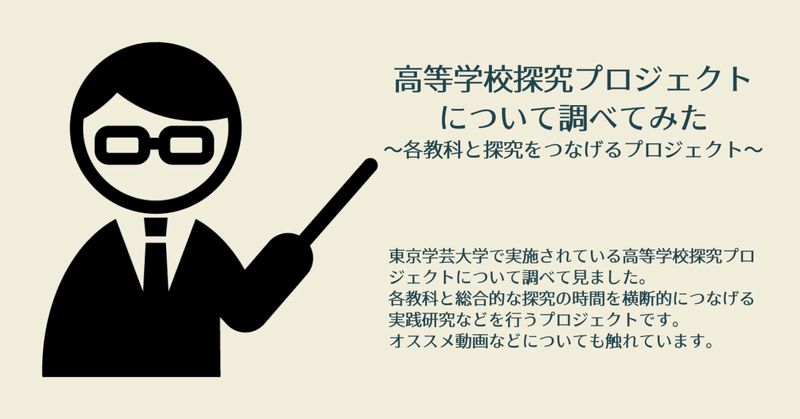
高等学校探究プロジェクトについて調べてみた〜各教科と探究をつなげるプロジェクト〜
2022年度に入り、高等学校においても新しい学習指導要領が1年生から順次適用されはじめています。科目も新しくなり、以下のように「探究」がついた科目が多く新設されました。
「古典探究」「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」「理数探究基礎」「理数探究」「総合的な探究の時間」
新設されたばかりということもあり、まだまだ授業実践などは少なく、これらの変更は先生方にとっても新しいチャレンジになっているのではないでしょうか。
そのような状況下において、東京学芸大学が高等学校における授業や先生方の教育モデルを開発・普及するプロジェクトとして「高校探究プロジェクト」を2021年12月に立ち上げました。

先日、プロジェクトリーダーの西村圭一先生と面談する機会をいただきましたので、ご紹介していこうと思います。
1.高等学校探究プロジェクトの概要
高等学校探究プロジェクトは、三菱みらい育成財団の2021年度の助成金プログラムの一つとしてスタートしました。
目的や計画、背景などは以下の通りです。(ホームページより)
目的
各教科と「総合的な探究の時間」などの教科横断の双方を射程に入れた高等学校の教員の「探究的な学びの実践コミュニティ」の創出を目的としています。
計画
全国の高等学校において探究的な学びを実現するために、以下のことに取り組むとしています。
1.教科において育成すべき資質・能力に焦点化した授業及び教師教育モデルの開発
2.教科横断型の探究プログラムの開発 及び 教師教育モデルの開発
3.1. 2. の成果に基づく教職大学院における授業科目や免許更新講習科目の開発
本プロジェクトの背景
学習指導要領においては「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められ、「実社会や実生活における課題を探究する総合的な探究の時間と、教科の系統の中で行われる探究の両方が教育課程上にしっかりと位置付き、それぞれが充実することが豊かな教育課程の実現につながると考えられる」(文部科学省、2018p.10)とされています。
しかしながら、依然として、大学入試や就職試験資格試験対策など、出口指導による従来の知識伝達型の教育から離れられない授業も少なくありません。また、各教科の授業と「総合的な探究(学習)の時間」をまったく別のものと捉え、「総合的な探究(学習)の時間」 にはあまり力を注がない傾向も見られます。
このことは、探究的な学びの持続可能性に関わる問題でもあります。こうした実態をふまえ、本プロジェクトでは、各教科における探究的な学びと、「総合的な探究(学習)の時間」など教科横断で行われる探究的な学びの双方を射程に入れ、高等学校の教員の「探究的な学びの実践コミュニティ」の創出を目指します。現状、熱心な教員や学校の存在は、言わば「点」です。その「点」が「線」となり、「面」に拡げていくことが本プロジェクトの目的です。
2.プロジェクト内のコンテンツ
このプロジェクトでは、各教科と総合的な探究の時間に使える様々なコンテンツが用意されています。
授業研究のための各教科ツールキット(教材)の提供
学校の先生にとって最も役に立つのではないかと考えられるのが、各教科の授業をどのように探究化したらよいのか、ということについて触れられている教材の紹介ページです。
「ツールキット」という名称となっていて、「国語」「数学」「英語」「化学・生物」「総合的な探究の時間」などの動画教材が用意されています。
※現在、「地歴・公民」「情報」は準備中。
さまざまなコンテンツがありますが、どの先生方にも参考になるのが、「総合的な探究の時間」のコンテンツです。学習指導要領における「探究のプロセス」に合わせる形でコンテンツが用意されていますので、体系的に学んでいただくことができます。

各教科の先生にとって、気になることは、「教科指導に探究活動をどのように取り込んでいくか」ということになるかと思います。
「数学」の動画になりますが、授業実践などを見る際の「考え方の視点」について説明してくださっている動画が用意されています。2分30秒程度の内容で、「数学」を例にとっていますが、他教科の先生が見ても「探究」の授業へのちょっとした気付きを与えてくださるような内容になっていますので、おすすめしたい動画となっています。
3.ワークショップが盛り上がっている
ご存知の方も多いと思いますが、東京学芸大学は教員養成や先生方の研修など、教育の専門家が多く集まり、日々多くの授業実践に関する発表やワークショップなどが行われています。
このプロジェクトはそんな東京学芸大学の先生が取りまとめていらっしゃることもあり、ワークショップなどのイベントはかなり盛り上がるそうです。
プロジェクトリーダーの西村先生曰く、
「Zoomで双方向型のワークショップを実施しており、決して参加者の負担は軽いものではないはずなのに、毎回100~200名程度の参加者がいらっしゃる」
とのことです。
それだけ多くの先生方にとって興味深い内容なのだということがわかりますし、このような機会を通じて同じような課題を抱えた先生方に出会い、情報交換できる良い機会なのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
