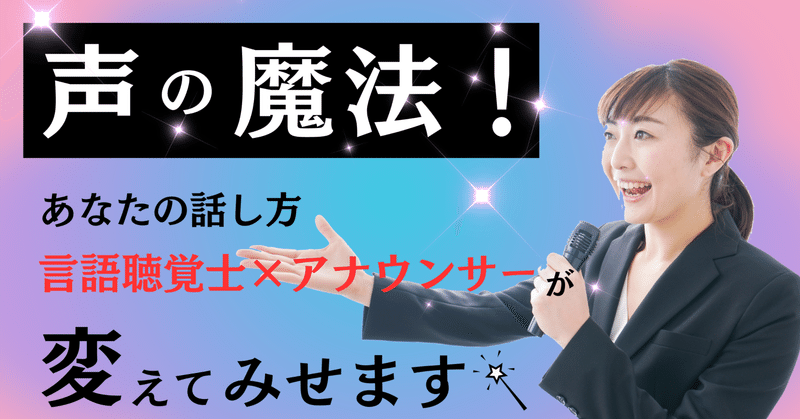
声の魔法! あなたの話し方、言語聴覚士✖️アナウンサーが変えてみせます🪄
声の先生と言えば誰?
言語聴覚士という仕事
「声」の先生と言えば、誰を思い浮かべますか?
歌手、歌の先生、ボイストレーナー、アナウンサー、ナレーターetc…。どれも「声」を仕事にしているプロフェッショナルな方々ですから、間違ってはいません。
そこにもうひとつ、ぜひ「言語聴覚士」を加えてほしい!というのが私の願いです。最近少しずつ名の知れてきた「言語聴覚士」。なぜ「声」のプロフェッショナルの仲間入りが果たせるのかーーというその前に。
そもそも言語聴覚士とはなんぞや、という話をしましょう。
一般社団法人日本言語聴覚士会のホームページには、「話す、聞く、食べる、のスペシャリスト」と紹介があります。さらに詳しい説明を抜粋してみました。
ことばによるコミュニケーションには言語、聴覚、発声・発音、認知などの各機能が関係していますが、病気や交通事故、発達上の問題などでこのような機能が損なわれることがあります。言語聴覚士はことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。また、摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。(日本言語聴覚士会HPより)
注目すべきワードは「ことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供」という部分。ここの「ことば」の中には、発声や発音、滑舌が実は含まれているんです。実際私たちは、言語聴覚士の養成校や大学で、何時間もかけてこれらを勉強しています。ざっとあげるだけでも、音声学、音声障害学、構音(発音)障害学、そのほか物理の仲間に分類される音響学や聴覚心理学も「声」にまつわる学問分野ですし、肺や声帯に関することを学ぶ解剖学や生理学も入ります。これだけみっちり「声」に関して必修かつアカデミックに学ぶ職業はほかにはありません。
何より言語聴覚士としての強みはずばり国家資格であること。先にあげた「声」のプロフェッショナルの職業は、資格制ではありません(中には民間資格化しているものがあるかもしれません)。つまり、誰でも勝手に名乗れる、と言えば失礼かもしれませんが、勝手に名乗っても罪に問われない職業です。
その点、言語聴覚士は国家試験を通った者しか名乗れない、いわば選ばれた職業。その一点において、他のプロフェッショナルを凌駕できるはずですが、ここでひとつの問題点が。
そう、言語聴覚士は「治す」プロであって、必ずしも本人が声のプロフェッショナルではないということ。
「自分の声をよくしたい」「プロの○○になりたい」と思ったとき、誰しもその道のプロに教えを乞おうと、自分より上手な人の門を叩くもの。残念ながら言語聴覚士全員が、発声や発音や滑舌の技術に優れているわけではありませんし、門を叩いてきたその人よりも劣る可能性すらあります。
言語聴覚士、ここにきて劣勢。けれど、私にはもうひとつカードがありました。そう、私、一応アナウンサーなんです。
キャリアを語れば、地方のCATV局で7、8年働いた後、東京でフリーのナレーターとして活動(この間、言語聴覚士の専門学校の学生をしていました)。一時期は言語聴覚士に専念した後、フリーランスに転向するきっかけでアナウンサーにも復帰。キャリアだけでいえば15年は超えますし、なんなら言語聴覚士としての職歴よりも長いです。

アナウンサーという仕事
アナウンサーの仕事については、私が語るまでもなく、みなさんよくご存知でしょう。「ちょっと自分の滑舌よくしたいな」「話し方を改善したいな」と思ったとき、真っ先に思い浮かべる先生といえば、アナウンサーかもしれません。
実際私も、滑舌を試されるような早口言葉は得意ですし、数千人入るホールで2階席、3階席のお客様にまで届く話し方も身についています。声のプロには必須の腹式呼吸だって無意識に行なっていますし、人前で挨拶を咄嗟に振られても、それっぽい話ができます。
これらの「得意技」について、当然ながら学生時代から練習をしてはきました。しかしながら面と向かって「どうやったら出来るようになりますか?」と聞かれると「たくさん練習したらいいと思います」以外に答えられなかったアナウンサー時代。
そう、私が身につけてきた「得意技」をいったいどう身につけてきたのか、それを言語化するのって案外難しいんです。だからこそ私がやってきた練習方法をシェアするくらいのことしかできていませんでした。
言語聴覚士×アナウンサーとしての強みが、声や話し方を変える
感覚から理論へ
そんな私がアナウンサーを一時的に引退して通った言語聴覚士の養成校。そこで出会った上記の学問たちは、とにかく目から鱗の連続でした。私が得意としていたことがどのように成り立っているのか、どういった技術に裏打ちされているのか、すべてが教科書や授業の中で「論理的」に「言語化」されていたんです。
「アナウンサーの技術に言語聴覚士の知識が加われば、私って最強の声や話し方の先生になれるんじゃ?」
そう思ったのも無理ないこと。そもそもアナウンサーになろうという人たちは、初めからその分野が得意な人たち。きっと子どもの頃から国語の音読で褒められていたことでしょう。そんなふうに苦労なく「できる人たち」は、自身の技術を感覚的に捉えてしまう傾向があります。実際、アナウンサーの方々向けのセミナーの講師を、言語聴覚士の立場でさせていただいたとき、よくいただいた意見が「今まで全部、感覚でやってきた」というものでした。
対して言語聴覚士は、自身が声のプロフェッショナルではありませんが、悪いところを的確に評価し、その部分を改善するアドバイスが論理的に言語化できる人種です。教えることにはある意味特化しています。
感覚VS理論、ではなく、感覚+理論
たとえば「バス、ガス爆発」の滑舌練習をするとき。
「口を大きく動かして、ことばの切れ目を意識して、はじめはゆっくりのスピードから、だんだん早く」と感覚的に説明するのがアナウンサーとするなら。
「この言葉が言いにくいのは、両唇音、歯茎音、軟口蓋音の3種類が含まれており、口唇や舌の動きが活発なため」と分析するのが言語聴覚士。
たとえば「遠くまでよく通る声」をマスターしたいとき。
「ボールをぽーんと投げるようなイメージで声を飛ばしてみましょう」と勧めるのがアナウンサーとするなら。
「口の中の軟口蓋という組織を上手に使って共鳴させていきます」と説明するのが言語聴覚士。
もちろん、アナウンサーの中にも論理的な説明が得意な方はいらっしゃいます。軟口蓋の理論などは声楽を勉強されている方もよくよくご存知ですから、指導に取り入れていらっしゃるでしょう。
そもそも感覚と理論のどっちがいい・悪いの話ではありません。私も言語聴覚士として患者さんに指導する際、「ボールをぽーんと投げるようなイメージで」と説明したことは何度もあります。実際、軟口蓋がどうちゃらこうちゃらと言われて「なるほど!」と思う人はあまりいませんよね。(ちなみに指導の際には口の解剖図を見せながら説明はします)
感覚VS理論ではなく、感覚+理論。そのどちらがよりハマりやすいかは、その人によります。しかし間違いなく言えることは、ハイブリッドなら最強の「声」や「話し方」を手に入れられる確率があがるということ。
声の魔法で、あなたの話し方を変える!
声の改善は何も、カラオケでうまくなることだけが目的になるわけではありません。電話応対、ミーティングの司会、プレゼン、面接、ちょっとしたスピーチ。社会人として生きていく中で、声を使うシーンは多くあります。
そのシーンで、魅力的な声が出せたら。誰かを引き込むような話し方ができたら。
あなたの評価も、あなたの日常も、あなたの人生も、魔法がかかったように変わるかもしれません。
声は変えられます。話し方も変えられます。
年齢性別に関係なく、今よりもっといい声になりたいという思いは、必ず叶います。
私が言語聴覚士×アナウンサーの肩書きにかけて、あなたの声をよりよく変えるお手伝いをさせていただきます。
声の魔法vol.1 https://note.com/kotobanohattatsu/n/nd744857539ac
声の魔法vol.2 https://note.com/kotobanohattatsu/n/n8dfd5860dbe2
声の魔法vol.3 https://note.com/kotobanohattatsu/n/neeada92dbf77
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

