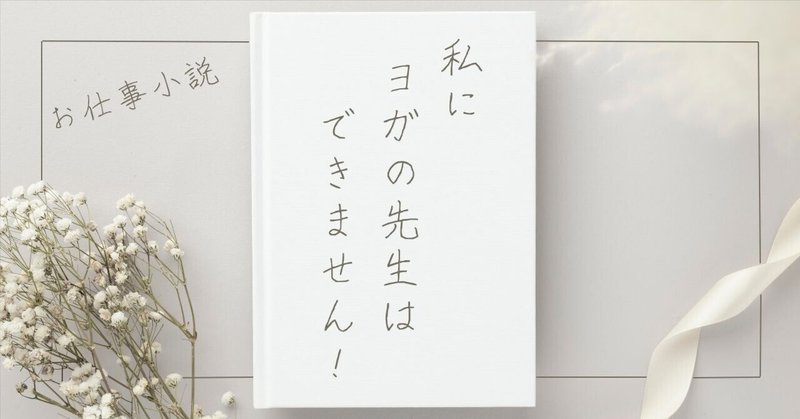
私にヨガの先生はできません!【第十四話】集客に苦戦して
【第十四話:集客に苦戦して】
六月がやってきた。
じめじめとした生ぬるい空気が肌に纏わりついて、体力も気力も削っていく。
そして、私を悩ますのは、そんな蒸し暑さだけじゃなかった。
インストラクターとしてデビューできたはいいものの、二ヶ月目にして、もう目の前には巨大な壁。こちらをあざ笑うかのように、ででんと立ちふさがっている。
「十六人か……」
ぽつりと呟いたのは、レッスン後のことだった
三十人定員のスタジオで、参加者はたったの十六人。
スタジオ内に点々と人が散っている光景は、ところどころにかろうじて葉が残っている公園の木や、まばらにしか咲かなかったお花畑を見ているようで、もの悲しさを覚える。これが、初心者向けのビギナーヨガであれば、参加者が少なくなるのも珍しいことじゃない。ステップアップしたくて、他のレッスンを受けるのは自然なことだから。
でも、今のクラスはハタヨガなんだ。曜日や時間帯の集客のしにくさを考慮しても、えりかさんや他のインストラクターのレッスン人数と比べると……。
「人気ない、よね」
どうしてだろう。
レッスンデビューしたばかりの二ヶ月前、四月には二十五人を超える日がたくさんあった。ここ最近は、じわじわと減り続けている。
「はあ」
やっぱり、私にヨガのインストラクターは向いていないのかもしれない。いくら知識や柔軟性を身に着けたところで、まるっきりダメ。そういうタイプの人間なのかもしれない。つまり、ヨガとの相性がよくないんだ。
考えたくもない思考が浮かんでは、消えずに頭の片隅にこびりついていく。
系列店のフィットネスクラブ・Altairの社員、チーフである橘さんが突然スタジオに来たのは、そんなときだった。
「笹永さんのレッスン、受けてみようと思って」
橘さんはアッシュグレーのベリーショートヘアがよく似合う女性だ。目鼻立ちがはっきりしていて、きりっとした顔をしている。
それもあってか、じっと見つめられると、私の目は逃げるように泳いでしまう。
「ええ? 私のですか?」
よりによって、集客で悩み中のレッスンに?!
そう声を出したいのをぐっと押さえる。もしや、と思った。人が少ないことを知ったからこそ、偵察に来たのかも。
「なにか問題でもある?」
橘さんはぴしゃりと尋ねる。
うう……。ちょっぴり怖い。
正直、私はこの人が苦手だ。あんまり会う機会がないからか、目の前に立たれると、緊張して話すのも、動くのも、ぎこちなくなってしまう。
もともとミュージカルダンサーとして活動していて、足のケガが原因で退団。その後はフリーランスのヨガインストラクターになり、六年ほど前にフィットネスクラブ・Altairに社員として入社した、と聞いている。
年齢は三十半ばくらいだったはず。
「い、いえ。ただ、最近、あんまり参加者多くなくて……」
橘さんは小さくうなずいた。
「知ってる、知ってる。日報のメールにそう書いてあったから、気になってさ。きてみたんだ」
数日前の自分に言いたい。
どうして、集客数のことを全社員が読む日報に書いたのだと……。あのときは、閉店後の静かなスタッフルームで妙に感傷的になり、ついつらつらと書き綴ってしまったんだ。
夜に手紙を書くなということわざを思い出す。
まさにそれだと後悔しても、もう遅い。
「そうなんですね」
「私のことは気にせず、普段通りにレッスンすればいいから」
橘さんはそう言うけれど、こっちはそうはいかない。ましてや、彼女は集客力のある人気インストラクターとして有名だ。
そんな凄い人に参加されて、平然となんてしていられる人なんているもんか。気にするなといわれても、気になるに決まっている。
そう思いながらも、うなずくしかできない。
「はい」
「じゃあ、よろしく」
橘さんはそう言い残し、すたすたとロッカールームの方へと歩いていってしまった。
彼女は一応気を遣ってくれていたのか、スタジオのすみっこにひっそりといて、当たり前だけれど、指先まで美しいお手本のようなポーズをとっていた。
あまり意識せずに、意識せずに。そう言い聞かせながら、私はなんとか六十分のレッスンをやり遂げた。誰にも言わないけど、いつもの倍、どっと疲れた。
その日のハタヨガの参加人数は、十四人だった。もしも、橘さんがいなかったら、たったの十三人だ。
「お疲れ」
橘さんが声を掛けてきたのは、レッスン後、他の参加者がスタジオから去ったタイミングだった。ニコニコしているわけでも、ふくれっ面というわけでもない。
レッスンにどういう感想を抱いたのか、表情からはさっぱり読み取れなかった。
「ありがとうございました。あの……。どうでしたか?」
私はおずおずと尋ねる。
「……自信のなさが伝わってきて、こっちまで不安になるんだけど」
「え?」
てっきり、このポーズがわかりにくいだとか、声が聞きとりにくいとか、注意点の説明を忘れているだとか、そういう指摘を受けるのだと思っていた。
「自信。なくしてる?」
「……はい。参加者の人数減ってきたので」
俯きながら伝えると、聞こえたのは盛大なため息。橘さんが呆れている。そのことだけがひしひしと伝わってきた。
「あのねえ、今、参加してくれた人たちは、あなたの状況なんて、知ったこっちゃないんだからね。それなのに、あんなレッスンしたら、どんどん人が減っていくかもよ」
橘さんの言葉は淡々としている。
そのせいで、余計に言葉が胸に刺さる。
なんにも、言い返せない。
「すみません」
「私に謝ったってしかたないよ」
「……はい」
かろうじて掠れた声を絞り出す。気を抜くと、声が震えそうだった。そんな私の様子を見た橘さんは、今度は小さなため息を吐いた。
その些細な行動が、あんたはダメなのだと責めてくるように思える。
「一応伝えておくけど……。さっきのレッスン見た感じ、参加者が一気に減るような致命的なことはなかったよ。一番後ろまで声もちゃんと聞こえてたし、インストラクションも研修で習った通りだよね? シンプルでわかりやすかった」
「でも……」
実際に人数が減っているんです。
そう伝えようとしたとき、ロッカールームとスタジオを繋ぐ扉が開き、外のひんやりとした空気と一緒に会員さんの一人が入ってきた。さっき、レッスンを受けてくれた人だ。
「あ、すみません。タオルを忘れてしまって。あ、あった!」
その人は、奥の方へと小走りしていく。濃いブラウンの色をしているからか、まだ暗いスタジオと同化して見えなくなっていた。
「あ、気がつかず、すみません!」
私はとっさに謝った。
「いえいえ。こちらこそ、失礼します!」
女性は元気よくそう言うと、ぺこりと頭を下げて、再び扉の向こうに去っていく。
今のたった数分のできごとで、私と橘さんの間に流れる空気の色ががらりと変わったような気がした。
「そろそろシャワー空いたかな? じゃあ、頑張って」
もう、お話はおしまいでいいんだろうか。
「ありがとうございます」
「……あ、そうだ。言い忘れるところだった。笹永さん」
橘さんは、扉に手をかけたまま、顔だけこちらへと向けてきた。
「はい」
「覚えておくといいよ。集客ができないときってだいたいが三パターン。一つ目は、なにかしら人が集まらなかったり、リピートに繋がらなかったりする原因がレッスンにあるとき。すみやかにその要素をなくして、改善しないとダメ。これはわかるんじゃないかな?」
「わかります」
「それから二つ目は、レッスンというより、スタジオ運営のなかに要因があるとき。例えば、会員数が少ないと一レッスンあたりの参加者は少なくなるし、シンプルに暑い季節になると人数が減る。時間帯に需要がない、とか」
「はい」
「ラストの三つめはさ、なぜだかわからないけどそうなるとき」
「ええ?」
あまりにも抽象的が飛び出てきたものだから、思わず聞き返す。
「あるんだよね。一つ目で考えられる原因を全部取り払った後や、人に見てもらってもとくにこれといった何かが見つからないときでも、どうしてか、自分だけが全然集客出来ないってことがね」
「……そうなんですね」
「笹永さんがどのパターンなのかは、ちょっと単発でレッスン見ただけじゃわからないけどね。まあ、参考にして。とにかく、今の自信がなさげなのはなんとかしないと。さっきも言ったけど、もっと人数減るよ?」
橘さんはそう言い残してスタジオを後にした。
彼女がここまで言いたくなるくらい、レッスンに対する自信のなさが出ていたんだろうか。自分では、表面上には出さないようにしていたつもりなのに……。
私は小さくため息を吐く。
今の状態がさらなる集客数の低下に繋がると言われても、レッスンの参加人数が戻らないことには自信だってつけられない。
まずは、どこがダメなのか、原因を明確にしないと。
でもさ……。
もしも、集客数低下の理由がレッスンにない場合、どうやって対処すればいいんだろう。
例年よりも早い梅雨入りとともにやってきた新たな課題。それはやっかいで、どこまでも手ごわそうな予感がした。
この連載小説のまとめページ→「私にヨガの先生はできません!」マガジン
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

