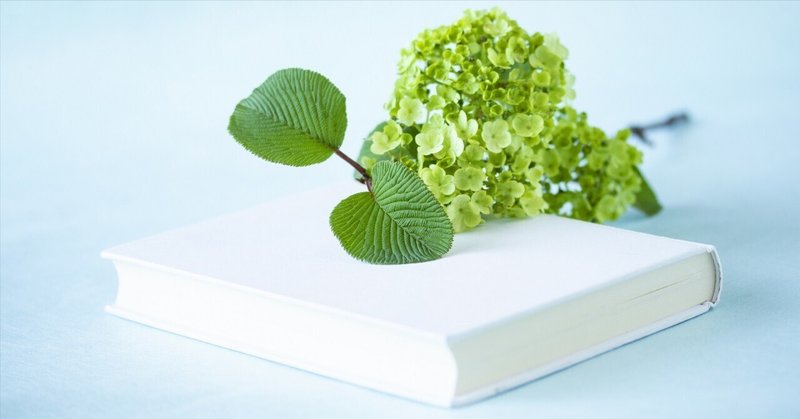
【雑記】本当に昔読めば良かったのか?
先日「もっと若い内に読めば良かった本」といった話題を見かけて、理想的な本との出会いとは何だろうと思いました。厳密には「いつ」読むのが理想的なのでしょう。特に着地点を決めないまま何とはなく思ったことを書いてみますね。そんな深刻な話ではないので、まあまあ、どうぞ気楽にお付き合いください。
愛読書を「もっと若い内に読めば良かった」と思うのはわかります。私もおなじことを考えたりします。でも、若い内に読んでいたらその本の良さを理解できなかったかも知れない、ある程度年齢をかさねていたおかげで理解できたかも知れない、といった可能性も捨てられないのですよね。なまじ出会いが早すぎたために魅力を感じず、自分の愛読書に加え損ねることもあり得る話ですから。
自分の場合は三島由紀夫の『金閣寺』が好例です。私はこの小説を3回、それも何故か10年経過するたびに再読して、読むたびに評価を覆してきました。初めて手に取ったのは16歳。奇しくも『花ざかりの森』を執筆したときの三島由紀夫と同年齢の頃でした。15歳になるまで活字本の頁なんて開きもせず、広大無辺なる文学の世界も、文学の混沌とした可能性も知らなかったルリビタキの雛は三島由紀夫の精密機械のような文体と構造の妙味がわからないばかりか、彼が文学の中で主張してきた象徴と美学もちんぷんかんぷんで、結局最後まで足並みを揃えられないまま本を閉じてしまいました。どこを取っても面白いと思える箇所はなく、何故世間で名作と謳われているのか見当もつかなくて疑問符を浮かべていました。
そうした経緯があるため長年自分の中で三島由紀夫は市ヶ谷駐屯地での自決と併せて「修飾まみれのナルシスト」という評価に落ち着いていました。
なお若干話を脱線させると「修飾まみれのナルシスト」なのはあながち間違いではないのですけれど、そこに至る思想を解釈していくと彼の自己陶酔は単なる自己陶酔で済ますにはあまりにも思考の道程が深く、暴力性もまた同様の理由で安易に切り捨てられなくなります。当時の自分にはここの解釈が欠落していましたから散々な感想を抱いたのも無理はないでしょう。それに三島由紀夫の作品を酷評する人は名高い表現者の中にも大勢いるように良くも悪くも個性的なのは変わりありません。
話を戻しましょう。次に『金閣寺』を読んだのは26歳。禁断のTwitter(現X)を開始した年です。16歳の頃よりは知識も読解力も身に付けていましたし、微々たるものながら感受性は深まっていたと思います。で、改めて『金閣寺』を再読したところ、彼の豊富な語彙と表現に圧倒されるとともに、美学を支柱とした緻密な構成に建築物の設計図を見るような新鮮な読後感を覚えたものです。この体験には驚きましたね。三島由紀夫の美学をテクストの内として切り離すと、以前は見えなかった表現の妙が眼前に現れました。類似するものの見あたらない特異な小説であり、大きく評価を改めることになりました。
このあたりは当時より作品を評価する上で「共感できること」を重視しなくなった点も働いていたと思います。
大雑把にまとめるなら三島由紀夫の思想は共感できる点と共感できない点が極端にわかれているのですが、変に文学的思想に共感できるか否かを重視するから擦り合わない部分が足枷になるのであって、独立したテクストと割り切った方が自分自身の固定観念に縛られず吟味できます。あたり前のようですけれど、こうした割り切りは意外と難しいです。でも、その方が先入観という厄介な代物を捨てて純粋な気持ちで読書を楽しめますし、自分なりに冷静な評価をくだせるので意識的に実践したいものではあります。以前より客観的な視点から『金閣寺』を評価できた要因はこの辺にありました。この時期から三島由紀夫は再評価に値する作家と認知し、徐々に自分の文学的思想に影響を与える存在となっていきました。
また年月は流れて36歳。立派なおっさんの登場です。否定したくても認めなければなりません。おっさん以外の何ものでもありません。とはいえ無駄な人生を送ってきたわけではなく、この10年間で読書の対象は格段に広がりましたし、読書法というと大袈裟ですけれども読書におけるテクニックも大分習得したのではないかと自覚しています。別に目標を立てていたのではなくて、好きなことを続けていた結果ですね。この間にラテンアメリカ文学を筆頭に各国の翻訳小説を読み込み、日本の近現代文学にも深く潜り込み、バイブルに埋もれることになりました。
あれも面白い。これも面白い。それも面白い。
読書慣れするほど書物に寄り添う読み方がわかってきます。
もっとも読書量の増加にともない、心酔していたはずの書物に昔ほどの情熱を向けられなくなることもあります。こういうときはさびしい気持ちになりますね。感性が変化したのか、絶賛していたのは単なる知見不足故だったのか。蛙化現象とはいかなくても単純に「もっと面白い本があることを昔は知らなかった」という非情な現実にはしばしば直面します。同時に歳月を経て存在感を強めていく大器晩成型の作品もあります。どうしてこの作品の面白さに気付けなかったのか、と。その代表格が『金閣寺』でした。再々読してどれだけ感銘を受けたのかは第27回【読書備忘録】で紹介した通り。お時間のあるときにご覧になっていただけると嬉しいです。
とはいえ「早い内に読んでよかった」と思うこともあります。やはり個人的な例をださせていただくと、10代なかばで芥川龍之介作品に出会えたのは本当に僥倖でした。正確には15歳の春ですね。芥川龍之介の『魔術』は人生初の読書体験であり、読書に目覚める契機となった特別な作品です。母から勧められたこの短編小説を読まなかったら、果たして読書の面白味を知ることはできたのでしょうか。できたとして何年も遅れていたかも知れないと想像すると寒気を覚えますね。15歳で『魔術』を読むことは特筆して早いわけではないと思いますが、頑固に活字を拒み続けていたガキんちょの自分を思い返すと、なかなか早めの出会いだったのではないかと思います。
少年期に読んだことが奏功した芥川龍之介の『魔術』、少年期に読んだことが禍した三島由紀夫の『金閣寺』、対照的な両者両作ですけれど、この二人が私自身の近現代日本文学における「推し」として肩を並べているのはなかなか興味深い現象です。
結局どの作品を何歳で読むのが正解なのかはわからないとしか言えませんね。早ければ良いとも限りませんし、遅ければ良いとも限りません。もしかすると結果論でしか判断できない問題かも知れません。私としては過去を悔いるより「もっと早く読みたかった」と思うような素敵な本に今出会えた事実を大事にして、新たなバイブル探しの旅に出るのが理想なのかなと思ったりしています。
といった話でした。

よく見るとボロボロの天井照明が映り込んでいますが、恥ずかしいのでよく見ないでください。
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。

