
【5G学級経営シリーズ第3話】 学力保障ではなく,学習権保障があるクラス
私のクラスの一番大切にしていることが、今日お話しする学習権保障についてです。
学習権保障とは、どの子もが安心して授業を受けることができる権利を持つことを指します。
授業を安心して受けるというのは、ひょっとすると多くの先生方にとって、『何を言ってるんだ、当たり前のことをわざわざnoteに書いてなんのつもりだ』と思うかもしれません。
しかし、私が初めて赴任した学校では例えば、授業中に私語がやまない子、授業中に勝手に教室から飛び出してそのまま学校の塀を乗り越えていく子、授業に集中することができずいつも寝ている子、、、そんな子が当たり前のようにいました。
先生方のクラス、お子さんのクラスにそういった子は少なからずいませんか?そんなクラスでみんなが安心して学習できますか?おそらくできなくて困っている子がいると思います。
あの座らない子も、1時間の授業できちんと椅子に座って鉛筆を持つまでにどんな手立てを施してきたかについて、私の経験を示しながら、先生方の明日のクラスづくりの何かヒントを伝えたいという思いで以下にその具体的な手立てを書いていきたいと思います。
①思考のユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザインという言葉は、近年あらゆる研修会、あらゆる本で耳にするようになりました。
多くは視覚的な支援という意図で書かれていることが多いです。
例えば、1時間の授業の流れを掲示していたり、1日の見通しをホワイトボードに書いていたり、その方法は多岐に渡ります。
しかし、私のクラスではそういった目に見えるユニバーサルデザインは通用しませんでした。
いくら、見通しを持たせたとしても子どもの実感がその視覚的なユニバーサルデザインにそぐわなければ返って落ち着きがなくなり無意味だったのです。
1時間の授業の中で、今は何をして次に何をしているのかが明確に区切られていることをして、どの子もが目的意識をもって取り組めるように授業デザインをすることが大切です。
わかりやすい手立ては、全員を立たせ、話し合い活動の中でわかったら座る。座った人から書くという方法です。
立ったり、座ったりする動作を頻繁に行うことで、区切りを持たせやすく、子どもの思考も整理されやすいです。
この手法は、例えば国語の音読で速読した子から座る、社会のグラフで3つわかることをしゃべったら座る、道徳のテーマについて思いを伝えたら座る、のように、どの教科にも汎用させやすいのも利点です。
同じ話題をだらだらとすると、手遊びをしたり、私語をしたり、子どもなりに退屈を表現し出します。発達障害を持っている子はなおさらです。そういった芽を事前に摘んでおくことが、思考のユニバーサルデザインの肝になります。
②整理整頓をルーティーン化する
当たり前のようで、難しいのが整理整頓です。
子どもにとって、整理整頓されていない環境は落ち着かない要因を生むきっかけになります。
例えば、朝の宿題提出。
うちのクラスでは、ノートの右上に番号を書かせ、必ず番号順に提出させます。
何かをもとに並べるという目的があると、自然と綺麗に並べようとします。
例えば、お道具箱の中。
うちのクラスでは、朝の会で必ず机の中の整理整頓の時間をとります。整理の仕方は子どもに委ねていますが、例えばプリントがぐちゃぐちゃになっていたら、すぐに捨てる。色鉛筆やクレパスが出ていたら、入れ物に直す。こういった視点を示しながら、毎朝の健康チェックの後に、身の回りの健康チェックと題して、隣の席の子にお道具箱の中を見せ合いっこして整理整頓のアドバイスをしあうという時間を確保します。
毎日継続すると、多くても30秒で全員が整理整頓できるので、意外と時間的な負担にはなりません。
例えば先生の机の上。
余裕がないときほど、教室の机の上も職員室の机の上も物が増えていませんか?
山積みの机を見て、心地いい子どもは誰一人としていません。
しんどいときほど、先生の机の上だけでもきれいにしておきましょう。置く場所がなければ、更衣室のロッカーや使っていない教室に隠しておくともアリです。とにかく目に見えるところは最低限きれいにしておきましょう。
③体を動かす時間を確保する
私のクラスでは、週2時間ある体育の最初の10分は体を動かす遊びを入れます。
なるべく、その時の単元に合わせて遊びの中で身体を動かさせます。
だるまさんが転んだ、氷鬼、バナナ鬼、レンチン鬼、笛鬼、この指とまれ、震源地、大縄とびなど、とにかく運動量の多い遊びを取り入れます。
身体を動かすことで、子どものストレスを発散させ、集中力を高めることができます。
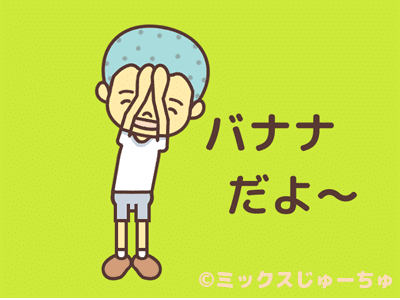
④自尊感情を高める
自尊感情といっても、いろんな自尊感情があります。自尊感情とは、『自分には価値があると思える感覚』のことを指します。
自尊感情と授業中の安心感には、明らかな相関関係があります。
自尊感情の底上げを心がけることで、問題行動を予防できます。
自尊感情には大きく5種類があります。
自己受容感・・ありのままの自分を認める感覚
自己効力感・・自分にはできると思える感覚
自己信頼感・・自分を信じられる感覚
自己決定感・・自分で決定できるという感覚
自己有用感・・自分は何かの役に立っているという感覚
この5つの自尊感情を、意識しながら声をかけたり、場の設定をしたり、お家の人に協力を求めたりします。
特に意図して、高めやすいのは自己有用感です。掃除の時間にふと『ーさんのおかげで、窓がきれいになったね』と声をかけるだけで、救われる子もいます。
難しいのは、自己受容感です。ありのままでいいんだよということを価値づけることができたことがありません。もし先生方でおすすめの実践があれば教えてください。私の感覚では、自己受容感は長期的な視点で大人になる過程で子ども自身が気づくタイミングがあるような気がしています。
①ー④はあくまでも一例にしか過ぎませんが、どの子もが学校で安心して学ぶ権利を保障されるようにするのも教師の役割だと考えています。
もし目の前の子ども達との関係で悩んでおられる先生や、どうしたらいいか困っている先生がおられたら、どれか自分でもできそうなことからチャレンジしてみてください。
応援しています。
国語授業研究室
記事の購入代や、クリエイターサポートで応援すると購入代金の一部を目の前の子どもたちへよ教材づくりに使わせていただきます。応援よろしくお願いいたしますm(_ _)m
