
“何者か”になれなくてもいい。わたしは私。 会社員を辞め、移住10年を経て三星千絵さんが気付いた、人生で大切なこと。
「30歳くらいの時期って、人生に迷うよね」
三十路をちょっとすぎた年齢になって、友人たちとよくそんな話をするようになった。僕自身、30歳のちょっと手前で「これからどう生きていこう?」と悩んでフリーランスになった経緯があるから、「迷ってたなぁ、あの時期」なんて、しみじみ思う。
キャリアデザインの文脈では、20代後半から30代前半にかけて、つまり人生の4分の1を過ぎた時期に訪れる人生への焦りや停滞感を感じる時期ことを、「クオーターライフ・クライシス」と呼ぶようだ。
しかし、そうした転機は不安をもたらすだけでなく、あたらしい世界へとつながる扉にもなる。「クオーターライフ・クライシス」から目を背けず、乗り越えた先には、それまでとは異なる人生の豊かさが待っているのかもしれない。
今回インタビューしたのは、三星千絵さん。三星さんは20代の頃、都内の企業で昼夜問わず働く生活に違和感を感じ、28歳で千葉県いすみ市へ移住。空き家を活用した古民家シェアハウス「星空の家」、私設図書館「星空の小さな図書館」、カフェ&シェアスペース「星空スペース」を立ち上げ、2018年に株式会社スターレット設立。「今あるモノで、まだないコトを。」をテーマに、地域資源を活かした場づくりや編集、イベント企画、事務局運営まで、幅広く活動している。
「28歳の頃は、何者かになりたくて焦ってました」という三星さん。でも、それから10年が経った今、そんな焦りはなくなってきたのだという。三星さんはどのようにして、大きな転機を乗り越えたのだろう。そして、乗り越えた先に見えてきた世界は、どのようなものだったのだろう。
三星さんの語りに、少し耳を傾けてみましょう。
(聞き手:山中 康司)
三星千絵
1982年千葉県生まれ。大学卒業後、人材系営業、PR代理店を経て2011年、千葉県いすみ市へ移住。古民家シェアハウス「星空の家」、「星空の小さな図書館」、「星空スペース」を立ち上げ、2018年に株式会社スターレット設立。「今あるモノで、まだないコトを。」テーマに、地域資源を活かした「場」づくりだけではなく、編集、イベント企画、事務局運営まで、幅広く展開中。ローカルに軸を置き、都会と地域をつなぐ。
移住から、10年。
わたし、東京の会社を辞めて、28歳のときにいすみ市に移住してきて。ここでの暮らしも、もう10年が経ったんですよ。
移住してきた当初は、「何者かになりたい」っていう焦りみたいな気持ちが強かったんですよね。でも、シェアハウスの管理人になったり、NPO法人で働いたり、私設図書館を立ち上げたり、病気を発症したり…ここでのいろんな経験を通して、そんな「何者かになりたい」っていう焦りは、だんだんとなくなってきました。
移住から10年っていう節目で、今日は28歳のわたしに語りかけるような気持ちでこれまでのことを振り返りつつ、あの時のわたしと同じようにモヤモヤとしたものを抱えたまま日々を過ごしている皆さんに、なにか伝えられたらと思ってお話したいと思います。

自分の意見を言うのが苦手だった
わたし、小さい頃から自分の意見を言うことが苦手だったんです。「なにがしたいの?」って聞かれても、こまっちゃう。まわりの顔色を伺って、「わたしがこうすれば、この場がうまく進むだろうな」っていうことを、一番最初に考えるようなタイプでした。だから自分の意見というよりも、「誰かのため」とか「なにかのため」を考えて、いつも動いてました。そう考えると俄然やる気が出ちゃうので。責任感は強かったんでしょうね。
大学でもそうでしたし、社会人になってからも、上司から「お前はどうしたいの?」って聞かれても「どうしたらいいですかね…」みたいな。自分の意見を聞かれるのが一番こまるんですよね。でも、お客さんのためとかチームのメンバーのためであれば、周りの状況を考えて最良の選択をするような、そんな人間でした。
だからずっと、「自分はこれをやりたいんだ!」って、自分の意見を持ってる人に憧れてましたね。「自分もそうなりたいなぁ」って。そんな気持ちが特に強くなったのが、28歳くらいのときでした。
「この仕事は誰を幸せにしてるんだろう」
新卒でリクルートっていう会社で営業をやって、3年勤めた後、25歳の時にPR代理店に転職したんです。最初に担当したのが某キャラクターグッズを扱うお店で、新商品が出るとプレスリリースを書いて、出版社に持ち込んで、取材をお願いしたりしてました。そのあと、横浜の商業施設の担当になったときは、クライアントの会社に出向して、イベントのときにはテレビ局にアプローチして取材に来てもらって。クリスマスとか年末年始とか、そういった休みは返上して仕事してましたね。

>28歳の頃からつけはじめたという日記は、これまでに8冊にものぼる。
もともとPRの仕事に興味があったので、仕事は楽しかったんです。だけど、だんだんと違和感も持つようになってきたんですよね。たとえば、お店がオープンして、テレビに出て、お客さんが殺到して、クライアントも「良かった〜」って言ってくれるんですけど、「はたしてお店で働く現場の人にとって、本当に幸せなことのかな?」って思っちゃって。
メディアで取り上げられても、せいぜい反響があるのって一週間くらいなんですよ。そういう短いスパンなのも、すごく切なかったですし。もっと長い目で見て、みんなにとって幸せになれる方法があるはずなのに、一瞬の話題性のためだけに着飾るのって、なんていうか、持続可能じゃないよなぁって。
それに、仕事を通して同僚たちがどんどん疲弊していくのも目の当たりにしてたので、「この仕事は、一体誰を幸せにしてるんだろう」って、わかんなくなっちゃったんですよね。
人間らしい生活ができていなかった
仕事が忙しい日が続くと、同僚たちとよく、「人間らしい生活をしたいね」って言ってました。朝から晩まで、オフィスのこうこうとした電気の下で仕事をしてるわけです。そうすると、今日が何月何日で、季節がなんなのかっていうことがわかんなくなるんですよね。地下鉄の中吊り広告を見て初めて、「あぁ花見特集だから、もうじき桜咲くのか」なんて思うわけです。
スーパーに行っても、季節問わず、なんでも並んでいるから、旬の野菜がなにかがわからない。田舎だったら、畑の景色を見れば「今はピーマンが旬なんだな」ってわかるし、どこからか金木犀の香りがすれば「秋だなぁ」なんて思うんですけど。都心にいると便利になりすぎてそれがわからない。身体の調子がわるいなっていう時には、三食ちゃんと食べて、ぐっすり寝たらいいのはわかっていても、栄養ドリンクでごまかして乗り切ったりとか。
東京でのそうした働き方が、はたして本当に幸せなのかなって。そんな疑問が生まれてしまったら、その違和感はどんどん大きくなってしまって。
でも、わたし流されやすいタイプなので、都会のど真ん中で大勢のなかに入っちゃうと、「わたしは違和感があるけど、まわりの人はこっちがいいと思ってるんだから、こっちが正しいのかなぁ」っていう気持ちもぬぐいきれなかったんですよね。そうやって違和感をそのままにしているうちに、本当に苦しくなってきてしまったんです。

>当時の三星さん。(写真:三星さん提供)
「人生上がり!」の向こうにあった現実。
それとわたし、26歳で最初の結婚をしてるんですけど、1年で別れてるんです。
結婚したときは、「二人で稼いで、都内でマンション買って、いい生活をするのが幸せ」だとずっと思ってました。今思えば、「結婚したら、人生上がり!」みたいなイメージもあったんですよね。
でも、いざ結婚してみたら、そこに待っていたのは、リアルな現実だったんです。理想と現実のギャップに苦しんで、思っていたようにいかなかったんですよね。
わたし、彼が喜んでくれる「理想の妻」になろうと頑張りすぎちゃってた気がします。大学を卒業してから数年間、わたしの生活は彼を中心にまわってたんですよ。彼がどうしたら喜ぶかとか、彼が居心地がいい場所をどうしたらつくれるのかとかをいつも考えてました。だから、結局のところ、「自分がどうしたいのか」っていうのがわからなくなっていたんですね。
それで苦しくなって、いろいろあって別れることにして。あらためて一人になったけど、さてこれからどうしよう、みたいな。
そんなふうに、仕事での違和感と、プライベートでの転機がちょうど同じタイミングできて。「このままいったら、だめなんじゃないかな」って思うようになったのが、ちょうど28歳になるぐらいのタイミングでした

>当時を振り返った日記には、「将来の保証も安定した収入もあるのに、なぜか違和感。何だか、毎日が何かに流されていってるような気分。」とある。
「わたし、田舎が好きだな」と気づいた
それでまずは、「自分がやりたいこと」を見つける作業を始めたんです。「そういえば、電車の旅が好きだったなぁ」と思って、夏休みをながくとって、青春18切符で西日本をぐるっとまわってみることにしました。
ゴトゴトゴトゴト、電車に揺られながら、「わたし、なにがしたいんだっけな」って考えつつ、一週間ぐらいかけて、自分が行きたいと思ってた場所に行ったりとか、会いたいと思ってた人に会いに行ったりとか。
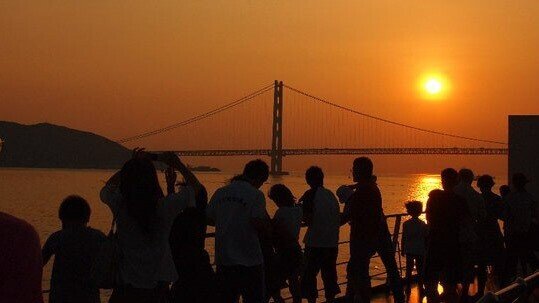
>旅で見た景色。(写真:三星さん提供)
その旅を通して気づいたのは、「わたし、田舎が好きだな」ってことです。それまでは「田舎に住むなんていやだ」って思ってたんですどね。わたし千葉県の内房出身なんですけど、そこはいわゆる新興住宅地で。都会でもなければ田舎でもない、中途半端な感じが好きになれなくて。東京生まれ、東京育ちの人がうらやましいと思ってたんですよね。でも、「田んぼがあって、昔ながらの景色があって。そういうのが自分は好きなんだなぁ」って、あらためて気づいたんです。
そんなタイミングで、たまたま雑誌で電車の旅特集をやってたんですよ。2010年7月号の『オズマガジン』なんですけど。今もこうして、とってあります。

いすみ鉄道が表紙になってるんですね。これを本屋さんで見つけて、「あ、鉄道の旅好きだ、わたし!」って思って。買って読んでみたら、中島デコさんの「ブラウンズフィールド」とか、今は移転してますけど、パン屋「タルマーリー」とか、「大多喜ハーブガーデン」とか、移住してお店をはじめられた「珈琲抱」、「蔵精」「手打ちそばゆい」が載っていて、「千葉にこんな素敵な場所があるんだなぁ」ってびっくりしたんですよ。
読みながら、「地方移住もありかも!」ってひらめいちゃって。わたし、平日はバリバリ東京で働いて、週末に逃げるように電車に乗って旅に出てたんですけど、「それって、逆でもいいんじゃないのかな? 平日は田舎で暮らして、週に何回かだけ東京に行くっていうほうが、幸せなんじゃないかな?」って思ったんです。
それから、雑誌とかイベントとかでいすみについての情報を拾い集めるようになって。思い切って、いすみ市役所で開設していた移住相談窓口に行ってみたんですね。そしたら、わたし一人に対して向こうは6人で迎えてくれて(笑)! 東京でやるような、事務的な面談を想像してたから、びっくりしました。
どうやらその日はわたししか面談の予約がなかったみたいなんですけど、「この人たちは、その他大勢のなかの一人じゃなくて、わたしっていう人間と向き合ってくれるんだな」っていうのは、すごく新鮮に感じましたね。もう、その日のうちに「いすみに移住しよう!」って決めてました。
移住について、あまり迷いはなかったですね。あのときのわたしは、なにか理由をつけて東京を出たかったんだと思います。仕事は楽しかったけど、違うなにかに挑戦するために、きっかけがあったらすぐにでも動きたいなって思いが、ずっと心のなかにあったんだろうなと、今振り返って思います。
でも、会社に辞表を出す時も、引っ越しの手続きをする時も、「本当にこれでいいのかな?」って、何度も考えました。「一歩踏み出したら後戻りできないな」って、そんなことを何度も繰り返し考えたりして。最終的には、「えいや!」と覚悟を決めましたけど。
強く持っていた「何者かになりたい」という思い
正直、そのときは胸を張って「田舎に行きます!」って言えませんでした。2010年当時は、まだ「地方移住はドロップアウト」みたいなイメージがあったんですよね。
でも実際に移住してみると、「東京もおもしろいけど、田舎も楽しいよ」って言う方がたくさんいて、本当に楽しそうに暮らしてるんですよ。そういう人たちと出会って、「あ、田舎は都会が嫌になった人が来るところじゃなくて、新しい可能性がある場所なんだな」って気づいたんですよね。
移住した当初、強く持っていたのは、「何者かになりたい」っていう思いでした。よく考えるとわたし、子どものときから親が「よし」と思うことをやってきて。いわゆる大勢の人が進むであろうレールの上に、ただただ乗っかって来てたんです。いい大学を出て、いい会社に就職する、という。自分がどうとかではなくて、「何に所属しているのか」が大事、っていう価値観ですね。
そのおかげで、大学も行き、運良く就職もできて、ずっとどこかしらに所属してきてたんですよね。だから「どこどこの人間です」って自己紹介ができてたんです。だけど、いざ所属がなくなった時に、「わたしって一体、何者なんだろう」って、わかんなくなったんですよ。
あるとき、いすみ市内で開催されたイベントに参加して、自己紹介の時間に「はじめまして」の次の言葉が出てこなかったんです。まわりの参加者は「農家やってるんです」とか「カフェやってるんです」とか話してるのに、わたしはとくに、これからなにをやるのかも決まってなくて。「なにをしたいの?」って聞かれても、「ちょっとまだ考えてないんですよね…」しか言えなくて、すごく肩身の狭い思いをして。そのときに、「ちゃんと自己紹介できるように、何者かにならなきゃ!」って、強く思いましたね。

まずは、ひたすら目の前のことに取り組んだ
そのあとは、ひたすら目の前のことに取り組んでました。田舎だと、若いってだけで人手が増えて重宝されるので、「人手が足りない」って言われたら、自分になにができるかわかんなくてもだいたい行ってました。田植えとか、イベントの手伝いとか。田植えは人生で初でしたけど、あんなに大変だとは思ってなかったな(笑)。あとは、会議があったら「聞きに行っていいですか?」ってお願いして顔を出したりとか、プレゼン資料つくってほしいと言われたら手伝ったりして。そういうの、以前の仕事でも得意だったので。そうやって、わたしがどんな人間なのかを皆さんに知ってもらうっていうことをやってました。

>(写真:三星さんご提供)
今思えば、それがすごく良かったですね。「何者かにならなきゃ」って焦る気持ちもあったけど、自分の理想があったとしても、目の前のことの積み重ねの先にしか、自分で納得する答えは出せなかったと思うんです。まずはまわりの人の話を聞いて、歩調をちょっとずつ合わせていって、そこから自分のやりたいことに進んでいく…っていう順番でした。
移住してからの収入に不安はあったけれど、タイミングよくNPOの臨時スタッフの仕事の募集があって。PRの仕事とも通ずるものがあったので、採用が決まって。フルタイムで仕事をするようなりました。
だからお金の心配は少なからず解消されたんですけど、「何者かになりたい」って気持ちはぬぐえなかったですね。わたしは雇われて働くんじゃなくて、自分の足で立ちたかったんですよ。「結局所属している団体の肩書なんだよな」って、1年ぐらいモヤモヤしながら仕事してました。

「シェアハウスの管理人」という肩書きを持てた
「何者かになりたい」っていう気持ちが解消されたのは、シェアハウスの管理人になったときですね。なにか自分だけの肩書きが欲しいなって思い続けていたら、あるとき市役所の方から「空き家になった古民家があるから、誰か活用する人いないかな?」って相談があったんです。
最初は「すごいとこですね〜、誰か借りる人いないか探してみますね!」って言って、知り合いにあたってみてたんです。でも、「いいねいいね!」って言う人はいるんですけど、実際は誰もやらなくて。「もったいないな〜」と思ってたんですけど、ふと「あ、わたしやるか」って思い立っちゃったんですよね(笑)。
NPOでの仕事も、更新が1年単位なので稼ぎの保証はないし、自分の肩書きを持つためにもなにかやりたいなって思ってたので。かといって、新しいことに仕事を全振りするのはリスクも大きいわけで。その覚悟は当時はまだなかったですけど、シェアハウスの運営なら他の仕事と並行してできるなって思って。シェアハウスの運営だけで食べていくのは無理だけど、みんなで家を借りるぶん家賃は安くなりますしね。それで、2012年6月に「古民家シェアハウス 星空の家」をはじめたんです。
その時はじめて、「シェアハウスの管理人」っていう自分だけの肩書きができて、ちょっと自信が持てるようになりましたね。

>「星空の家」の、ある1日。(写真:三星さんご提供)
根幹にあるのは「シェア」
それ以来、活動はどんどんひろがってきました。2014年の12月にはシェアハウスの敷地内にあった納屋を改装して、私設図書館「星空の小さな図書館」をはじめて、2016年9月には結婚を機に、夫と一緒にカフェ&シェアスペース「星空スペース」をオープンして。
2018年には「株式会社スターレット」っていう法人をつくって、今は空き家・空き施設の利活用やイベントの企画・運営などに取り組んでいます。最近では「い鉄ブックス」っていう、本を寄付していすみ鉄道を応援するプロジェクトもはじめました。私の移住のきっかけになったいすみ鉄道とこういう形で一緒に仕事をするとは、思ってもみなかったですけどね。

>子どもから大人まで、さまざまな人が訪れる「星空の小さな図書館」(写真:三星さんご提供)
いろんな活動をやってますけど、根幹にあるのは「シェア」だなって、最近気づいたんです。シェアハウスは住まいのシェアだし、図書館は本のシェア、星空スペースではみんなでイベントやったり、農業体験を企画したり、学びの場を提供するなかで体験をシェアしてるわけだし。事務局も、誰かの「やりたい」っていう思いをシェアする手伝いをしてるんですよ。
振り返ればわたし、小さい頃から、「その場にいる人が楽しいかな」とか、「誰かが居心地のわるい思いをしてないのかな」とかをすごく気にするタイプだったんですね。もしかしたらそのときと変わってなくて、「時間や場所やモノを分かちあうことで、そこにいるみんなが楽しい思いをして欲しい」って気持ちが、わたしの根っこにあるのかもしれないですね。

>「星空スペース」(写真:三星さんご提供)
「自分は何者か」という問いへの答えは、ひとつじゃなくていい
いろんな活動をしているから、結局、今でも自分が何者なのかって聞かれたら「これ!」っていうふうに答えられないです。だけど、それがべつにネガティブなことじゃないって、最近は思えてきました。
シェアハウスの管理人として住人と話してるのも、草刈りしてるのも、図書館の館長としてカウンターに立って利用者さんをお迎えするのもわたしだし、事務局として誰かのお手伝いをしているのもわたしだし。別に、肩書きをひとつにしぼらなくていいんじゃないかなって。前は「自分が何者か、明確に言えなきゃいけない」って思ってたけど、自分がそう思い込んでいただけであって、まわりは別にそんなこと求めてなかったんですよね。

今までやってきてる仕事って、ぜんぶまわりの誰かに必要とされて成り立つものばかりなんです。シェアハウスの管理人もそうですし、事務局もそうですし。「こういう暮らしがしたい」「こういう仕事をしたい」っていう人がいて、はじめてわたしが役に立てるというか。だから、その時々でわたしの肩書きって変わっちゃうんです。だけど、それでもいいんじゃないかなって思います。そこにいるみんなが楽しい思いができるのであれば、ひとつに絞る必要ないんですよね。
子どもの頃からいつも、「誰かのため」「なにかのため」って動いてきていて、それがやりがいだった反面、行き過ぎて他者に依存していた部分もあったと思うんです。20代のころのわたしは自覚はなかったけれど、実は何かに寄りかかっていかないと生きていけない弱さがあったんだなぁって。必死にもがいて、自分の足で立ちたいと進んできたこの10年間を経て、ちゃんと地に足がつけられたんだと思うんですよね。今ならば、「誰かのため」「何かのため」でも、依存せずにちゃんと自分らしく向き合っていけような気がしてます。

このまちだから、病気とともに生きていくことができる
人は一人じゃ生きてけないなぁって、言葉では簡単にいえますけど、いすみに来てから本当に実感しましたね。
わたし2019年に、「1型糖尿病」っていう病気を発症したんです。今まで大きな病気もしたことがなかったので、あまりに突然のことに本当にびっくりしました。人生初の緊急入院でした。
ちょうど、会社を立ち上げて1期目が終わったばかりの時で。まだまだ夫婦2人の小さな会社でしたが、イベントやらケータリングやら、それと講演や視察も重なっていて、本当に毎日忙しい時期だったんです。そんななか、急遽わたしが入院してしまったので、残された夫は大変だったと思います。
でも、多くの人に助けてもらってなんとか乗り越えられて。普段から一緒に仕事をしていたり、お互いの家を行き来していたりしていて事情がよく分かるからこそ、みなさんがいろんな形で手伝ってくれて。ほんと、感謝しかなかったです。

病気とはずっと付き合っていかなければならなくなったんですけど、あまりネガティブな感情もなくて。多くの友人や仲間がいるこのまちにいる限り、何かあってもなんとかなるんじゃないかな、って、なんか不思議な安心感があるんですよね。このまちには、誰か困ってる人がいたら、みんなで困ってることをシェアして解決しようっていう、そういう文化があるからか、安心して暮らしていける気がしています。
それと、移住してからは日々、少し先の未来を見ながら、今目の前のこととちゃんと向き合うことをしていたから、何があっても受け止める覚悟ができていたのかもしれないですね。どうなるかわからない未来を憂うよりも、今を楽しむ方が大事って思えるようになったなって。
でも、一番は夫の存在が大きいですよね。「自立しながら支え合う」を自然にできる、本当にいいパートナーに出会えたなと、思ってます。

何者かになるより、このまちでの暮らしを続けていきたい
小さい頃から、「これをやりたい」っていうことを言えなくて、正直今も、これがやりたいっていうことはあんまりありません。ただ、あるとしたら、「このまちでの暮らしを続けたい」っていうことですね。
20代も楽しかったですけど、毎日いろんなことに追われて、日々をきちんと振り返る間もなくすごしてたんです。それが積もり積もって、違和感が出てきて、「何者かにならなきゃ」と焦ってたのが、移住した28歳の頃でした。
あれから10年経って思うのは、焦らずに、自分のした選択に対して一つひとつ向き合うことが、実はすごく大事だったんだなって。毎日なんとなく生きて時間が過ぎちゃうんじゃなくて、ちゃんと一日一日を振り返って、「今日も良い一日だったな」って眠れたら、それで十分幸せだなって思うんですよね。
そう思えるようになったら、自分にとって大事なモノも見えてきて、いつの間にやら公私共に最良のパートナーにも出会えたという、本当に予想もしていなかった展開です。

今は、いつも6時半ぐらいに起きて朝ごはんを食べ、家事をすませて、8時過ぎのぐらいから仕事を始めてます。9時までに一気にメールを返信しちゃって。そのあとは打ち合わせしたり、本の整理をしたり、草刈りをしたり。夫と2人でお昼ごはんを食べて、レポートや資料をまとめて、オンライン会議して。夕飯はたいていシェアハウスの住人さんと一緒に食べて、日付が変わる前には寝るような生活をしてます。
こんなふうに、日が昇ったら仕事して、日が沈んだら休んで、「今日もいい一日だったなぁ」って、眠る。そんな日々を続けていくことができたら、何者かにならなくても十分幸せじゃない? って、今は思うんですよね。
あの時の自分が描いた10年後の未来にちゃんと立てているかな、と考えると、正直わからないけれど、今の仕事にも暮らしにも満足はしているかな。満足というか、充実してますよね。ちゃんと中身がある感じ。そう思えるようになったことが、この10年間で成長できたことなんでしょうね。
実は、毎日モヤモヤを抱えて、「何かが違う」という違和感を抱えていた20代の終わりのころ、「きっと自分にとって運命的な出会いが私を変えてくれるんだろう」と思っていました。
でも、今なら思うんです。運命的な出会いなんてきっとない。待っていたって何も変わらないって。
自分で動いて、目の前のことと向き合って、まずはひとつひとつのことをちゃんと考えてみる。考えて、自分で「よし!」と選択して。大小関係なく選んだことに責任をもって、それを続けてみる。そんな小さな決断を積み重ねることが、モヤモヤを解消する最短ルートなんじゃないかな、と、今なら思います。
変化はきっとゆっくりで、自分ではなかなか気付けない。だけど、焦らなくたっていいじゃない。人生はまだまだ長いんだしね。
サポートがきましたって通知、ドキドキします。
